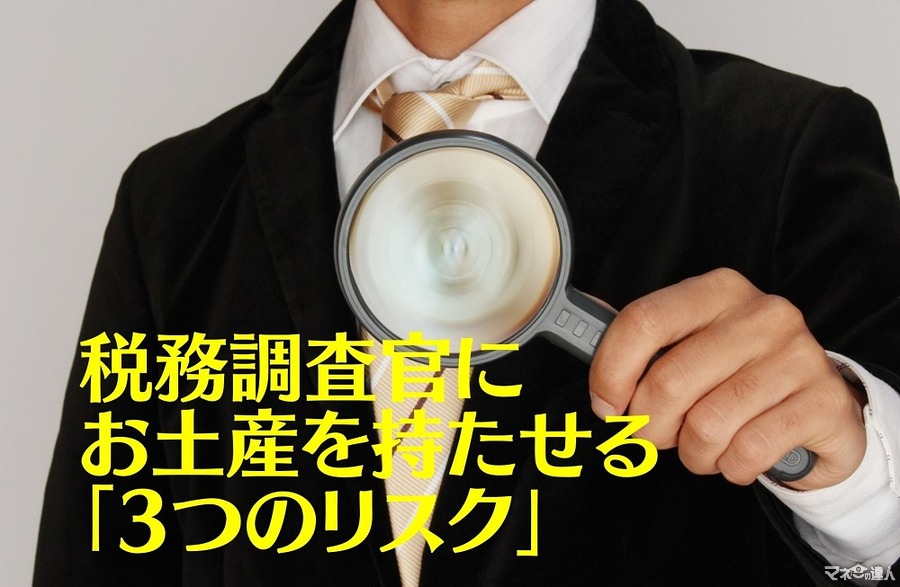税務調査には、「調査官に『お土産』を持たせることで調査官を満足させると、早く調査を切り上げてもらえる」という昔からのうわさが存在しています。
ここで言う『お土産』とはもちろん本当の手土産などではなく、「あえて処理の誤りを発見させて、調査官に追徴税額を与えることでお引き取り願おう」という考え方を指します。
しかし、実際の税務調査の場では、お土産を持たせるという考え方がかえって災いのもととなることも少なくありません。
今回は、税務調査官の心情を踏まえて税務調査でお土産を持たせることのリスクを見ていきます。
目次
税務調査官にお土産を持たせることの3つのリスク
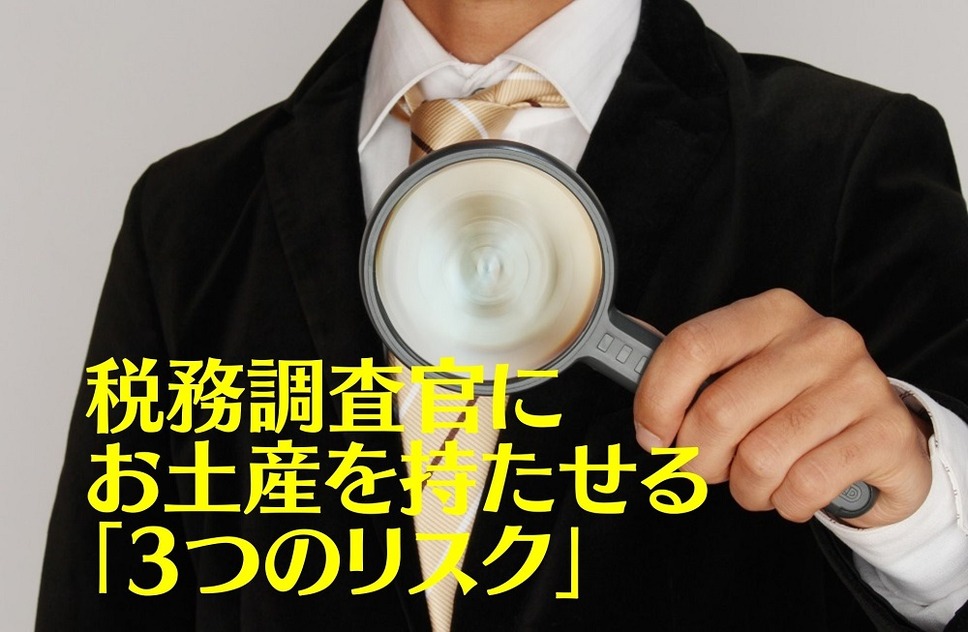
リスク1. 却って調査が長引く
「ボクサーは相手の血を見ると元気になる」このような言葉を聞いたことがありますが、どのような仕事であっても成果を上げるチャンスが目の前に現れると、途端にモチベーションが上がるものです。
税務調査では、本来は「適切で公平な課税を実現すること」が最大の成果であるはずですが、実際には「追徴税額を徴収すること」が目的となってしまっていることも事実だと思います。
したがって、下手にお土産を持たせることで、「この会社は深堀りすれば、もっと大きな誤りが見つかるかもしれない」と調査官が感じる可能性が高いと考えられます。
調査官にそのような印象を持たせてしまうと、早く調査を終わらせてもらえるどころか却って調査期間が長引くことも十分に考えられるのです。
リスク2. 税務調査が慣習化するリスク
所轄の税務署内には、納税者ごとの過去の税務調査の記録が内部情報として蓄積していきます。
調査官にとって追徴税額を徴収することが1つの成果だとしたら、過去の税務調査で誤りが見つらなかった会社に比べ、修正事項の見つかった会社のほうが再度調査対象となる可能性は高くなることでしょう。
行くたびにお土産をもらえるということは文字通り相手を喜ばせることになり、結果的にオリンピックのように「数年ごとに必ず税務調査に入られる」などということにもなりかねないのです。
リスク3. 調査官のアップグレード・人数増加
過去の税務調査で毎回のように誤りが発見され、追徴税額の発生を繰り返した場合には、次第にやって来る調査官の役職が上がっていったり、調査官の人数が増えていくことがあります。
税務署内の調査官の人数は限られていますが、一般企業と同様に税務調査では少ない労力で大きな成果を得ることが重要です。
したがって役職の高い調査官がやって来たり、調査官の人数が増えるということは、あなたの会社がそれだけの人件費を掛ける価値のある会社だと認識されているということを表している即ち、そのコストを回収できるだけの成果を求められているということを意味しています。
このような状況に陥ってしまえば、お土産という表現では済まないほどの追徴税額を課されるリスクも高まっていきます。
「この会社は探しても何もないな」と思わせることがベスト
ここまではお土産を持たせることによって生ずる悪循環についてお話ししましたが、対照的に適切な処理ができている場合には良い循環を生むことが可能です。
「探しても何も見つからなそうだ」
調査官からこのような評価をもらえることのほうが、その場の調査だけではなく、長い目で考えてもよっぽど大きなメリットがあるはずです。
税理士という立場上、税務調査に立ち会うことがあるのですが、何も修正事項の見つからない「申告是認」で終える調査も少なからず存在します。
したがって「調査官は何かしら追徴税額を見つけるまでは帰らない」という認識は間違いであり、いくら調査官であっても誤りのないところから修正事項を挙げることはできないのです。
「お土産」はデメリットをもたらす
税務調査に関する「お土産」の有効性について解説しました。
日頃の経理をきちんとやっているつもりでも、うっかりミスが見つかってしまうことは十分に考えられます。
しかし、お伝えした通り、あえて「お土産」を持たせるという考え方は、そのときの調査結果だけではなく将来的にさまざまなデメリットをもたらす可能性がありますので、避けるべきであると言えるのです。(執筆者:税理士 服部 大)