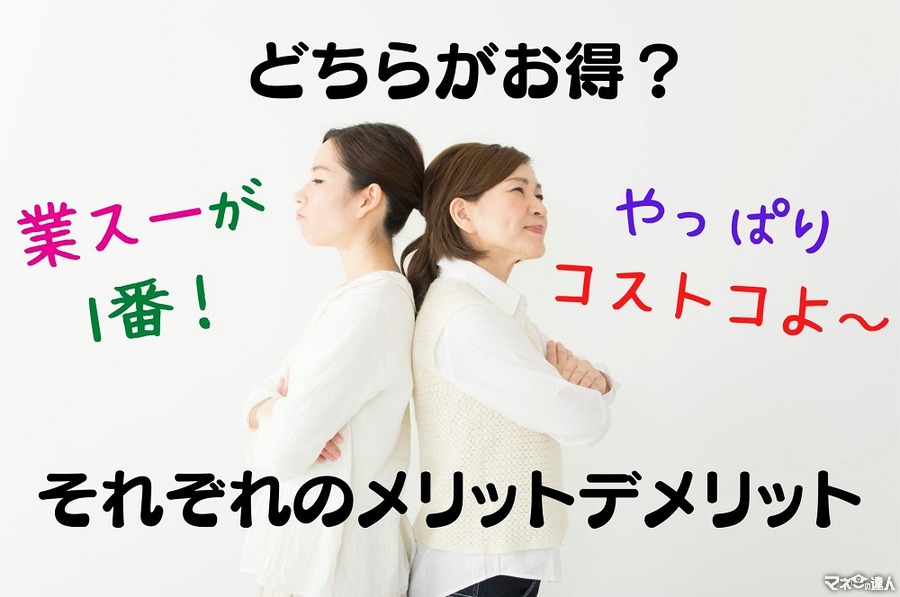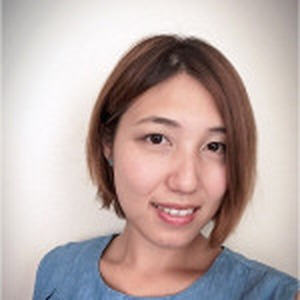大容量でお得な商品を購入できるお店と言えば「業務スーパー」と「コストコ」が定番です。
しかし、買い物をしようと思った際にどちらで購入した方が得なのか迷ってしまいませんか。
そこで今回は、業務スーパーとコストコはどちらがお得なのか、それぞれのメリット・デメリットも合わせて紹介します。
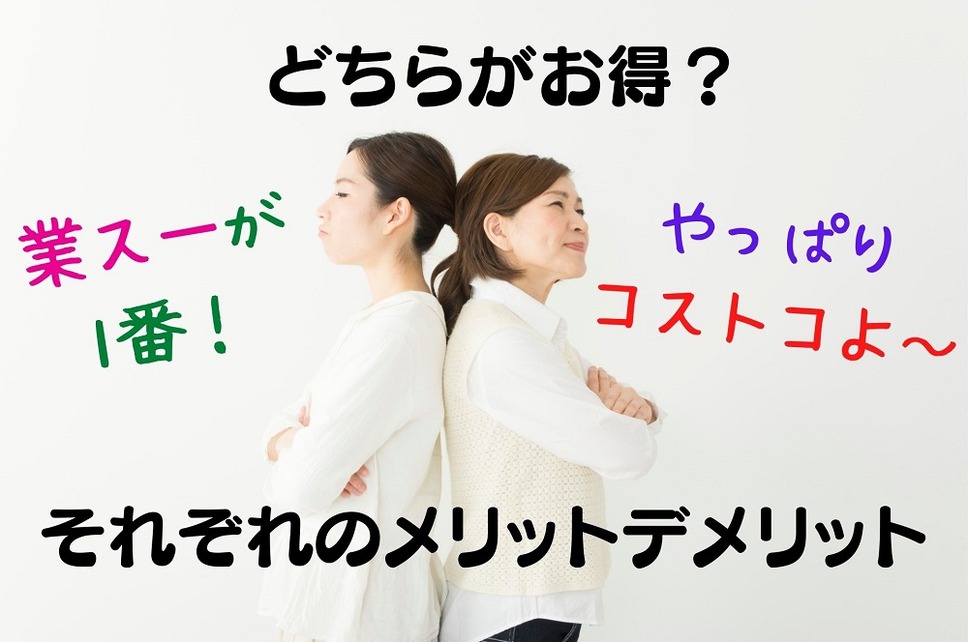
目次
業務スーパーのメリット・デメリット
まずは業務スーパーのメリット・デメリットを考えます。
業務スーパーのメリット
業務スーパーには、コスパだけではなく入店や買い物のしやすさなど、さまざまなメリットがあります。
・ コストコよりも価格が安い
・ 大容量のみではなく普通サイズの商品も多い
・ 店舗数が多い
・ 時短できる商品が多い
業務スーパーは、その名の通り業務用の食材を取り扱っていますが、一般客でも買い物できます。
会員登録などは不要ですし、年会費なども一切かかりません。
他スーパーと同じように買い物を楽しめるのは、業務スーパーならではの魅力と言えます。
また、大容量で安い商品が多く、全体的に価格はコストコよりも少し安めです。
業務用だけではなく、一般家庭向けの普通サイズ商品も多く取りそろえているので、安くてもムダにするリスクが低いという点も業務スーパーのメリットです。
さらに、店舗数が多く、買い物に行きやすいことも業務スーパーの大きな強みです。

業務スーパーのデメリット
業務スーパーにはメリットしかないように思えるのですが、いくつかのデメリットもあります。
・ ときどきクセのある商品もある
・ 業ス人気から、在庫がない、品薄のときもある
業務スーパーには国産商品も多いのですが、それ以上に外国産の商品がたくさんあります。
そのため、産地にこだわりのある方や国産しか使いたくないという方は購入できる商品が少ないというデメリットがあります。
また、筆者はこれまでに数々の業ス商品を試してきましたが、なかには少しクセのある商品もありました。
基本的にはおいしくて使い勝手のよいものばかりですが、口に合わないものにあたる可能性もゼロではありません。
また、最近の業ス人気から商品が品薄・品切れになることが多いようです。
特に、メディアで取り上げられた翌日や土日には客足が伸びて在庫がないこともあります。
コストコのメリット・デメリット
次にコストコのメリット・デメリットを考えます。
コストコのメリット
業スと比較しながら、コストコのメリットをまとめました。
・ 食料品の種類が多い
・ 食料品以外の商品も多く、ジャンルが幅広い
・ 購入後でも返品できる補償サービスがある
・ 試食が多く、口に合うか試してから購入できる
・ 安くておいしいフードコートで食事も楽しめる
コストコには、「カークランド」をはじめとしたコストコでしか購入できない商品があります。
「さくらどり」の鶏肉、プルコギビーフなどの肉類のほか、パンや調味料もコストコだから購入できるものが多いのです。
また、業スとは違って、コストコでは食料品以外の商品も多く取りそろえています。
日用品やアウトドア用品、電化製品など、ありとあらゆるものをお得に購入できるのはコストコの強みです。
そしてコストコといえば、豪華な試食があるということも魅力のひとつです。
試食をしたうえで購入できる商品も多いので、買って失敗することが少ないこともメリットだと言えます。
安い、おいしい、ボリューム満点の食事が楽しめるフードコートも業スにはないコストコの魅力です。

コストコのデメリット
コストコにも業スに負けないほどの魅力がたくさんありますが、もちろんデメリットもあります。
・ 店舗数が少ない
・ アクセスがあまりよくないため、車が必須
・ 業スよりも大容量のものが多く、保存や使い切るのが大変
・ 1つあたりの金額が大きいので、高額な買い物になることもある
・ 専用のバッグがないと持ち帰りが難しい
コストコのデメリットは、やはり「年会費」がかかる点です。
業スは無料ですが、コストコは税込み4,840円の年会費がかかります。
ひと月あたりに換算すると403円と決して高くはないのですが、年に1回支払う際には大きな出費です。
この年会費で、コストコでの買い物を諦めている人も少なくないと思います。
また、コストコは巨大倉庫のため、少し行きづらい場所にあることが多いと言えます。
そのため、行く際には車が必要です。
1つ1つの商品も大きくて量が多いことから、使い切るのが大変、支払額が高くなるといったデメリットもあります。
持ち帰る際にコストコ専用のバッグでないと入らない商品も多く、買い物バッグを購入するお金も必要です。
うまく使い分けよう
業スとコストコには、それぞれにメリットとデメリットがあります。
筆者は、普段買い物に行くのは「業務スーパー」、1~2か月に1回のストレス発散もかねてまとめ買いをするのに「コストコ」を利用しています。
それぞれをうまく使い分けて利用すると食費節約にも効果的です。(執筆者:三木 千奈)