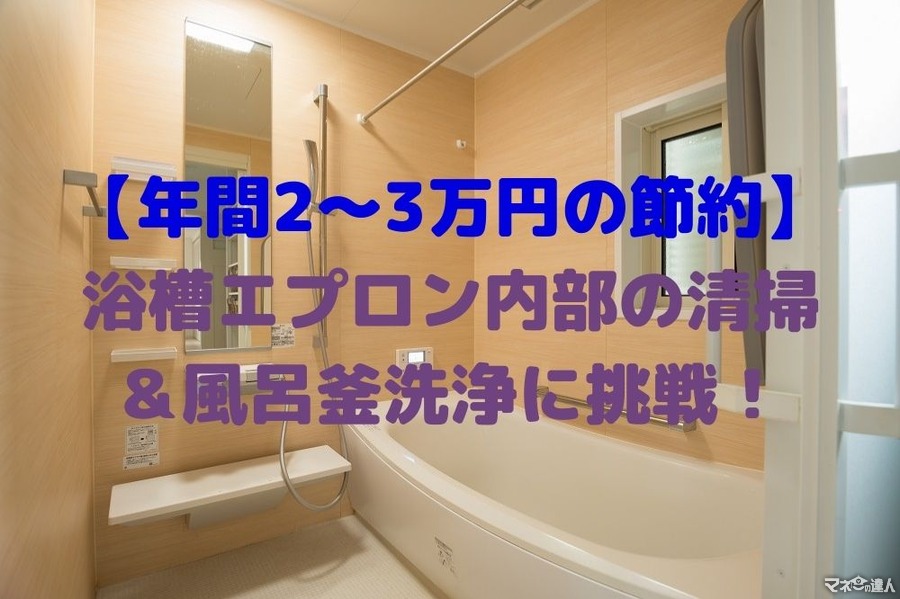浴槽エプロン内部の清掃や風呂釜の洗浄は、普段はなかなか手の行き届かない部分ですよね。
年に1~2回は業者に依頼していたのですが、金額的には2~3万円ほどかかってしまうので「何とか自分でできないものか…」と思い立ち、挑戦してみることにしたのです。
プロと同じクオリティとは言えませんが、これからは節約のためにも自分でできる範囲をやってみようと思いました。
この記事では、浴槽エプロン内部の清掃や風呂釜の洗浄などの大掃除を自分でやってみての体験談と、掃除のコツや用意するグッズについてお伝えしたいと思います。
目次
浴槽エプロン内部の清掃、風呂釜の洗浄

浴槽エプロンとは、浴槽の側面カバーのことです。
浴槽エプロン内部とは、浴槽とエプロンの間の隙間のことで、近年のシステムバスの多くは浴槽エプロン部分が取り外せるようになっています。
浴槽エプロン内部は湿気が溜まりやすく、カビの発生しやすい環境です。
掃除をお願いしていた業者の方に聞いたところ、エプロン内部の掃除頻度は「最低でも年に1~2回」は掃除したほうが良いとのことでした。
浴槽エプロンの取り外し方や簡単な掃除の仕方についても、業者の方に教えていただきました。
風呂釜とは、浴槽とつながっているお湯を沸かす装置のことです。
風呂釜の配管内には皮脂や水垢、細菌や微生物などが繁殖するため、こちらも年1~2回の配管内の洗浄が望ましいそうです。
セルフ大掃除をやってみた
業者の方に聞いたコツや、ネットで調べたやり方を参考に実際にセルフ大掃除をやってみました。
ここでは、浴槽エプロン内部や風呂釜の洗浄を中心に紹介していきます。
用意したもの

私が今回の掃除で用意したものは、
・ 風呂釜用洗浄剤
・ 防カビくん煙剤
・ オキシクリーン
・ 掃除用スポンジ
・ キッチンペーパー
・ 小さめのブラシ
・ カビハイター
・ パイプクリーナー
・ クエン酸
・ お風呂掃除用洗剤
・ ゴム手袋
・ マスク
です。
家にあるものがほとんどなので、新たに購入したのは風呂釜用洗浄剤と防カビくん煙剤の2つだけです。
浴槽エプロン内部の清掃

最初に、浴槽エプロンを取り外します。エプロン下部を両手で持って、上に持ちあげながら手前に引き出すと外れました。
なお、わが家のバスタブはPanasonic製で、取り扱い説明書にも「エプロンを取り外して、エプロン内の浴槽パンを清掃してください」と記載があります。
メーカーによっては取り外せないものもあるので、浴槽に貼付してあるラベルや取扱説明書でご確認ください。
半年ぶりに開けた浴槽エプロン内部には、案の定、カビが発生していました。
まずは、熱めのシャワーでザっと汚れを流し、排水口のゴミをキッチンペーパーで取り除きます。
頑固なカビ汚れには、カビハイターを吹きかけて30分程度の時間をおきます。シャワーで洗い流しても落ちなかったカビ汚れは、スポンジでこすると落ちました。
手の届く範囲はやったのですが、バスタブの奥部分には手が届きにくいので「柄の長いブラシがあればよかった」と思いました。
次に、エプロン内部側の排水口に、パイプクリーナーをかけて30分の時間をおいて水で流しました。
浴槽エプロンを取り外す機会は少ないので、この機会にパイプ洗浄もやっておくと良いと思います。
浴槽エプロン内部の掃除が終わったら、水を切って乾燥させて、防カビくん煙材を使います。
ここでのポイントは、浴槽エプロンを外した状態で防カビくん煙材を使うという点です。
湿気のたまりやすいエプロン内部まで防カビ対策ができるので、より一層効果的だというわけです。
風呂釜の洗浄


かかった時間と費用・やってみての実感&節約効果
ここからは、かかった時間・費用、実際にやってみての感想と節約効果をお伝えします。
時間
かかった時間は、合計で4時間程度でした。
カビハイターやパイプクリーナー後の放置時間1時間と、防カビくん煙材を使用していた時間と換気時間の約2時間も含めての時間なので、実際に浴室で作業していたのは1時間弱程度だったと思います。
費用
かかった費用は、新たに購入した
・ 風呂釜洗浄剤:298円
合計で796円
でした。
やってみての実感&節約効果
自分でやってみて感じたことは、
・ 風呂釜洗浄は2年に1回程度はプロに依頼したほうが良さそう
ということです。
わが家では業者に依頼する回数を少なくしたことで、年間2~3万円の節約になりました。
自分でできる箇所とプロに頼むタイミングを見極める
この記事では、浴槽エプロン内部の清掃や風呂釜の洗浄などの大掃除を自分でやってみての体験談をお伝えしました。
やはり素人には真似できないプロの技術もあるので、自分でできる箇所とプロにお願いするタイミングを見極めて、上手に節約しながら快適で綺麗な浴室をキープしていこうと思いました。
水回りの大掃除は億劫ですが、できる部分は自分でやって節約につなげてみてはいかがでしょうか。(執筆者:桐里 もえ)