「ららぽーと」は、全国に点在する三井不動産系のショッピングセンターです。
この、ららぽーと等に便利な「三井ショッピングパークカード」というクレジットカードがあります。
このカードがららぽーとで最強であることを確認していきましょう。
目次
三井ショッピングパークカードの特徴
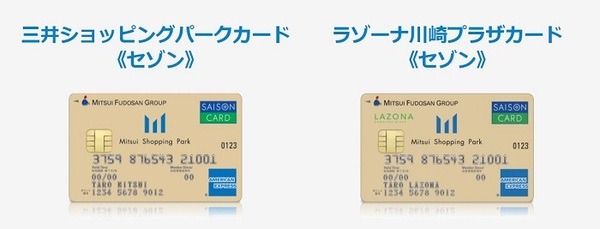
支払手段が多様化した昨今、商業施設で系列のクレジットカードが最も得になるとは限らないという事例が増えてきました。
しかしながら、三井ショッピングパークカードについては、ららぽーと等で間違いなく最も得になる決済手段です。詳しく見ていきましょう。
どこで「お得」になるのか
三井ショッピングパークカードが役に立つのは、全国の三井不動産系列のショッピングモールです。
対象の主な商業施設は次の通りです。
・ ららぽーと
・ ラゾーナ川崎
・ 三井アウトレットパーク
・ ミッドタウン
・ ララガーデン
・ ららテラス
・ コレド
・ ダイバーシティ東京プラザ
他にも多数あります。
三井系ではWポイント
ららぽーと等の三井系商業施設で「三井ショッピングパークカード」で決済すると、次の2種類のポイントが貯まります。いわゆるWポイントです。
100円につき2ポイント(2円相当)→ ポイント還元率2.0%
【永久不滅ポイント】
月請求合計1,000円につき1ポイント(5円相当)→ ポイント還元率0.5%
ららぽーと等での買い物は、合計ポイント還元率2.5%と高率還元です。
時折、QRコード決済での10~20%還元の大型キャンペーンがありますが、この機会を除くと三井ショッピングパークカードに敵う決済方法はほぼありません。

他の商業施設 × 他のカードと比較
三井のライバル商業施設で、系列のカードで支払う場合と比較してみます。
<平常時>
還元率1.0%(ポイント2倍)
<毎月10日・20日・30日>
還元率2.5%(ポイント5倍)
【アリオでセブンカード・プラス決済】
還元率1.0%
いずれのカードも、買い物1回(200円)ごとにポイントが算定されるので、端数切捨てが発生しやすい点は同様です。
数字を見ると、三井ショッピングパークカードの価値がよくわかります。
貯まったポイントの使い方と注意点
三井ショッピングパークカードはセゾンカード発行であるため、セゾンのポイントプログラム「永久不滅ポイント」が貯まります。
ららぽーと等に限らず、どこで買い物をしても同率です。
永久不滅ポイントは1ポイント5円(等価)で三井ショッピングパークポイントに替えられます。
三井ショッピングパークカードの利用で貯めたポイントは、すべて三井ショッピングパークポイントにできるのです。
ただし、ポイントの使い方には要注意です。
館内の実店舗では500ポイント(500円)単位で決済に利用できるので、ポイント端数が出やすくなっています。
端数を使い切りたい場合には、公式通販サイトで1ポイント1円で利用可能です。
ボーナスポイントもある
三井ショッピングパークカードは、三井系商業施設での年間利用額(4月から3月)に応じて特典を得られます。
年1回「10%オフ」
【年間30万円(プレミアム)】
年1~3回「10%オフ」
さらに、年間30万円達成(プレミアム)の場合、年間利用額に対して最大1.0%のボーナスポイントももらえます。
先に計算したポイント還元率に置き換えると3.5%ということになります。
三井ショッピングパークカードは年会費無料
三井ショッピングパークカードには、VISA、Mastercard、JCB、アメックスの4ブランドがあり、すべて年会費無料です。
これ以外にプレミア・アメリカン・エキスプレスカードもありますが、年会費が3,300円(初年度無料)で、海外旅行傷害保険付帯です。
三井ショッピングパークカードは、人気の「セゾンカード」のラインアップに、無料でショッピング特典が付いていると考えると、そのお得さが理解しやすくなります。
三井ショッピングパークカードは、セゾンカードのカードブランドに次の通り対応しています。
セゾンカードインターナショナル
【アメックス】
セゾン・パール・アメリカン・エキスプレスカード
【プレミアアメックス】
セゾン・ブルー・アメリカン・エキスプレスカード
セゾンカードが欲しい人にもおすすめできます。
三井ショッピングパークカードの即日受取り
三井ショッピングパークカードは、ららぽーと等に買い物に行くと決めたその日に手に入ります。
ウェブから申し込んで審査を通過したら、全国のららぽーとのカウンターで受け取れます。
カード現物を受け取らなくても買い物できます。会員専用のQRコード決済が、審査通過後にららぽーと等ですぐ使えるためです。
三井ショッピングパークカードでは、入会で最大2,000円のキャッシュバックも実施しています。
ららぽーと等でのお買い物の際にはぜひカードを作りましょう。(執筆者:沼島 まさし)








