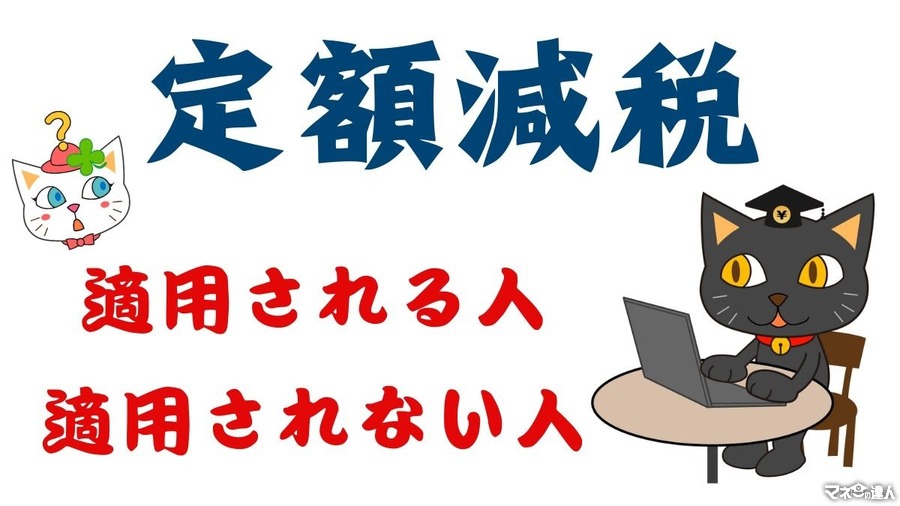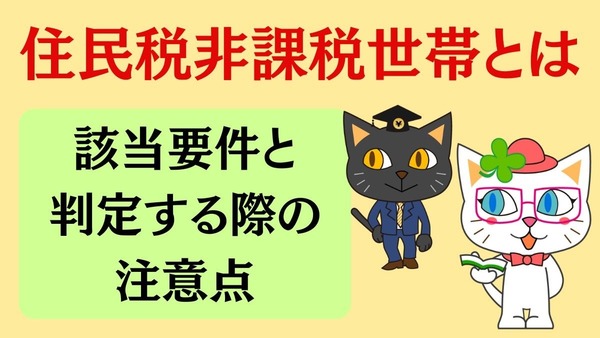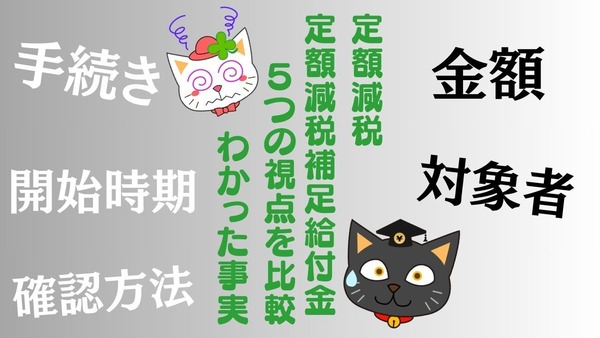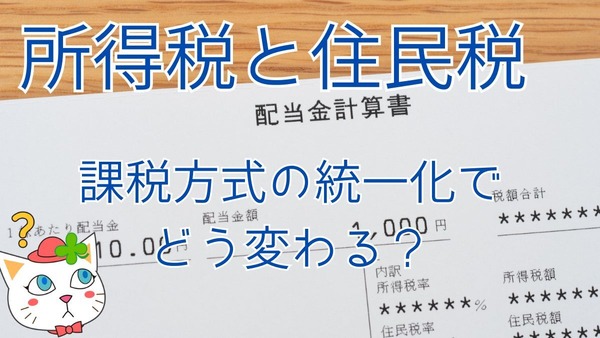何かと話題になっている定額減税ですが、令和6年分の所得税および令和6年度の住民税で適用されることになっています。
減税額が所得税・住民税の額を超える際の措置が設けられている一方、国民全員が適用できる制度ではありませんので、今回は定額減税の概要と適用要件について解説します。
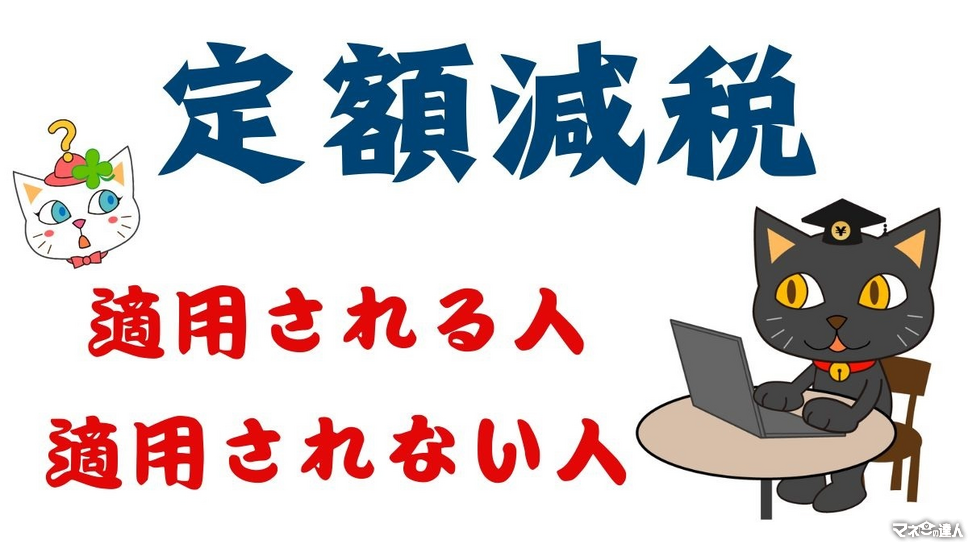
定額減税とは
定額減税は、所得税・住民税から差し引かれる特別控除をいい、特別控除額は本人および同一生計配偶者と扶養親族の人数によって決まります。
たとえば、本人と同一生計の配偶者、扶養親族の子1人の家庭であれば、所得税から9万円、住民税から3万円が控除されます。
<定額減税の特別控除額>
対象者 | 所得税 | 住民税 |
本人 | 30,000円 | 10,000円 |
同一生計配偶者または扶養親族 | 1人につき30,000円 | 1人につき10,000円 |
過去には「定額減税」と似た制度として「定率減税」がありましたが、定率減税は税額から金額から一定割合を控除するのに対し、定額減税の控除額は一定です。
そのため所得金額の大小で控除額は増減しませんし、扶養家族の人数が多いほど控除額は多くなるのが特徴です。
定額減税の適用要件
定額減税には適用要件は、所得要件と居住要件の2つです。
所得要件
合計所得金額が1,805万円以下
(所得税は令和6年分、住民税は令和5年分が基準)
居住要件
国内に住所を有する個人、または現在まで引き続き1年以上居所を有する個人
年間収入が給与のみの居住者の場合、給与収入が2,000万円以下(子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は2,015万円以下)であれば、定額減税の対象です。
居住者に該当しない「非居住者」となる方は、合計所得金額が1,805万円以下でも適用できず、海外に住んでいる家族も対象から外れます。
定額減税の調整給付金とは
定額減税調整給付金は、定額減税を差し引くことができない額が生じる方を対象にした制度です。
定額減税は所得税・住民税から控除する制度なので、納めている所得税・住民税の額が少ない場合、全額を控除しきれないケースも想定されますが、そのような方々を救済する措置として調整給付金が支給されることになっています。
所得税・住民税の納税額が少ない方(無い方)でも、算出される定額減税額分の恩恵を享受できるよう対策が施されている一方、自治体ごとに独自の給付要件を設けている場合がありますので、詳細はお住まいの自治体HP等でご確認ください。
定額減税の実施される回数
本記事を執筆時点において定額減税が実施されるのは、令和6年分の所得税および令和6年度の住民税のみとなっています。
しかし、税制改正大綱では「今後、賃金、物価等の状況を勘案し、必要があると認めるときは、所要の家計支援の措置を検討する」との記載があるので、令和7年分以降の所得税・住民税にも適用される可能性は残っています。
対象期間が延長するとなれば大きな話題になると思いますが、要件や控除額が変更することも考えられますので、延長が決まったときに再度要件等をチェックしてください。