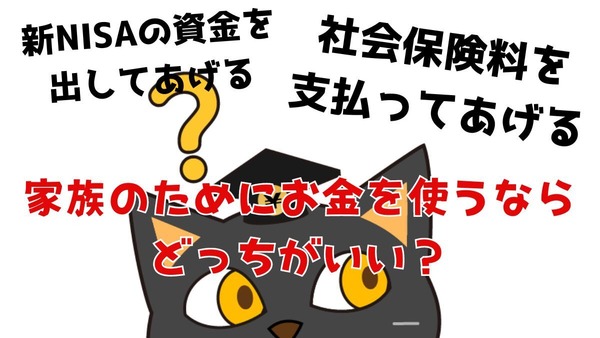「親が土地を提供してくれる」というが、その場所が、夫婦二人にとって、ベストな場所かどうなのかが問題となります。
例えば、それぞれが働きに行く場所への利便性の問題があります。また車がおけるのか。
いずれかの親の土地に家を建てる場合。
親の土地の敷地内なのか、近隣の土地となるのか、調整区域の土地に分家住宅の場合なら「許可基準」の問題もあります。

親の土地なら、土地代金が不要
メリットは、土地代金が不要となる事です。
夫婦二人で借入できる金額には、当然ながら限度があり。
その中での資金計画が、建物のみでいいわけです。これは大きなメリットです。
ところが、夫婦のいずれかの親の近くで生活することは、実際、お互い気持ちの上で大変なことです。
親子も、その子が結婚することで、関係性も難しくなります。
ましてや、子の配偶者も近くに居住するわけですから、一人一人が、どんないい人でも、毎日のことは大変で、トラブルが発生して当然な訳です。
もちろん、近くに居住しているだけに、「小さな子の面倒を親が見てくれる(かも)」など、夫婦にとってありがたいことではあります。
これも限度を過ぎれば、関係性にヒビができます。
親の土地であれば、その土地の利用方法について口も出るかもしれません。
土地の購入は難しい
土地購入するということは、物を買うのと違い、選択肢が限られてきます。
土地の金額だけではなく、自分が希望する場所、面積、形状の「売り物件」を探さないといけないわけです。
すべて希望通りのものがあるとは限りません。
近隣に難しい人が住んでいるかもしれません。
住環境も、朝昼晩と現地に足を運ばないと本当のことは分かりません。
購入土地の履歴も大切
検討している土地の登記簿謄本の取得は大切です。
その土地をどんな人が所有していてどこで借入いていたのか、地目の変更、分筆の有無(その原因)も、確認してください。その土地との相性もあるかと思います。
親からの資金援助を受けられるなら
住宅取得資金については、上限1,000万円(耐震、省エネ等条件あり)まで、非課税で贈与が受けられます。
これは、受ける人別の上限金額であるため、夫の親から1,000万円、妻の親から1,000万と贈与を受けて2,000万円を無税で資金調達も可能です。
もっとも、双方の親に、それなりのゆとりがあればの話です。
さらに、親にゆとりがあれば、今年から改正された相続時精算課税制度を利用し、資金援助を受ければ、2,500万円+110万円(基礎控除)までなら贈与時には贈与税がかかりません。
ただし、相続が発生した時にその贈与分(基礎控除110万円除き)を加算して相続税を計算することになります。
贈与をするとさまざまな問題を残す
一人の子にのみに資金援助していると、相続発生時に、他のきょうだいから、その贈与分を相続で調整したいと申し出される可能性があります。
住宅取得資金の非課税贈与は、相続税申告には、反映されませんが、非課税の適用時には、税務署に申告が必要で資料も残ります。
他のきょうだいをごまかそうとすると、余計にこじれることになりかねません。
もし離婚した時の財産分与は
結婚後に取得(購入)した住宅は、夫婦の一方の名義になっていても、夫婦の共有財産とみなされ、その夫婦がその後、離婚することになった場合は、原則、財産分与の対象になります。
問題は、住宅資金の内訳です。
まず、土地が、夫婦名義ではなく、いずれかの親等(夫婦以外)の名義等であれば、当然ながら、その土地は、財産分与の対象にはなりません。
注意したいのは、住宅資金の中に、それぞれの親から贈与、相続で取得したものがあった場合、その部分は、特有財産として、財産分与から除かれる訳です。
この辺り、住宅資金の内訳について、夫婦で整理、共有して整理しておくこと、そんなリスクに対する備えとして必要かもしれません。