
騒動を機に制度の動きを理解する あるフリーアナウンサーがブログで、人工透析の患者に対して「自業自得の」とした上で、過激な表現で中傷したことで猛烈な批判を浴びることになり、出演していたテレビ番組を全て降板する事態にまで発展

住民税の税額や所得をもとに、福祉制度の給付金等が左右されるのですが、所得に関しては制度ごとに判定する所得が異なります。また世帯員の所得を合算して判定することもあります。 基準となる所得について 基準となる所得がいくつもあ

国民健康保険料(自治体によっては国民健康保険税)は、多くの自治体では住民税といっしょに6月頃に金額が決まって納付書が送られてきます。 この保険料(税)、計算方法から言って払う側がうまくコントロールすることも可能です。特に

60歳から完全にリタイアして年金を繰上げ受給するというのなら話は単純です。これが働きながら、かつ繰上げ受給する場合は、本当にそれでいいのか考える必要があります。 働きながらですと年金が減らされたり、さらに雇用保険から給付

国の制度である公的年金は支給開始年齢の引き上げも議論され、これを補完する位置づけにある生命保険会社の個人年金保険を薦められた経験はあるかもしれません。 しかし公的年金を補完する年金であれば、節税の観点からもう少しお得なも

厚生年金をもらいながら働いていたのに、 「平成28年10月から社会保険の対象者となりそうで、そうしたら厚生年金まで減らされそうだ…」 そういう方もいらっしゃるようです。 社会保険料が給与から天引きされた挙句、年金まで減ら

平成28年10月からの、パートも社会保険に加入することになる、手取りが大きく減ってしまう…という、一種の騒動にもなっています。 ではこの制度変更に対して、どのように対処していけばいいのでしょうか? 簡単にいえば、 ・ も
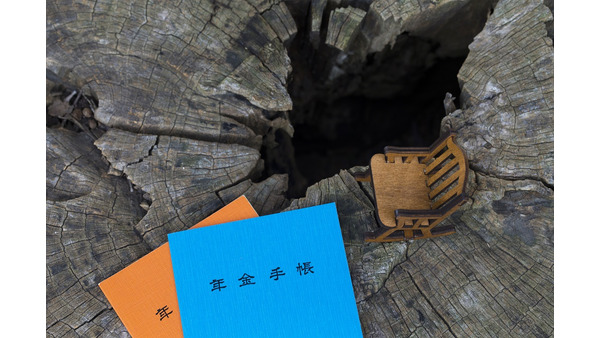
健康保険の料率は労使併せて10%前後、厚生年金の料率に至っては15%弱と、企業・労働者どちらにとっても社会保険料は大変な負担になっています。 昨今、社会保険料の削減がコスト削減の有効策になっていますが、落とし穴もあるので

日本は国民皆保険制度があるとはいえ、大病を患ったりするとどうしても医療費がかかってくることがあります。 「でも医療費が戻ってくるよ」なんて話を聞いたことがあるかもしれません。確かにそういう制度がありますが、その「制度」と