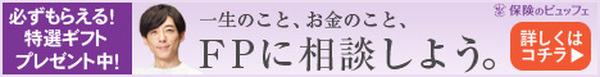最近子どもが生まれ、初めての出産ということで、人生のこと、お金のことなどについて見直すいい機会となりました。
そんな私が改めて考えた、子どもと保険についてまとめました。

目次
子どものために必要な保障とは?

まずは、子どもにとって必要な保障、つまり子どもが成長していく過程で起こり得るさまざまな経済リスクについて考えてみましょう。
子どもの死亡保障
生まれたばかりの子どもを前に考えたくないですが、子どもが死亡した場合に経済的損失が生じる場合は加入の検討が必要です(子どもが家計を支えている場合など)。
しかし、そんなケースはかなり特殊でしょう。
年齢が小さいうちに加入すれば年間の保険料額が安く済むというメリットはありますが、基本的に保障は必要ないため、保険料をオムツ代等に充てる方が賢明だと思います。
子どもの医療保障
子どもは体調を崩したり、ケガをしたりすることが大人よりも頻繁にあるので必要だと感じるかもしれませんが、医療保険についても我が家では不要だと結論付けました。
子どもの医療保険が不要と考える理由1:医療費助成制度がある
すべての都道府県・市町村で、子どもに対する医療費の助成が行われています。
私の住む自治体でも、中学3年生まで入院1日・通院1回あたりの自己負担額は200円、調剤は無料となっており、決して大きな負担ではありません。
(東京23区では中学3年生まで全額助成されるようです。)
自治体によって助成を受けられる子どもの年齢、自己負担額、所得制限の有無などは異なります。
遠方にしか病院がなく交通費がかかる、病気になったときに付き添いをする親の収入が減るといった事情があればそれらも加味し、お住いの自治体の制度を確認の上で、医療保険の必要性をそれぞれ考えてみてください。
子どもの医療保険が不要と考える理由2:入院のリスクは低い
抵抗力の低い子どもは、さまざまな病気にかかるリスクがあります。
また、外で元気に遊ぶことの多い子どもは怪我をすることも多いでしょう。
しかし、いずれも外来で治療をするケースがほとんどです。
事実、厚生労働省が発表する平成29年(2017)患者調査の概況によると、外来の受療率(10万人あたりの受療者数)は1~4歳で6,517、5~9歳で4,377と高い水準です。
一方、入院は1~4歳で169、5~9歳で86とかなり低い数字を示しています(全年代の総数は1,036)。
医療保険は入院した場合に給付金を受け取れる保険ですから、必要となる確率は決して高くないと言えるでしょう。
子どもの医療保険が不要と考える理由3:重い病気になっても手厚い福祉制度がある
医療費助成制度の他にも以下のような福祉制度があり、重い病気を抱えた子どもに対してはさまざまな助成が用意されています。
・特別児童扶養手当:精神又は身体に障害を有する児童に対し、支給される手当。1級は月額5万2,200円、2級は月額3万4,770円。対象は20歳未満。
・障害児童福祉手当:重度障害児に対し、支給される手当。月額1万4,650円で、20歳未満が対象。
・小児がん交通費等補助金制度:がんの診断・入院治療(治験含む)のため、自宅から120km以上離れている病院へ通う場合の交通費及び宿泊費を補助する制度。
親の保障

子どもに何かあった場合の保障よりも、親である私たち自身の保障こそこれまで以上に重要だと思います。
将来の経済状況や健康状態などが不確かな中、人ひとりを育て上げることは、それだけ大変なことだからです。
学資保険
学資保険は、子どもの教育資金を準備するための貯蓄型の保険ですが、親である契約者が亡くなったり高度障害状態になった場合、以後の保険料の払い込みが免除となるという特長があります。
貯蓄と保障の両面を備えており、親に万一のことがあっても子どもの教育費用を準備できる心強い存在だと言えるでしょう。
収入保障保険
子どもを育てる上での大きな支出は教育に関するものですが、それ以外に日々の生活費も必要です。
契約者が死亡または高度障害状態になったとき、遺族に年金形式で保険金が支払われる収入保障保険は、子どもを含む遺された家族の生活を金銭的に支えてくれるでしょう。
ただし、死亡した場合は公的年金から遺族年金が支払われる可能性があります。
万一死亡した場合の生活費を試算し、支払われる年金額を差し引いた上で、必要な保障額を考えてください。
所得補償保険・就業不能保険
親にとってのリスクは死亡や高度障害状態だけではありません。
病気やケガなどで働けなくなり収入が減少した場合も、子どもの生活に大きな影響を及ぼします。
そういったリスクに備えるには、所得補償保険や就業不能保険が有効です。
(ただし、妊娠・出産を理由に働けない場合は保障(補償)の対象になりません。)
他人に対する補償
「自転車で人にぶつかって怪我をさせてしまった…」
遊び盛りの子どもには十分起こりうることです。
が、子どもがやったことだからといって賠償責任がないわけではありません。
万一第三者の命を奪ってしまったら、親に億単位の賠償責任が生じるおそれもあるのです。
このような事態に備えるためには、個人賠償責任保険が有効です。
この保険は、日常生活での偶発的な事故により、第三者に怪我を負わせたり財産を毀損させたりした場合の、法律上の損害賠償責任を補償するものです。
個人賠償責任保険は、単独で加入する方法の他、クレジットカードの付帯サービスや自動車保険・火災保険の特約として付加する方法があります。
その他子どもが生まれたらチェックしたいこと

すでに入っている保険についても、万一のときに役立つかどうか改めて確かめておきましょう。
現在の保障で十分か
子どもが生まれる前から入っている保険があれば、保障の内容と金額が十分であるかを確かめましょう。
子がいないなら、夫(または妻)が万一亡くなっても妻(または夫)が働いて生計を立てることができるかもしれませんが、子どもがいてさらに小さいうちは難しいおそれがあります。
そういったことを踏まえ、保障の上乗せが必要なら、必要な期間だけ定期保険などで補うのもおすすめです。
保険金受取人は適切か
独身時代から加入している保険、定期的な見直しをしていますか?
保険金受取人が親になったまま…といったことも考えられます。
何かあったときに子どもと配偶者に保険を役立てられるよう、名義が適切かどうかは定期的に確認してください。
子どものために出来る限り不安を取り除こう
子どもが生まれたら検討したい保険に関するさまざまなことを列挙しました。
個々の置かれる状況によってそれぞれの保険の必要性は変わりますので、参考にしてみてくださいね。
親になって改めて、自分の健康や経済状態が良好であることの大切さを感じました。
しかし、突然不慮の事故に巻き込まれたり病に襲われたりするおそれは誰にでもあり、心配は尽きません。
お金が全てではありませんが、お金が重要であることも確かです。
子どもが伸び伸びと遊んで学び、好きなことに存分に打ち込めるよう、できる限り不安は取り除きましょう。(執筆者:近藤 あやこ)