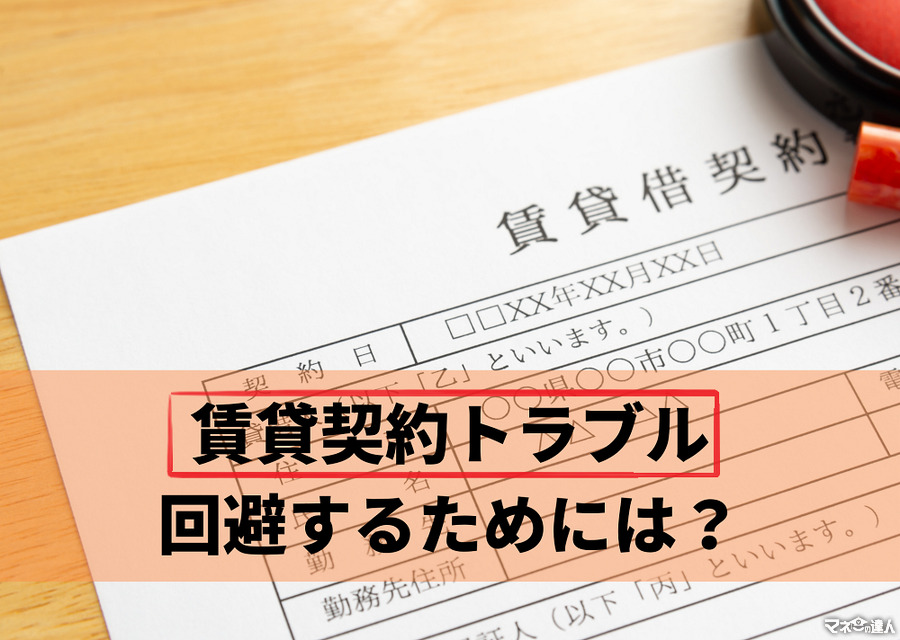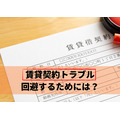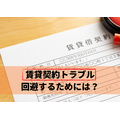賃貸物件を利用する場合に、オーナーの方が所有する物件を使用する「賃貸借契約」を結ぶことになります。
賃貸物件で懸念されるのは、
・ 退去時における原状回復の範囲・内容に関するトラブル
です。
今回は賃貸物件を利用する時に気を付けたいポイントについて解説していきたいと思います。
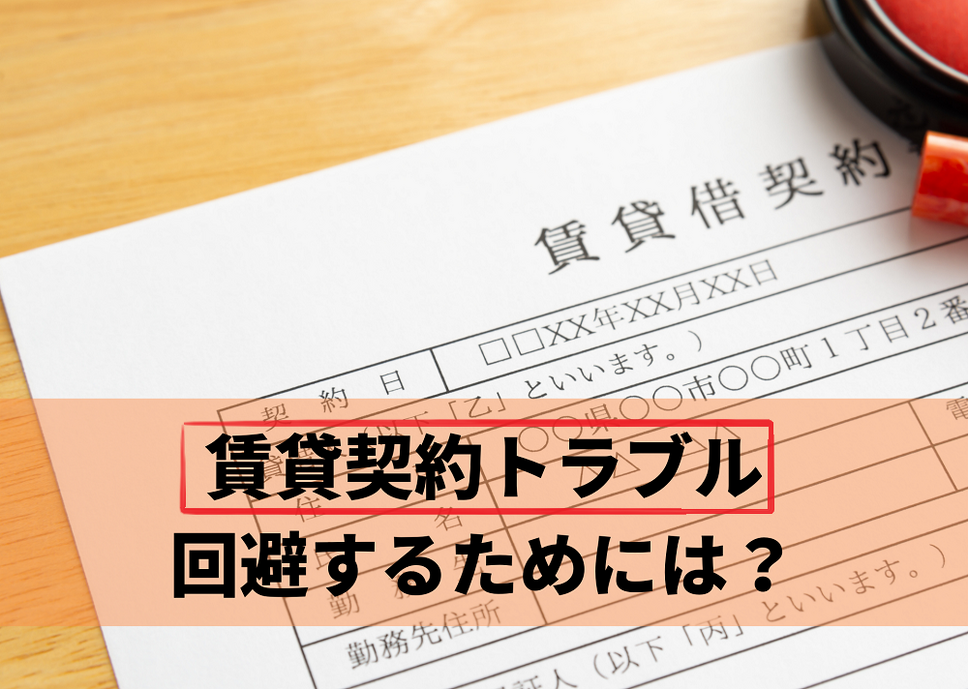
目次
賃料の値上げなどの契約更新に関するトラブル
契約更新時に、管理会社の委託費や周辺の家賃相場が変動したなどの理由で管理費や家賃などの値上げを求められるケースがあります。
賃借人はこうした要求にどの程度応じる必要があるのでしょうか?
賃貸借契約の契約や変更に際し、オーナーは原則として自由に契約内容を定めることができますが、実際に契約するかや変更を認めるかは双方の合意があって成立します。
このため、こうした要求に関してもオーナー側に正当事由が無い場合は賃借人は拒否もできます。
そして、契約変更について応じなかったとしても賃貸物件を明け渡す必要はなく、「法定更新」を用いれば現在の契約内容と同一の内容で賃貸契約を更新することができます。
賃貸借契約の内容は原則として自由に定めることができますが、条文より優先される「強行規定」という決まりがあります。
賃貸借契約における強行規定は、
・ 立退料などを請求しない
・ オーナーの要求によっていつでも賃貸借契約を解除できる
などの賃借人おいて不利な特約が無効とされています。
しかし、無効と知らずに契約してしまい実際にその条文を履行してしまった場合、契約の無効をさかのぼって主張することはできません。
契約更新の際に付け加えられている場合もありますので、契約更新時は現在の契約内容と更新後の内容をしっかりと見比べて契約内容の変更点の把握を行いましょう。
原状回復に関するトラブル
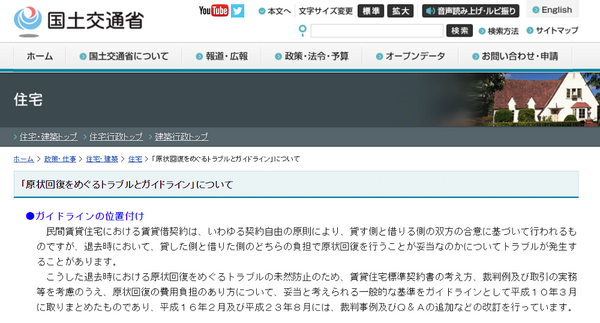
退去時の原状回復に関するトラブルの増加を受けて、国交省は「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を策定しました。
このガイドラインにより、原状回復の範囲とオーナーと賃借人の費用負担の責任範囲の目安が示されました。
しかし、ガイドラインはあくまでも双方の主張が合意できない場合に用いる交渉のための指針であり、基本的には入居時に契約した賃貸契約の契約内容に沿った履行が求められます。
原状回復の問題は退去時ではなく入居時から始まるものと考え、ガイドラインを過信せず、契約前に原状回復の範囲の内容をしっかりと確認してから契約を行うようにしましょう。
契約内容をよく理解しトラブルを防止しよう
賃貸借契約は知識差もあり、無効と知りつつ契約書の中に盛り込み、賃借人が任意に履行してしまうことを期待するケースもあります。
賃貸借契約においては直接的な取り締まりルールが整備されていないため、話し合いによる解決が基本となります。
契約内容を把握しトラブルを未然に防ぐことが大切です。
しかし残念ながらトラブルに至ってしまった場合は、不動産仲介会社や消費者センター、地方公共団体などに相談を行い解決のための方策を提案してもらうようにしましょう。(執筆者:菊原 浩司)