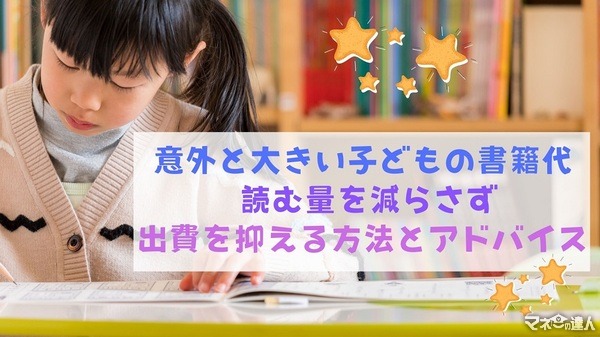子どもが本に興味を持ってくれることは、親にとってうれしいことですが、本好きな子どもは読むスピードが速い傾向があり、新しい本を買ってもすぐに読み終えてしまいます。
しかも、本は高額です。
子ども向けの文庫本でも1冊700円前後、カラーの印刷が入った本は1,500円程度するものが多いでしょう。
親は「ゲームではなく本だから」と思って買いますが、正直、月に数冊買えば数千円から1万円以上になり家計に与える影響も大きくなります。
今回は、子どもの読書量を減らさずに書籍代を抑えるコツを紹介します。
目次
書籍代を抑える王道の方法とアドバイス

大人や子どもに関わらず、書籍代を節約するならば、図書館の利用や古本の活用が王道です。
しかし、図書館が自宅近くにあればいいのですが、遠ければ親が一緒に行く必要があり、なかなか時間がとれない可能性もあります。
人気の本は借りたい人も多く予約の必要が出てきます。
子どもは自分が読みたいと思ったときに手に取らなければ、待っている間に読む気を失ってしまうことが多いです。
図書館を上手に利用するならば、目当ての本を探しに行くよりも、図書館の中を歩きながら自分の興味を惹く本との出会いの場として利用するといいでしょう。
実際に借りて読んだ後に「借りるのではなく欲しい」と思ったならば、フリマサイトなどで探して購入する方法が1番出費を抑えられます。
古本は思わぬ落とし穴も
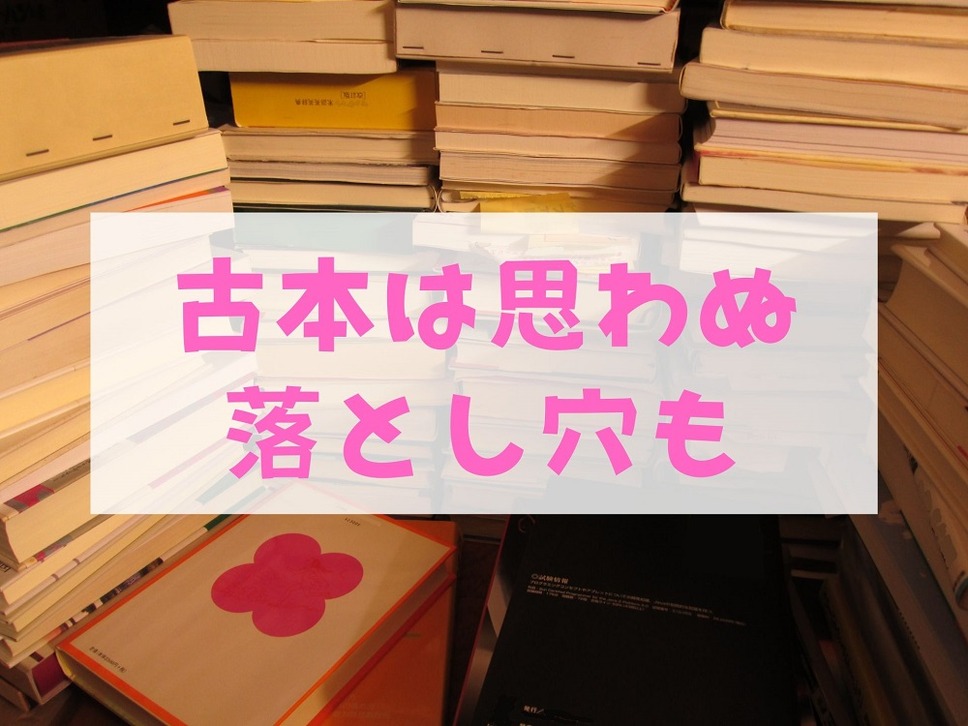
大手古本チェーン店に行くと、大きな書店と同じくらいの品ぞろえがあります。
人気の子ども向けの本は長年売られていることが多く、古本もたくさん流通していますが、古本はすべてが大幅に安くなっているわけではありません。
需要がある本は定価よりも数百円安くなっているだけで、「これしか安くないのなら新品で買った方がいい」と思うこともよくあります。
古本を上手に活用するコツは、「バラ売りではなくセット購入すること」です。
セット売りされているものはバラ売りよりもお得な価格設定になっていることがあります。
セット購入するときの注意点
セット購入には、全巻セットと欠けている巻があるセットの2種類があります。
同じセット購入でも、全巻そろっているセットと欠けている巻があるセットとでは1冊当たりの値段が大幅に違うからです。
1冊足りなくても全巻セットにはならないため、そのセットの値段は低く設定されます。
つまり、全巻そろっていなくても読めるシリーズや欠けている巻をすでに持っているようならば、全巻セットにこだわらずに探したほうがお得になるのです。
どんなに安くても古本がNGな本
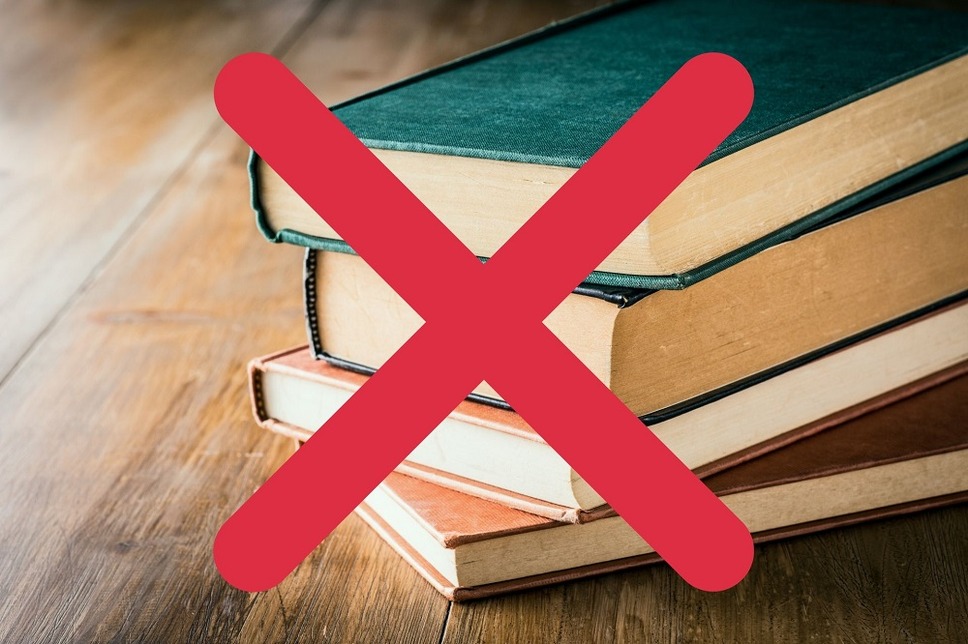
どんなに安くても、古本で探さない方がいい本もあります。
それは、資格試験や参考書類です。
学校受験や資格試験は年々変化します。
古本で安く勉強していても、情報が古く意味のない範囲を勉強してしまっては、せっかくの勉強時間が水の泡です。
子どもが勉強に関する本や資格情報を集めているならば、金額のことは二の次にして新品購入したほうが結果的にはお得かもしれません。
活字好きなら「小学生新聞・中高生新聞」
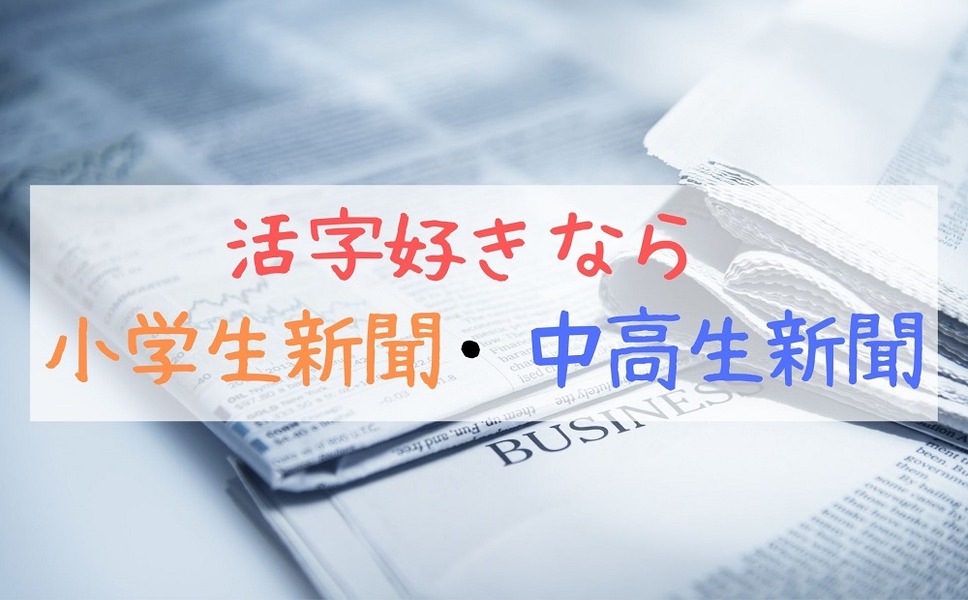
ジャンルを問わず本を読む子どもならいいのですが、親が本を選んで購入し、その中から気に入ったものを選んで読む子どもも多いのではないでしょうか。
そうすると、せっかく親が本を買っても、子どもは興味がわかずに放置される本が出てきます。
放置される本の出費は、ムダな出費です。
好きなジャンルや興味を持つ本がわかりにくい子どもや、とにかく読むことが好きで本を買う機会が多い場合は、本という形にこだわらないのもひとつの手段です。
たとえば、活字の多い小学生新聞や中高生新聞を読むというのもおすすめです。
「小学生新聞」や「中学生新聞」がおすすめの理由
小学生新聞や中学生新聞は、週刊と日刊があります。
取り上げられるジャンルも幅広いため、今まで知らなったジャンルや親も知らなかったジャンルとの接点になる可能性があります。
しかも、週刊は月900円程度、日刊でも1,600円前後のため本を何冊か買うよりもずっと節約になります。
中高生になると視野や世界が広くなり、親も本人もどのような本を読んだらいいのか「本の選び方」が難しくなります。
そのようなときは、読売中高生新聞に掲載されている「ほんのレストラン」で、紹介されているおすすめ本を参考にすれば、効率よく買う本を選べるでしょう。
書籍代を上手に抑えて価値ある出費を

子どもの書籍代は教育費の一部として考え、惜しまずに出費する親もたくさんいます。
たしかに子どもの頃に読んだ1冊の本が人生を変えたり、お金にはかえられない知識を与えたりすることもあるでしょうが、1冊数百円から数千円の出費という「現実」があります。
同じ出費をするならば少しでも価値のある出費をしたいものです。
2,000円の服は買って消費すればその2,000円の価値は終わります。
しかし、2,000円の本は、本を捨ててしまった後も、知識や用法は一生頭の中に残り、人生の糧になることがあります。
子どもの糧になるような本を上手に選んで上手に購入したいものです。(執筆者:式部 順子)