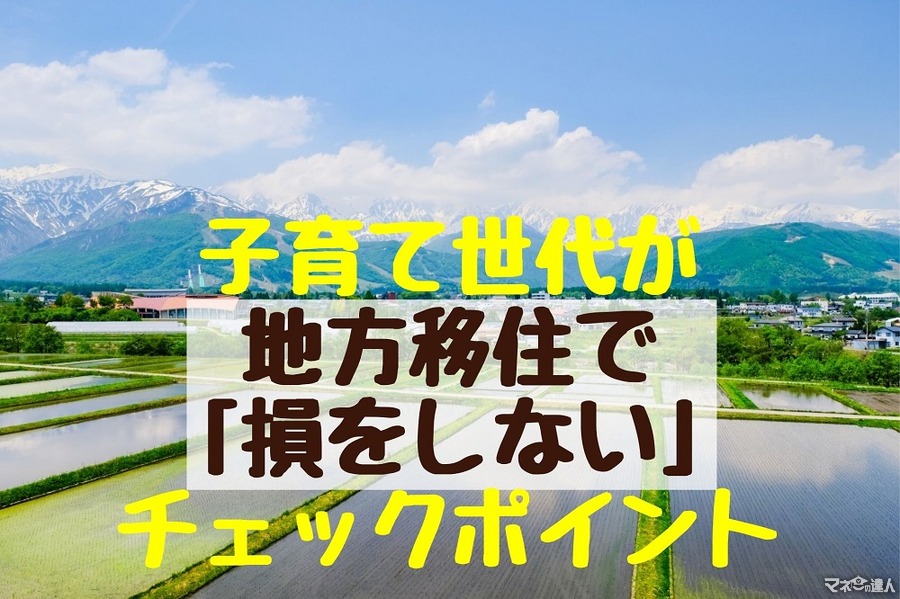少しでも良い環境で子供を育てたいと考える子育て世代を呼び込もうと移住者受け入れに積極的な自治体には、子供の医療費無料や特色ある公立校の魅力を打ち出しているところが多くあります。
地方移住で「子育てしやすい地域かどうか」に注目している人に、自治体の広報だけでは見えない「地方生活で損するポイント」を解説します。
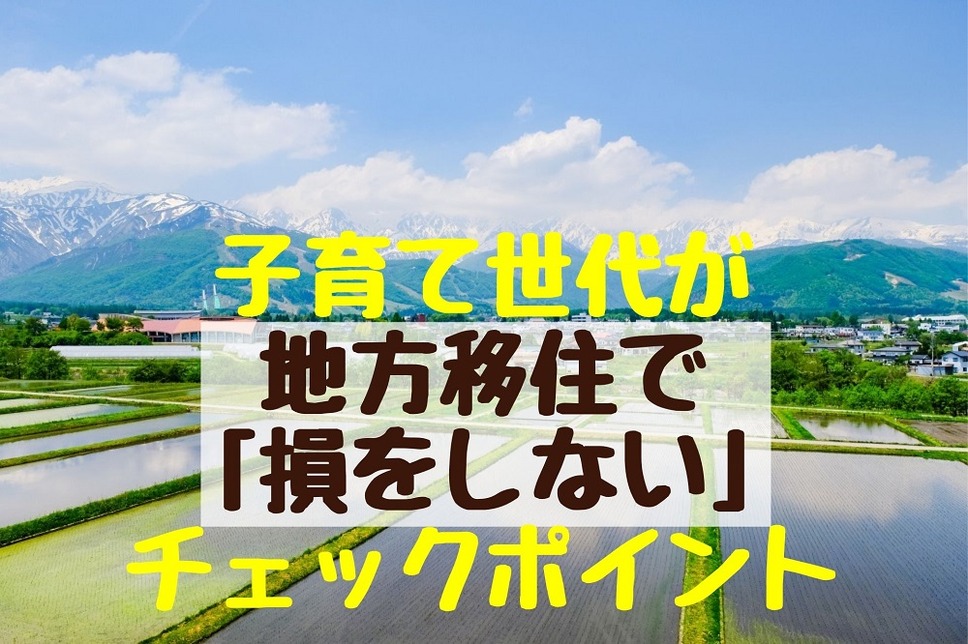
目次
子育て世代の移住チェックポイント:保育園
首都圏に比べると地方では子供の数が少なく、保育園にも入園しやすいと言われています。
しかし、地方でも待機児童が問題になっている自治体は存在します。
子供を保育園に入れたい人は、移住前に自治体のホームページ等で4月時点の待機児童数を確認しておきましょう。
ここで重要なのは、
という点です。
実は、子供が年度初めに保育園に入園できなかったことで、求職中なのに就職をあきらめる親、育休復帰を諦めて退職する親も少なくありません。
そういったケースでは、保育園の入園希望自体を取り下げることになります。
そうなると、5月以降の待機児童数は見かけ上は減少するのです。
直近で待機児童がいなくても年度初めに何人も待機児童が発生していた自治体は、希望すればすぐ保育園に入園できるという環境ではないかもしれません。
子育て世代の移住チェックポイント:小学校・中学校
子育て環境の良さから、自然が多い環境を移住先に選びたい人も多いことでしょう。
しかし、過疎化が進む地域では子供の数が少なすぎて小学校・中学校が閉校になり、子供がスクールバスで別の学区の小学校・中学校に通っている地域も少なくありません。
2017年に文部科学省が発表した資料によると、過去3年間で小学校・中学校の数は1,617校から694校に減少しています。

2015年に文部科学省が発表した「公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引(pdf)」により、国の方針で児童・生徒数が少ない学校の統廃合が行われたためです。
具体的には1学年1学級以下の「クラス替えできない学校」が統廃合の可否を検討するラインとされています。
今後もこの施策は継続されると見られており、移住して子供を通学させている学校が在学中に廃校になってしまう事態もないとは言えないのです。
筆者の地元では、小学校が廃校になってしまったため、他県から移住してきた複数の家族が再び別の地域に出て行ってしまったという事例がありました。
移住費用が無駄になってしまわないよう、田舎の少人数学級でのびのび学ばせたいと考えている親御さんは注意が必要です。
子育て世代の移住チェックポイント:高等学校

子連れ移住で小学校・中学校を気にする親御さんは多いのですが、意外と忘れてしまっているのが高校進学の状況です。
バスや電車といった公共交通網のない離島や中山間地域では、子供が自力で通学できる範囲内に高校がなく、高校進学と同時に下宿や寮に入る子供もいるのです。
また、高校の選択肢が少なく「学力を伸ばしたい」、「スポーツ・芸術などの特技を伸ばしたい」という子供の希望を叶えられない場合もあり、自宅を離れて私立高校の寮に入る子供もいます。
移住先によっては子供が下宿や寮を利用する可能性をふまえて、生活資金を貯蓄する必要があると言えます。
子育て世代の移住チェックポイント:大学進学
子供の大学進学における地方出身者のハンディキャップは想像以上に大きなものです。
子供の希望にもよりますが、首都圏とは異なり地方では自宅から通学できる大学はそれほど多くありません。
2018年度の文部科学省学校基本調査によると全国の平均自県内入学率は42.8%で、大学進学者の5人のうち約3人が県外の大学に進学しています。
鳥取県のように県内の大学に進学する学生が20%以下という地方もあります。

子供が県外の大学に進学してひとり暮らしをする場合には、地方在住の親は仕送りが必要です。
また、子供自身も生活費を稼ぐためにアルバイトをしたり、奨学金を申し込んだりするかもしれません。
このため、地方出身の学生は
・ 卒業時点で奨学金という名の借金を背負う
場合があり、自宅通学をしている学生に比べて学業的にも金銭的にも不利な状況に置かれてしまいます。
また、地元の地方大学に進学したとしても、子供の希望する就職先が地方にないかもしれません。
首都圏に就職活動で何度も上京する場合には交通費や滞在費もかかります。
このようなことから、地方出身者は首都圏在住者より金銭面で不利な状況に陥る傾向にあるのです。
子育て環境の先にある将来も考えたマネープランを組む
子供が育つ環境としては、確かに地方でのびのびと過ごした方がよいと思えるかもしれません。
しかし、子供の年齢が上がるにつれて、進学先や就職先の少なさなどといった地方ならではの問題にぶつかることもあるのです。
移住して地方の良さを満喫するだけではなく、子供の将来にも目を向けてマネープランを組みなおすことも頭に入れておきましょう。(執筆者:久慈 桃子)