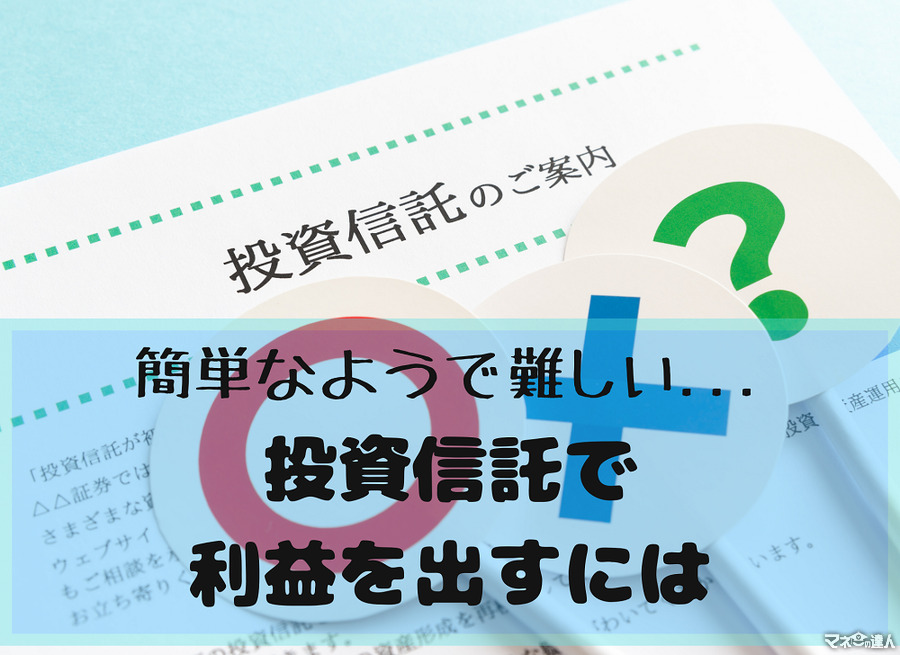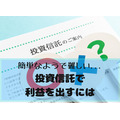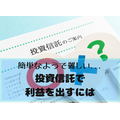投資信託といえば、最低1万円程度から購入できるということで、誰でも手軽にスタートできるという印象があります。
というイメージを持つ方も多いのではないでしょうか。
また、投資信託は、日々の運用はすべてファンドマネージャーにお任せです。
資産配分比率の調整はもちろん、銘柄の選別や売買タイミングの判断まで、運用のほとんどをプロに任せておけます。
しかし、実際に投資信託を利用した方から意見を聞くと、「意外ともうからない…」という声も少なくありません。
プロの運用管理者に任せているはずなのに、どうして投資信託は利益が出にくいのでしょうか。
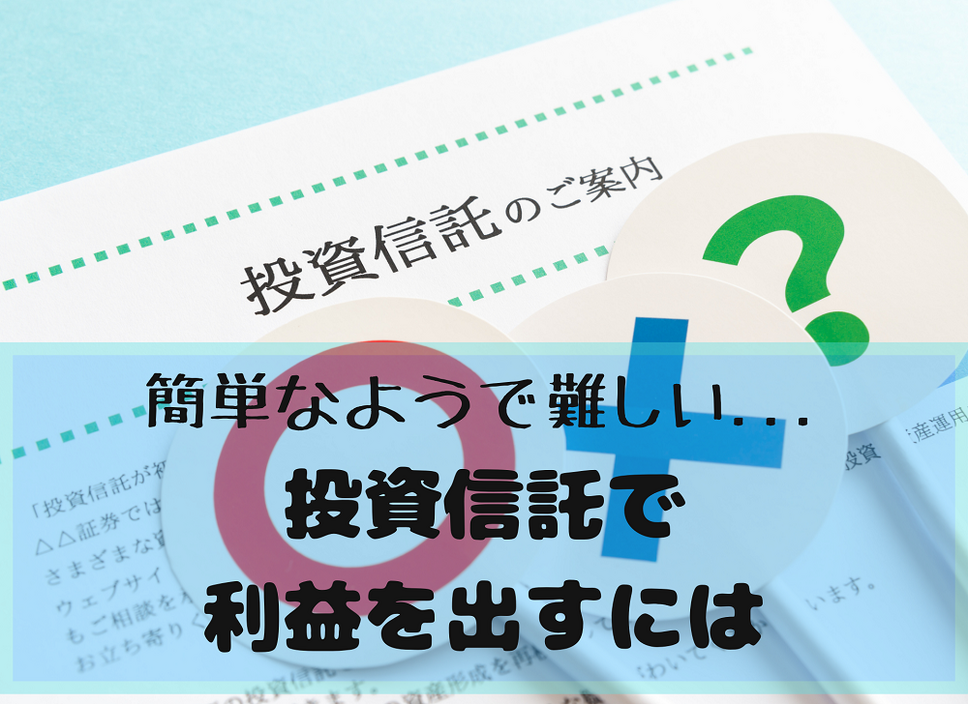
目次
利益を出すには「いくらで」、「どのタイミングで」買うかが重要
実は、投資信託で失敗する人の共通点は、その「買い方」にあります。
「このファンドは人気があるから大丈夫」、「金融のプロに勧められたのだから上がるに決まっている」という判断基準では、決して投資信託で成功することはできないでしょう。
投資信託で利益を上げるには、「いくらで」、「どのタイミングで」買うかが非常に重要です。
いくら運用はプロにお任せでも、この2つを間違ってしまうと損ばかりすることになってしまいます。
この記事では、「いくらで」、「どのタイミングで」買うかという判断基準を詳しくお伝えしていきましょう。
投資信託の判断基準 「基準価額」と「騰落率」
投資信託を買うときの判断基準として、「いくらで」、「どのタイミングで」ということをお伝えしました。
これは、それぞれ「基準価額」と「騰落率」という数値で表すことができます。
両者の基準についてしっかりと理解することで、投資信託を成功に導いていくことが可能です。
判断基準(1) 基準価額
基準価額とは、投資信託の受益権1口あたりの純資産総額のことです。
受益権とは、投資信託によって利益を得る権利のことを表します。
株式投資でいうところの「株券」のようなものです。
投資信託の基準価額を出すには次のような計算式を使います。
つまり、基準価額は、該当する投資信託の資産価値を示しています。
運用中に株式や債券などファンドの資産が増えると、それだけ基準価額も上がりやすいのです。
そして、買ったときの基準価額より売ったときの基準価額が上がっていれば、その分だけ利益(売却益)を受け取ることができます。
投資信託の失敗で多いのは、たとえ定期的に分配金を受け取っていたとしても、この基準価額がどんどん目減りしていき、気付いたときには価値が大きく下がっていたというケースです。
そのため、基準価額を参考にして買うことが何よりも重要となります。
判断基準(2) 騰落率
騰落率(とうらくりつ)とは、一定期間中に基準価額がどれだけ上昇(または下落)したかを示す数字です。
たとえば、騰落率プラス10%なら、その期間で基準価額が1割だけ上昇したということになります。
過去の騰落率を参考にすることで、ある程度の運用成績を知ることができます。
投資信託を選ぶときの重要な判断基準です。
騰落率は統計期間によって成績も異なってくるため、買いのタイミングを決める指標として使えます。
「基準価額」と「騰落率」を参考に自分に適した投資信託を選ぼう

投資信託は、自分なりに正しいと思える判断基準を持つことが成功の秘訣です。
今回は、基準価額と騰落率の2つの判断指標をお伝えしてきました。
基準価額は「いくらで」、騰落率は「どのタイミングで」買うかという重要な基準になります。
いくら配当金を定期的に受け取っていたとしても、基準価額がどんどんマイナスになっていれば利益は期待できません。
そのため、上記2つの指標をもとに、ご自身に最適な投資信託をお選びください。(執筆者:柳本 幸大)