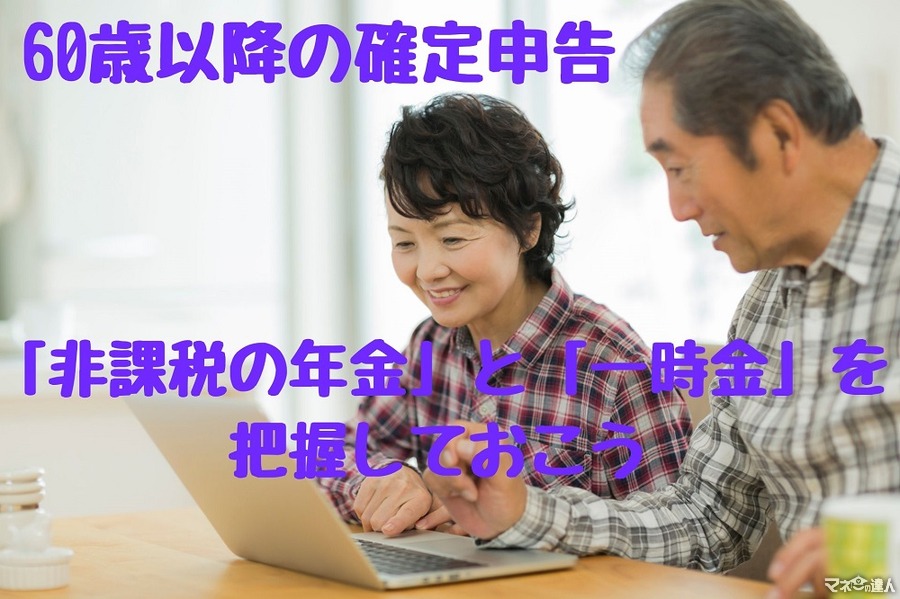60歳以降に公的年金を受給するようになると、確定申告をしなければならない場合があります。
これに負担を感じる方が多いようですが、次のような2つの要件を満たした年金受給者の場合、2011年分以降の所得税については、原則として確定申告をする必要がなくなりました。
(B) 公的年金等以外の所得が20万円以下
その理由として確定申告の負担を減らすために、「年金受給者の確定申告不要制度」が導入されたからです。
確定申告をしたくないという方は、(A)の「公的年金等の収入金額の合計額」や、(B)の「公的年金等以外の所得」の中に含めるものと、含めないものを、分類できるようにしておく必要があります。
この両者の中に含めないものの例として、非課税で受け取れる年金や一時金があります。
これを把握しておくと、確定申告の義務があるか否かを、判別しやすくなるだけでなく、確定申告の書類を作成する際に、収入に含むか否かで迷わなくなると思うのです。
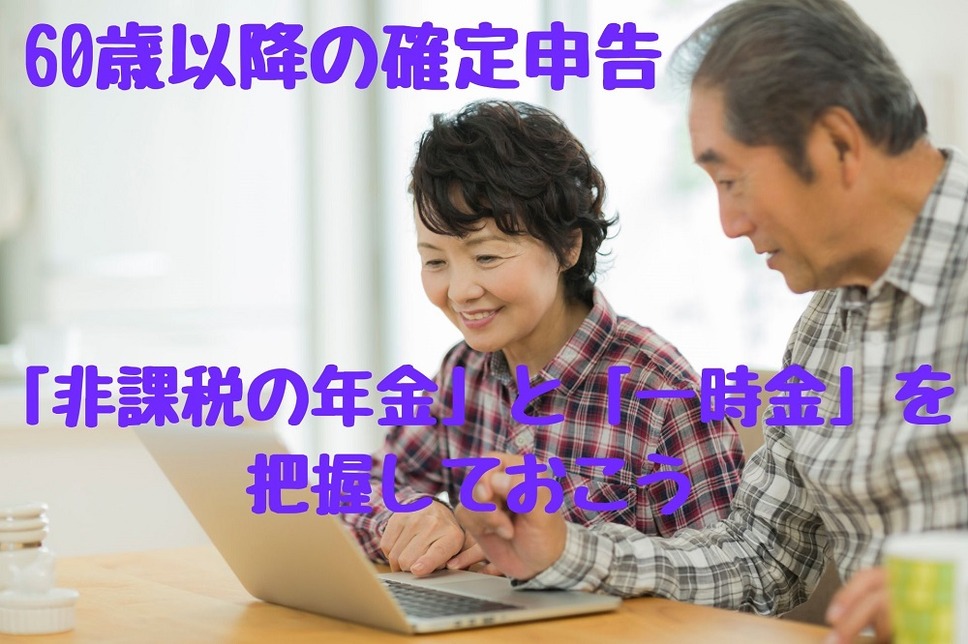
目次
公的年金(一時金)は課税されるものと、非課税になるものがある
会社員として働いていた場合、原則65歳になると国民年金から「老齢基礎年金」が支給され、その上乗せとして厚生年金保険から、「老齢厚生年金」が支給されます。
また1961年(女性は1966年)4月1日以前生まれの場合、60~64歳になると厚生年金保険から、「特別支給の老齢厚生年金」が支給されます。
これらの老齢年金は「公的年金等の雑所得」に該当するため、所得税などが課税されるのです。
それに対して一定の障害状態になった時に、国民年金から支給される「障害基礎年金」、厚生年金保険から支給される「障害厚生年金」、「障害手当金(一時金)」は非課税になります。
また公的年金の加入者などが死亡した時に、国民年金から支給される「遺族基礎年金」、「寡婦年金」、「死亡一時金」、厚生年金保険から支給される「遺族厚生年金」も非課税になります。
ですから(A)の「公的年金等の収入金額の合計額」の中に含めるのは、老齢年金だけであり、かつ(B)の「公的年金等以外の所得」の中には、いずれの年金(一時金)も含めません。
年金生活者支援給付金は公的年金と違って、老齢でも課税されない
2019月10月から低所得の年金受給者を対象にして、月額5,000円を基準にした「年金生活者支援給付金」が支給されますが、これは次のような3種類に分かれているのです。
・ 障害基礎年金の受給者に支給される「障害年金生活者支援給付金」
・ 遺族基礎年金の受給者に支給される「遺族年金生活者支援給付金」
この3つの年金生活者支援給付金は公的年金と同じ口座に、公的年金と同じ支払期月(偶数月)に振り込まれます。
また公的年金と同じように毎年度、物価の変動などに応じて金額が改定されます。
このように年金生活者支援給付金は、公的年金との共通点が多いのですが、いずれの年金生活者支援給付金も非課税という、公的年金との相違点もあるのです。
そのため(A)の「公的年金等の収入金額の合計額」や、(B)の「公的年金等以外の所得」の中に、年金生活者支援給付金を含める必要はありません。

健康保険の現金給付は年金のように、継続して支給されるものがある
健康保険の保険給付は原則的に、保険医療機関や保険薬局などに2~3割の自己負担を支払い、医療サービスを受けるという、「現物給付」になっております。
しかし一部の保険給付は、協会けんぽや組合健保などから現金を受け取るという、「現金給付」になっているのですが、60歳以降の方は主に次のようなものを受給できます。
移送費
緊急時などに移送された場合に、交通費として支給される保険給付です。
療養費
保険証が手元になく、全額自費で診療を受けた場合などは、請求によりその一部が、療養費として払い戻しされます。
埋葬料(埋葬費)
葬儀費用の一部を補助するために、遺族などに対して支給される保険給付です。
傷病手当金
業務外の病気やケガで仕事を休んだ時に、休職前の給与の3分の2程度が、最長で1年6か月に渡って支給される保険給付です。
高額療養費
支払った医療費が高額になり、一定の「自己負担限度額」を超えた場合には、その超えた分が高額療養費として払い戻しされます。
ただ「限度額適用認定証」の交付を受け、それを保険医療機関などに提示すると、自己負担限度額を超える分は支払う必要がなくなるため、高額療養費は現物給付という側面もあるのです。
以上のようになりますが、傷病手当金以外については、国民健康保険や後期高齢者医療にも、同様の保険給付があります。
これらの保険給付は一時金が多いのですが、傷病手当金は支給要件を満たしていれば、公的年金のように継続して支給されます。
ただいずれの保険給付も非課税になるため、(A)の「公的年金等の収入金額の合計額」や、(B)の「公的年金等以外の所得」の中に、含める必要はありません。
なお傷病手当金は公的年金との併給調整があるため、受け取る年金(一時金)の種類によっては、支給停止になる場合があります。
雇用保険の保険給付は非課税になるが、年金との併給調整に注意する
雇用保険に加入する年齢には上限がないため、加入要件を満たしている場合には、何歳になっても加入します。
また雇用保険は健康保険と違って、現金給付が中心になるのですが、60歳以降に受給できる保険給付としては、主に次のようなものがあります。
基本手当、高年齢求職者給付金
65歳より前に失業した時に支給される「基本手当」と、65歳以降に失業した時に支給される「高年齢求職者給付金」の、2種類の保険給付があるのです。
前者を受給するために、ハローワークで求職の申込みをすると、特別支給の老齢厚生年金は支給停止になりますが、後者は老齢厚生年金と併給できるというメリットがあります。
介護休業給付
一定の家族を介護するために介護休業を取得し、給与が支払われなくなった時に、所得保障として支給される保険給付です。
高年齢雇用継続給付
60歳以降の給与が60歳時点と比べて、75%未満に低下した時に、60歳から65歳までの間に支給される保険給付であり、「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」の2種類があります。
いずれの給付金についても、特別支給の老齢厚生年金と併給すると、最高で月給の6%程度に相当する特別支給の老齢厚生年金が、支給停止になってしまうのです。
以上のようになりますが、一時金である高年齢求職者給付金以外については、公的年金のように継続して支給されます。
例えば高年齢雇用継続基本給付金は支給要件を満たしていれば、最長で5年に渡って支給されるのです。
ただいずれの保険給付も非課税になるため、(A)の「公的年金等の収入金額の合計額」や、(B)の「公的年金等以外の所得」の中に、含める必要はありません。(執筆者:社会保険労務士 木村 公司)