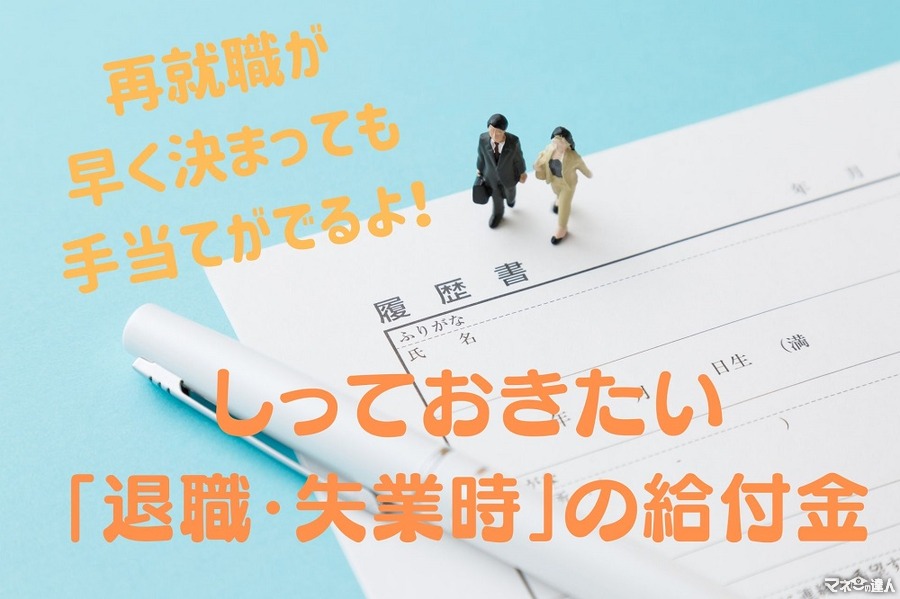失業給付金や再就職手当など、退職や転職の際に知っておきたいのはお金の問題です。
退職する際には、こういったお金に関する知識や段取りを把握しておくことはがとても重要です。
今回は、失業時のお金に関係する手続きや退職前後に気を付けたいポイント、その後の生活をフォローする給付金や手当などについて紹介します。
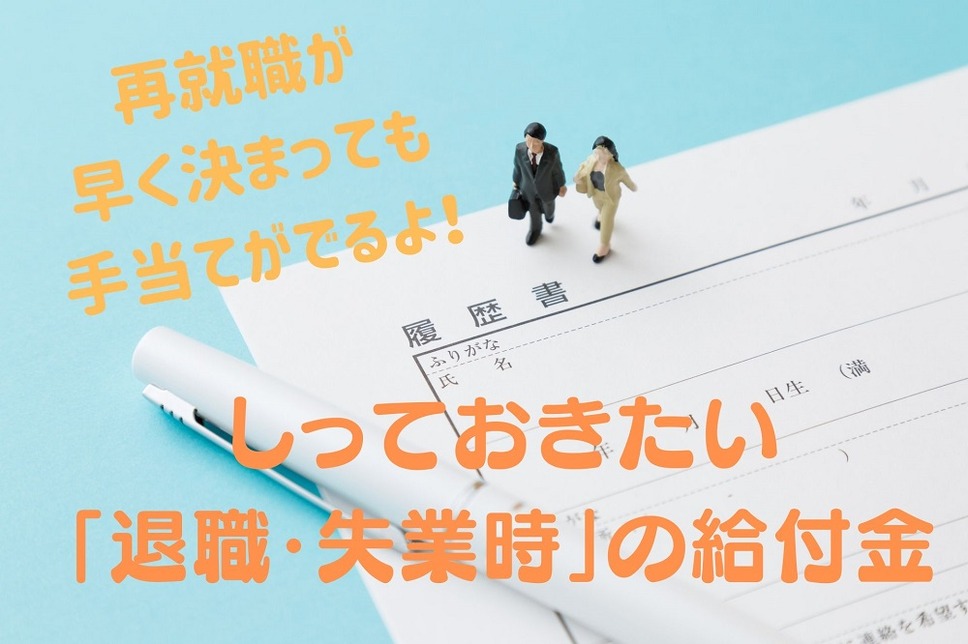
目次
1. 退職後の生活をフォローする「失業給付金(基本手当)」
「失業給付金」とは、働きたいという意思や能力があるにも拘らず、就職先が見つからない状態の人に支給される基本手当のことです。
雇用保険被保険者として離職日からさかのぼって2年間に最低12か月以上働いた期間があることも給付の条件です。
懲戒解雇を除く会社都合による退社の場合は7日間、自己都合による退社は3か月間の待機期間があり、その後まだ転職先が決まっていなければ支給されます。
ハローワークで求職の申し込みを行い、就職の積極的な意思があるにも関わらず失業状態にあること。
離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上あること。
【申請先】
ハローワーク
【必要な書類】
・ 雇用保険被保険者離職票
・ 官公署の発行した写真付きの本人確認書類(運転免許証等)
・ 写真2枚
・ 印鑑
・ 普通預金通帳
・ 個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号記載の住民票のうち1つ)
ここがポイント
失業給付金の金額は退職前6か月の給与を基に算定されるため、あらかじめ退社が分かっている場合にはこの期間にたくさん働いておくと給付額も高くなります。
雇用保険に加入していればパートやアルバイトでも対象です。
2. 再就職のための教育訓練受講費の一部が支給される「教育訓練給付制度」
「教育訓練給付制度」とは、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とし、教育訓練受講に支払った費用の一部が支給される制度です。
「厚生労働大臣の指定」を受けた教育訓練が対象です。
講座には、医療、福祉、介護、土木、建築、農業、電気、服飾、情報通信などさまざまな分野のものがあり、厚生労働省HPの「教育訓練講座検索システム」からも見ることができます。
受講開始日時点で雇用保険の加入期間が通算3年以上(最初の支給は通算1年以上)等一定の要件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)または被保険者であった方(離職者)
【申請先】
住所地のハローワーク
【必要な書類】
・ 教育訓練給付金支給申請書
・ 教育訓練修了証明書
・ 領収書
・ 本人・住所確認書類および個人番号確認書類
・ 返還金明細書
・ 払渡し希望金融機関の通帳またはキャッシュカード、教育関連経費等確認書など

ここがポイント
支給額は教育訓練経費の20%に相当する額(上限は10万円)で、4,000円を超えていない場合には支給されません。
支給申請手続きは、教育訓練修了後1か月以内に本人の住所を管轄するハローワークで行います。
3. 雇用保険を受給できない人も受け取れる「職業訓練受講給付金」
「職業訓練受講給付金」とは、雇用保険を受給できない人が職業訓練と訓練期間中の生活保障のための給付制度です。
医療、介護、福祉、情報技術、電気設備、農林水産業など職業訓練の内容は多岐の分野に亘り、地域のニーズ等も踏まえたものが用意されています。
ハローワークに求職者登録していること。
雇用保険の求職者給付、職業転換給付金の就職促進手当及び訓練手当を受給できない方。
さらに本人月収8万円(世帯月収25万円)以下金融資産が世帯で300 800万円以下、原則すべての訓練日に出席しているなどです。
【申請先】
住所地のハローワーク
【必要な書類】
・ 本人確認書類(所得証明など)
・ ハローワーク所長の受講勧奨通知書または受講推薦通知書
・ 世帯の主たる生計者であることを確認する書類(残高証明など)
・ 年収を確認する書類
・ 世帯の金融資産を確認する書類
・ 住民票
・ 給付金の振込先の通帳のコピー
ここがポイント
「職業訓練受講給付金」の支給額は次の通りです。
10万円/月
4. 再就職が早く決まった場合に受け取れる「再就職手当」
「再就職手当」とは、失業給付金の受給資格を得た後、再就職先が早く決まった場合に受け取れる手当です。
基本手当の支給残日数が所定給付日数の1/3以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就き、支給残日数が所定給付日数の1/3以上ある場合
【申請先】
住所地のハローワーク
【必要な書類】
・ 事業主の署名・捺印が記載された再就職手当支給申請書
・ 雇用保険受給資格者証

ここがポイント
【支給残日数が所定給付日数の1/3以上の場合】
所定給付日数の支給残日数 × 60% × 基本手当日額(就職日が平成29年1月1日前の場合は50%となる)
【支給残日数が所定給付日数の2/3以上の場合】
所定給付日数の支給残日数 × 70% × 基本手当日額(就職日が平成29年1月1日前の場合は60%となる)
※基本手当日額の上限は6,165円(60歳以上65歳未満は4,990円)、毎年8月以降に変更される可能性あり。
このほかにも就業促進手当として、
・「再就職手当」の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合などに受けられる「就業手当」
などもあります(それぞれ一定の要件あり)。
退職する際の注意点
退職が決まれば、会社側からも必要書類や手続等についての指示やアドバイスがあると思いますが、必要なものや退職までの流れについては社会人として把握しておく必要があります。
また、似たような手続きが多くなるため、できるだけこまめにメモを取って不明な点やミスがないよう気を付けるようにしましょう。
退職時に受け取るもの
【離職票】
会社を退社したことを公的に証明する書類。
ハローワークで行う失業給付金の受給手続きや健康保険の被扶養者受給手続きに必要です。
【雇用保険被保険者証】
雇用保険の加入者であることを証明する書類、失業給付金の受給手続きに必要です。
再就職が決まれば新しい会社へ提出する。
【年金手帳】
公的年金に加入していることを証明するもの。
勤務先に預けている場合は返却してもらうことが必要です。
【健康保険資格喪失証明書】
加入していた健康保険被保険者資格を喪失したことを証明する書類です。
退社後に国民健康保険へ加入する際に必要となる。
【源泉徴収票】
退社までの収入や支払った所得税の金額を証明する書類です。
確定申告時、もしくは転職先に提出する。
退職する前に要確認 ここにも気を付けて
・ 社内預金や団体保険の解約
・ 財形貯蓄や確定拠出年金は転職先が決まっていれば引き継ぎ可能なケースもあるが、そうでない場合は解約が必要
・ 賃貸物件への転居、ローンやクレジットカードの申し込みは退社前に契約しておくのがオススメ
・会社員のうちに病院に行っておきましょう。
転職先が決まっている場合には安心ですが、決まってないと退職後は「無職」になってしまいます。
「会社員」という肩書があったからこそスムーズに進められていたことも、無職ではハードルが高くなります。
そういったことまで視野に入れて退職を考えるようにしましょう。
給付金や手当といったものについても把握しておく
退職までの時間を十分に取っていたつもりでも、いざその日が近付いてくるとバタバタしてしまいます。
退職の事情は人それぞれですが、退職に関する手続きをできるだけスムーズに、そしてその後の生活で困らないように、自分が受け取れる給付金や手当といったものについても把握しておくことが大切です。(執筆者:藤 なつき 監修:社会保険労務士 拝野 洋子)