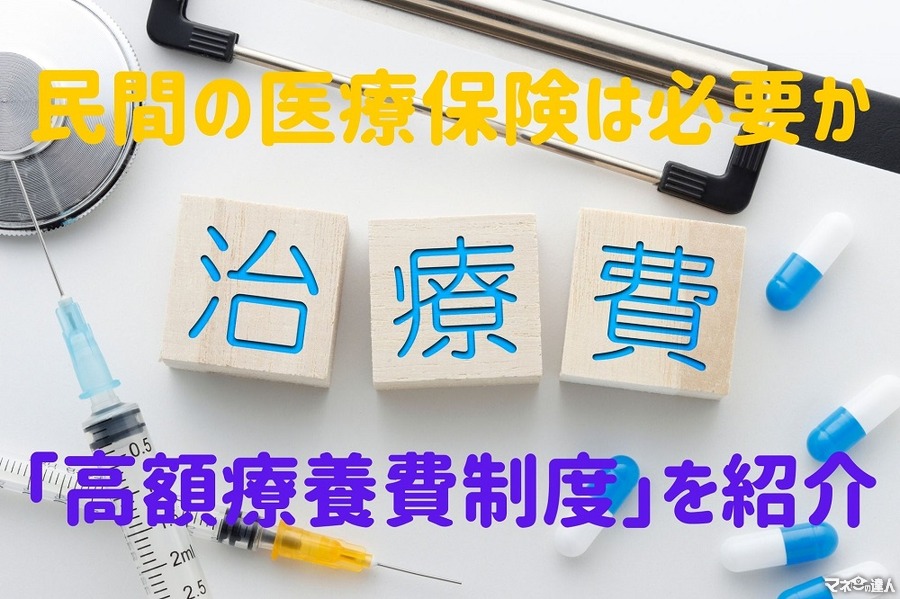民間の医療保険に加入している方は、入院や手術をすると保険会社から保険金が支払われます。
もし、民間の医療保険に加入していないにも関わらず、治療費が思った以上にかかった場合はどうすればいいでしょうか。
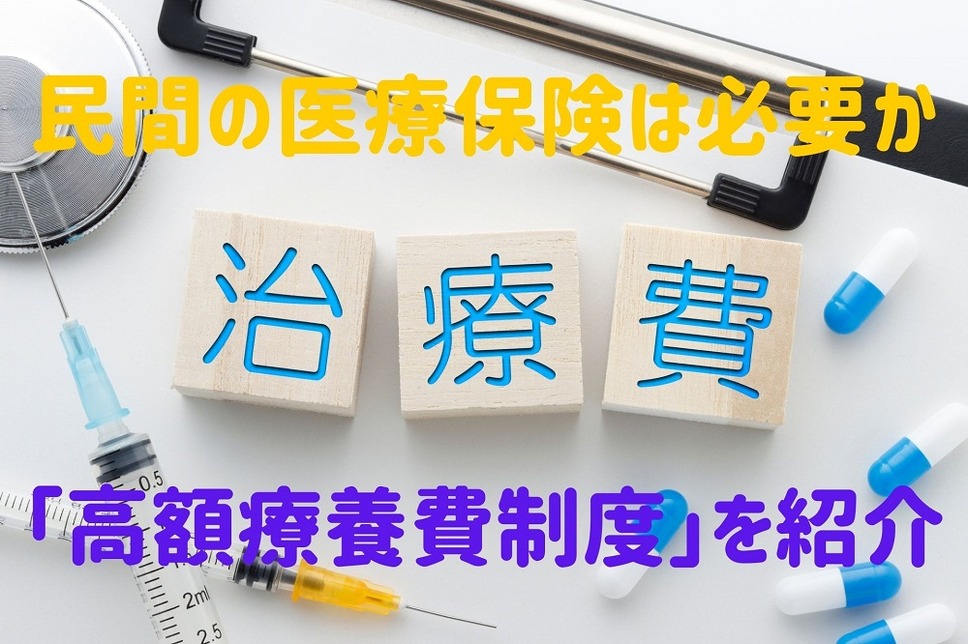
目次
日本の優れた公的医療保険制度 4つの特徴
民間医療保険の加入は任意ですが、公的医療保険は国民全員が加入しています。
これは「国民皆保険制度」と呼ばれ、日本の公的医療保険制度の特徴の1つです。
その他にも、保険料と国庫を主な財源として医療費を負担する「社会保険方式」や、保険証があれば、どの病院でも診察してもらえる「フリーアクセス」も大きな特徴です。
そして、日本のみの制度として「高額療養費制度」があります。
参照:厚生労働省
「高額療養費制度」とは
高額療養費制度とは、病院や薬局での支払額が1か月(月初から月末まで)の上限額を超えた場合、申請すれば、差額を受け取ることができる制度です。
上限額は年齢や所得に応じて違いがあります。
例えば、70歳未満で年収約370万円から770万円の方で、医療費が100万円の場合は、病院窓口での負担額は3割負担30万円です。
高額療養費制度を利用すると、21万2,570円を高額療養費として受けとることができますので、自己負担額は8万7,430円です。
計算式は
です。
なお、入院時の食費や差額ベッド代は高額療養費制度の費用に入れることはできません。
また、70歳未満の方は1つの医療機関で1か月の治療費が2万1,000円以上の場合のみ、高額療養費の計算に入れることができます。
参照:厚生労働省

入院・手術すると実際にはどのくらい費用がかかるか
入院・手術は治療内容や病気、けがの種類によって費用が変わります。
入院時の自己負担平均額は21万円という調査結果があります。
例えば、乳がんの場合、病院窓口での支払い平均額は3割負担で21万4,900円です。
70歳未満で年収約370万円から770万円の方が高額療養費制度を利用すると、自己負担額は8万4,600円です。
同じように、
椎間板ヘルニアの場合は支払い平均額21万9,500円、自己負担額8万4,700円
という計算です。
あくまでも平均額の一例ですが、治療費のみで考えると高額療養費制度でかなり負担が減ることが分かります。
高額療養費制度を利用したい場合
70歳未満で入院までに時間のある方は事前に「限度額適用認定証」を用意すると便利です。
もし、70歳未満の方が健康保険証のみを提示して、入院・手術を行うと、退院時に病院窓口で3割負担の金額を請求されます。
先ほどの椎間板ヘルニアの例を出すと21万9,500円です。
入院時に健康保険証と一緒に「限度額適用認定証」を提示すると、高額療養費制度が適用されます。
ですから病院窓口で支払う額は8万4,700円のみになります。
限度額適用認定証の用意がなくても、申請すれば差額を受け取ることができますが、比較的大きな額をいったん、病院窓口で支払う必要があります。
限度額適用認定証は、加入している健康保険組合や市役所などへ申請すると発行してもらえます。
70歳以上の方は高齢受給者証を病院窓口で提示することによって、高額療養費制度が適用されます。
まずは公的医療保険制度を理解すること
公的医療保険制度の1つ、高額療養費制度を利用すると、治療費の自己負担額を少なくすることができます。
では、民間医療保険の加入は必要ないのかというと、意見が分かれるところです。
まず、収入に対して保険料の割合は現在、どの位なのか確認してみましょう。
もし、安心料として医療保険を長年掛け捨てで支払っているのであれば、年間でどの位の安心料を払っているのか、一度計算をしてみるのもいいかもしれません。
医療費の自己負担を減らす基本は、公的医療保険制度を理解し、上手に利用するところからです。(執筆者:AFP 大川 真理子)