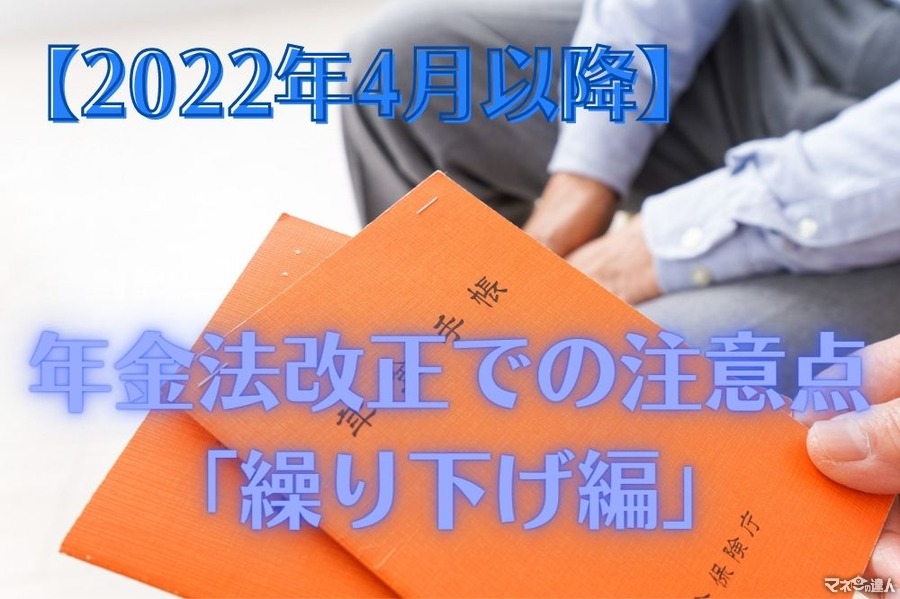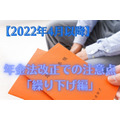2022年4月以降、続々と年金分野における法改正が施行されます。
そのなかでも特におさえておきたい論点をピックアップして解説してまいります。
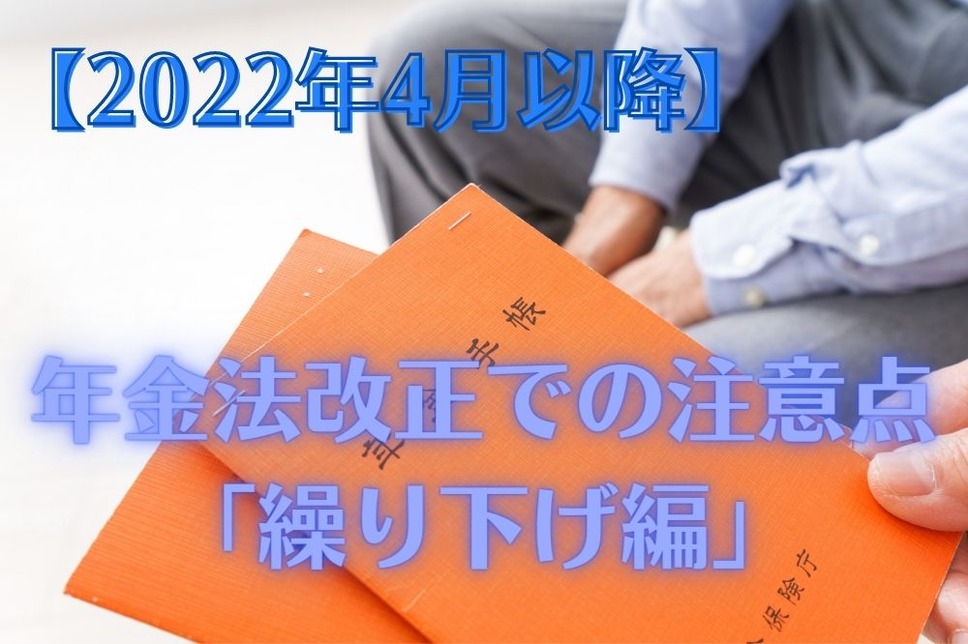
目次
2022年4月から改正 年金繰り下げ
2022年4月から現行では70歳までの繰り下げ上限年齢が75歳に拡大されます。
よって、原則の65歳よりも前から受け取る繰り上げ(上限は60歳)可能期間と合わせると15年間もの間が受給開始時期の選択肢として存在するということになります。
しかし、繰り下げの注意点として、厚生年金の加入可能年齢は70歳までであり、70歳で退職した場合で、かつ、国民年金も厚生年金も両方75歳まで繰り下げた場合、他に収入がない場合は5年間無収入期間が生じてしまうことです。
この間は例えば退職金を生活費に充てるなどの考え方があります。
しかし、繰り下げのメリットの1つである増額率について1か月当たり0.7%の増額率が適用されますが、70歳以上も同じ増額率です。(繰り上げについては2022年4月から1か月あたり0.5%から0.4%に変更)
言うまでもなく年齢を重ねれば重ねるほど死亡リスクは高くなりますが、繰り下げによる増額率は旧来と同じままです。

繰り下げの盲点になりやすい部分
そして、繰り下げの盲点になりやすい部分として他の年金給付を受給できる状態になった場合はその時に繰り下げをしたものとみなすこととなります。
例えば夫が一定額以上の老齢厚生年金を繰り下げてさらに増額させようと「繰り下げ待機中」であった場合に結婚前に数年間パートとして働いたことのある妻が亡くなり、少額の遺族厚生年金が発生した場合を想定しましょう。
まず、65歳以降に老齢厚生年金と遺族厚生年金を両方受給できる場合は自身で現役時代にかけた保険料から受給権の発生する老齢厚生年金を優先的に受給しなければなりません。
その後、老齢厚生年金よりも遺族厚生年金が多額の場合、その差額を受給できるということです。
結果的には少額の遺族厚生年金の請求自体しなかったとしても受給権は発生していることから、その時に繰り下げをしたものとみなされます(以後繰り下げが不可能)。
この点の何が問題かと言うと、繰り下げで増額した年金を受け取ろうと考えていたとしてもその選択肢は取れないということです。
また、繰り下げの場合は実際に請求しなければ、年金の時効は5年間です。
ですから、5年以内であれば65歳当時にさかのぼって請求したものとみなす(当然、その場合増額率は適用されない)という選択肢も残っていましたが、繰り下げしたものとみなされることから、その選択肢も取れないということです。
なお、遺族厚生年金は繰り下げで増額していた方が亡くなった場合や、在職老齢年金で全額支給停止であった方が亡くなったとしても65歳の時の増額等していない「100%の状態」の老齢厚生年金の75%の額となります。
2023年4月から改正 70歳以降に請求する場合の5年前時点で繰り下げ制度
70歳以降に年金を請求し、かつ請求時点において「繰り下げ請求を選択しない」場合に、年金額の算定にあたっては5年前に繰り下げの申し出があったものとして年金を支給するとされています。
65歳から10年後というと健康状態がどのような状態になるかは多くの場合想像がつかないことが多いでしょう。
よって、繰り下げの改正を行ったとしても不透明な状況下では選択が難しくなることからこのような改正が行われると推察します。
想定しておくべきこと
「75歳以降に」繰り下げを行った場合は、75歳に繰り下げ申し出があったものとして年金が支給されます。
年金の繰り下げは75歳まで繰り下げた場合、84%の増額となります。
それ自体はデメリットとは言えませんが、その分所得税が多くなってしまうこと、年金額が増額したがゆえに年金生活者支援給付金が不該当になってしまうことなどは想定しておくべきでしょう。
また、繰り下げを希望する場合は65歳の時に意思を表明するだけでなく、実際に希望する繰り下げ年月以降(最低66歳以後)に請求手続きをする必要があることはおさえておきましょう。(執筆者:社会保険労務士 蓑田 真吾)