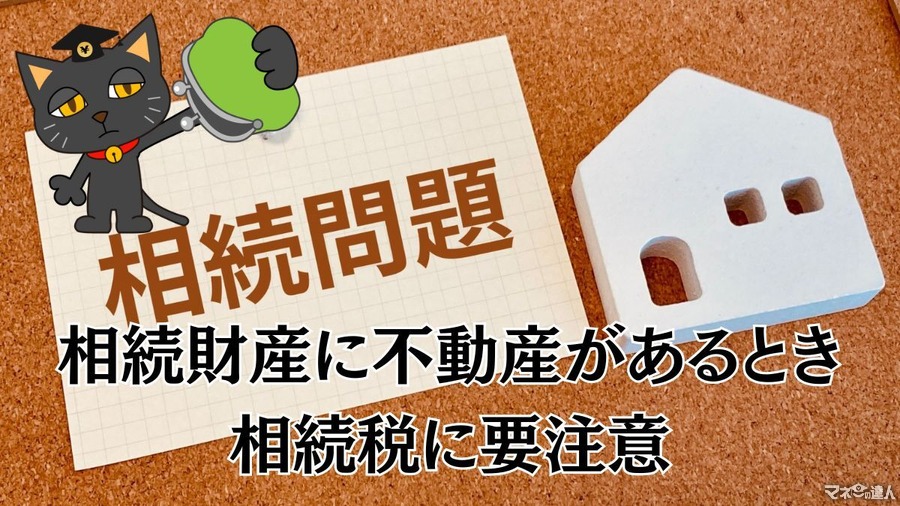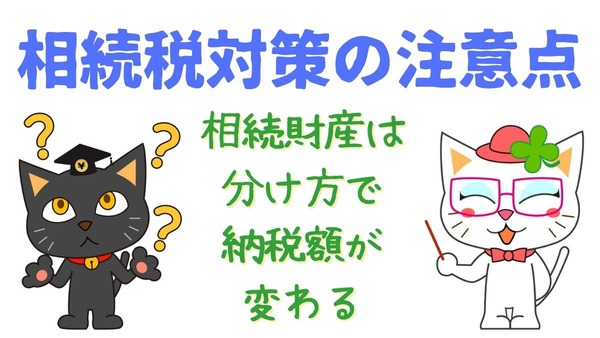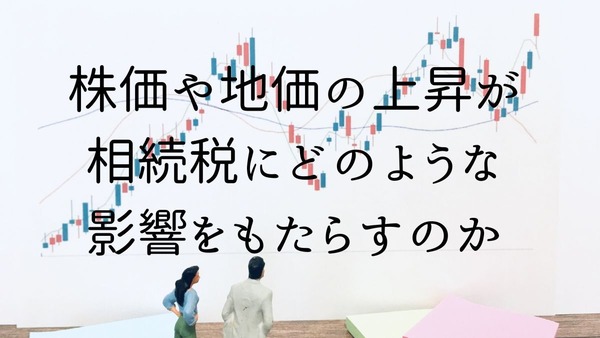相続税は亡くなった人が保有していた財産に対して課される税金なので、相続税の納税額が遺産より大きくなることはありません。
しかし、相続財産の大小にかかわらず、相続税の支払いに困ってしまうケースも存在しますので、今回は相続税の支払いが大変な理由について解説します。

相続税の申告・納税のタイムリミットは10か月
相続税には基礎控除額が設けられており、相続財産の総額が基礎控除額以内に収まる場合は申告は不要です。
一方で、被相続人(亡くなった人)が基礎控除額を超える財産を有していた場合には、期限までに申告手続きをしなければなりません。
相続税の申告期間は、被相続人(亡くなった人)が死亡した日の翌日から10か月以内で、相続税の納期限は申告期限と同日です。
相続税の支払いは原則一括払いとなっていることから、相続人は期限までに納税資金を確保することが求められます。
現金・預貯金以外の相続財産が多いと納税が大変
相続税は現金で納めることになりますが、相続財産は現金・預貯金だけではありません。
相続税の納税申告をしている人の相続財産の内訳として、現金・預貯金等が占める割合は3分の1程度です。
それに対し、現金化が難しい不動産は4割ほどあり、ご家庭によっては相続財産の大半が不動産のケースも珍しくありません。
引き継いだ相続財産の中に相続税を支払える金銭が無かった場合、相続人のお金を納税に充てたり、延納制度や物納制度を活用することが選択肢となります。
延納制度は相続税を分割して支払う方法、
物納制度は不動産など物で相続税を納める方法をいい、
制度を利用できれば納期限までに納税資金を準備できなくても対処できます。
しかし、両制度とも申請・許可制となっており、許可されるケースは限られるため、事前に適用要件や必要書類等を確認しなければなりません。
資産保有額が大きい人ほど相続税の納税額は多くなるため、現金以外の相続財産が占める割合が高いご家庭は、相続税の支払いに苦慮します。

相続税は未分割でも申告・納税が必要
相続人は、相続財産を取得した割合に応じて相続税を納めることになるため、相続人ごとで納税額は変わってきます。
相続税の総額が100万円で相続人が3人の場合、相続財産の6割を相続した人は60万円、4割相続した人は40万円を納めることになり、相続財産を取得しなかった相続人が納める相続税額はゼロです。
一方、相続税は遺産分割協議がまとまっていない場合でも、期限までに申告・納税を済ませなければなりません。
先ほどのケースにおいて、申告期限までに分割協議が完了しなかった場合、相続人3人が100万円を法定相続分の割合に応じて納めることになります。
相続人が兄弟姉妹であれば、各人が33.33万円を納めることになりますが、未分割の状態だと申告時点で相続財産が手元にないため、納税資金が不足することも考えられます。
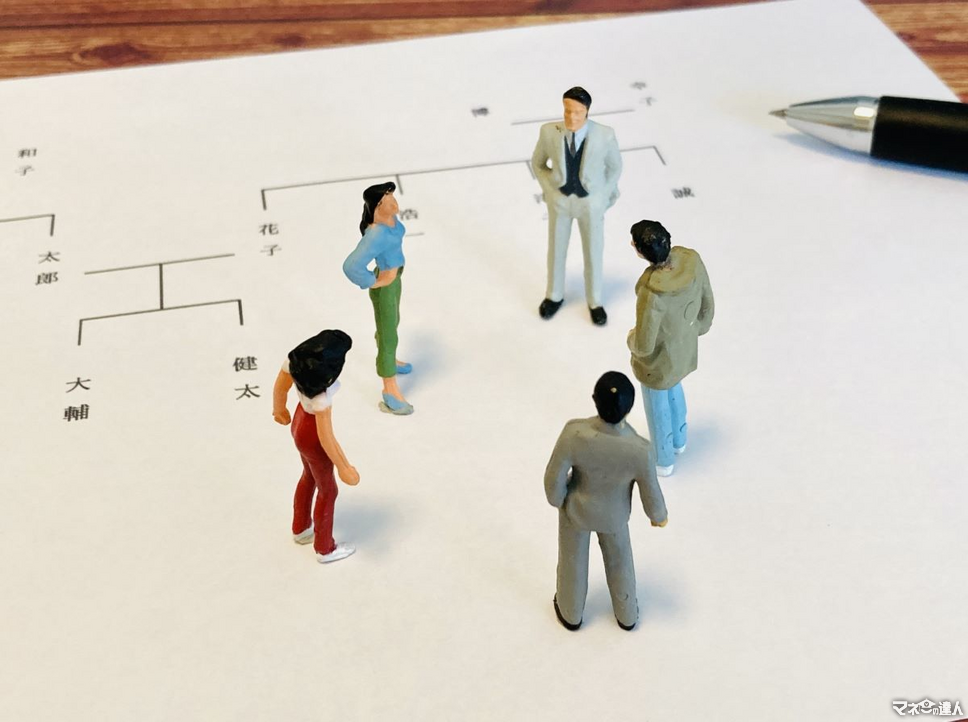
納税資金の確保も相続税対策のひとつ
遺産の中で不動産のみを引き継ぐ相続人は、手持ちの財産から相続税を支払うことになりますし、場合によっては相続財産を処分して納税資金を確保する必要も出てきます。
相続人間の話し合いがまとまらないと遺産を自由に動かせませんので、生前に財産整理をしたり、相続人に財産の所在場所を伝えるなどして、相続人に財産をスムーズに渡せるよう準備することも相続税対策のひとつです。