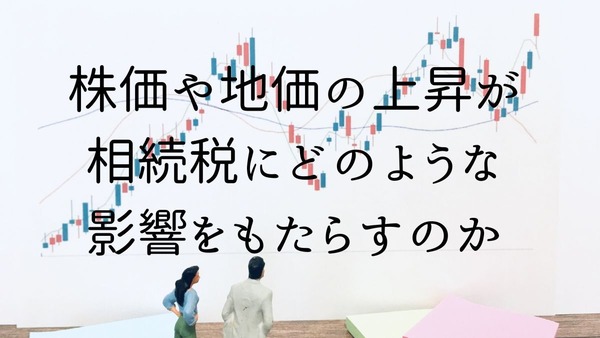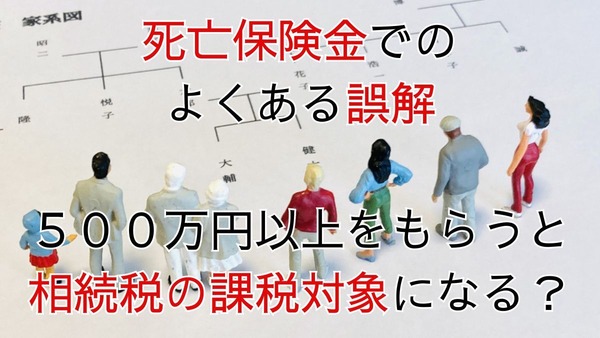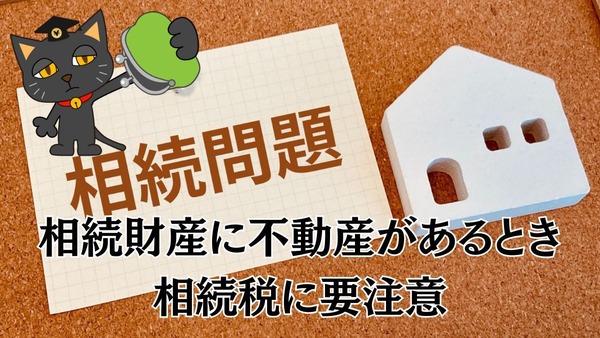家族に少しでも財産を残してあげたい場合、生前から相続税対策を行うのも選択肢の1つです。
ただ節税手段の中には、節税効果が低いものや、相続自体に悪影響を及ぼす手法も存在しますので、今回は相続税対策をする際に押さえておくべきポイントについて解説します。

相続税対策が必要になる相続は全体の1割
相続税は被相続人(亡くなった人)が保有していた財産に対して課される税金ですが、課税対象となるのは相続税の基礎控除額を差し引いた部分です。
基礎控除額を超える遺産がある場合には、亡くなった人の翌日から10か月以内に相続税の申告および納税が必要です。
一方で、遺産が基礎控除額以内に収まれば課税対象となる金額はゼロとなりますので、相続税額は発生しませんし、申告も不要になります。
<相続税の基礎控除額の計算式>
3,000万円+600万円×相続人の数=相続税の基礎控除額
国税庁が公表している資料(※)によると、令和4年分の被相続人数は156万9,050人、相続税の申告書の提出に係る被相続人数は15万858人、相続税の課税割合は9.6%です。
つまり、相続税はおよそ10人に1人しか課税対象にならない税金ですので、残りの約90%に該当する相続においては、基本的に対策を講じなくても相続税は課されません。
参照:国税庁「令和4年分相続税の申告事績の概要(pdf)」
相続税だけを考えた節税はトラブルになりやすい
相続税には、
配偶者が取得した財産1億6,000万円まで非課税になる「配偶者の税額軽減の特例」や、
土地の評価額を最大80%減額できる「小規模宅地等の特例」など、
節税効果の高い特例が数多く存在します。

特例を適用するためには要件をクリアしなければならず、生前から準備していないと適用が難しい特例も少なくありません。
相続税の節税を第一に考えるのであれば、特例を適用しやすいように相続財産を分けるのが最良の選択となりますが、節税のみを考えた遺産分割に同意しない相続人も出てきます。
遺産が1億6,000万円以内に収まる場合、配偶者が全財産を相続すれば配偶者の税額軽減の特例を適用することで相続税を非課税にできます。
しかし、相続税の納税額がゼロになったとしても、配偶者以外の相続人は財産を取得できないため、配偶者が全財産を相続する方法に応じない相続人がいても不思議ではありません。
また、相続税の特例制度の多くは遺産分割協議が成立していることが前提なので、申告期限までに遺産分割がまとまらないと特例を適用できない問題も生じます。
よって、対策を講じる際は、相続税の節税だけでなく、相続のことまで考えて進めるのがポイントになります。
相続税の特例制度は改正されやすい
相続税は相続開始時点の法律に基づいて計算することにあるため、現在の相続税に関する法律と、将来の相続時点における法律の内容が異なる可能性があります。
税金に関する法律は毎年改正されており、相続税に関する法律については大きな税制改正が実施されています。

たとえば、
相続税の基礎控除額は平成27年から大幅に引き下げられましたし、
令和5年度の税制改正で贈与加算の範囲が3年から7年に拡大することが決定するなど、
相続税は増税する傾向にあります。
現時点で相続税対策を万全にしたとしても、税制改正で対策の見直しが必要となることも十分考えられますので、相続税対策を講じる際は毎年行われる税制改正の内容もチェックするようにしてください。