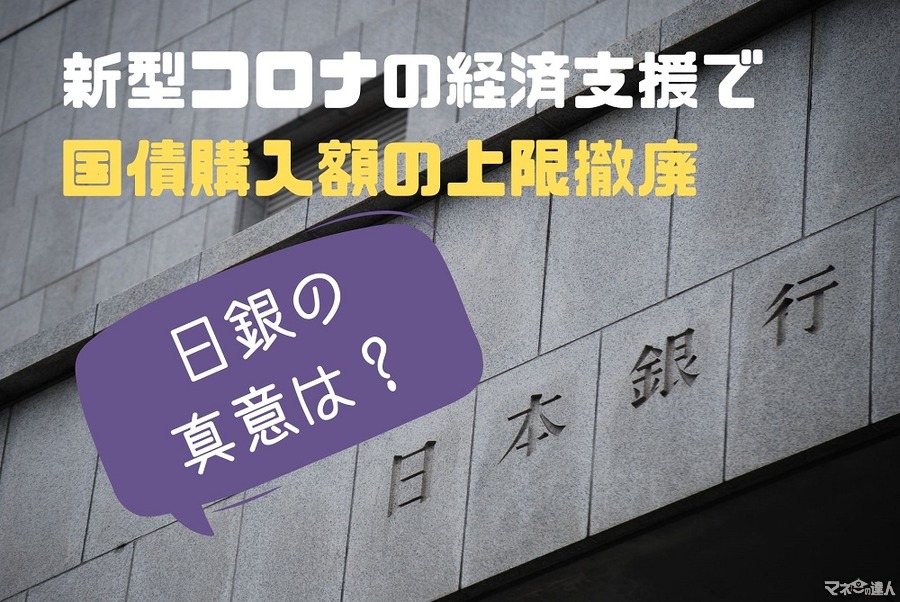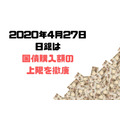目次
上限が撤廃されるまでの金融緩和手法

日銀はこれまで、長期のデフレから脱却するために前年比プラス2%という物価目標を掲げ、金融緩和に取り組んできました。
2016年9月の金融政策決定会合において導入された「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」では、
・ 長期金利:0%
ほどで推移するように国債を買い入れることが決定されています。
その国債の買入れ額は、日銀の国債保有額が1年間で80兆円程度増加するペースとされています。
一方で、実際の日銀の国債保有高の増加額(2019年1年間)は15兆円程度と、目途としている80兆円とは大幅に乖離しています。
この要因としては、年間80兆円も増加させなくても上記の目標金利を達成できているということが挙げられます。
また、買入れる国債が枯渇しつつあることも一因です。
国債保有高の増加スピードは落ちている
2019年末に日銀が保有している国債残高は、発行済み国債の47%弱を占めるまでに膨らんでいます。
つまり、日本国が発行している国債の半分近くを、日銀が保有しているという異常な状態になっています。
これは、日銀が物価上昇率を2%まで高めるために、国債をどんどん買入れてきたからにほかなりません。
しかし、上でみたように、2019年の1年間だけを見ると、国債保有高の増加額は15兆円程度と増加スピードは落ちています。
つまり、足元は国債の保有高をそれほど増加させなくても、目標とする金利は維持できています。
80兆円の買入れ上限撤廃に意味はあるのか
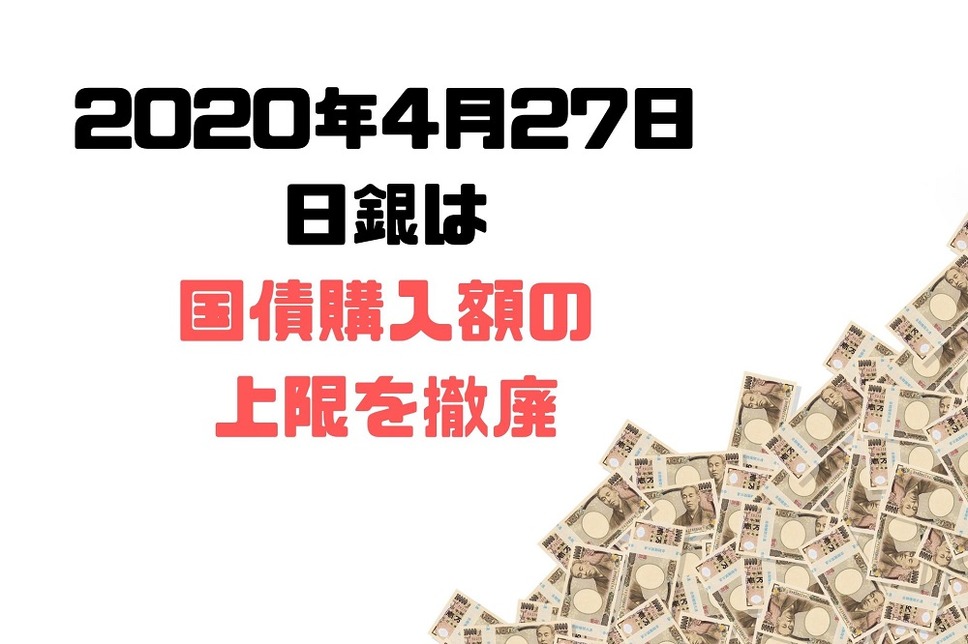
日銀は4月27日に、コロナにより停滞している経済を支援するために追加の金融緩和策を発表し、年間の保有国債残高の増加額を80兆円から無制限に変更しました。
表向きは金融面からの経済支援ですが、年間15兆円程度しか増加していなかった国債残高の増加目途を、80兆円から無制限にする意味はほとんどないと言ってよいでしょう。
もちろん、今後日本政府が取り組む補正予算により国債が増発されることは想像に難くなく、国債増発による金利急騰に備えるという意味はあると思われます。
しかし、ほとんどの投資適格債券に利回りが残っていない現在、多少の国債増発で金利が大幅に上昇することは考えにくいです。
それでは、日銀が80兆円の目途を撤廃した真意はどこにあるのでしょうか。
上限撤廃の真意
新型コロナウィルスが世界的に拡大して以降、各国の中央銀行は大胆な金融緩和に舵を切っています。
一方で日銀は、社債やCP、ETF、REITの買入れ額を増加させた程度に留まっています。
見方によれば、日本は世界各国ほど金融緩和を実施しなくてもよいためそのような差が生じているとも考えられます。
しかし本当のところは、これまで既に大胆な金融緩和策を採ってきている日銀には残されたカードがほとんどないということでしょう。
従って日銀としては、そのことを市場に見透かされ、急激な円高・株安が起こることを何としても食い止めたいところです。
そのため、マイナス金利の深掘りなどの残されたわずかなカードは、円相場が急騰した際に温存しておき、現段階では各国中央銀行と歩調を合わせてコロナに立ち向かっていることを市場にアピールすることが必要になります。
今回の国債買入れの上限額撤廃の真意がここにあるのは間違いないでしょう。(執筆者:土井 良宣)