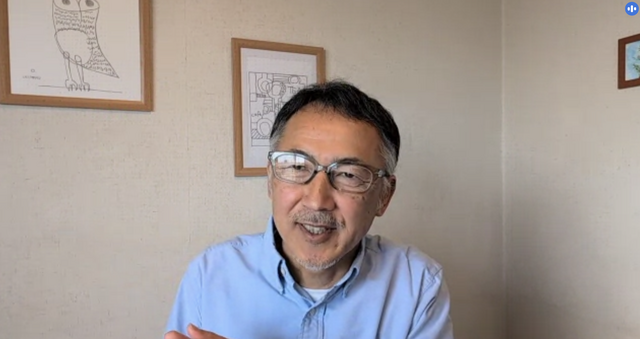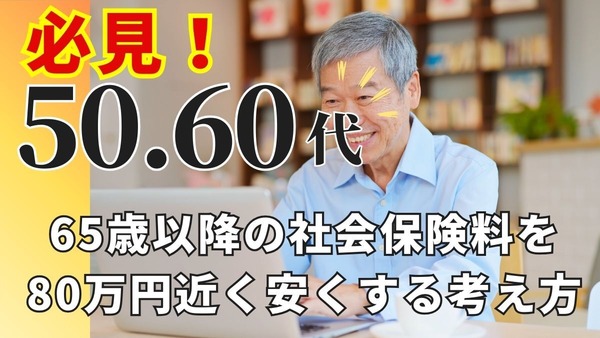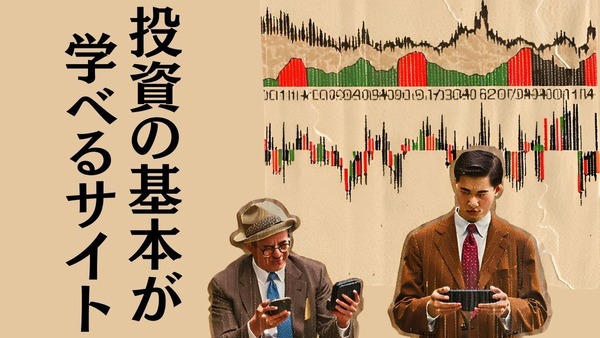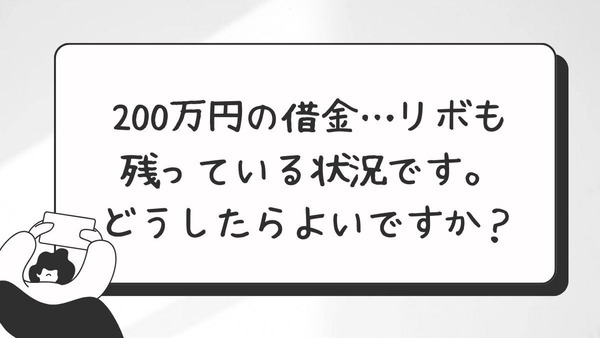定年退職後の生き方に「お金の悩み」はつきものだ。2023年に総務省が発表した「労働力調査」によると、60歳以上の人の就業率は年々上昇しており、60歳~64歳は74%が就業している。“人生100年時代”と言われる現代において、退職後も働き続けることが「当たり前」になりつつある。
そんな中、YouTubeチャンネル「定年男子」を運営している のりさん(60歳)は、昨年5月末に定年退職し、再雇用を選ばなかったという。妻・ゆりさん(58歳)も来年に定年退職を控えており、再雇用は考えていないそうだ。
「残された人生を自由に楽しむため、60歳で働くのをやめる」。のりさん夫婦がこの決断に至った背景には、綿密な資産シミュレーションや夫婦間での話し合いがあったという。退職から1年が経った今、「想定外」のことはあったのか? 経済面や健康管理、夫婦関係を含め、豊かな「セカンドライフ」を送るためのリアルな知恵を聞いた。
お金がいくらあっても、命がなければ意味がない
––再雇用を選ばず、60歳で定年退職を決めた理由は何でしょうか?
定年退職の1年前に会社側から「再雇用はどうする?」という話をいただきました。条件自体は悪くなかったんですが、自分が元気にやりたいことを満足にできる時間がどれだけ残っているのかを考えたとき、「早めに退職して自由に動ける今を大事にしたい」と思いました。
統計データを見ると、男性の場合、75歳までに4人に1人が亡くなり、健康寿命も72~73歳くらいと言われています。もちろん人によって違いますが、60歳からずっと健康を保てる保証はないですし、体力や視力などの衰えもいつ来るか分かりません。ならば、「自分の時間を優先する」という選択をしてもいいのでは、と決断しました。
––定年退職後のお金の不安はどのように折り合いをつけたのでしょう?
定年後も生活費は当然必要ですが、極論すればお金がいくらあっても健康や命がなければ意味がないわけです。僕自身、30代前半までは収入が少なく、外食なんて年に数回くらいしかできなかったんです。それでも幸せでしたし、一方で40代・50代になってそこそこお金を使えるようになっても、それが「より大きな幸せ」に直結するかといえば、そうでもない。
最終的には、スプレッドシート(表計算ソフト)で自分が持っている資産・今後の支出をすべて書き出して、「なんとか食べていけるだろう」という目処が立った段階で退職を決めたんです。
60歳で定年退職すると、(繰り上げ受給をしない限り)年金受給まで5年空きますよね。まず、この5年間の生活費をどう賄うかが問題です。その後、年金が始まったとしても、収入と支出のバランスが崩れて貯蓄が尽きることはないか。いま何年生きるか見通しが立たない時代ですから、もし90歳まで生きたらどうなる?と想定しなきゃいけません。
僕はそこを全部スプレッドシートに落として、各口座の残高、将来もらえる年金額、毎月必要な生活費などを何度も試算し直してアップデートしてきました。
––65歳になったタイミングで、どのくらい年金を受給できる予定でしょうか?
夫婦2人合わせて月23万円少々だと思いますね。当然それだけでは生活しきれないんですが、そこは貯蓄を取り崩しつつ補っていくしかないと最初から計画していました。
老後資金については、いわゆる大きな投資で利益を出すという考え方は、僕自身あまりしていません。一番大事なのは、持っている資産そのものをなるべく減らさないことだと思っていて。物価上昇と同じくらいに資産価値を伸ばせたら十分、という感じですね。
60歳から65歳までの5年間に関しては退職金でまかないます。この5年間は、夫婦二人で1500万円程度の生活資金が必要だと計算しています。勤めていた会社はあまり大きくなく、僕も妻も退職金がそこまで多くないので合計1000万円くらいかなと。その上で、お互い確定拠出年金(BC)を少しずつ積み立てていました。
例えば確定拠出年金を月5万円を積み立てれば1年で60万円、5年なら300万円貯まる。2人合わせれば退職金+確定拠出年金の積み立てで何とか5年間の生活費をまかなえる、という計画を立てていました。
––定年退職後、1年間過ごしてみて「想定外な出来事」はありましたか?
想定外だったのは物価の上昇ですね。ここ1年ほどで野菜やお米がものすごく高くなっていて、当初「食費は夫婦二人で月4万円」と見込んでいましたが、実際は毎月2000円ほどオーバーしています。
一方でいい意味で想定外だったのは、定年退職後の気持ちの面です。「退職して家にいると社会から取り残される」という話もよく耳にしますが、僕自身はわりと仲間との繋がりがあって、ネガティブな気持ちにはなりませんでした。具体的には、ランニングサークルを主催していて、イベント企画なんかもしているんですよ。仲間が楽しんでくれると僕も嬉しいですし、「取り残された感」はないですね。
やっぱり「誰とも関わらずに1人でこもる」のが一番きついと思います。僕も以前、在宅の自営を1年だけやっていた時期があって、そのときは妻は外で働いて帰ってきて……という状況で、会話が噛み合わないというか、孤独を感じました。でも今は仲間と社会的なつながりを持てているので、物価高などの多少のギャップがあっても、精神的には穏やかに過ごせています。
「妻と一緒にどう老いていけるか」がいちばん大事
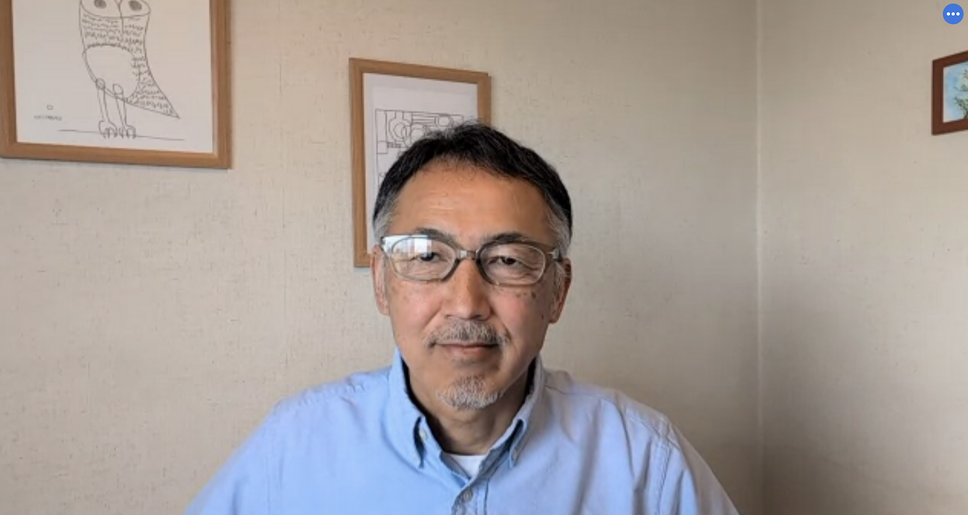
––ご家族、特に奥様の反応はいかがでしたか?
定年5年前くらいから「60歳で仕事辞めたいな」と妻には話していました。最初は「また愚痴言ってる」くらいに流されていましたが、退職2年前くらいからは本気だと分かってくれたようで、夫婦で生活設計を話し合うことが増えました。
妻自身も2歳年下で、あと1年ほどで定年を迎えます。お金の面ではやはり不安はありましたが、「早く自由な時間を一緒に楽しみたい」という思いが共有できていたので、特別大きな反対はなかったですね。ただ、収入がゼロになる間の生活費をどうするかなど、細かい計画はかなり入念に立てました。
––動画を拝見し、のりさんは奥さんとの関係を大切にされているように感じました。
まず自分の健康も大事なんですけど、いちばん大事に思ってるのは“これから一緒に年老いていく妻”との関係をどう健やかに構築できるかなんですね。
退職前の自分は、正直あまり家のことを手伝うタイプじゃなかったんです。でも子どもが大学を出て県外就職するタイミングで、家族3人だった生活が夫婦2人に戻るという大きな節目を迎えまして。それまで“父親と母親”としての役割を中心に暮らしていたのが、子どもがいなくなると“2人だけの夫婦”に戻るわけですよ。そこにどうやってシフトしていったらいいのか、葛藤があったんです。
振り返ると、妻が家事を全部引き受けていて、負担がすごく大きいなと思いました。だから、老後を仲良く暮らしていくには、妻が過度に負担しているところをこちらがある程度担って、重荷を取ってあげないと元の良い関係に戻れない。そう思ったんですね。
そこでまず始めたのが、家事の分担です。いちばん最初にやったのは「洗濯は全部自分がやるよ」と宣言するところから。実際にやってみると、妻が家事に使う時間を減らしてあげられるし、妻自身も気持ちに余裕ができますよね。お互いが自由な時間をしっかり持ったうえで、家に帰ってきたときに“その日に自分がやったこと”を話せる環境を作りたかったんです。
健康についても同じで、妻が時間の余裕をつくれるようになった分、仕事帰りにジムへ行って体を動かせるようになりました。僕は昼間にランニングを続けているので、お互いが健康でいられるようになれます。いつか体調を崩すことはあるかもしれないけど、その日を少しでも遅らせるためにも“家事分担”とか“相互理解”というのがいちばん大事だなと思っています。
––実際に奥さんが担っていた家事をやってみて、どんなことを感じましたか?
男性が家事を“手伝う”というと、少しやっただけで『こっちの方が合理的だよ』とか、部下に教えるみたいに物を言いがちだと思うんです。でもそれではダメだなと。文句を言わずに全部自分でやってみる。とにかく自分が全部負担してみて、妻に口を挟む隙を与えないくらいしっかりやる。そこまでして初めて『対等』というか、妻も安心して任せられるんじゃないかと思ったんです。
うちの場合、妻が家でやっている家事はトイレ掃除とか、私がご飯を作った後の後片付けの一部くらいです。それ以外はすべて私がやっているので“どちらが負担する”なんて押し付け合いもなく、スムーズにいってますね。
結局“こうすれば効率いいよ”と口で言うだけじゃなく、まず自分が先に全部やってみせることで納得してもらえたんです。あれこれ指示するより、まず肩代わりするのが導入としてはうまくいったと思います。
「退職してよかったな」と心の底から実感している
––動画では「最後の1年はモチベーションが低かった」とお話されていました。実際、どんな気持ちが強かったのでしょうか?
役職定年という制度がありますよね。一定の年齢に達すると役職から外れるという仕組みで、うちの職場の場合は、60歳になって再雇用になるタイミングで役職が外れる形でした。
そこで会社としても新しい体制を作りたくなるわけで、退職する1年前くらいから後任の人が配属されるんです。やがてその後任が仕事を覚えるにつれ、僕の居場所が少しずつ減っていく感じがする。「自分がいなくても仕事が回る」「あと半年しかいない人に振るより後任に振った方がいい」となると、自然と疎外感が出るんです。
僕は趣味でマラソンをやっているのですが、42.195km走る中でラスト数kmがとにかく苦しいように、定年が見え始めると「早くゴールしたい」「今すぐやめたい」という気持ちが強まっていきました。ゴールが遠いときは「走り続けるしかない」と思えるのに、見えてきた途端に“あともう少しだからこそ辛い”という状況が起こるわけですね。
––実際に定年退職の日を迎えたときは、どんなお気持ちでしたか?
僕の場合は、正直「寂しさ」はなかったですね。通勤に1時間、渋滞すれば2時間前に出ないといけないような職場でしたから、退職すると「もうあの道を通わなくていいんだ」という開放感で肩の荷が下りました。実際、退職してから職場の近くを一度も通っていないんですよ。
退職後の気持ちとしては「日々のストレスから解消された」というのがいちばん大きいです。仕事って、たとえ「これをやりたい」と思って入社しても、ずっと同じ内容を続けられるわけじゃないですよね。部署が変わったり環境が変わったりすると、自分が本当にやりたい仕事から離れることも出てきます。
僕の場合、後半は望まない仕事を延々こなしていましたし、通勤時間も片道1時間、渋滞を考えれば2時間前に出なきゃいけない。帰りも同じくらいかかって、往復4時間。つまり1日の半分近くは「やりたくない業務+通勤」に奪われるわけです。これは正直つらかったですね。
でも、退職してからはほぼすべてが自分の思い通りに時間を使える。これが本当に嬉しいです。たまに「もっと早く辞めてもよかったかもしれない」と思うぐらいで、今は「退職してよかったな」と心の底から実感しています。
––最後に、これから定年を迎える読者へのメッセージをお願いします。
やっぱり時間がいちばん大切だと思います。体が元気で動けるうちに、やりたいことは全部やるつもりで老後設計をしていくのが大事じゃないかなと。
それに、できるだけ早い段階で気づいて準備を始めれば、それだけ自由に退職を選べる可能性が広がると思うんですよ。たとえば55歳で気づくより50歳で気づいた方が、積立や貯蓄、確定拠出年金など、いろんな対策を前倒しでできるじゃないですか。
「もしこの歳までにこれだけ貯まっていたら退職もありだよね」というシミュレーションは、早めに取り組むほど心強いと思います。僕自身、確定拠出年金を活用して月々コツコツ積み立てていたら、いざ退職する段になってかなり助かりました。定年退職後の生活については、早めの準備とシミュレーションをおすすめします。
【PICK UP】
・世界的な株安!シニアがこんなタイミングで新NISAを始めても大丈夫か?
・【コラム】リストラ経験ありの58歳がハローワークに行ってきた話