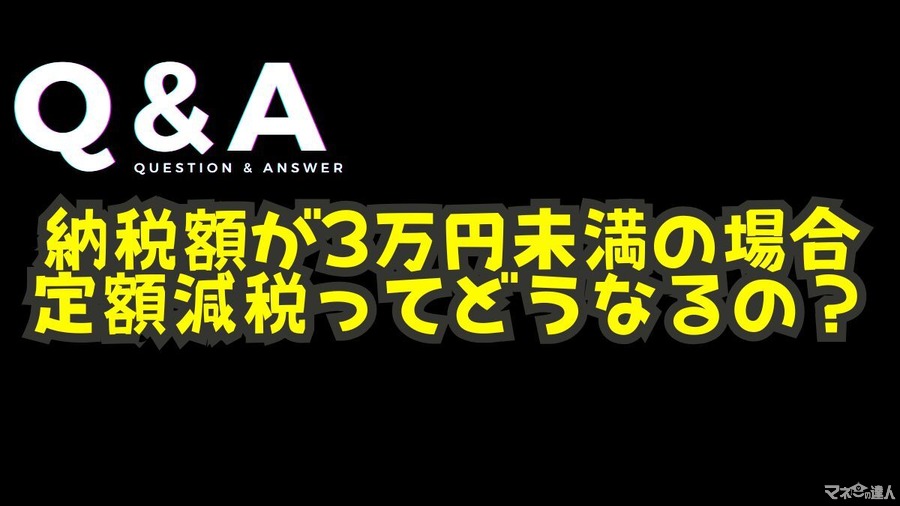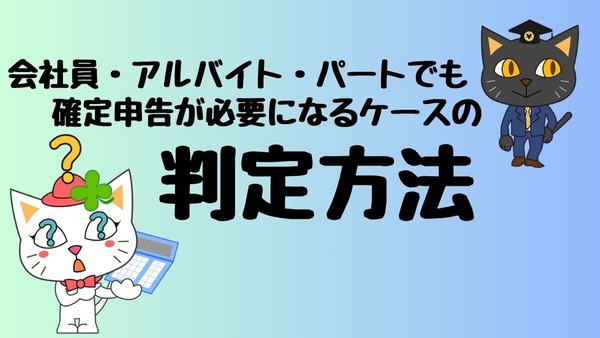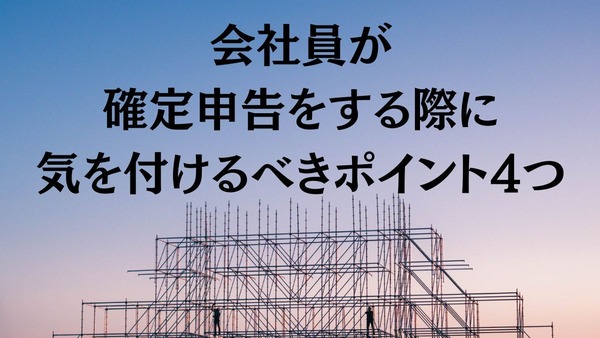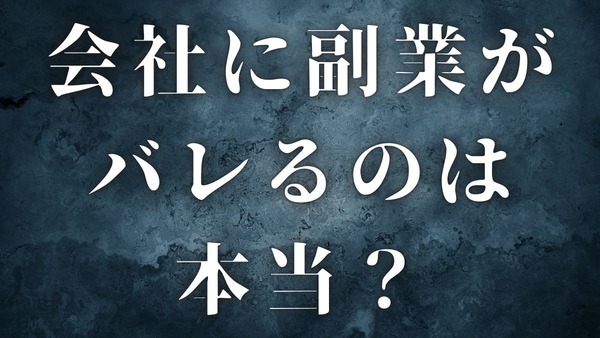令和6年分の所得税では、定額減税として1人あたり3万円(住民税は1万円)が控除される措置が適用されました。
しかし、定額減税は税金を配る制度ではないため、所得税の納税額が3万円未満の場合など、定額減税額をすべて差し引くことができないケースもあります。
そこで今回は、所得税から控除しきれなかった定額減税の残額が生じる場合の取扱いについて解説します。
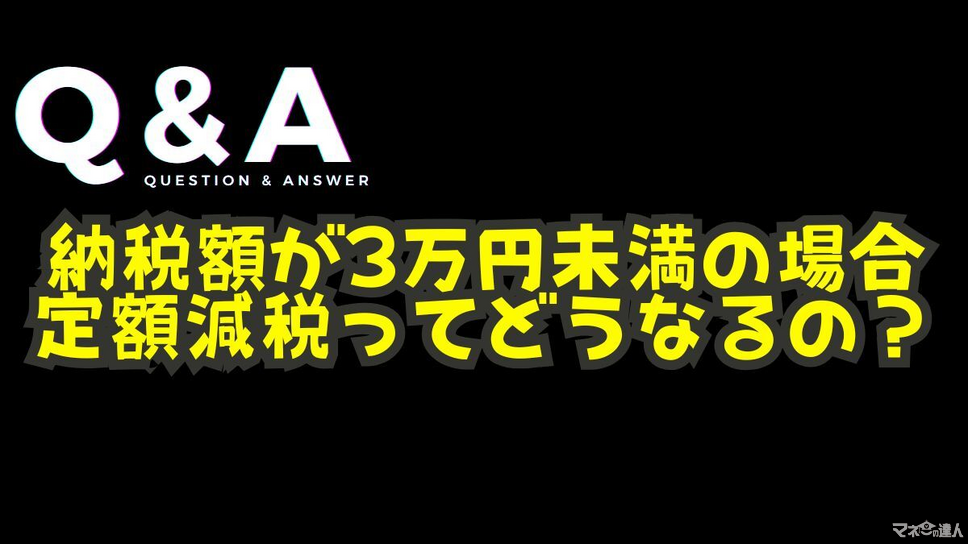
定額減税の基本的な取扱い
「定額減税」は、納税者本人および扶養親族の人数に応じて算出される定額減税額を、所得税および住民税から差し引くことで、税負担を軽減する特例措置です。定額減税の対象となるのは所得税や住民税の納税義務がある人ですが、専業主婦(主夫)や子どもなど、扶養に入っている方は扶養者の所得税・住民税の計算で定額減税が適用されます。
一方、合計所得金額が一定以上ある方や、海外に住んでいる方については定額減税の適用対象から除かれます。
<定額減税の金額>
定額減税額 | 所得税 | 住民税 |
本人分 | 3万円 | 1万円 |
同一生計配偶者または扶養親族 | 1人につき3万円 | 1人につき1万円 |
給与所得者に対する定額減税の適用

給与所得者の場合、令和6年6月以降に支払われる給与等に対する源泉徴収税額から、定額減税が適用されています。定額減税が給与から控除しきれなかった場合でも、以降の支払いから順次適用されますので、給与所得者は特別な事情がない限り、確定申告手続きをする必要はありません。
ただし、医療費控除や寄附金控除を適用するために還付申告を行う方については、定額減税も含めて計算した確定申告書の提出が必要です。
控除しきれなかった定額減税の残額は給付される
所得税や住民税から控除しきれない定額減税額は、納税者が不利益を被らないよう、市区町村から給付される対応が取られます。定額減税で引ききれないと見込まれる方については、令和6年の時点で調整給付金が支給されています。
また、令和6年分の所得税と定額減税の実績の額が確定した後に、当初給付の不足額が生じた方に関しては、追加で給付が行われます。不足分の追加給付は令和7年以降に住民税が課税される市区町村から支給される予定で、不足額給付の支給対象者の方には市区町村から確認書が送付される見込みとなっています。
まとめ
納税額が定額減税額を下回る場合には、給付対応が取られますので、納税額が少ない人も定額減税額分の恩恵は享受することができます。給与所得者が確定申告書を提出した場合も、定額減税を適用することは可能です。ただし、確定申告書に定額減税に関する記載漏れがあったときは未適用の状態となるので、万が一定額減税を記載していなかったときは、更正の請求書の提出などの対応が必要になるので注意してください。