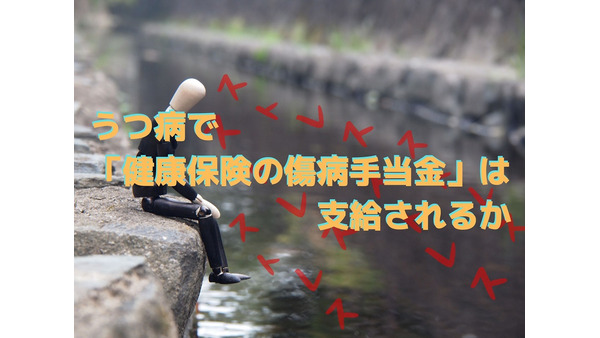
ストレス社会の現在 会社員の方は何らかのストレスを抱え、ストレスがたまることにより、うつ病を発症してしまう会社員も少なくありません。 うつ病は年齢に関わらず発症するため、仕事上休むことが難しい人でも発症する可能性がありま
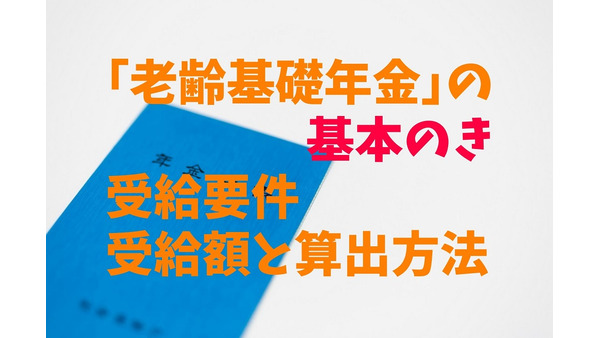
日本に住んでいるすべての人が、20歳になったら国民年金に加入します。 そして、保険料納付要件を満たしたら、基本的には65歳から「老齢基礎年金」を受給します。 「老齢基礎年金」だけでは老後の生活は厳しいと言われていますが、

パートで働く主婦の中で、扶養の範囲内で働きたいという人が多いでしょう。 しかし、「扶養の範囲内」とはいったいどういうことでしょうか。 扶養の範囲内で働くことにより、税金上に関する扶養と社会保険に関する扶養と2つのメリット

雇用保険の中に、「傷病手当」という給付があります。 健康保険の中にも「傷病手当金」という給付があり、名前はよく似ているのですが実はまったく違うものです。 今回は、雇用保険の「傷病手当」について解説していきます。 雇用保険
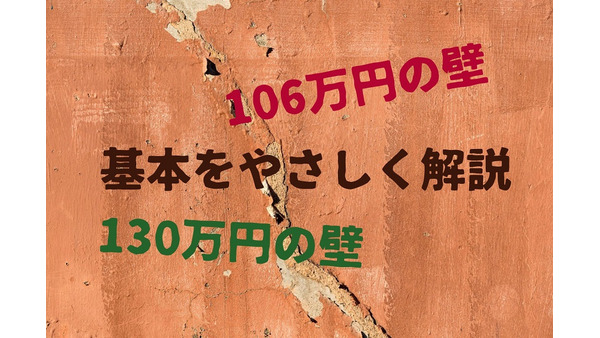
主婦の方などが会社員の夫などの家族の扶養に入り、健康保険などの社会保険に加入しないためには、「130万円の壁」という言葉が使われます。 いったい「130万円の壁」とは何なのでしょうか。 今回は、社会保険の「130万円の壁
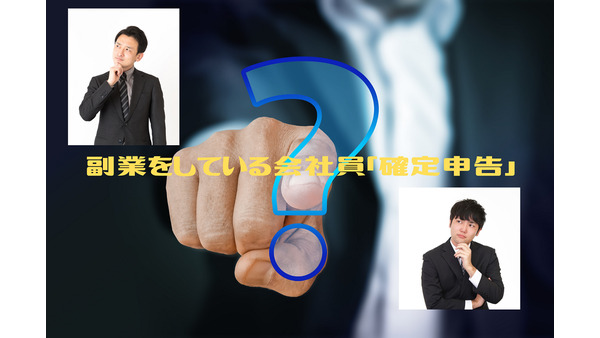
近頃では、副業を認める企業も多くなってきています。 そのため、会社に勤務しながら副業をしている人も増えています。 しかし、意外と見落としてしまうのが、 勤務先以外の収入がある場合は、確定申告しなければいけない ということ

会社員の副業やダブルワークが拡大 最近では、従業員の副業を認める会社も増えてきました。 また、求人にも「ダブルワーク可」などとする企業も目立つようになりました。 このように、世間は会社員の副業やダブルワークが当たり前にな

雇用保険には教育訓練給付金という働く人の主体的な能力開発の取組みや、中長期的なキャリア形成を支援し雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とした給付金があります。 その内容は、厚生労働大臣が指定する講座を受講するために支
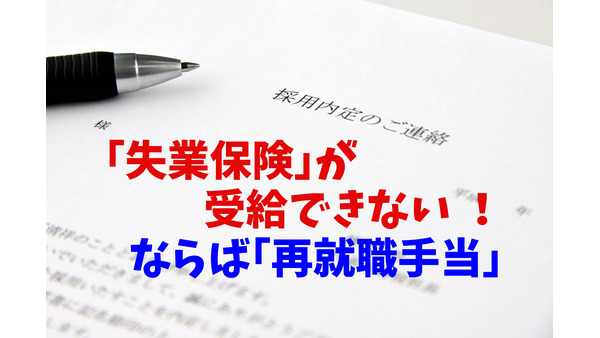
雇用保険の失業保険を受給中の人が就職活動をして再就職が決まった場合、失業保険はもう受給できなくなります。 なぜならば、失業保険は、失業中の人しか受給できないからです。 そのため、中には失業保険を全部もらってから、本格的に

失業保険とは、雇用保険の基本手当のことです。 給付を行うことにより、労働者が失業した場合であっても生活の心配をせずに再就職のための活動ができることを目的としています。 しかし、実際に会社を辞めようと考えている人は、失業保

パートで働いている場合でも、労働条件によっては雇用保険に入らなければなりません。 雇用保険に加入するとなると、当然ですが雇用保険料を支払う必要があります。 しかし、パートで働いている人が雇用保険に加入することで多大なメリ

産休(産前産後休業)とは? 会社などに勤務していて産休を取得する場合、ほとんどの会社が無給になると思われます。 そのような時のために、健康保険には「出産手当金」という制度があります。 産休(正式には産前産後休業)とは労働
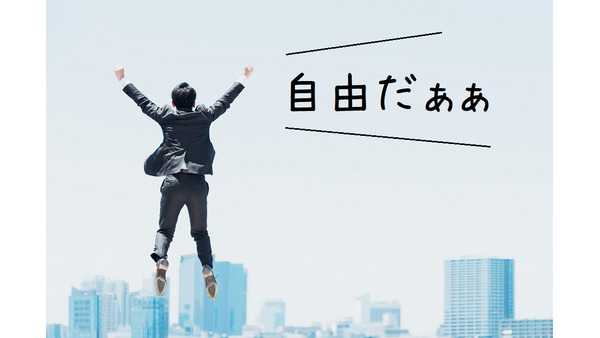
会社を辞めた場合でも、 次の会社が見つかるまで失業手当をもらえば生活は何とかなるだろう と考える人もいるでしょう。 そう思って会社を辞めてしまう前に、ちょっと待ってください。 失業手当は、会社に勤務していた全員がもらえる

育児休業とは、子が1歳(一定の条件の場合は2歳)まで従業員の申し出により取得できる休業のことです。 また、父母の2人共に育児休業を取得する場合は、子が1歳2か月に達するまで取得できます(パパ・ママ育休プラス)。 育児のた
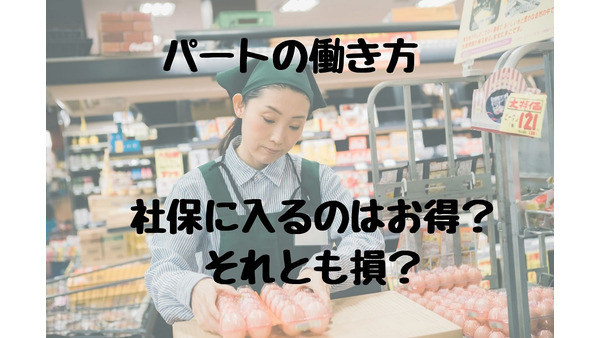
2016年10月や2017年4月の改正により社会保険の加入対象者が広がったため、パートで働く人にとっても場合によっては厚生年金や健康保険の保険料を払う可能性が高くなりました。 このことにより、今まで配偶者の社会保険の被扶

病気やケガなどで3日以上会社をやすまなければならない時、4日目から無給であれば健康保険の傷病手当金が支給される可能性があります。 入院や自宅療養で仕事ができなくて無給であれば、健康保険から所得補償をしてくれます。 今回は

出産の時にかかる医療費は、健康保険の適用外のため基本的には全額自己負担になります。 地域や出産する施設などによっても違いますが、一般的には自然分娩で30万円~70万円くらいの出産費用がかかります。 この大きな負担となる費
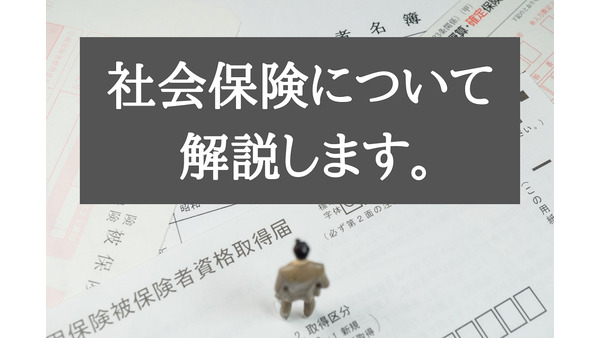
社会保険制度とは、 老後や病気や障害や失業などの世の中に存在していて個人では解決できないリスクを、社会全体で支えていくという制度 です。 会社員であっても、個人事業主であっても、主婦であっても必ず社会保険は生活に関わって
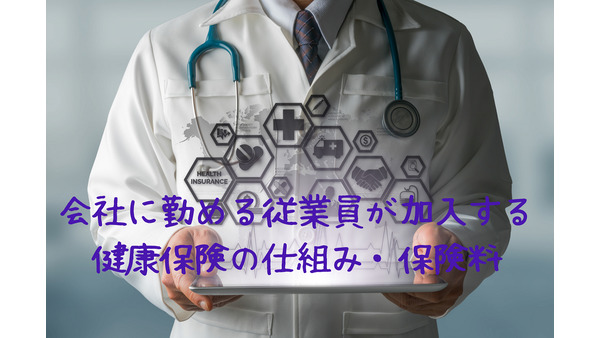
日本では国民皆保険制度の基に国民全員が、公的医療保険に加入しなければなりません。 公的医療保険は、健康保険などの被用者保険とそれ以外の国民健康保険の2種類に分かれます。 被用者保険とは非雇用者が加入する保険で、国民健康保
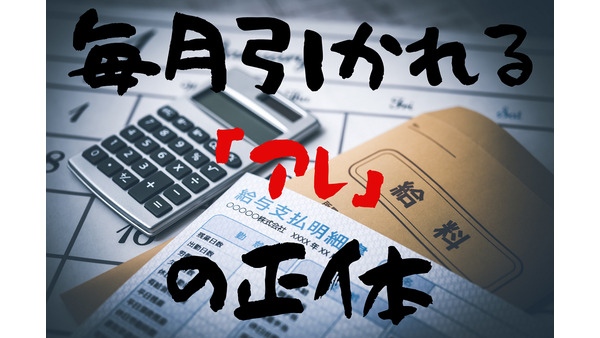
毎月給料から引かれる「アレ」の正体 会社員の毎月の給料明細からは、健康保険料や厚生年金保険料が控除されていると思います。 毎月給料からかなりの金額が引かれて疑問に思っている方も多いのではないのでしょうか? 健康保険や厚生