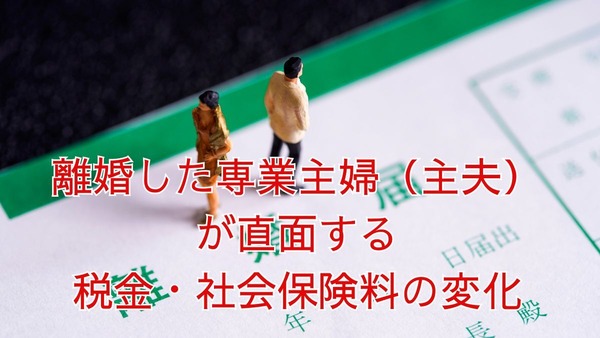
離婚した専業主婦(主夫)は、税金と社会保険料の変化に直面します。収入が得られるようになると所得税と住民税が発生し、国民健康保険に加入が必要になります。また、離婚後に控除が適用できる場合もあります。

公売制度は、税務署などが差押財産を売却する仕組みで、安価に購入できる可能性あり。返品や品質保証がないため注意が必要で、参加者は出品物の状態確認が推奨される。
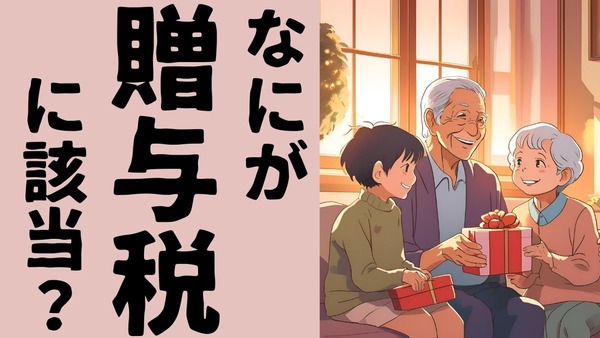
贈与税は、無償で財産を渡す際に発生する税金で、受贈者が申告する必要があります。基礎控除110万円を超えた場合は、申告が必須です。扶養義務者からの生活費や教育費は非課税。

物価が上昇傾向にある昨今、自宅の価値がどれくらいあるか気になると思います。
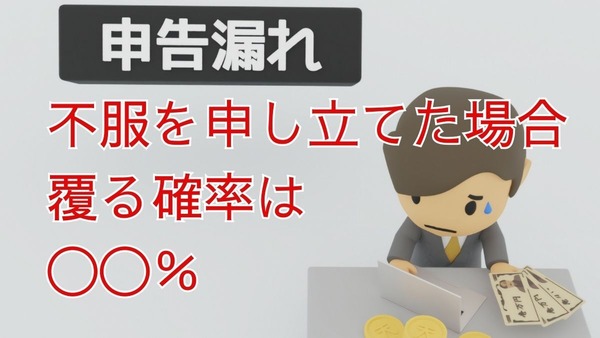
税務調査で納税者が不服を申立てることができるが、調査結果が覆る確率は低い。再調査や審査請求を経て裁判に進むことも可能で、結果が変わる場合もある。
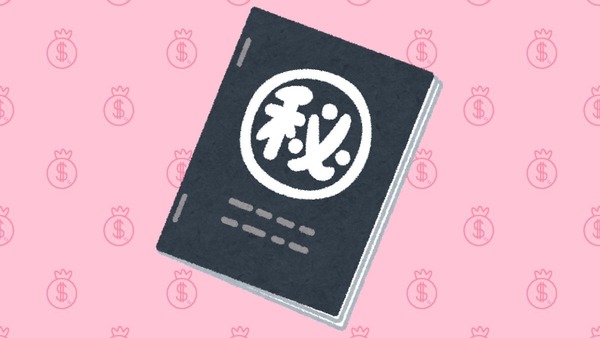
節税手段には秘密はなく、法律内での適法な範囲で行う必要がある。特例制度は厳しい要件があるため、知らないと適用できず、結果的に多くの人がまだ認識していない制度が存在する。
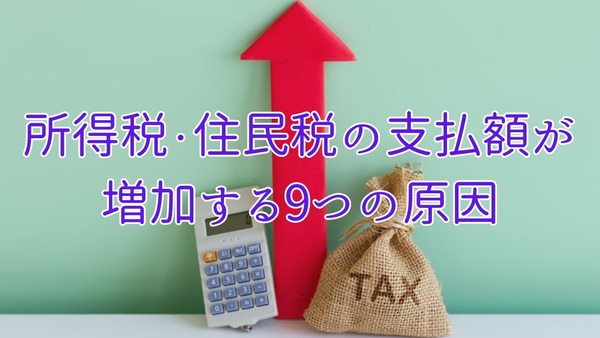
昨年より税金の支払いが増える9つの原因を紹介。給与増加、副業収入、不動産売却、生命保険金などが影響し、控除の減少も関与。特に扶養家族の変動や医療費控除の変化に注意が必要。

離婚時に受け取る財産分与や慰謝料は基本的に贈与税の対象外。しかし、過大な分与や節税目的の場合は課税されることがある。贈与税の申告は金額が110万円を超えると必要。

資産運用に成功すれば財産を増やせますが、失敗すると大切な財産を減らすことになります。

サブスク(サブスクリプションサービス)は、年間払いにすると料金が割引されることもあるのに対し、クレジットカードの分割払いは利息が上乗せされますので、住民税も支払方法の違いで損得が発生する疑問を抱かれるかもしれません。
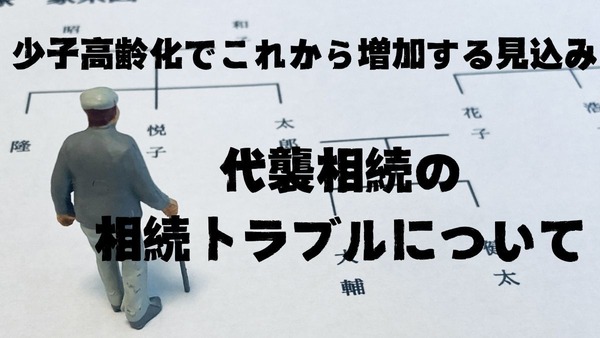
日本の平均寿命(令和5年)は女性が87.14歳、男性が81.09歳と長寿大国であり、寿命が延びたことで相続人が高齢者となるケースも増えています。
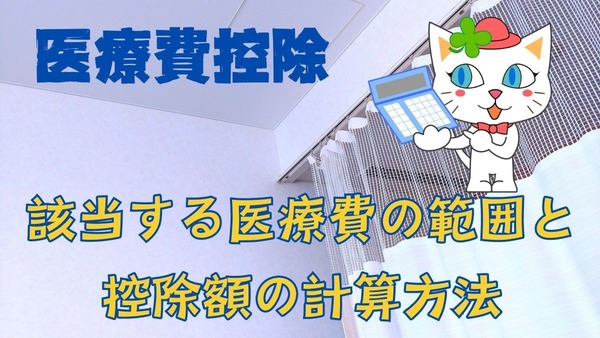
医療費に該当する範囲は何となくイメージできるかもしれませんが、意外な費用が医療費になる場合や、支出した目的によっては医療費として認められないものもあるので注意が必要です。
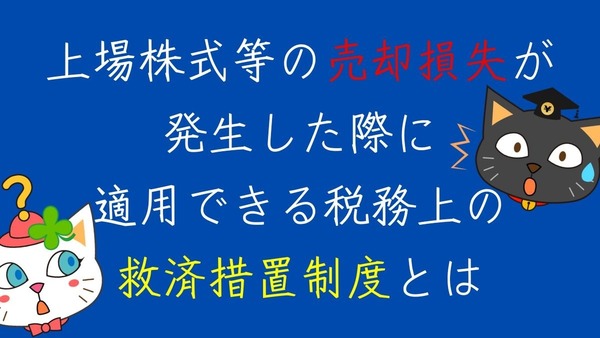
2024年8月5日、日経平均株価が過去最大の下げ幅を記録するなど、8月の株式市場は大きく荒れています。
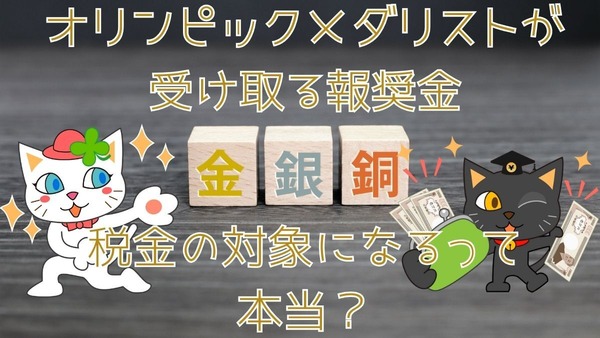
2024年パリオリンピックでも日本人選手の活躍が目覚ましいですが、オリンピック・パラリンピックでメダルを獲得した選手に対しては報奨金が支給されます。

マイホームを購入した際、一定の要件を満たすことで所得税の住宅借入金等特別控除(通称:住宅ローン控除、住宅ローン減税)を適用することができます。
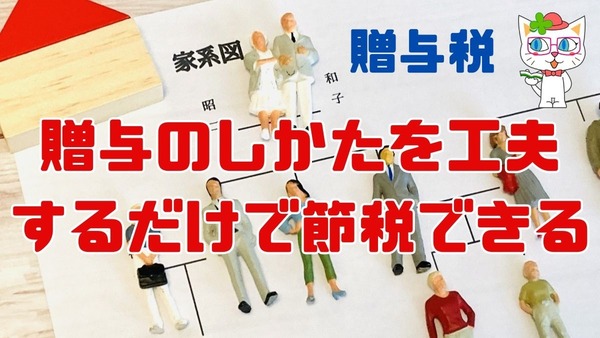
贈与税は、財産を無償でもらった際に課される税金であり、贈与税の申告手続きは財産を受け取った側(受贈者)が行うことになります。
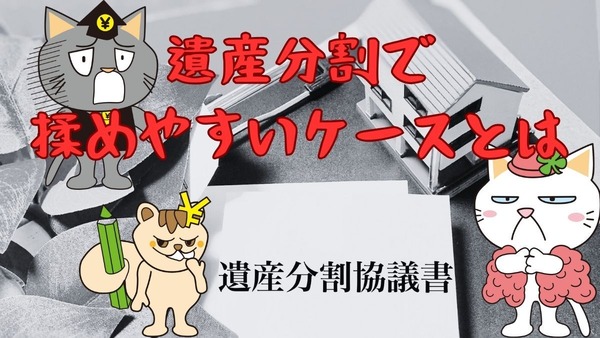
相続税は相続人が取得した財産の割合に応じて納めることになりますが、遺産をどのように引き継ぐかは相続人間で話し合って決めます。
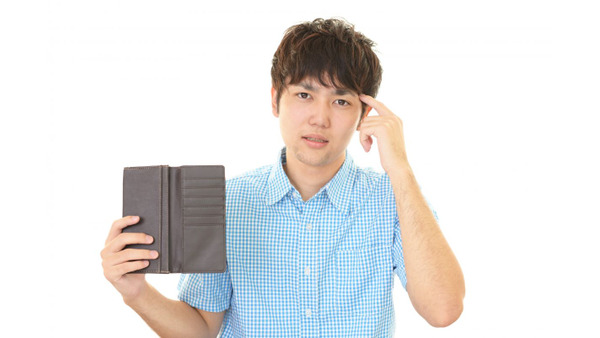
日本政府は投資を後押しするためにNISA制度を拡充していますが、投資をするにしても手元にお金がないと資産を増やすことはできません。
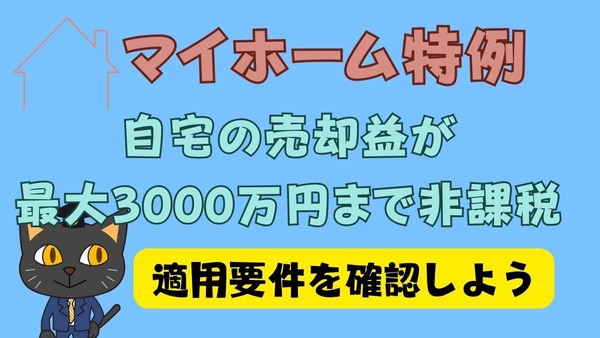
自宅売却時の譲渡所得税を解説。マイホーム特例で3,000万円まで無税になる。所有期間が長ければ税率は低くなり、確定申告が必要。建物の減価償却費相当額も注意。
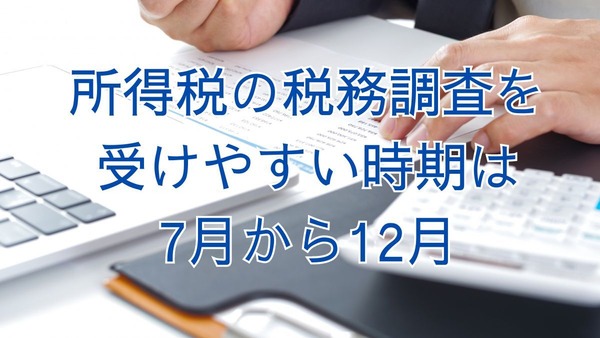
税務調査は1年中行われていますが、個人が納めている所得税の税務調査は、7月から12月が最盛期です。
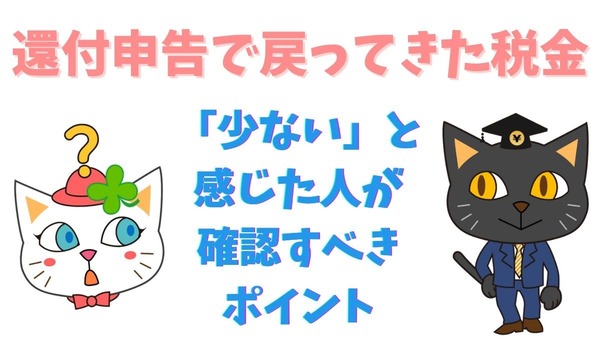
還付申告書を提出したのに、思ったほど税金が戻らなかった人もいるかもしれませんが、実は同じ税金対策を実施したとしても、申告する人の所得や納税状況によって還付される金額は異なります。
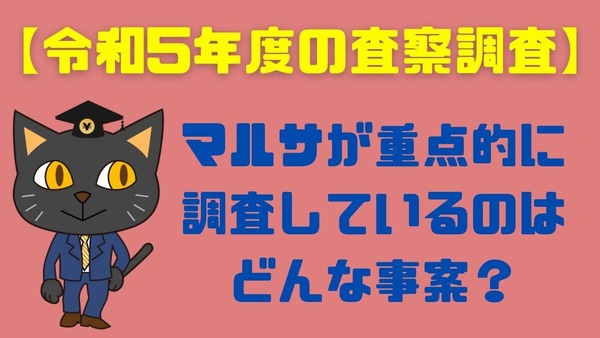
国税庁は、令和6年6月21日に令和5年度の査察調査の実績を公表しました。
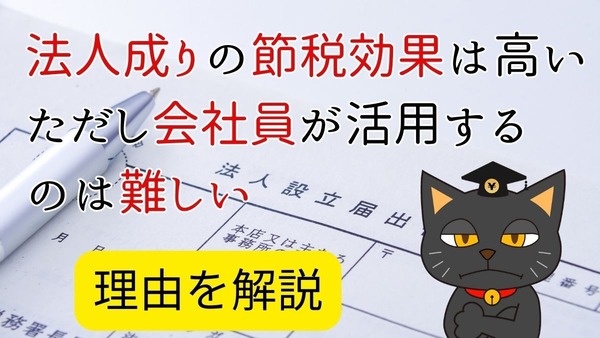
「法人成り」は、数ある節税手段の中でも高い節税効果が期待できる方法ですが、法人成りを活用して節税できる人は限られています。
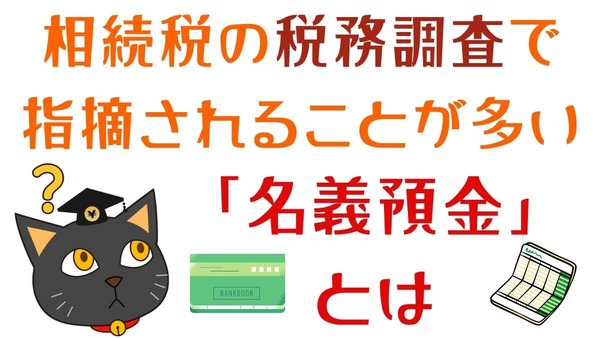
相続税は亡くなった人(被相続人)の財産に対して課される税金なので、家族が保有する財産は相続税の対象にはなりませんが、「名義預金」に該当するケースでは相続税の課税対象になってしまいます。

世の中には数多くの税金がありますが、税金の数だけ節税手段も存在します。
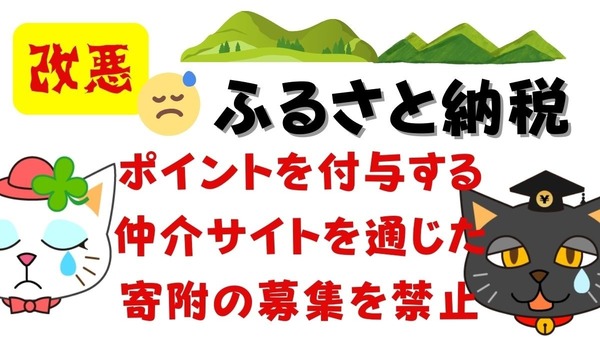
総務省は令和6年6月25日、ふるさと納税のルール見直しを発表し、利用者にとっては事実上、ふるさと納税制度が改悪となる見込みです。
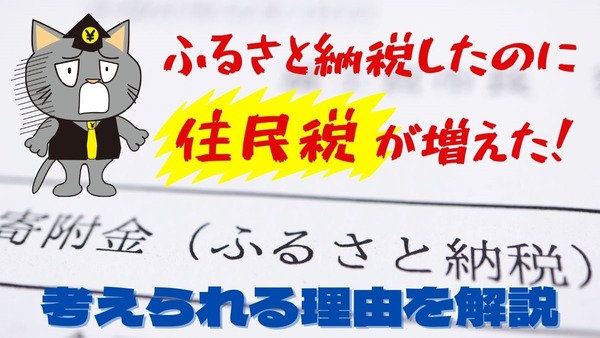
ふるさと納税は返礼品の魅力も相まって受け入れ額は年々増加しており、令和5年度(2023年度)には1兆円を超えたとされています。
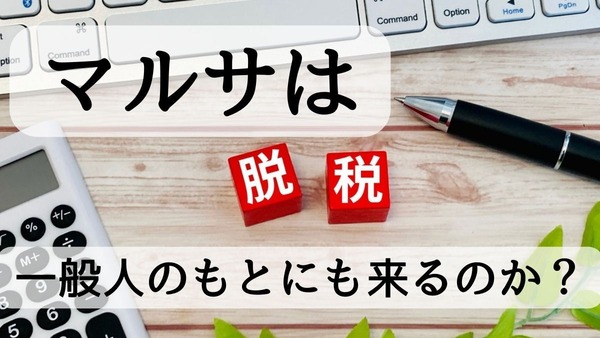
税金の調査といえば「マルサ」のイメージを持つ方もいるかと思いますが、税務署が実施する「税務調査」とマルサが実施する「査察調査」は、調査の種類が違います。
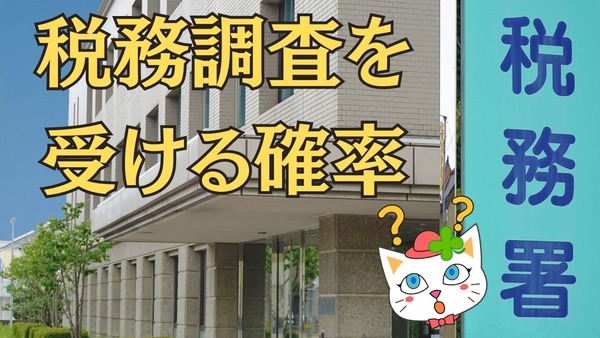
税金の種類が違えば確定申告書の提出件数は異なりますし、税務調査が実施される件数にも差があります。

家族に少しでも財産を残してあげたい場合、生前から相続税対策を行うのも選択肢の一つです。
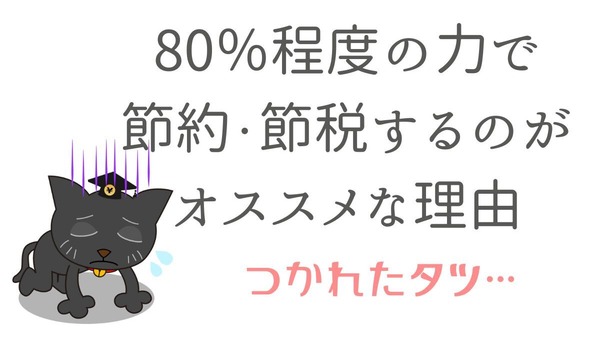
節約や節税は手元に残るお金を少しでも増やすことが目的であり、節約・節税術を一つでも多く実践できれば、お金をたくさん貯めることができます。

令和6年4月から相続登記が義務化となり、不動産名義を亡くなった人のまま放置することができなくなりました。
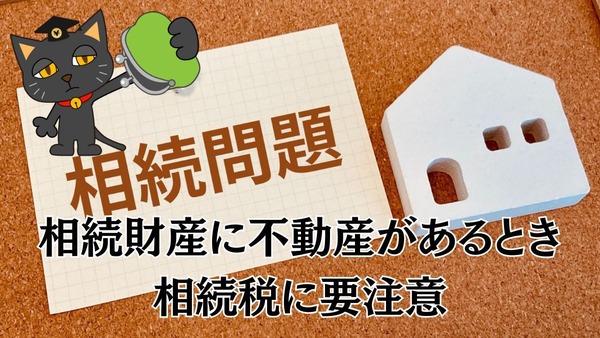
相続税の支払いが大変な理由について解説。申告期限や未分割の際の対処法、納税資金確保の重要性。
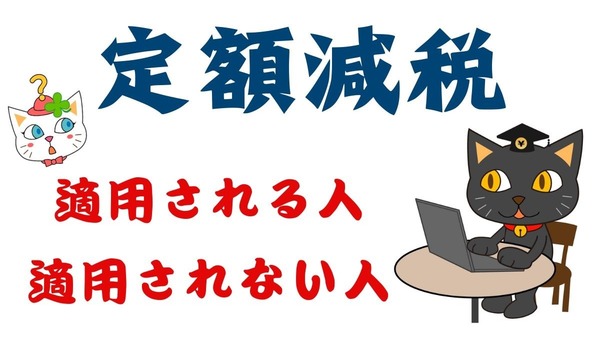
何かと話題になっている定額減税ですが、令和6年分の所得税および令和6年度の住民税で適用されることになっています。
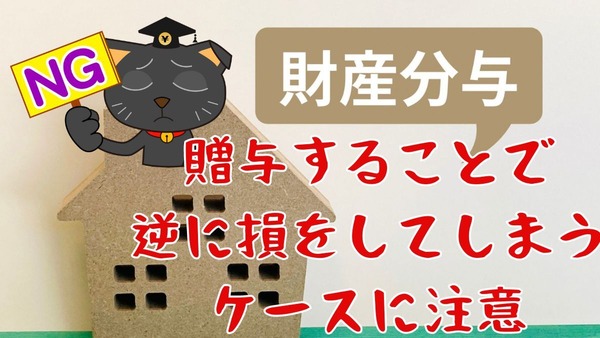
相続税の節税には、不動産を生前贈与する方法もあるが、価値が下がる時期に引き継ぐ方が良い場合も。特例適用のため、タイミングも重要。
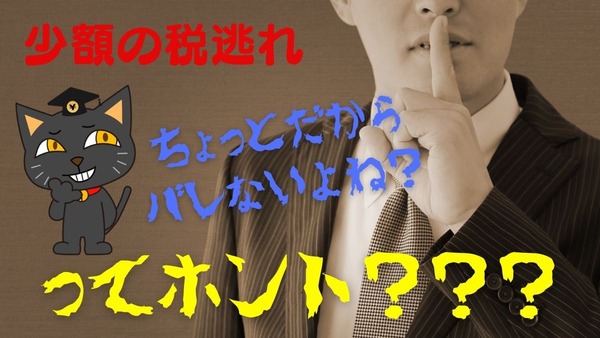
少額なら税務署にバレないかも?という疑問に、税務署は全員を調査しないし100%回避できない。税務署は強力な権限を持っており、無申告の後処理は面倒。