
固定資産税は、土地や建物を所有している場合に課される税金です。 ただ同じ地域にある土地でも、用途によって課される税金の額は異なりますので、 固定資産税が高くなるケースと、 固定資産税の減税措置が適用されるケース をご紹介

会社員の方は、10月から12月の間に勤務先で年末調整を行うことが多いと思います。 年末調整で税金手続きを完了させれば確定申告が不要になる一方、年末調整をしないと確定申告が税金の精算をすることになりますのでご注意ください。

マイホームを購入する際は不動産の購入費用だけでなく、維持管理費にも着目しなければいけません。 特に固定資産税は毎年支払うことになる税金であり、不動産が高いほど支払う金額も大きくなります。 本記事では、固定資産税の仕組みと

生命保険は相続税を節税するだけでなく、相続税の納税問題も解消できる一石二鳥の相続税対策の方法です。 ただ相続税対策として用いる際に注意すべきポイントもありますので、生命保険の節税効果と合わせて解説します。 死亡保険金は別
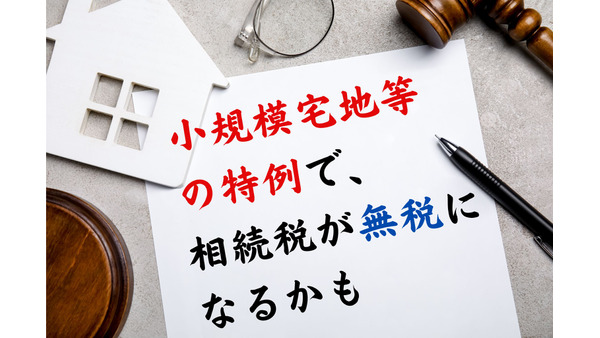
「小規模宅地等の特例」は、相続税の中でも高い節税効果が期待できる制度です。 一般のご家庭であれば、小規模宅地等の特例を適用するだけで相続税が無税になることもあります。 今回は小規模宅地等の特例の概要と、適用する際の注意点
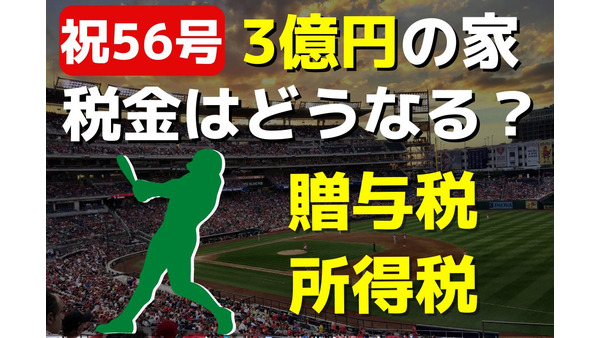
プロ野球のヤクルト球団に所属する村上宗隆選手が、NPB日本人記録になる56本目のホームランを打った際、当初スポンサーからは、「1億円の東京の家」がプレゼントされるとのアナウンスがありました。(※) しかし、村上選手が56
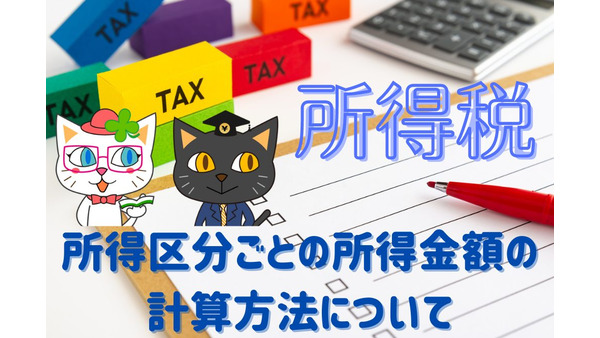
所得税は所得の性質に応じて10種類に区分され、所得区分ごとに所得金額の計算方法は異なります。 また所得の種類によっては、個別に所得税の税率が設定されているものもあります。 本記事では所得区分ごとの所得金額の計算方法につい
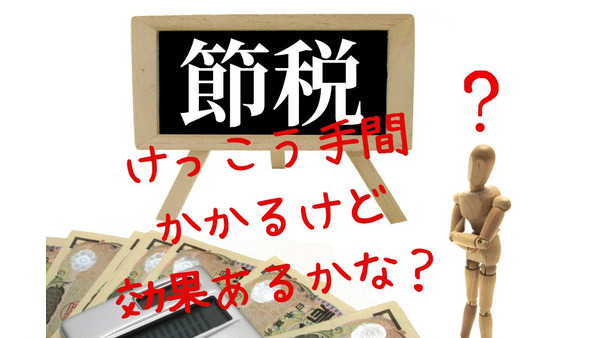
所得税は、給与や個人事業主の売上などに対して課される税金です。 配偶者控除や住宅ローン控除など、節税手段は多数用意されていますが、所得税対策は一定の条件を満たさないと効果を発揮しません。 そこで本記事では、所得税を節税す
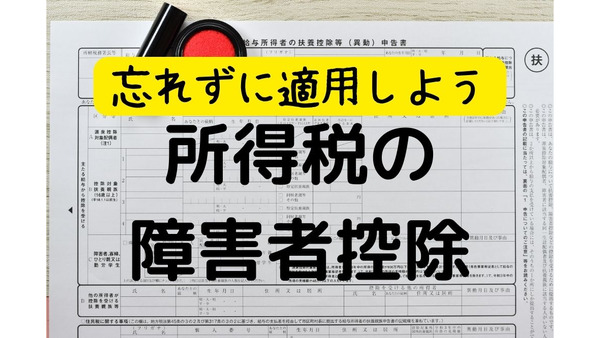
所得税の障害者控除は、本人だけでなく扶養親族に障害者がいる場合にも適用できる所得控除です。 所得控除は要件を満たしていても適用するかは任意となっているため、障害者控除の適用するのを忘れていた場合、所得税を余分に納めている
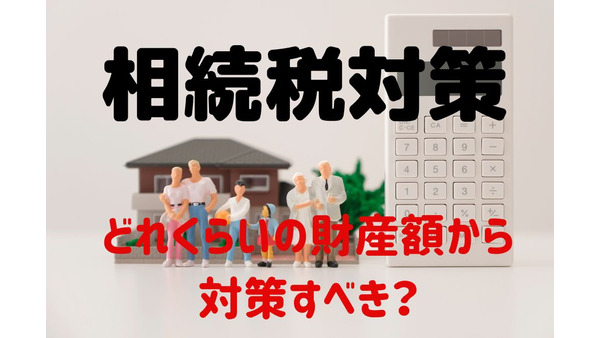
相続税は亡くなった人の財産に対して課される税金なので、相続財産が多い人ほど対策する必要があります。 一方で、相続財産が一定金額以内に収まっている方が相続税対策を行うメリットはあまりないですし、対策するための費用だけ支出が
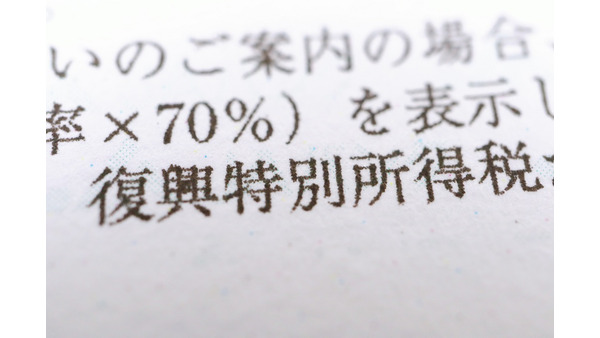
給与や年金などの所得に対し、所得税や住民税が課されていることは知られていますが、平成25年以降はそれらの税金に加え、復興特別所得税も納めることになっています。 復興特別所得税は期間限定の税金ですので、税率や対象期間などの
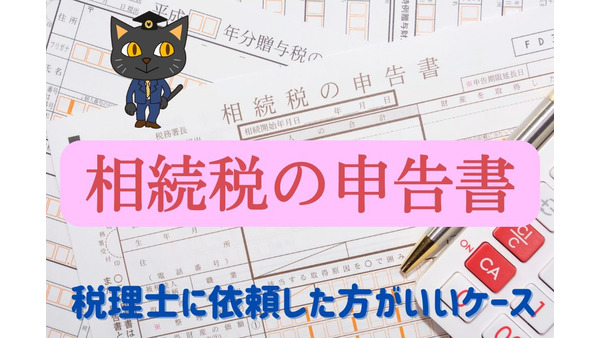
税理士に申告書の作成依頼をする際は、報酬費用が発生します。 そのため相続税に関する費用を抑えたいのであれば、相続人だけで申告書を作った方がいいでしょう。 一方で、税理士は節税に関する知識を持っているため、本記事で紹介する

事業を営む場合、個人事業主として活動する方法と、株式会社などの法人を設立して活動する方法の2パターンあります。 個人事業主として事業を始めた人でも、ある程度の売上が出ると個人から法人に変更する「法人成り」を行う人が一定数
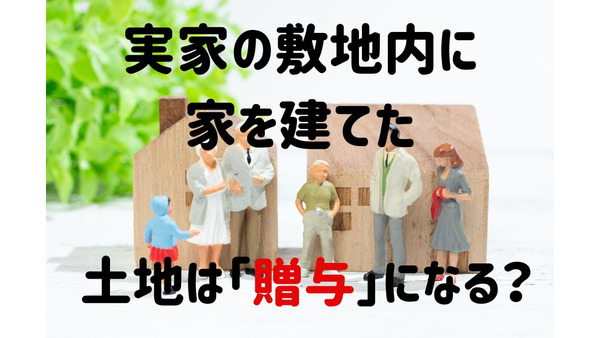
親子間の貸し借りは贈与税の対象となるケースが多く、税務署から贈与税の無申告を指摘されるケースもあります。 そこで今回は、親子間での土地の使用貸借および、金銭貸借を行った際に贈与税の課税対象になるのかについて解説します。

NISAは投資により発生した利益が非課税になる制度ですが、適用期間は限られているため、NISAが終了すれば投資に対する利益はすべて課税対象となります。 そんな中、金融庁はNISAの抜本的拡充を推進しており、先日税制改正の

所得税や贈与税は、確定申告期間が設けられていますので、申告書の提出時期はどなたも同じです。 それに対し相続税の申告期限は、相続の開始があつたことを知った日の翌日から10か月以内と定められているため、相続税の申告書を提出す
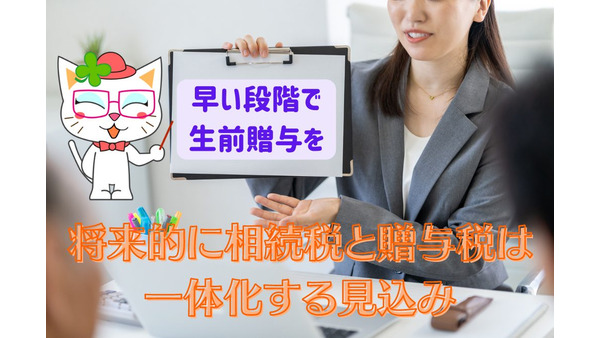
相続税は平成27年に大幅な増税が行われましたし、最近も消費税が増税するなど、税負担が軽くなる雰囲気はありません。 また生前贈与を活用した相続税対策は、将来的に利用できなくなる可能性が出てきましたので、今のうちから相続税対
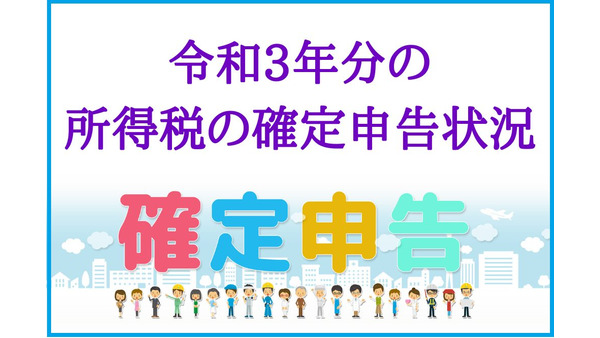
会社員や学生の方は、確定申告をした経験が無い人も多いと思います。 しかし所得税の確定申告書の提出件数は年々増加しており、日本人の6人に1人は所得税の確定申告を行っている計算です。 本記事では、国税庁の「令和3年分の所得税
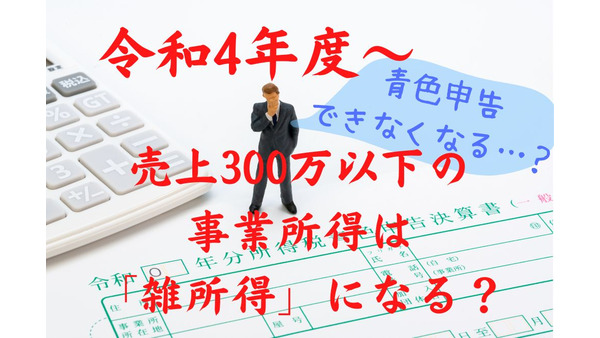
令和4年8月1日に、所得税基本通達の取扱い変更についての意見募集が開始されました。 所得税基本通達とは所得税の解釈について定めたもので、売上300万円以下の事業者は、事業所得ではなく雑所得で申告しなければいけない可能性が
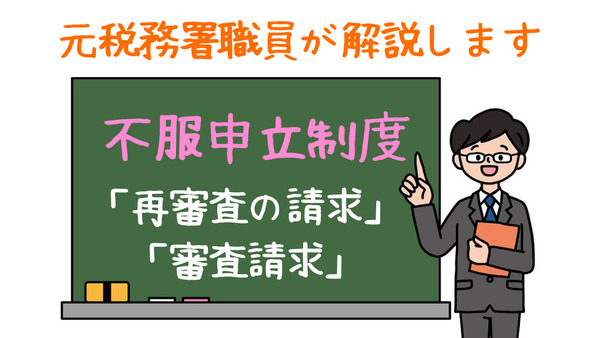
税務調査を受けた際、調査担当者の指摘に納得できないときは、不服申し立てできる制度が存在します。 本記事では不服申し立てで納税者側が勝つ確率と、不服申し立ての結果に納得できなかった場合の対応方法を解説します。 不服申立制度
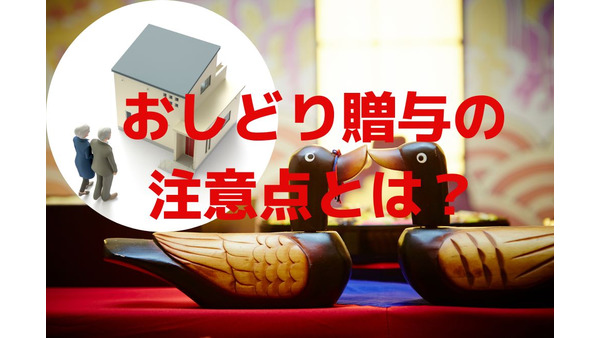
贈与税には、2,000万円までの贈与財産が非課税になる「贈与税の配偶者控除(別名:おしどり贈与)」があります。 贈与税の配偶者控除は夫婦間でのみ利用できる特例制度ですので、適用する前に要件と注意点をご確認ください。 特例

所得税の還付手続きについてはよく話題になりますが、自分や家族が所得税の還付対象者になるかを確認する方法はあまり知られていません。 そこで今回は、所得税の還付が見込まれるケースと、還付手続きをする際の注意点について解説しま
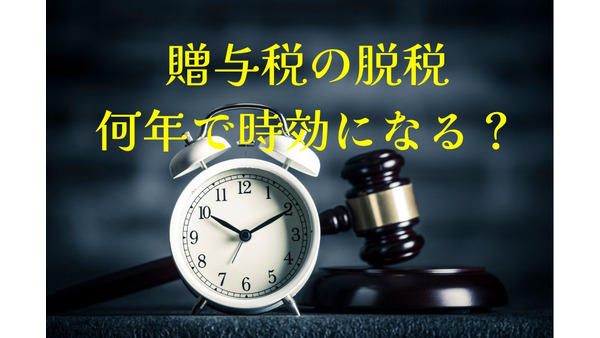
脱税は絶対にダメですし、元税務署職員の筆者としてもオススメすることはありません。 しかし知識として、脱税が成功するのに必要な期間は知っておくのも悪くないと思いますので、今回は贈与税の時効が成立するまでの期間について解説し

税務調査といえば「マルサ」を思い浮かべる人も多いかと思いますが、税務署が行う税務調査と、マルサ(国税局査察部)が行う査察調査は別物です。 今回は税務調査と査察調査の違いと、マルサの調査実績について解説します。 税務署の税

令和4年分の路線価が令和4年7月1日に公開されました。 路線価は相続税・贈与税で土地を評価する際に用いますので、路線価の変動は納税額に直接影響してきます。 本記事では令和4年分の路線価の傾向と、路線価図の見方について解説
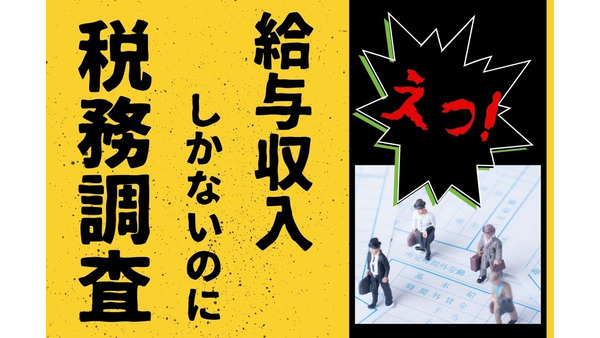
税務署は、会社経営者や自営業者だけでなく、給与所得者に対して税務調査を実施することもあります。 調査を受ける確率は1%かもしれませんが、その僅かな確率に当たってしまうと余計な税金を支払うことになりますのでご注意ください。
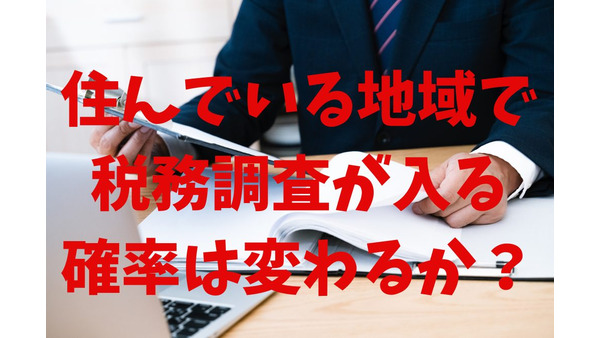
人生で1度も税務調査を受けたことがない事業者の方もいれば、脱税していないのに、何度も税務調査を受けた経験のある事業者の方もいらっしゃいます。 税務調査の対象者になるかは、脱税の有無だけでなく、実は住んでいる(事務所が所在

贈与税には110万円の非課税控除がありますので、うまく活用することで贈与税を支払わずに財産を移動させることが可能です。 特例制度を適用すれば110万円を超える贈与でも非課税にできますが、贈与税の仕組みおよび特例制度の適用

相続税は、各相続人が取得した財産に応じて支払う税金です。 しかし本来相続税を納めるべき相続人が滞納した場合、他の相続人が代わりに相続税を支払うことになる「連帯納付義務」の規定が存在しますのでご注意ください。 相続税の連帯

不動産を所有している人は、毎年固定資産税の支払いが発生しますが、年によって税額が変わることもあります。 また不動産所有者が亡くなった際は、相続人が代わりに固定資産税を支払わなければいけませんので、今回は固定資産税の計算方

不動産をもらう際は、贈与税が発生するかは事前に調べますが、不動産取得税についてはノータッチなことが多いです。 不動産を取得した後に届く、不動産取得税の納税通知書に驚かないためにも、基礎知識は身に付けておきましょう。 不動

贈与・相続で取得した財産が不動産だった場合、贈与税・相続税だけでなく、登録免許税を支払うことになります。 贈与税や相続税が非課税でも、登録免許税を支払うことになるケースもありますので、今回は登録免許税の概要と税率、そして

「贈与税」という税金自体は多くの方に認知されていますが、どのような場面で課税対象になるかはあまり知られていません。 間違った知識は余計な税金を支払う原因となりますので、今回は贈与税に関する基本的な知識をご紹介いたします。

不動産を売却した際は、売却金額と購入金額の差額利益に対して譲渡所得税が課されます。 少しでも納税額を抑えるためには、できるだけ経費を計上するのがポイントです。 ただ一見経費計上できそうなものでも、譲渡所得の計算上、経費に

税務調査で脱税犯が摘発されたことがニュースになることもありますが、現実問題として、脱税している人がそのまま野放しになっているケースも存在します。 確定申告のケアレスミスを指摘された経験がある方なら「自分よりも調査すべき人
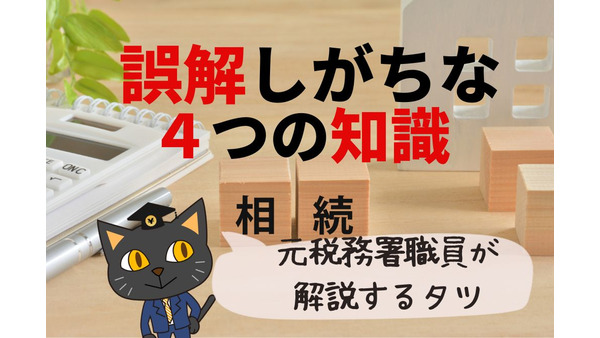
「相続税」という税金の名前は知っていても、実際に手続きしたことがある人はひと握りの方だけです。 申告経験がないと、誤った情報をそのまま覚えていることが多いですので、今回は誤解されやすい相続税の知識について解説します。 1