※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています
注目記事※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています
注目記事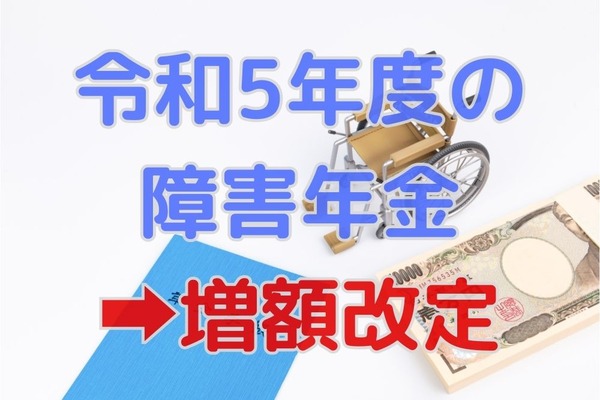
令和5年度の障害年金額が発表されています。 今回は令和5年度の障害年金の年金額と、一定の要件を満たす場合に支給される障害年金の加算について解説します。 障害年金の金額改定 障害年金の額は、老齢年金等と同様に毎年度見直しが

週刊誌などの報道によると、昨年の参議院選挙で初当選した芸能人の方が、約313万円もの国民年金の保険料を未納にしていたそうです。 国民年金に加入して保険料を納付するのは原則として、20歳から60歳までの40年間になります。
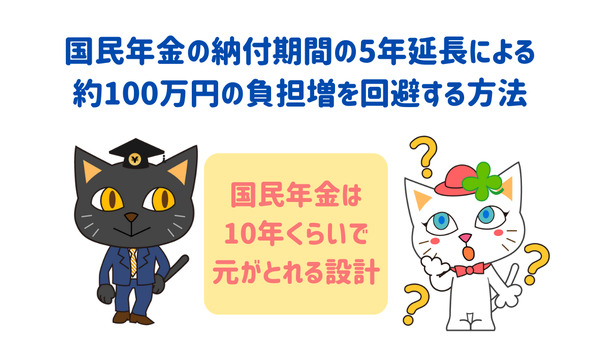
日本国内に住む20歳以上60歳未満の方は、厚生年金保険の加入者などを除き、最大で40年(480月)に渡って国民年金に加入し、定額(2022年度額は月1万6,590円)の保険料を納付しなければなりません。 この40年の間に

「特別支給の老齢厚生年金」や、「老齢厚生年金」を受給できても、年金受給だけでは生活できないため、働きながら年金を受給することを選択する方も多くいるでしょう。 また、年金が受給できても、やりがいなどのために、働きながら年金
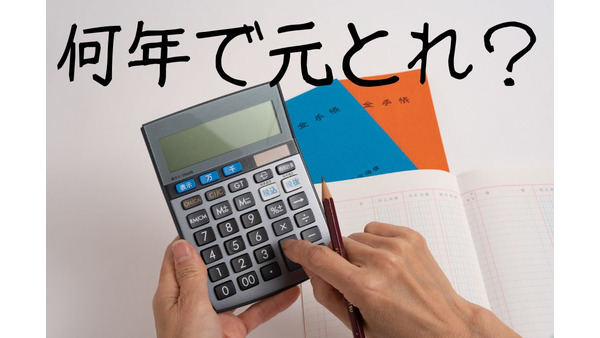
なにかと話題になる年金制度ですが、意外と内容が充実しています。 国民年金は約10年で元が取れることに加え、受け取る年齢を遅らせれば割り増しもあります。 普通の国民年金に200円追加して収める付加年金は、受取時に2年で元が
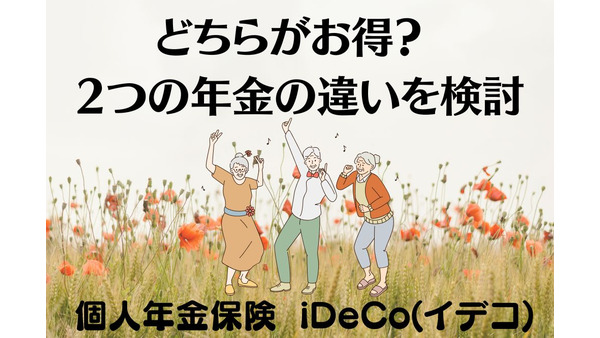
「公的年金だけでは不安」と思っていませんか? 「自分年金」として生命保険会社の個人年金保険の加入や、個人型確定拠出年金であるiDeCoの加入を考えているかと思います。 どちらに加入すべきか迷っている方のために、さまざまな
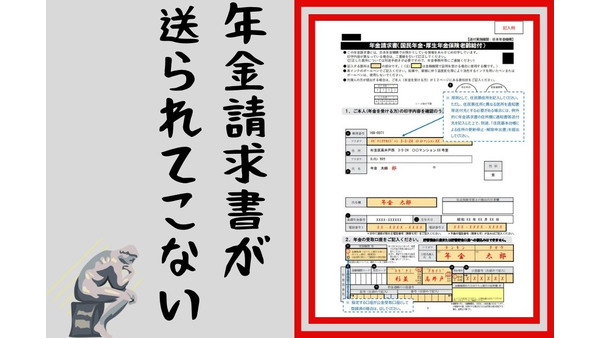
周囲の友人が年金機構から年金の請求書が続々と届いているにも関わらず私には一向に届かないという相談事例があります。 例えば一度も年金制度に加入したことがない(終始海外に赴任していた)という例外的なケースであればあり得ますが

医療費控除のための還付申告が、1年中いつでもできることは意外と知られていません。 同居している家族分だけではまとまった金額にならないと思っていても、別居家族分を合算したり、薬局で買った風邪薬やPCR検査の費用も含めたりす
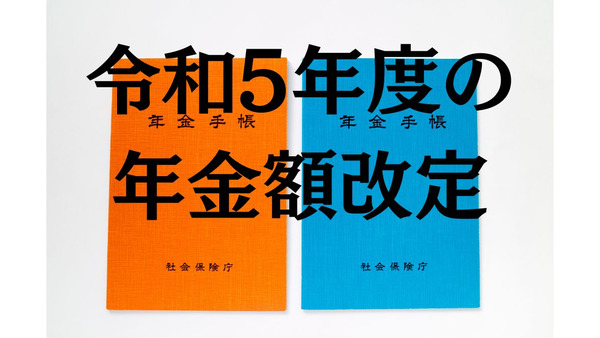
年金の受給額は、現状1年ごとに物価や賃金の変化により見直しが行われています。 年金額の改定は、物価変動率や賃金変動率による改定率からマクロ経済スライドによる調整率を差し引いて算出しています。 2023年1月20日に発表さ
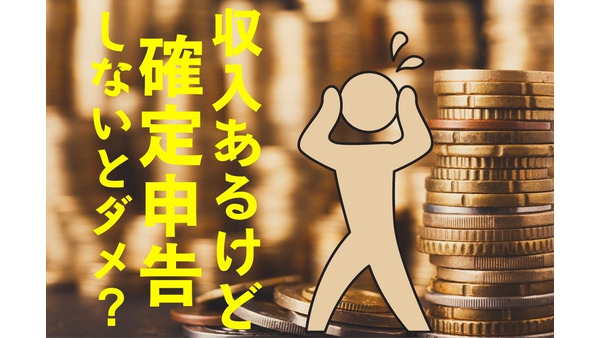
所得税の申告期間は翌年2月16日から3月15日までの1か月で、申告期限を過ぎてから手続きする場合には、ペナルティが課されることがあります。 ただ確定申告は、収入がある人全員がやるべき手続きではありませんので、今回は収入が

楽天スーパーセールや買いまわりで、あと1店舗で10店舗達成なのにと思った時、楽天ふるさと納税を候補にするのはいかがですか。 楽天ふるさと納税は、自治体ごとに「1ショップとして換算」されるため、筆者は少額寄付金自治体を「買

株式の売却損失が発生した場合、要件を満たせば損失金額を最大3年間繰り越すことができます。 ただ損失金額を繰り越すためには確定申告をしなければなりませんし、すべての売却損失が繰越対象になるわけでありません。 「上場株式等に
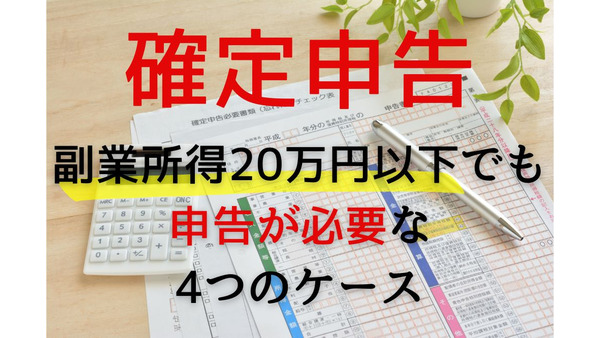
所得税には申告不要制度が存在し、会社員であれば副業所得が20万円なら基本的に確定申告をしなくても問題ありません。 一方で、本記事で紹介するケースに該当する方は、副業による所得が20万円以下であったとしても、申告手続きが必

お子さんがいない家庭は、相続でさまざまな問題がでてきます。 今回は、保険の受取人の確認と検討について考えてみたいと思います。 子供がいない夫婦で、配偶者が親より先に亡くなっている場合 例えば、夫が、夫の親より先に亡くなっ

老後の資産形成として脚光を浴びているiDeCoですが、単に年金を増やせるだけがメリットではありません。 今回はiDeCoの税法上のメリットについて解説します。 iDeCoの税法上のメリットとは iDeCoは原則として国民
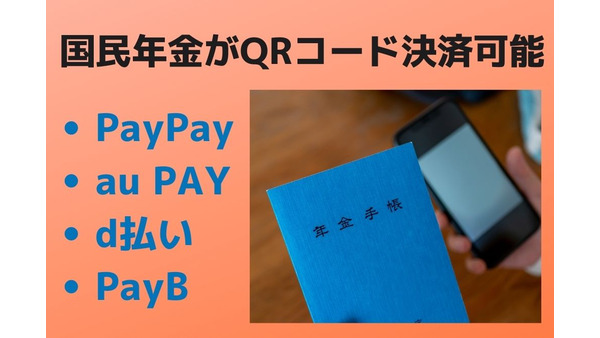
2月20日より国民年金がPayPay・au PAY・d払い・PayBの4つのキャッシュレス決済に対応しました。 これにより、国民年金の納付書のバーコードを読み取るだけで、簡単に納付可能となります。 わざわざコンビニなどに
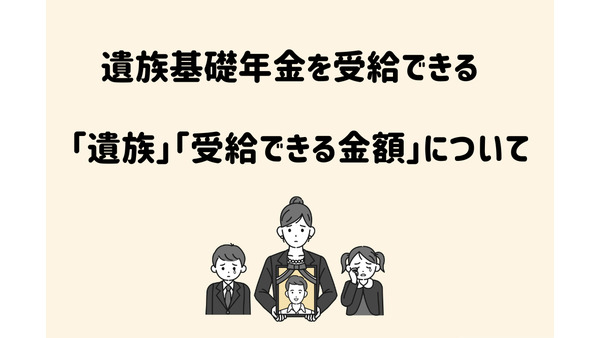
日本の公的年金の中の遺族に対する国民年金の給付として、遺族基礎年金があります。 遺族基礎年金とは、国民年金の被保険者などが亡くなった場合に、その方に生計を維持されていた一定の遺族の方が受給できる年金です。 この遺族基礎年
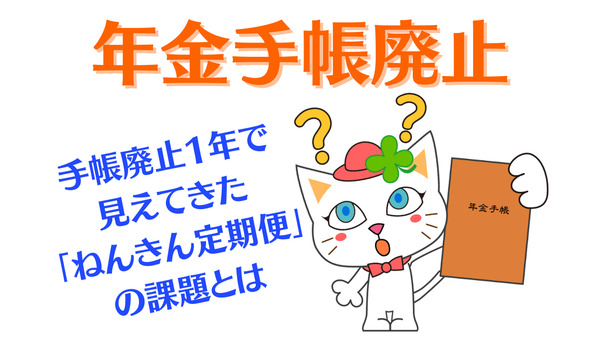
政府は紙やプラスチックなどの健康保険証を、2024年秋頃を目途にして原則廃止し、マイナ保険証(健康保険証としての登録を済ませたマイナンバーカード)に一本化する方針です。 また一本化後にマイナ保険証を保有していない方には、
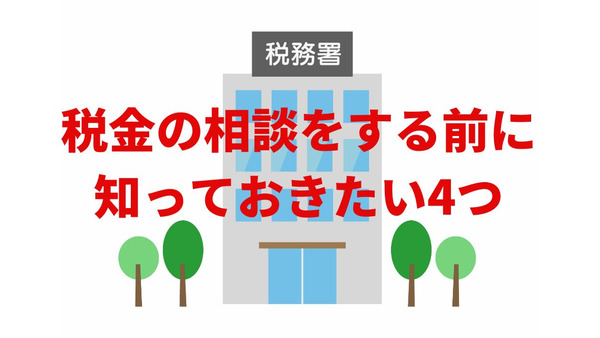
税務署は電話や窓口で税金相談を行っていますが、相談のしかたを間違えてしまうと求めていた回答が得られないことがありますので、税務署へ税金相談をする前に知っておくべきポイントを解説します。 1. 税務署職員は節税アドバイスを
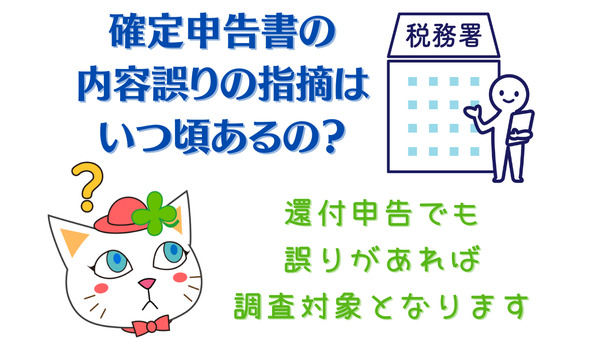
確定申告書の内容にミスがあれば、税務署から誤りを指摘されることになります。 ただ申告書を提出した直後に指摘されるケースは意外と少ないので、今回は税務署から申告誤りの連絡が来る時期について解説します。 税務署は期限前に申告
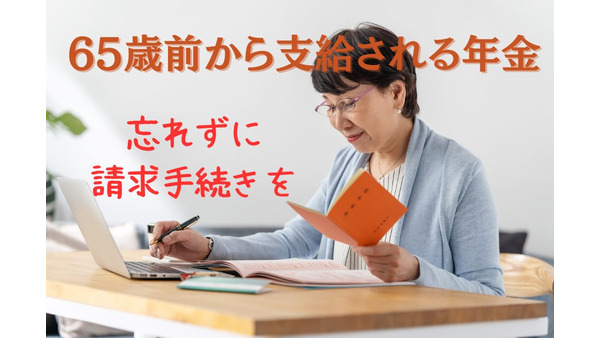
65歳よりも前から支給される年金として、「特別支給の老齢厚生年金」があります。 これを受け取るには老後の年金の受給資格を得ていることと、厚生年金に1年以上加入している必要があります。 法改正によって、75歳までの繰り下げ
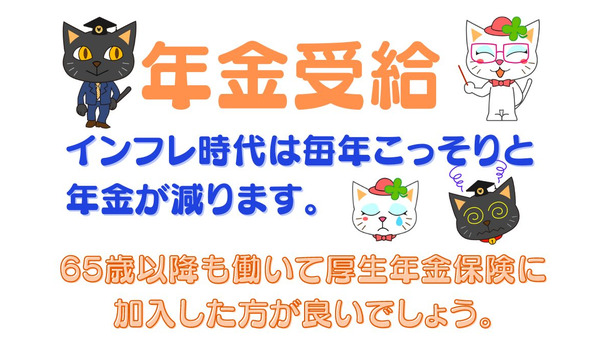
公的年金(老齢年金、障害年金、遺族年金)は、その時々の経済状況に合わせて、年度ごとに金額を改定します。 つまり毎年4月に金額が変わりますが、公的年金は偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)に、前2か月(前々月、

相続人が遺産を取得できる割合(相続権)は民法で規定されていますが、相続人全員が合意していれば、遺産をどのように分割しても問題ありません。 一方、相続税は遺産を「誰が・いくら」取得したかによって、納税額が変動することがあり

2023年度(令和5年度)税制改正大綱で生前贈与の持ち戻し期間が3年から7年に延長されました。 今後の私達への影響とその他の改正を一部解説します。 生前贈与の課税方式 生前贈与には2つの課税方式があります。 おもには、暦
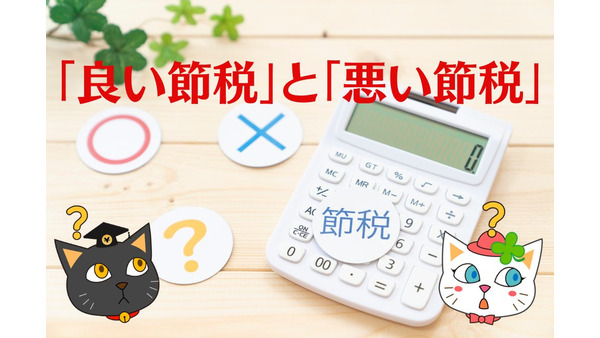
税金を支払う額を抑える方法は多数存在します。 しかし、節税することが必ずしも家計にとってプラスになるとは限りません。 誤った節税術を用いた場合、損をする結果になるケースもあります。 節税する際に注意すべきポイントを解説し

産前産後の期間は、会社員の方であれば産前6週間(双子以上の場合は14週間)、産後8週間の産前産後休暇を取得できます。 自営業の方は、会社員と異なり産前産後休暇はありませんが、健康のことを考えれば産前産後の期間は休んだり、
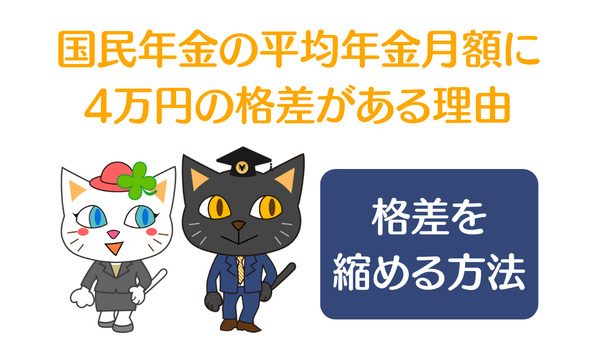
原則65歳になると公的年金制度から支給される年金は、次のような2種類に分かれているのです。 (1) 老齢基礎年金 公的年金(国民年金、厚生年金保険)の保険料の納付済期間や、国民年金の保険料の免除期間などが、原則10年以上

贈与税には「住宅取得等資金の非課税制度」など、多くの節税特例が用意されています。 特例を適用するためには申告手続きが必要ですが、贈与税の特例制度は申告期限を過ぎてから適用することはできませんので注意してください。 特例制
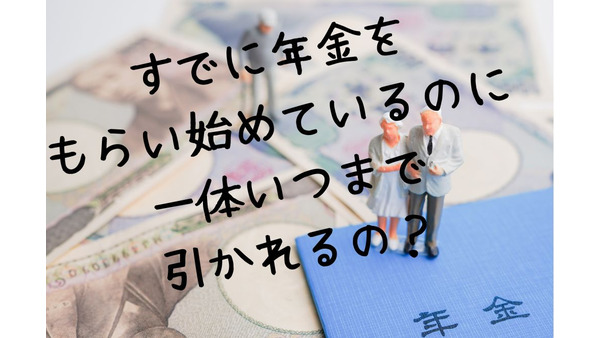
70歳までの継続雇用努力義務化が施行され、旧来よりも長く働くことが前提の社会が訪れています。 給与明細の中でも最も「高額」な保険料である厚生年金の保険料ですが、 「既に年金をもらい始めているのに、一体いつまで引かれ続ける
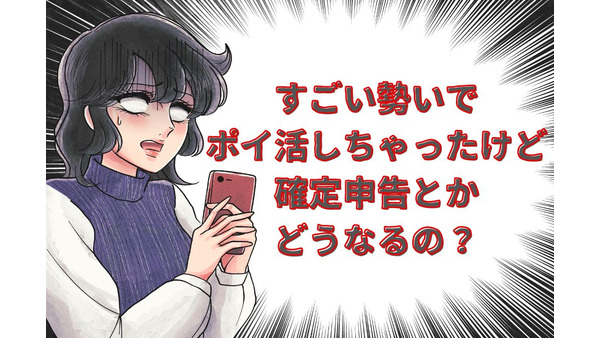
2022年、獲得できた楽天ポイント数は、20万2,662ポイント獲得した主婦が焦ったのは、確定申告です。 調べると、雑所得は年間20万円を超えると確定申告をしないといけないとか……。 そこで、税理士法人の先生に詳しく聞い
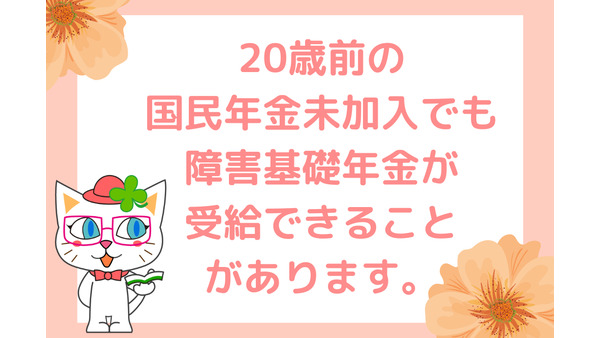
日本の公的年金のひとつとして、国民年金があります。 国民年金は、日本に居住している20歳以上60歳未満のすべての人が加入する必要がある年金制度です。 その国民年金には、障害状態になった方に対する給付として障害基礎年金があ

年金事務所への年金の請求手続きとは別に請求手続きが必要となるものがあり、その中の一つに厚生年金基金というものがあります。 年金事務所での請求手続きでほっと一息という方もいらっしゃるかもしれませんが、今回は厚生年金基金への
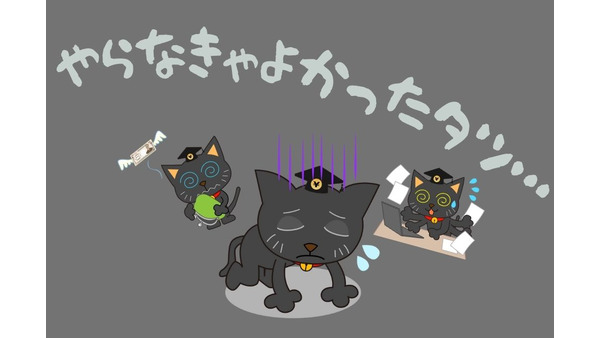
還付申告は、納め過ぎた税金を戻してもらうために行う手続きです。 税金が還付されるのは嬉しいですが、申告手続きをしたことで損をしてしまうケースもありますのでご注意ください。 還付金が少ないと申告手続きの費用対効果は低くなる
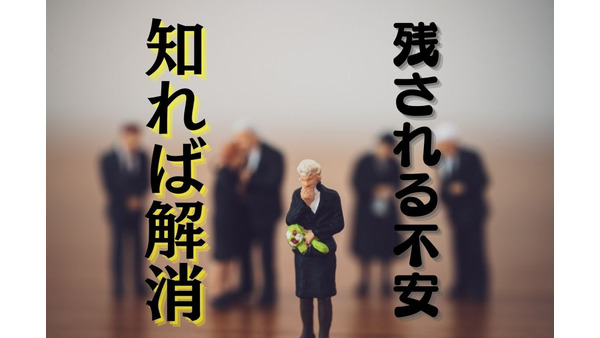
配偶者や家族が亡くなった場合、今後の生活が不安になります。 遺族年金は、残された方の生活保障の目的で支給されるものです。 遺族年金について、心づもりがあると安心できるのではないでしょうか? そこで、遺族年金についてわかり
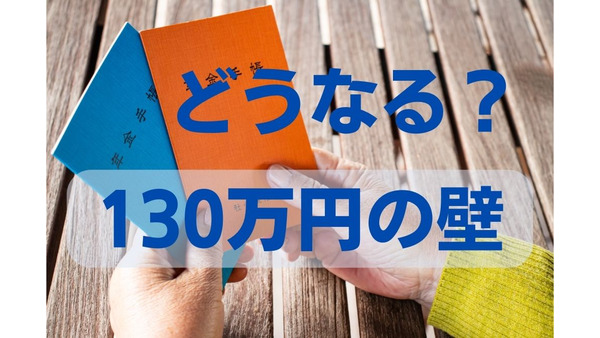
国民年金から支給される老齢基礎年金を65歳から受給するためには、国民年金の保険料を納付した期間や、納付を免除された期間などの合計が、原則として10年(120月)以上必要になります。 また20歳から60歳までの40年(48
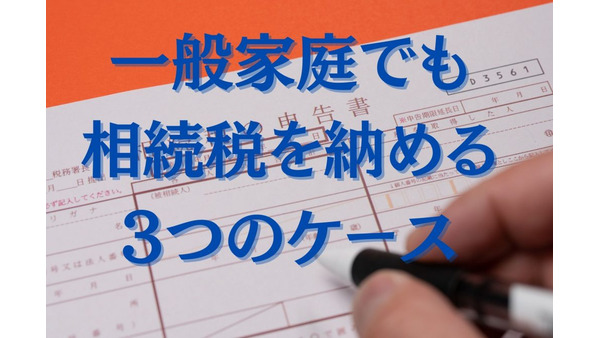
相続税は富裕層が支払うイメージの強い税金ですが、亡くなった人が会社員・公務員だった場合など、一般家庭においても相続税を支払う可能性はあります。 そこで今回は、一般家庭で相続税が発生しやすい3つのケースをご紹介します。 1