※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています
注目記事※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています
注目記事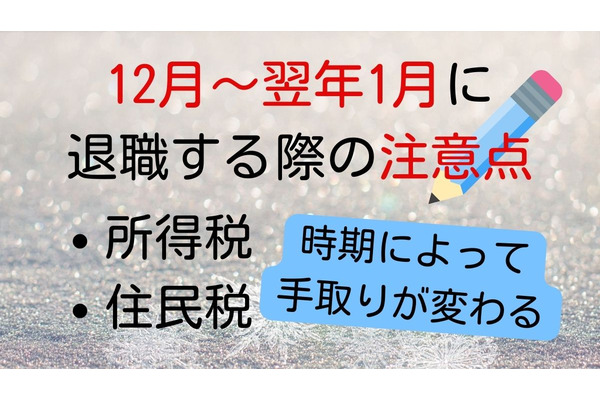
事業収入を得ている自営業者やフリーランスなどは、12月が終わって年収が確定する段階になってから、次のような手順で所得税を計算する場合が多いのです。 (A)年収(1~12月の事業収入の合計額)-必要経費=事業所得 (B)事
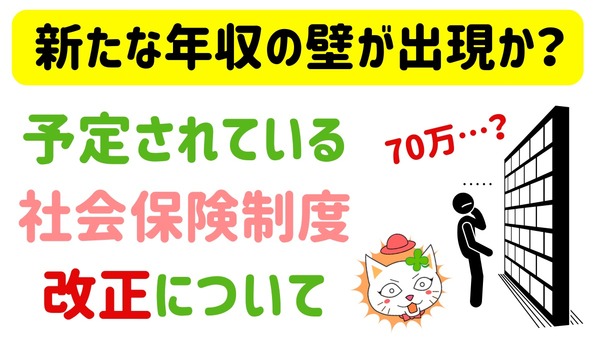
いわゆる「106万円の壁」問題は連日、報道でも多く取り上げられています。 執筆時点では101人以上の企業に勤めるビジネスパーソンの場合、配偶者等の扶養から抜けて社会保険に加入しなければならないこととなっています。 そこで

岸田首相の「減税」が迷走しています。 マスコミ事例では、すでに来年6月には所得税3万円、住民税1万円の定額減税をおこなうということになっていいます。 世帯1人あたり4万円の減税で、4人家族なら16万円の減税になるのだそう
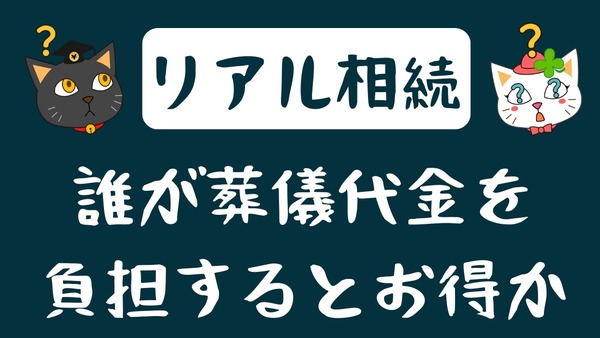
筆者は、かつて会計事務所に勤務して数多くの相続申税告のお手伝いをしてきました。 おかげで、リアル相続がどんなものか知ることができました。 親が亡くなられた場合、子が成人していれば、一般に長男が喪主を務められます。 喪主が
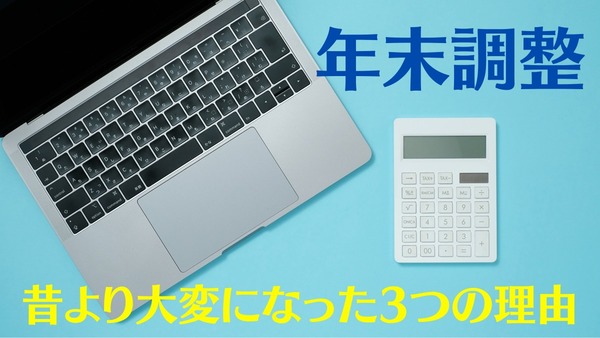
正社員、契約社員、パートタイマーなどの、雇用されて働いている方に課税される所得税は、次のような手順で勤務先が計算する場合が多いのです。 (A) 1月~12月に勤務先が支払った給与(通勤手当のうち非課税になる分などは除く)

年末が近づきますと、勤務先で年末調整を行うことになります。 会社員・公務員の中には、年末調整をしない方や手続きを忘れてしまう方もいるかもしれませんが、年末調整に関するミスは後から対処することも可能です。 そこで今回は、年

所得税の計算は、一緒に住んでいる家族であっても別々に行わなければいけませんが、生命保険料などについては、一定の条件を満たせば家族名義のものも所得控除の対象にすることができます。 そこで今回は、家族名義の保険料を控除対象に
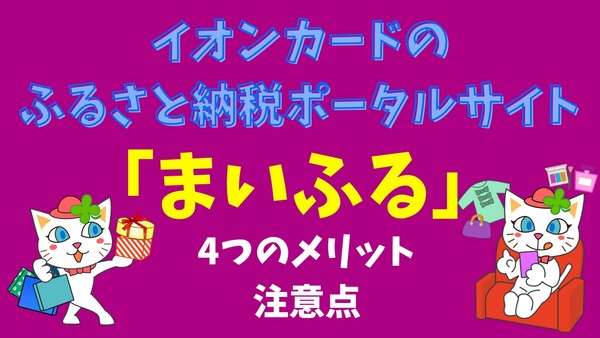
先日ふと思い立ち、9月にふるさと納税をした返礼品が10月の制度改革でどうなったのか、調べてみました。 すると、同じ商品、同じ容量にもかかわらず、1万円の寄附金額は1万4,000円にもなっていました。 実質値上げとは言われ

10月からふるさと納税は制度改革が行われ、内容量が減ったり寄付金額が上がったりと改悪されています。 お得感は目減りしていますが、めげてもいられません 。 調べてみると、楽天ふるさと納税とラクマを併用することでポイントアッ
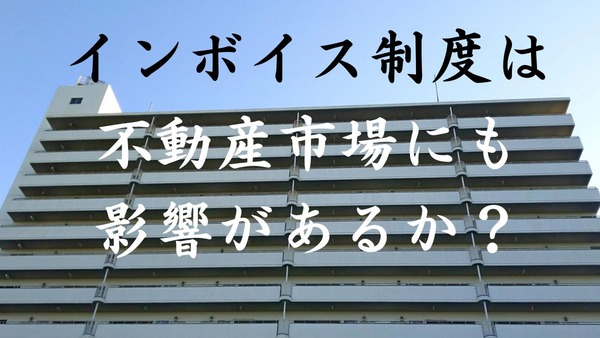
2023年10月より始まったインボイス制度は、事業者が適格請求書を受け取ることで消費税の仕入税額控除ができるようになるという制度です。 従って、「事業者」や「仕入」という言葉から、一般の人々(消費者)にはあまり影響がない
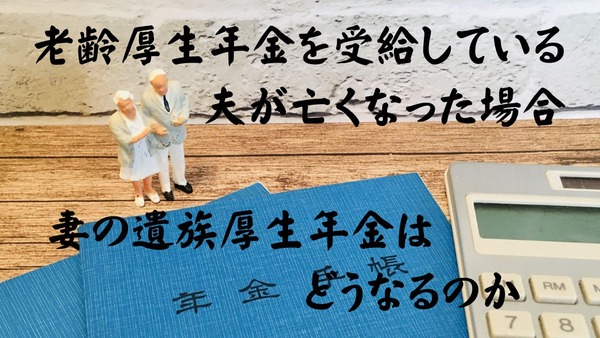
老齢基礎年金(国民年金)と老齢厚生年金(厚生年金保険)は、受給要件を満たした場合に原則65歳から受給できます。 夫の老齢年金を老後の主な収入源として生活している夫婦は、数多くいらっしゃいます。 この老齢基礎年金と老齢厚生

税金は定められた期限までに納付しなければならず、未納となっている場合、税務署は色々な手段を用いて税金を回収します。 そこで今回は、税金を滞納するデメリットと、税務署が税金を回収するために行う手段について解説します。 令和
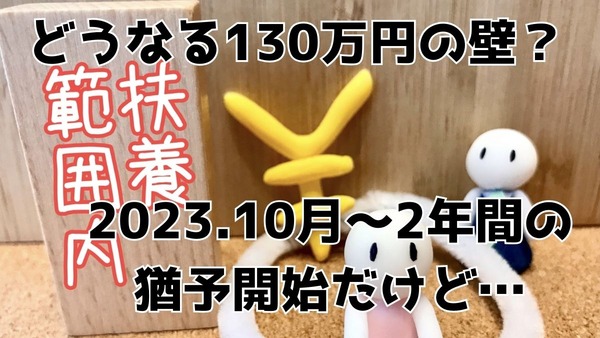
パートで働く方なら毎年気にしている「130万円の壁」。 この「130万円の壁」を越えないように、年末に仕事を調整している方がいかに多いことでしょうか。 しかし、2023年10月よりこの「130万円の壁」がなくなり、2年間
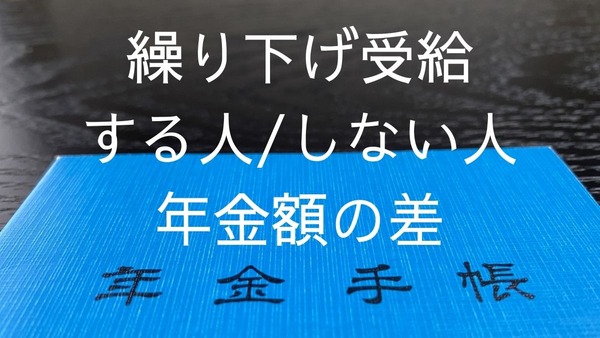
日本の公的年金には国民年金と厚生年金保険があり、その中の老齢のための給付として老齢基礎年金(国民年金)と老齢厚生年金(厚生年金保険)があります。 老齢基礎年金や老齢厚生年金は、基本的に受給要件を満たした方が65歳から受給
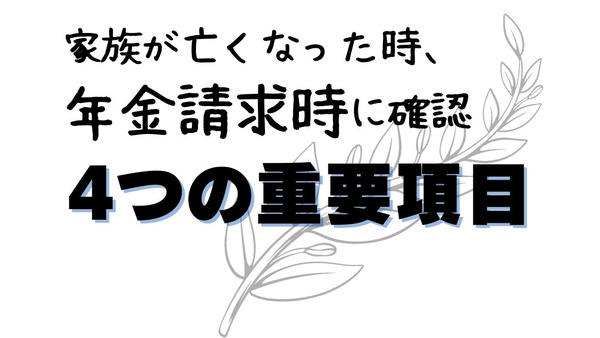
家族が亡くなった場合、多くの手続きが生じます。 年金分野に限定しても確認すべき論点は複数あります。 どのような可能性があり どのような確認をし どこで手続きをすべきか をおさえておくことがいざその時が訪れても慌てずに済む

ふるさと納税のしくみが、2023年(令和5年)10月から一部変更になりました。 制度改正により、ふるさと納税の節税効果が下がることを懸念されている方もいらっしゃると思いますので、今回は制度改正の内容と節税面への影響につい

日本の公的年金の中には、国民年金と厚生年金保険があります。 国民年金と厚生年金保険の老齢のための給付として老齢基礎年金と老齢厚生年金があり、それぞれ受給要件を満たせば65歳から受給できます。 しかし、生活費などの問題によ
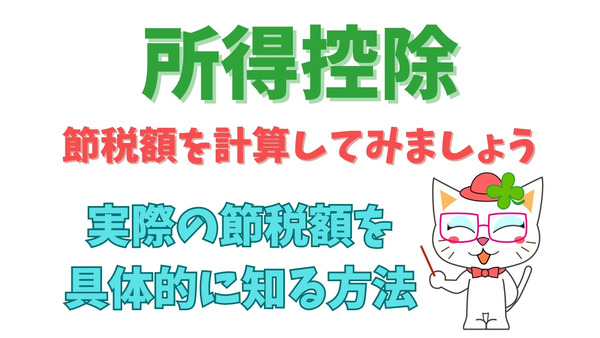
公的年金や私的年金については、税制面での優遇措置があります。 その一つには、本人が加入している年金の掛金全額に対して「所得控除」があります。 ただ、所得控除については、税額計算の仕組み上、掛金全額が節税額ではないのでそ
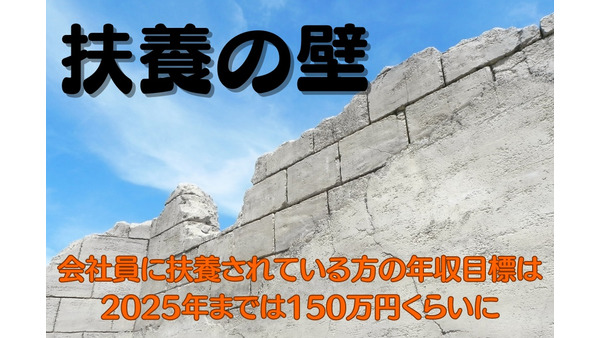
会社員が受け取る給与(月給、賞与)に課税される所得税は、それぞれの勤務先が次のような手順で計算します。 (1) 年収(1~12月の給与の合計)-給与所得控除(年収が850万円超で次のいずれかの要件を満たす時は「所得金額調
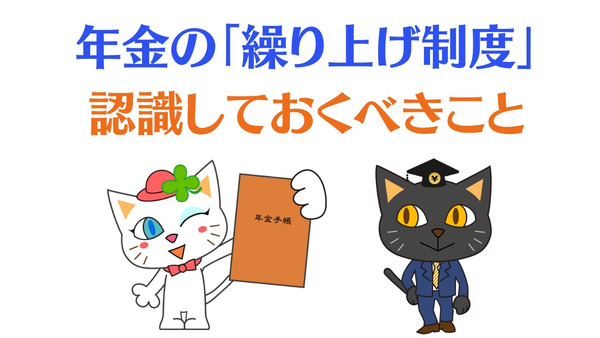
繰り上げの減額率が旧来の0.5%から0.4%となる(生年月日による区分があり)など制度としても改正が進められている繰り上げです。 他方、繰り上げの決断をすべき前には認識しておくべき部分が多数あり、今回は繰り上げ制度におい

会社員でも副業をする方は増えており、不動産賃貸業を副業として選ぶ方もいらっしゃいます。 不動産賃貸は不労所得を得られるだけでなく、節税ができるのも魅力とされていますので、今回は不動産賃貸業を営むことで節税ができる理由につ
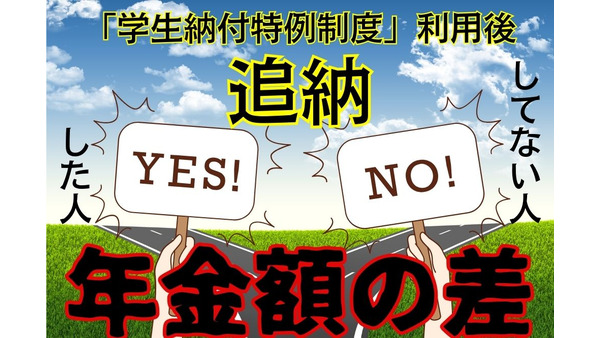
国民年金は、日本に住民票のある20歳以上60歳未満のすべての人が加入しなければなりません。 もちろん20歳以上であれば、収入のない学生であっても例外なく国民年金に加入する必要があります。 国民年金に加入している自営業者や
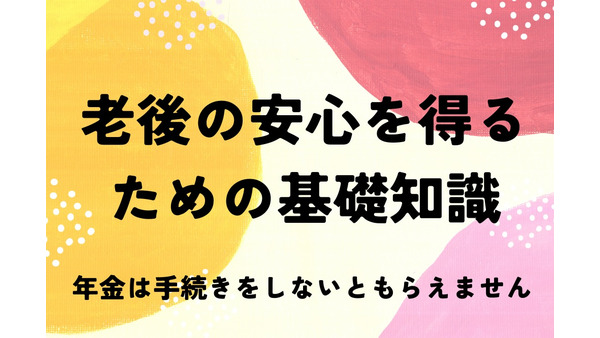
年金は老後の暮らしを支える重要な収入源となりますが、自動的に振り込まれることはありません。 保険料の支払いが難しいときにも、負担を減らす制度はありますが、ご自身で手続きを行う必要があります。 面倒でも、自分で行動を起こさ

今年中(令和5年12月31日)に贈与をし、3年超生きれば、相続税の節税ができます。 もっとも、贈与先が相続人でない孫への贈与であれば、贈与後3年以内の相続が発生しても、相続税法上、3年以内の持ち戻しはありません。 私事で
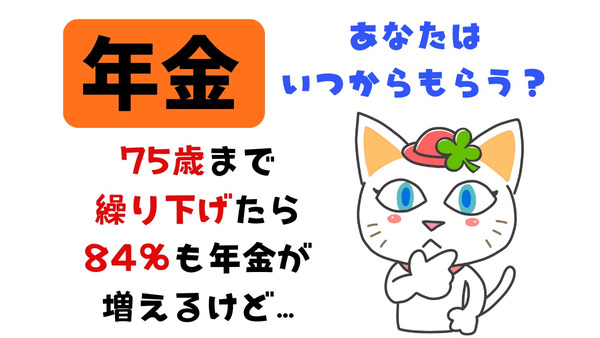
75歳まで年金を繰り下げることで84%も年金が増える制度に変わっています。 ただし、単に増えることばかりに着目するのは本質的ではなく、もちろんメリットを享受するには一定の制度的な理解が必須です。 今回は繰り下げにおいて抜
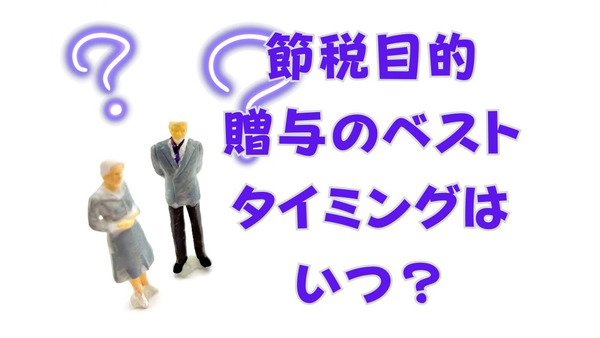
贈与税は個人から財産を無償でもらったときに課される税金ですので、贈与時期を調整するだけでも納税額を抑える(免除)ことが可能です。 そこで今回は、節税目的で贈与するのに適したタイミングと、贈与時の注意点についてご紹介します
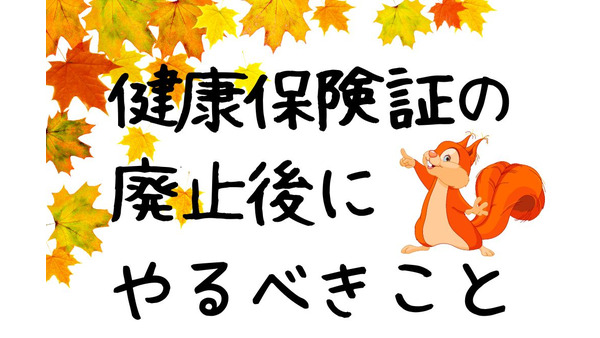
2022年4月以降は新規発行されないため、事実上の廃止になった年金手帳。 年金手帳の2つの役割 役割1:基礎年金番号の確認 例えば企業が社会保険の加入要件を満たす従業員を採用した場合、厚生年金保険の加入手続きを行います。

インボイス制度がスタートすると、消費税の免税事業者からの仕入れは仕入税額控除の対象外となってしまいますが、インボイス制度開始後一定期間は、免税事業者からの仕入れの一部を仕入税額控除の対象にすることができます。 本記事では
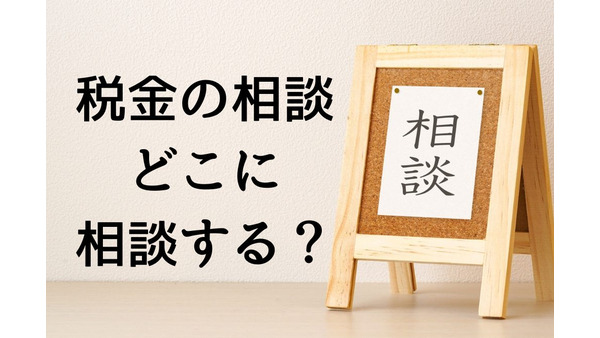
税金に関してわからないことは、インターネット検索を駆使すれば大半は解決することができますが、個別の状況に応じた判断は検索しても答えが出てこないことが多いです。 税金の種類は沢山あり、どこに相談すればいいかわからないと思い

マイナンバーカードの普及、キャッシュレス決済の利用拡大、消費の活性化などを目的にしたマイナポイント事業の第2弾では、申込みによって次のような金額のマイナポイントを受け取れます。 ・ 2023年2月末までに申請してマイナン
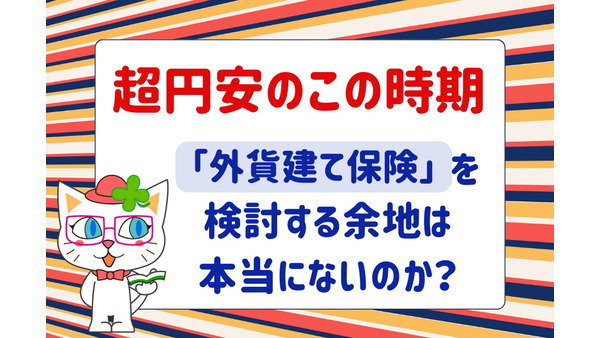
「外貨建て保険はやってはいけない」などの記事が散見されるようになってきました。 今回は一時払ドル建終身保険を念頭に、本当はどうなのか解説します。 外貨建て保険をやってはいけないと言われている主な理由 外貨建て保険をやって
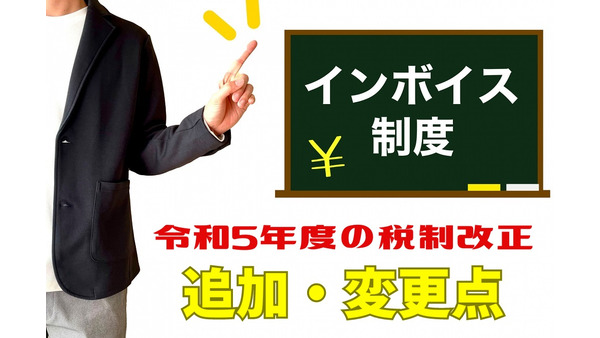
インボイス制度の導入は以前から決まっていましたが、令和5年度の税制改正でいくつか制度の追加・変更が行われました。 本記事では税制改正された内容のうち、特に抑えておくべきインボイス制度のポイントを3つ紹介します。 インボイ
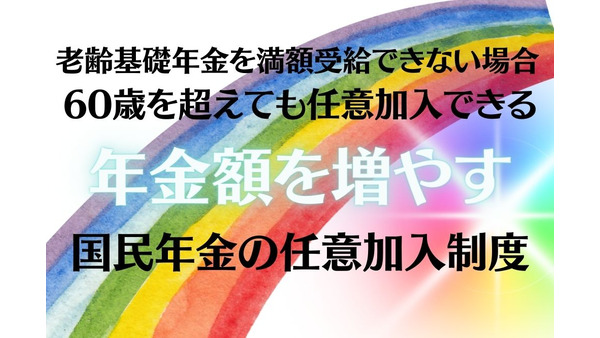
日本の公的年金の中には、日本に住んでいる20歳から60歳未満のすべての方が加入しなければならない国民年金があります。 国民年金の老齢のための給付に、老齢基礎年金があります。 老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期

10月から、「インボイス制度」がスタートします。 収入の少ない事業者ほど財布を直撃される制度なので、さまざまなところで反対運動が起きていて、私も集会への出席や反対署名その他にできる限り協力していますが、「聞く耳」を持たな
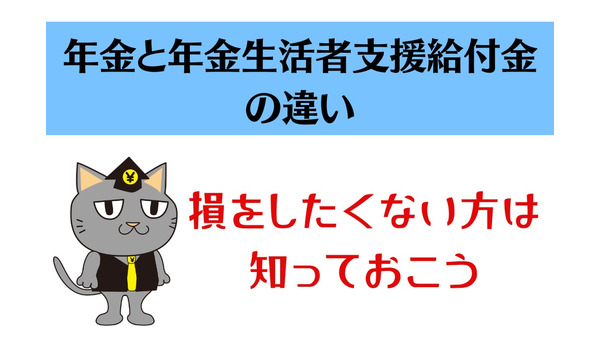
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方は、加入する意思の有無にかかわらず、国民年金に加入しなければなりません。 国民年金の年金としては、一定の障害状態になった時に支給される障害基礎年金、死亡した時に支給される遺族基
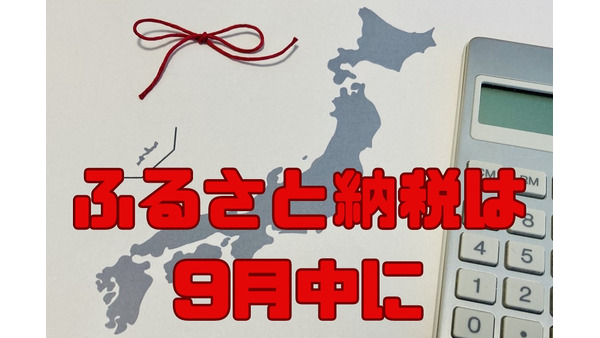
2023年10月にふるさと納税のルールが変更されます。 今回のルール変更によって、返礼品のラインナップ減少や内容量の減少など、利用者にとっては残念な変更が発生すると予想されます。 10月に行なわれるふるさと納税のルール変