※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています
注目記事※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています
注目記事
自営業者等が支払う国民年金は、前納によって安くなります。 1年または2年の前納が申し込める期間は毎年「2月末」までです。この機会を逃さず、前納でお得を得ましょう。 さらに効果は割引だけではありません。最強の支払方法があり

厚生年金保険や健康保険などの社会保険は、社会保険の適用事業所に常時使用される厚生年金保険は70歳未満、健康保険は75歳未満の方が加入対象者です。 社会保険の加入対象者は、国籍や、年金の受給の有無や、性別も問いません。 そ
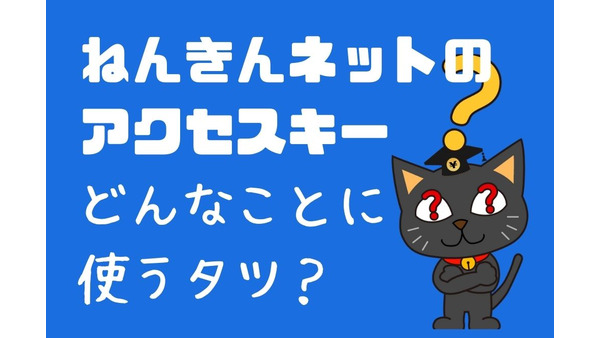
ねんきん定期便などでお知らせされる「アクセスキー」とは、どのような役割を担っているのでしょうか。 マイナンバーよりも長い17桁の番号ではありますが、活用することで一定のメリットがあります。 今回はこの「アクセスキー」につ

自営業や副業による収入がある方は、確定申告書の提出と同時に納税が必要になる可能性もあります。 所得税は納税者が自主的に納付手続きをしなければなりませんが、令和4年12月1日から納付方法の選択肢に「スマホアプリ納付」が追加

【この記事の最新更新日時 2023年2月9日】 国民年金は、最大2年まで前払いできることをご存じでしょうか。 前納すれば年金国民年金保険料が最大で約1か月分もお得になり、さらにクレカ払いにすればポイント還元も受けられます

日本の公的年金制度には、国民年金と厚生年金保険の2種類があります。 その中で、国民年金は、日本に居住している20歳から60歳未満のすべての方が加入しなければならない年金制度です。 一方、厚生年金保険とは、一定の会社員や公

「子どもの通帳を作ったのですが、転勤族なので遠くに引っ越した場合、解約するときとかに、大変にならないか不安です」 これは銀行で私の窓口にいらっしゃったお客様から聞いた言葉です。 子どもの通帳を作ったあとでいろいろ心配にな

心身に障害を背負った際に、年金制度では「障害年金」という形で年金を受け取れます。 ただし、80歳や90歳でも対象になってしまうとなれば、多くの方が該当する可能性があるため、65歳を起点に一定の制約が入ります。 そこで今回

娘の5歳の誕生日が2月にあるため、プレゼントを考えている時にふと 「ふるさと納税の返礼品は種類が多いが、子どもが楽しめる物もあるのかな?」 と気になりました。 高級品や大人向けは多いものの、家族で、小さい子供も楽しめる返

遺族基礎年金、遺族厚生年金、寡婦年金などの死亡に関する年金は、これらの金額がいくらであっても、非課税という取り扱いになります。 また障害基礎年金、障害厚生年金などの障害に関する年金も、同様の取り扱いになります。 それに対

みなさんから寄せられた資産運用などの質問に【金融教育家の上原千華子】が、お答えしてアドバイスをするコーナーです。 第5回目は、 配偶者が受け取る株の配当金と扶養の関係 について気になっている方からの相談です。 相談内容
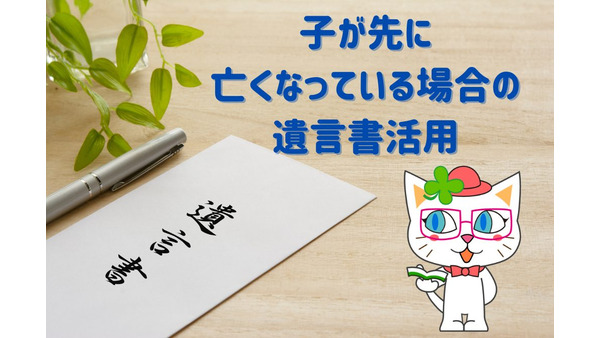
会計事務所の相続実務でまれに「故人の子が先に亡くなっている」というケースがありました。 子が先に亡くなっていますと代襲相続人としてその子の子(孫)が相続人になります。 そこで、故人の子が複数いると、代襲相続人である、子の

贈与税の申告手続きをした経験がある人は少ないと思います。 贈与税は所得税と同様、申告・納付期限が定められており、申告を忘れてしまうとペナルティを課される可能性がありますのでご注意ください。 贈与税の対象者は「財産をもらっ
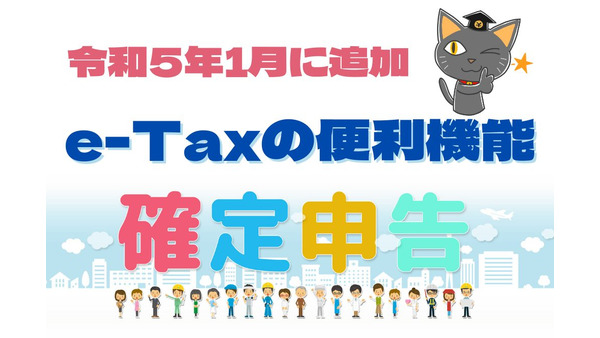
行政手続きのオンライン化は遅れている印象がありますが、e-Taxに関しては利便性向上のために毎年改良が重ねられています。 令和4年分の確定申告を行う今回もバージョンアップしていますので、令和5年1月以降に追加されたe-T

例えば個人事業主については、1月~12月の事業収入の合計額が確定したら、その翌年の2月~3月頃に税務署などで、確定申告(自分で所得税を計算したうえで、その金額を納付する制度)を実施します。 この後に年収などのデータは、税

確定申告手続きは面倒ですが、申告・納付期限までに手続きを行わないとペナルティを課される可能性があるので要注意です。 一方で、申告期限を過ぎた後に申告書を提出しても問題ないケースもありますので、確定申告期間に申告手続きを行

厚生年金保険とは会社員や公務員などの被用者のための年金制度で、適用事業所に常用的に使用される70歳未満の方は、国籍や性別を問わず厚生年金保険の被保険者となります。 パートタイマーやアルバイトなどであったとしても、一定の条

原則として65歳から受給できる年金としては、 国民年金から支給される老齢基礎年金と、 厚生年金保険から支給される老齢厚生年金の、 2種類があるのです。 また生年月日によっては60歳~64歳から、経過措置として支給されてい
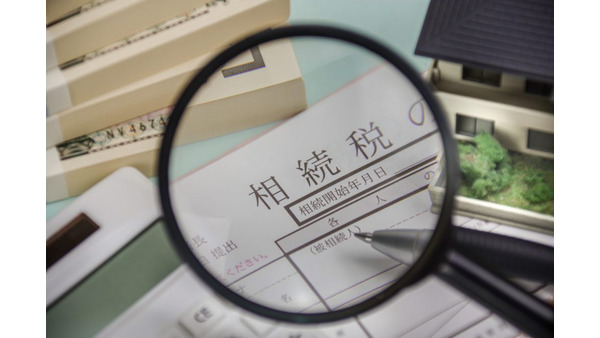
令和5年度の「税制改正大綱」では、NISAと相続税の贈与加算期間の拡大が注目されていますが、相続時精算課税制度の制度内容も大きな改正事項です。 使い方次第で以前よりも高い節税効果が期待できますので、今回は税制改正で「相続

確定拠出年金とは、確定拠出年金法で定められた老後における所得の確保による国民の生活の安定と、福祉の向上を目的とした年金制度です。 確定拠出年金の仕組みは、個人や事業主が拠出した掛金を基に、加入者が自己責任で運用の指図を行

企業などに雇用されている会社員(正社員、パート、アルバイトなど)に課税される所得税は、次のような手順で算出する場合が多いのです。 (A) 1月~12月の給与の合計額(年収)-給与所得控除(年収や親族の障害状態によっては「
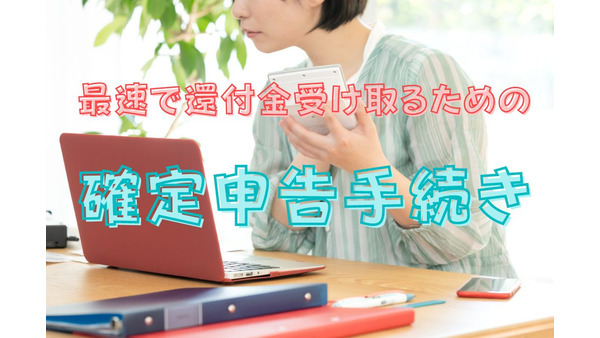
令和4年分の所得税の確定申告期間は令和5年2月16日から3月15日ですが、還付申告であれば、年明けから手続きすることができます。 還付金を早く受け取りたい場合、申告を提出するタイミングも大切ですが、それ以外にも注意すべき

老齢基礎年金や老齢厚生年金などの老齢年金は、受給要件を満たせば原則65歳から受け取れます。 しかし60代といえばまだまだ元気で、65歳を超えても現役で働いている方も多くいます。 そのような方のために、老齢年金は受給開始年
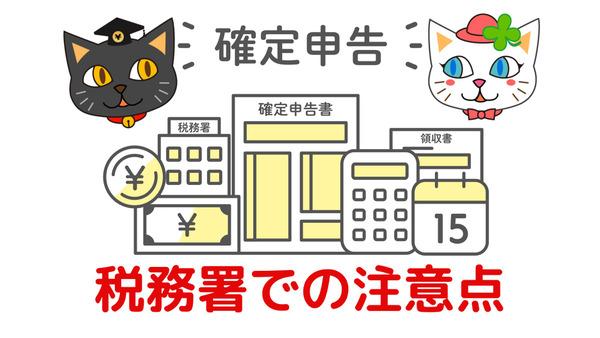
所得税や贈与税の確定申告書は、税務署で相談しながら作成できますが、確定申告期間の税務署はどこも混雑します。 税務署によっては、確定申告相談会場を税務署以外の場所に設置しているケースもありますのでご注意ください。 確定申告
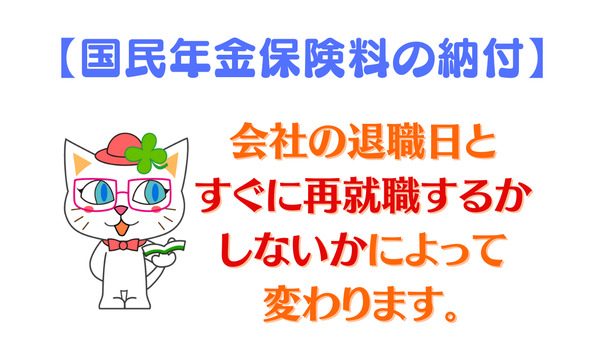
国民年金は、日本に居住している20歳以上60歳未満のすべての人が加入しなければなりません。 国民年金の被保険者は、以下3種類に分類されます。 ・ 自営業者、学生、無職などの「第1号被保険者」 ・ 会社員、公務員などの厚生
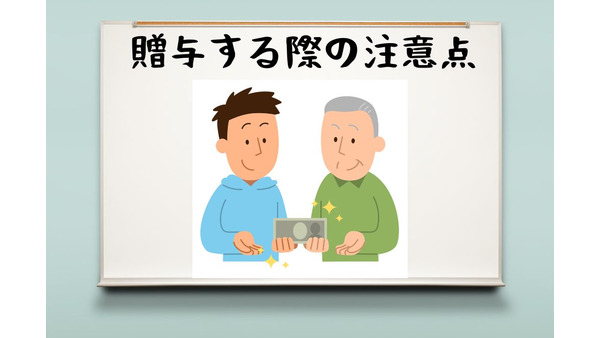
財産贈与は贈与税の対象となるので、税務署にバレないように贈与した方がいいと思っていませんか。 節税の観点で考えた場合、税務署に見つからないように贈与した方が後々問題になるケースがあるので注意しましょう。 今回は税務署に贈

令和5年度の税制改正大綱が発表されましたが、資産税関係では相続税の贈与加算の期間が3年から7年に拡大することが注目されています。 今回は贈与加算制度の概要と、加算対象期間の拡大がどのくらい影響するのかについて解説します。
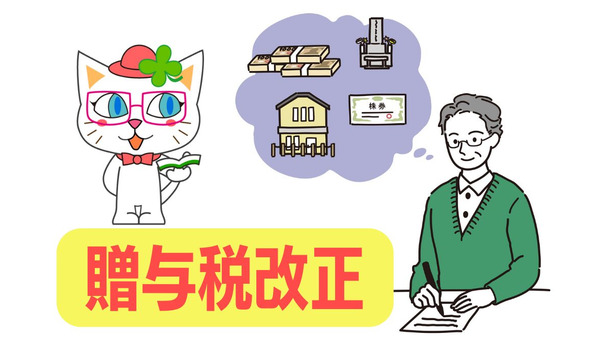
遺産が、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人)以上あると、相続税申告が必要になります。 この相続税の対象になる遺産には、相続開始前3年以内の暦年贈与も含まれ、原則課税対象となります。 ただし相続人以外への贈与

ふるさと納税は、自治体に寄附をすることで税金の還付を受けられるだけでなく、返礼品をもらえるのも魅力の制度です。 しかし返礼品が魅力的で、限度額を超えて寄附をしてしまうこともあります。 そこで今回は上限を超えてふるさと納税

今年も残りあとわずか。 大掃除をする人、帰省する人、出かける人など多いのではないでしょうか。 忙しい年末ではありますが、ふるさと納税の締切もあとわずかです。 忘れないように注意してください。 今回はマネーの達人にて楽天ふ

社会保険(健康保険、厚生年金保険)の加入に関する新基準が、2016年10月から開始され、2017年4月には新基準が少しだけ改正されました。 これらの改正によって、次のような5つの要件をすべて満たした方が、社会保険の加入対
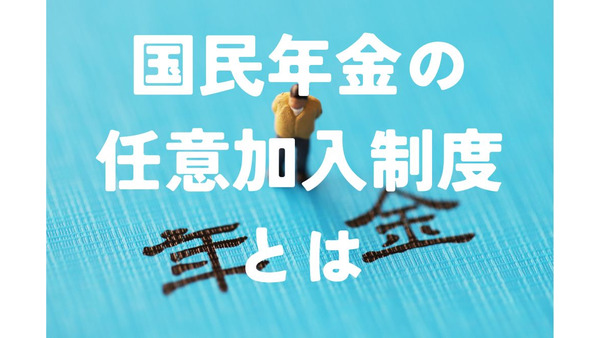
日本の公的年金制度のひとつである国民年金は、日本に住んでいる20歳から60歳未満のすべての方が加入する必要があります。 また、20歳から60歳までの国民年金に加入している40年間は、国民年金保険料を支払わなければなりませ

日本国内に住む20歳以上60歳未満の方は、職種を問わず加入する国民年金から、老齢基礎年金を受給するためには、次のような期間を合計したものが原則として10年以上必要になります。 国民年金の保険料を納付した期間 国民年金の保

令和4年12月16日に、令和5年度与党税制改正大綱が公表されました。 今回の税制改正で大きな目玉となっているのがNISAの大幅な制度変更で、関連法が成立すればNISAの恒久化が実現します。 本記事では税制改正におけるNI

今年も残すところ、あとわずか。 2022年のふるさと納税申込期限も迫っています。 2022年間ランキング ≪画像元:楽天ふるさと納税≫ 集計期間:2022年1月1日~9月30日 楽天ふるさと納税では先日、「2022年間ラ
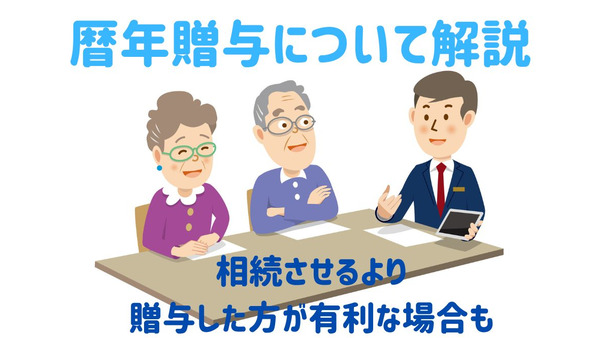
記事掲載時点には令和5年度税制改正大綱が公表されました。 執筆時点で既に増税色が濃そうな内容が漂っていますが、今回は改正が囁かれている暦年贈与について解説します。 暦年贈与とは? 暦年贈与とは簡単に言えば、毎年少しづつ贈