※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています
注目記事※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています
注目記事
産前産後の国民年金保険料が2019年から免除され、出産予定日の前月から4か月間対象。自営業者は自己責任で手続きが必要。
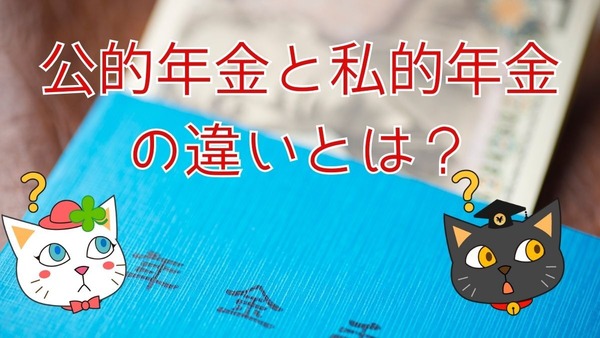
公的年金と私的年金の違いを解説。公的年金には国民年金と厚生年金があり、私的年金は任意加入。物価高に対抗するため、私的年金の重要性が増している。
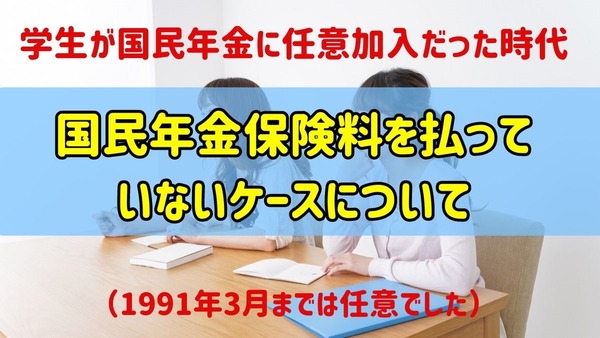
学生は1991年3月まで国民年金に任意加入だったため、未加入者が多い。老齢基礎年金受給には保険料納付が必要で、未納期間は年金額に影響しないが受給資格には含まれる。

物価が上昇傾向にある昨今、自宅の価値がどれくらいあるか気になると思います。
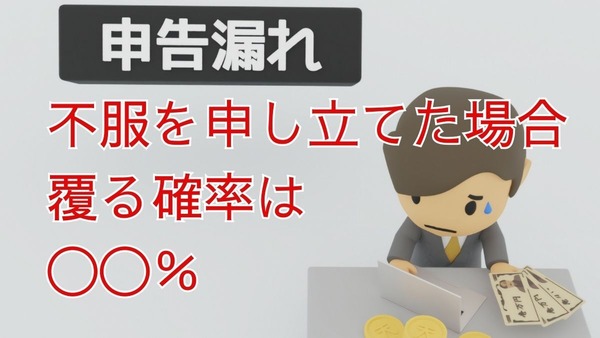
税務調査で納税者が不服を申立てることができるが、調査結果が覆る確率は低い。再調査や審査請求を経て裁判に進むことも可能で、結果が変わる場合もある。
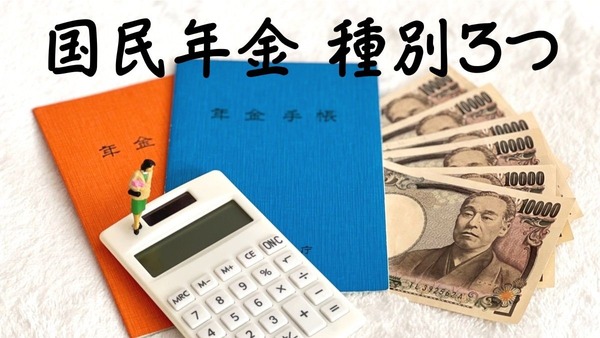
国民年金には第1号(自営業など)、第2号(厚生年金加入者)、第3号(第2号被扶養配偶者)の3種別があり、それぞれ保険料や受給額が異なる。将来の生活にはiDeCoなどの上乗せ制度が重要。
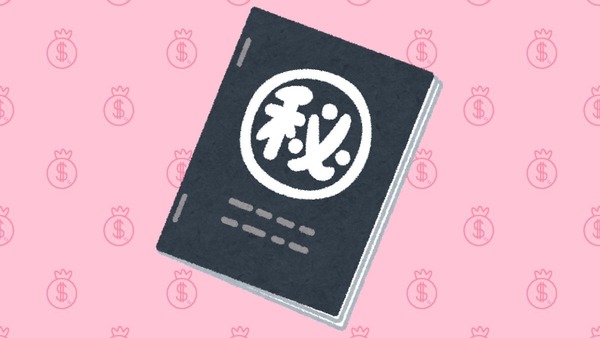
節税手段には秘密はなく、法律内での適法な範囲で行う必要がある。特例制度は厳しい要件があるため、知らないと適用できず、結果的に多くの人がまだ認識していない制度が存在する。
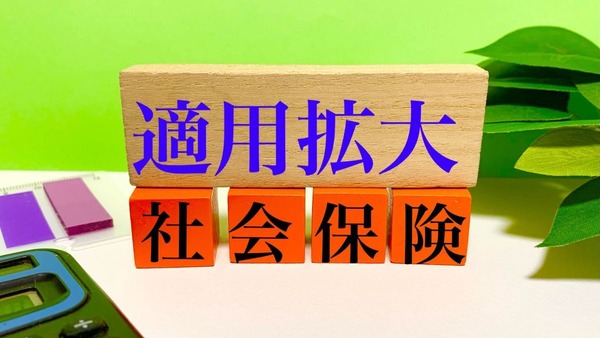
2024年10月から、パートやアルバイトの社会保険加入条件が緩和され、厚生年金保険の対象が拡大します。特定適用事業所の基準も変更され、加入者が増加する見込みです。

「不動産と預金」相続するならどっちら
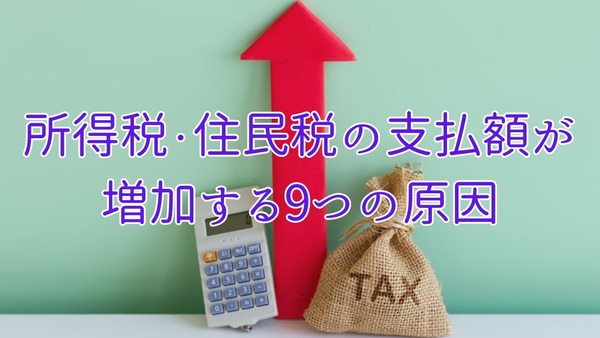
昨年より税金の支払いが増える9つの原因を紹介。給与増加、副業収入、不動産売却、生命保険金などが影響し、控除の減少も関与。特に扶養家族の変動や医療費控除の変化に注意が必要。
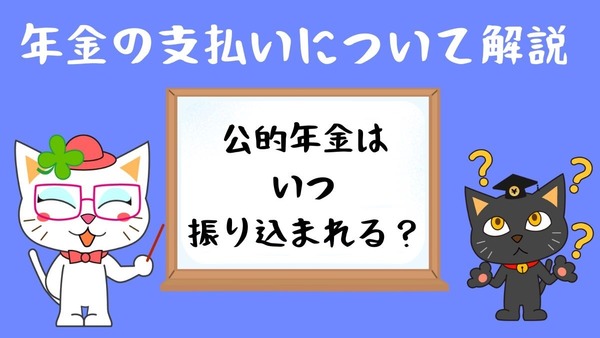
公的年金は偶数月の15日に振り込まれ、金融機関が休みの場合は前日に支給されます。受給には口座名義が必要で、初回請求はタイミングによる影響があります。年金の事項は原則5年間で、請求手続きが必要です。
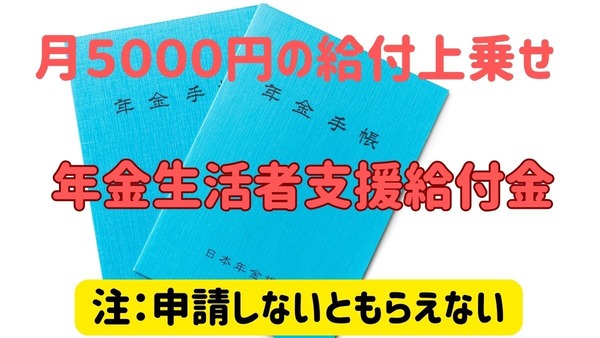
公的年金の支給が物価上昇に追いついていない中、「年金生活者支援給付金」は重要な制度です。所得基準を満たす年金受給者に支給され、申請が必要です。

離婚時に受け取る財産分与や慰謝料は基本的に贈与税の対象外。しかし、過大な分与や節税目的の場合は課税されることがある。贈与税の申告は金額が110万円を超えると必要。

ふるさと納税の人気が高まる中、コスパ抜群のメガ盛り返礼品が注目を集めています。
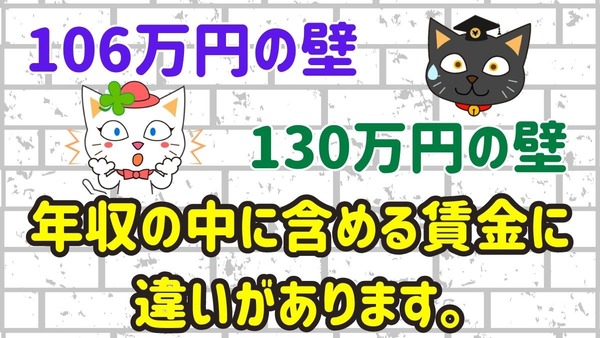
パートやアルバイトなどの短時間労働者は、年収106万円以上などの要件を満たすと、社会保険(健康保険、厚生年金保険)に加入する必要があります。
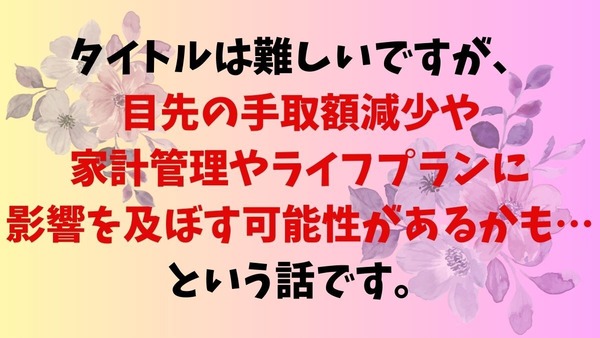
2024年の公的年金財政検証では被用者保険の適用拡大が提案され、所得代替率が変化する可能性が示された。適用拡大は社会保険料負担増を招き、家計に影響を与える可能性がある。
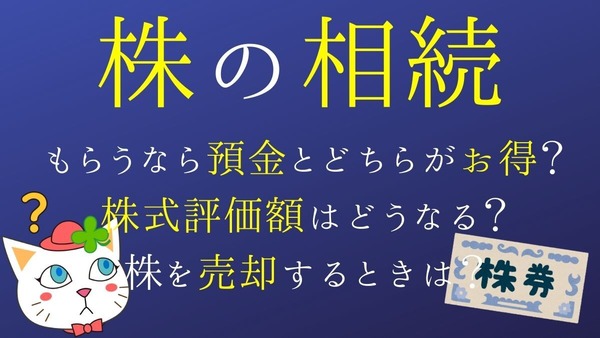
売却時のタイミングで大きく変わる株式の評価
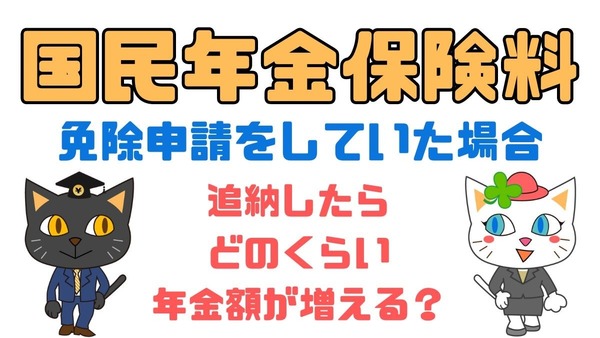
国民年金は、日本に居住している20歳から60歳未満のすべての方が加入しなければならない公的年金です。
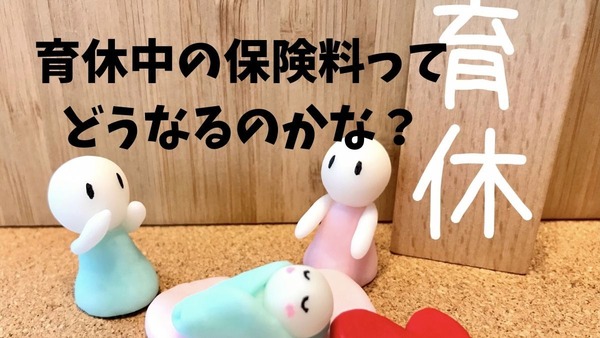
国民年金、厚生年金どの制度においても免除制度というものがあります。
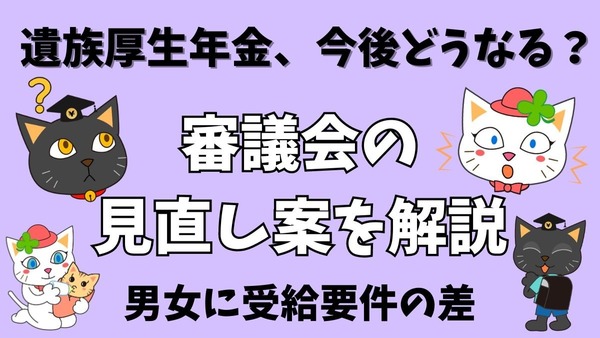
2024年7月30日、厚生労働省の「第17回社会保障審議会年金部会」が開催されました。

サブスク(サブスクリプションサービス)は、年間払いにすると料金が割引されることもあるのに対し、クレジットカードの分割払いは利息が上乗せされますので、住民税も支払方法の違いで損得が発生する疑問を抱かれるかもしれません。
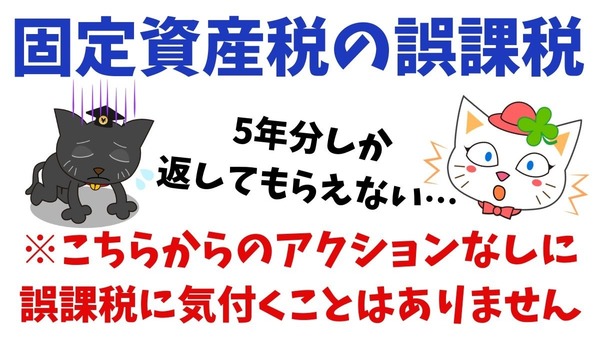
先日、クライアントから、固定資産税の誤課税に関する報告がありました。
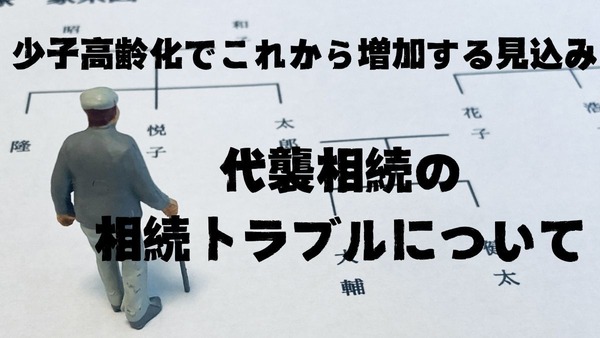
日本の平均寿命(令和5年)は女性が87.14歳、男性が81.09歳と長寿大国であり、寿命が延びたことで相続人が高齢者となるケースも増えています。
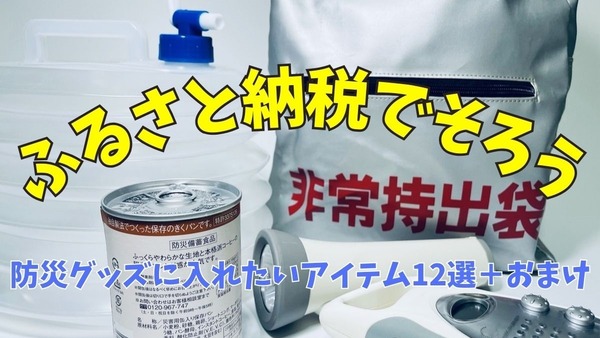
8月に入り大きな地震が続き、防災グッズを揃えなくてはと感じた人も多いはずです。
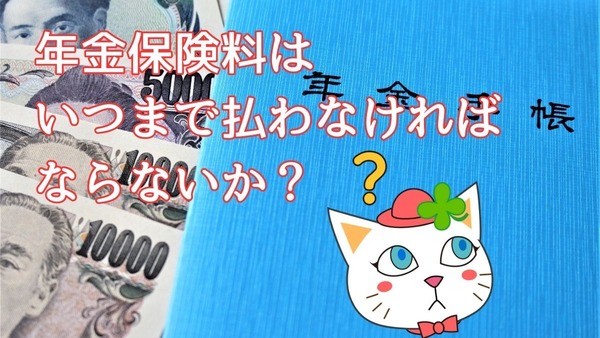
日本の年金制度は国民年金と厚生年金の2種類。国民年金は第1号被保険者が60歳まで、自分で支払うが、免除制度もある。厚生年金は被保険者期間中に70歳まで支払う必要がある。
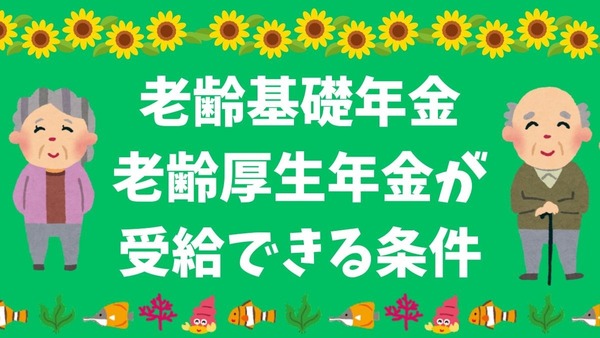
日本の公的年金は、日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての方が加入する国民年金と、会社員や公務員の方が加入する厚生年金保険の2種類です。
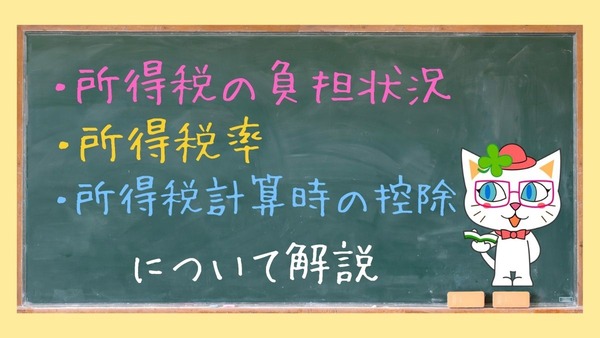
日本の国の歳入は年間約110兆で、内訳は所得税18%、消費税20%、法人税13%、相続税・揮発油税・酒税等9%、その他9%、公債金(借金)31%です。
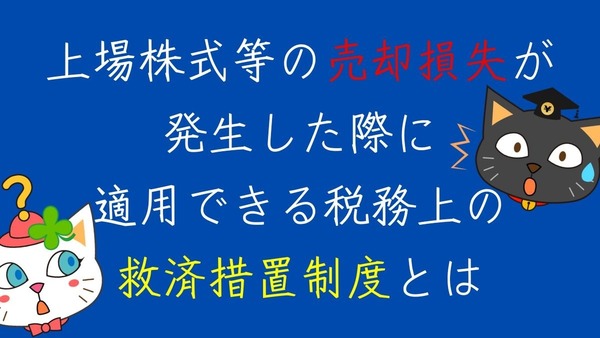
2024年8月5日、日経平均株価が過去最大の下げ幅を記録するなど、8月の株式市場は大きく荒れています。
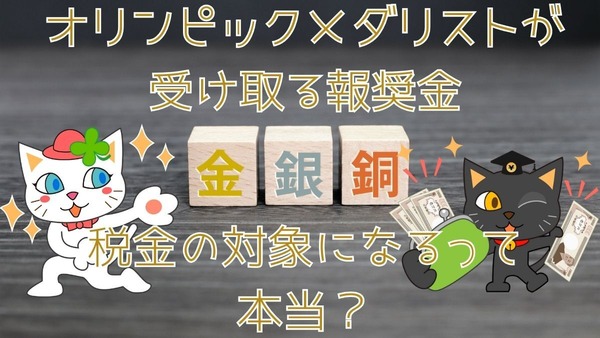
2024年パリオリンピックでも日本人選手の活躍が目覚ましいですが、オリンピック・パラリンピックでメダルを獲得した選手に対しては報奨金が支給されます。

会社を辞めて自営業者になった場合、将来の老齢厚生年金はどうなる?

マイホームを購入した際、一定の要件を満たすことで所得税の住宅借入金等特別控除(通称:住宅ローン控除、住宅ローン減税)を適用することができます。
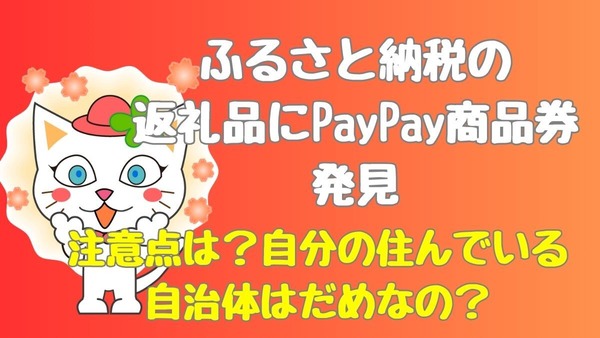
総務省がふるさと納税の「仲介サイトのポイント付与」を禁止すると発表したことは、記憶に新しいかとも思います。
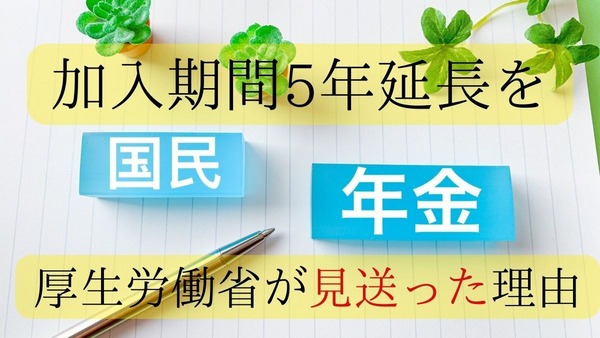
数年前から大きな話題になっていたのは、60歳という国民年金の加入上限を65歳に引き上げして、加入期間を5年延長する案です。

失敗しても勉強代では済まない住宅の購入
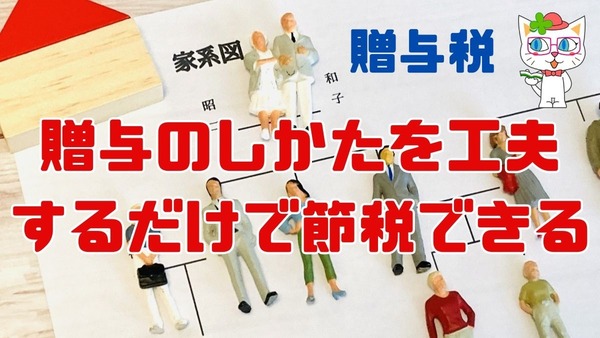
贈与税は、財産を無償でもらった際に課される税金であり、贈与税の申告手続きは財産を受け取った側(受贈者)が行うことになります。
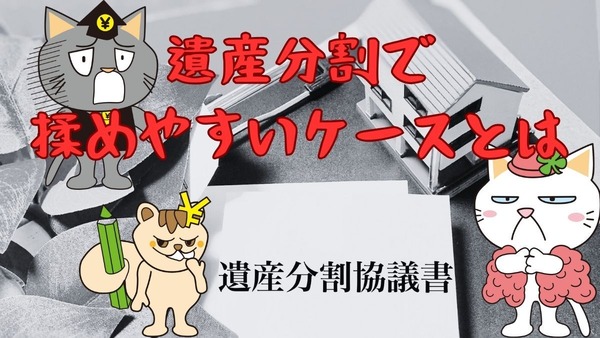
相続税は相続人が取得した財産の割合に応じて納めることになりますが、遺産をどのように引き継ぐかは相続人間で話し合って決めます。