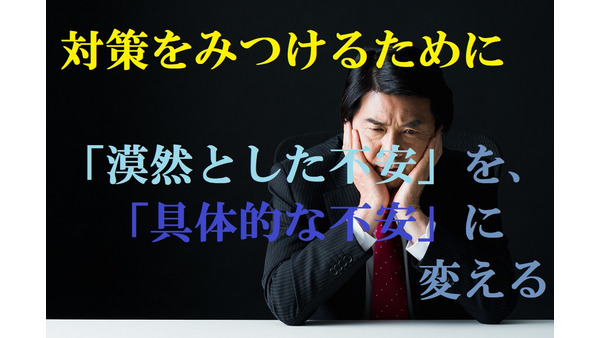
年金の支給開始年齢の引き上げを考える 2017年も終わりに近づいたので、今年話題になったニュースを振り返ってみると、個人的には「年金の支給開始年齢の引き上げ」に関連したニュースが、もっとも印象に残っております。 その発端

「遺族年金失権届」 夫の死亡によって受給権が発生した、遺族年金(遺族基礎年金、遺族厚生年金など)を受給している妻が、再婚(事実婚を含む)した時は、その遺族年金の受給権は消滅します。 また親の死亡によって受給権が発生した、

「就業規則」の作成 常時10人以上の従業員を使用する使用者は、従業員の賃金や労働時間などについて定めた「就業規則」を作成して、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。 これは労働基準法に定められた義務のため、就
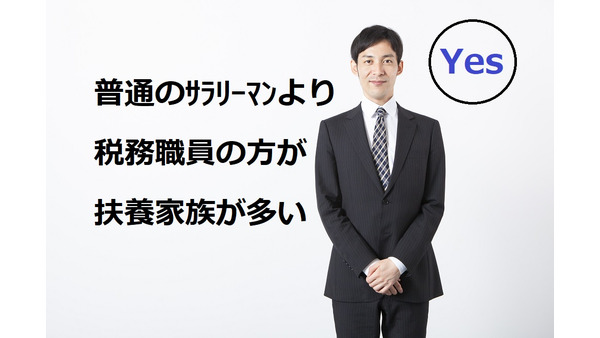
元国税調査官の大村大次郎さんが書いた本に、税務職員は普通のサラリーマンよりも、扶養家族が多いという話が記載されておりました。 その理由として税務職員は、「扶養控除」の対象になる扶養家族の範囲などを詳しく知っております。

2018年以降は新聞や雑誌などで特集されているように、夫が38万円の配偶者(特別)控除を受けるための妻の年収制限が、「103万円以下」から「150万円以下」に拡大されます。 また2018年以降は夫の年収が「1,120万円

この記事の最新更新日時:2021年7月19日 将来受給できる年金額の大まかな目安 ※1円未満の端数については、50銭未満は切り捨て、50銭以上1円未満は1円に切り上げしております。 詳しい説明は後半でしていきます。 早見

【読者の質問】 「配偶者控除が拡大で「パートの壁」の年収の目安は103万円から150万円へ 「4分の3基準」に注意ってどういう意味?」 上記記事を拝見しました。いろいろと細かく説明があり、わかりやすかったのですが、いつも

原則65歳から支給される老齢厚生年金の受給権者に、一定の要件に該当する配偶者がいる場合には、加給年金が上乗せして支給されます。 また加給年金の対象になっている配偶者が65歳になった時には、加給年金は振替加算に切り替わ
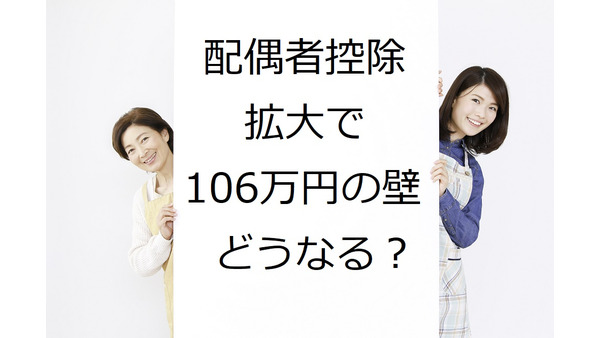
2016年10月からは皆さんもご存じのように、社会保険(健康保険、厚生年金保険)の適用が拡大されました。 具体的には次のような要件をすべて満たすと、本人の意思の有無にかかわらず、社会保険に加入する必要があります。 (A)

「加給年金」と「振替加算」 原則65歳から支給される老齢厚生年金の受給権者に、一定の配偶者がいる場合には、「加給年金」が上乗せして支給されます。 また加給年金の加算対象となる配偶者が65歳になると、加給年金は振替加算に切

2017年6月30日に厚生労働省から、2016年度の国民年金の納付率が発表されました。 それによると納付率は前年度比で1.7ポイント上昇し、65.0%になったそうです。 過去最低の納付率だった2011年度の58.6%と比

読者の質問 65歳男性 昨年結婚 厚生年金38年間 妻 30歳 外国人 年金の支払いはなし 子供なし 現在無収入 外国在住 今年で65歳になり加給年金の申請をしようと思っていますが、妻は30歳の外国人で昨年結婚しました

マネーポストWEBに掲載されていた、「70歳以上の自己破産が急増 2005年は3.05%で2014年は8.63%」という記事によると、高齢者の自己破産が増えているようです。 この記事の中で紹介されている、日弁連が実施した

自民党の小泉進次郎議員らが作る「2020年以降の経済財政構想小委員会」は、2017年3月末頃に、保育や幼児教育を実質的に無償化するため、「こども保険」の創設を提唱しました。 もちろん無償化を実現するには、財源が必要になる

テレビのワイドショーなどを見ていると、芸能人やスポーツ選手が離婚したという話題が、よく取り上げられております。 こういった番組に登場する芸能人やスポーツ選手は、高収入の方が多いため、慰謝料などの金額の多さに驚きを感じます

先日近所にある本屋さんへ行ったら、「不機嫌な長男・長女 無責任な末っ子たち」(著:五百田達成)という本が、山積みにされておりました。 個性的な表紙に興味を持ったので、購入して読んでみると、この本は世の中の人を出生順によっ

2017年度に入ってからも、社会保障の保険料の値上げや給付減が相次いでおり、暗い気持ちになります。 ただ明るい話題もないわけではなく、例えば雇用保険については、失業率の改善などを受けて、他の社会保障とは逆に、保険料の値下

国民年金の第3号被保険者となり、自分で保険料を納付する必要のない「専業主婦」、または「公務員」についても、2017年1月から個人型の確定拠出年金(以下では愛称に決まった「iDeCo」で記述)に、加入できるようになりました

内閣府の有識者会議である「高齢社会対策の基本的在り方等に関する検討会」は、 年金の支給開始を繰下げ(遅くする)すると、年金額が増額する「繰下げ制度」の上限を、現在の70歳から75歳程度まで、延長する案 を発表しました。

読者の質問 国民年金基金とiDeCoはどっちをやった方がいいの? 私の回答 iDeCoの掛金は収入などに合わせて、柔軟に変更できるのですが、国民年金基金の掛金はそれが難しいのです。 また国民年金基金は加入時に適用された予

健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度などの公的医療保険に加入している方が、医療機関などの窓口で支払う自己負担の割合は、年齢によって次のようになっております。 ・ 70歳未満の方… 3割(ただし小学校就学前の乳幼児は

2017年6月30日に厚生労働省から、次のような計算式で算出される、2016年度の国民年金の納付率が発表されました。 (実際に保険料が納付された月数 ÷ 保険料を納付する必要のある月数)×100 なお保険料の納付を全額免

ファイナンシャルアカデミーは2017年5月23日~5月28日に、2017年の夏のボーナスに関するアンケートを実施し、その結果は「夏ボーナスに関するアンケート」(pdf)にまとめられております。 これによると2017年の夏

先日ある有名な俳優さんが17歳の女性と、飲酒及び不適切な関係を持ったと週刊誌に報道され、所属事務所から無期限の活動停止が発表されました。 このように所属事務所が厳しい対応を取ったのは、未成年にお酒を飲ませただけでなく、青
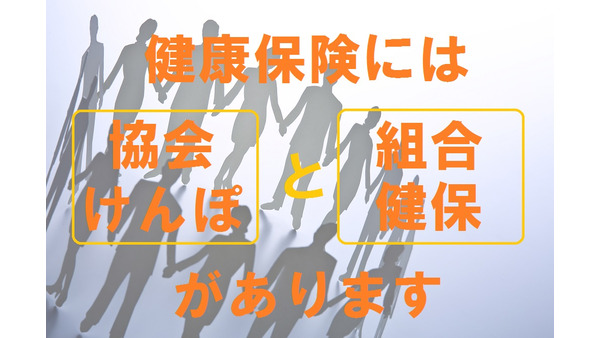
会社員やその被扶養者が加入する健康保険は、次のような2種類に分かれます。 ・ 全国健康保険協会が運営している「協会けんぽ」 ・ 健康保険組合が運営している「組合健保」 後者の健康保険組合を企業が単独で設立する場合には、常

個人型の確定拠出年金もはじまりました 2017年1月1日から、国民年金の第3号被保険者となり、自分で保険料を納付する必要のない「専業主婦」、または「公務員」についても、個人型の確定拠出年金(以下では愛称に決まった「iDe
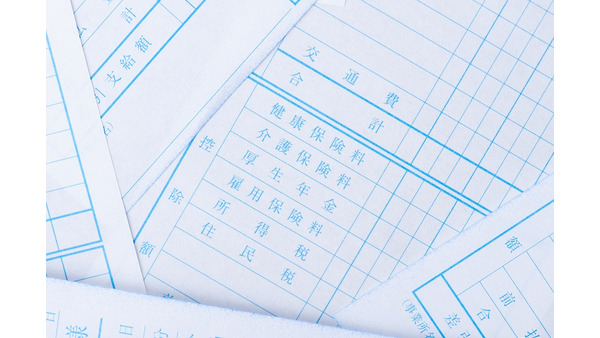
社会保険(健康保険、厚生年金保険など)の世界には、一般の常識と少しかけ離れたことがあり、この手続きの仕事を始めた当時は、少し戸惑いを覚えました。 そのひとつが社会保険の資格喪失日であり、普通に考えれば「社会保険の資格喪失

自営業者やフリーランスなどが加入する国民年金の、保険料の納付率を向上させるため、厚生労働省と日本年金機構は強制徴収する対象者を、2017年度から拡大する方針です。 あるインターネットの掲示板を見ていたら、こういった対象者

老後資金準備の為のiDeCo活用を例え話に 日頃から運動不足を感じていたAさんは、近所の公園にジョギングコースがあるのを発見したので、思い切って走ってみようと思いました。 Aさんは友人のBさんに対して、この話をしたところ

日本老年学会と日本老年医学会のワーキンググループは、平成29年1月5日の会見において、高齢者の定義を従来の「65歳以上」から、「75歳以上」に引き上げするよう提言しました。 日本の社会保障制度は65歳を基準にしているもの

厚生年金保険や国民年金などの公的年金は原則的に、現役世代から徴収した保険料を、その時点の年金受給者に年金として配分する、「賦課方式」という仕組みで運営されております。 例えるなら会社員や自営業として働く子供が、高齢になっ

2017年春からの値上げ 4月の初め頃に新聞やテレビなどを見ると、新年度から変わることの特集をやっております。 それらによると2017年度からは、 ・ オリーブオイル ・ サラダ油 ・ のり ・ 生乳などの食品 ・ タイ

2017年3月27日に参議院本会議で採決が行われ、自民党や公明党などの賛成多数で、2017年度の予算案が可決・成立しました。 この予算案の歳出(支出)を見てみると、高齢化で増え続ける社会保障費の伸びを抑えたにもかかわらず
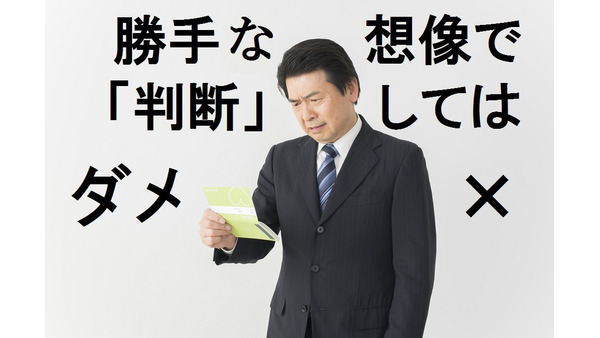
2017年1月から専業主婦、公務員、勤務先が確定給付企業年金などの企業年金を実施している厚生年金保険の加入者も、個人型の確定拠出年金に加入できるようになりました。 これにより60歳未満の公的年金の加入者であれば、国民年金

先日マネーポストWEBを読んでいたら、「銀行・生保の顧客満足度 大手が上位に入らないのはなぜか」という記事が、掲載されておりました。 この記事によると、生命保険に関する顧客満足度調査(2016年度サービス産業生産性協議会

物理学者でありながら、随筆家や俳人でもあった寺田寅彦さんが残した、「天災は忘れた頃にやってくる」という有名な言葉があります。 あえて説明する必要はないかと思いますが、「地震や台風などの天災は、その被害の恐ろしさを忘れた頃