
確定申告書の代理作成は、税理士資格を持つ人のみができる仕事です。 そのため申告書作成は税理士に依頼することになるのですが、税理士の中にも良い税理士もいれば、素人とあまり変わらない知識しか持っていない税理士もいます。 せっ

会社の転勤や転職に伴って、自宅を買い替えるケースは少なくありません。 旧自宅を手放した後に新自宅を購入できればベストですが、現実には旧住宅を売却するよりも先に新住宅を購入することもあります。 そのような時に気になってしま
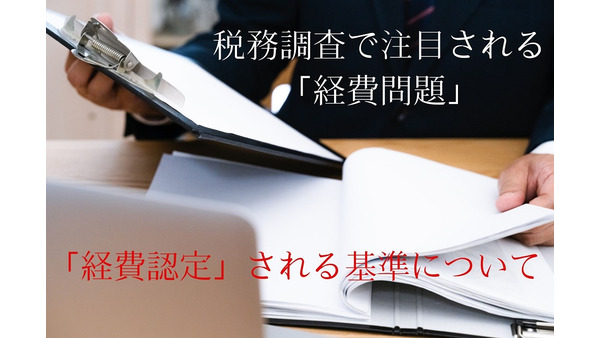
税務調査で注目されるのは脱税事件ばかりですが、法律の解釈が間違っていたことを税務署が指摘することも少なくありません。 代表的なのが、経費に該当する費用の判定です。 先日脱税が発覚した芸人さんも、私用の洋服を経費に入れてい

スマホ決済が乱立する中で、利用する決め手となるのがポイント還元率の高さです。 PayPayやLINEPayなど、ポイント還元率20%を打ち出したスマホ決済も多かったですが、実は付与されたポイントは所得税の対象です。 その
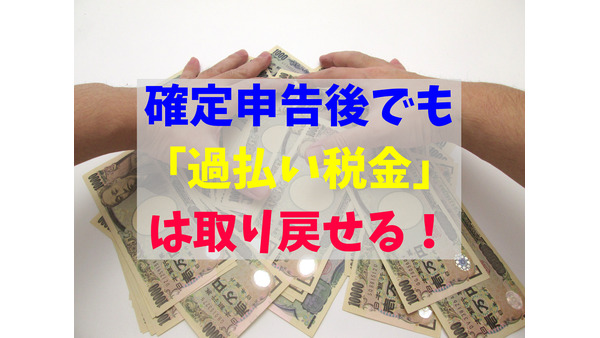
所得税の確定申告期間は2月16日から3月15日までですが、申告期限を過ぎた後でも還付申告の手続きができます。 また、一度確定申告の手続きをした後に内容の間違いを見つけた際には、「更正の請求書」を提出することで納め過ぎた税

贈与税の節税対策は、毎年やらないと損をする仕組みです。 贈与税には基礎控除額110万円があり、基礎控除額以下の財産であれば贈与税は非課税です。 ただ、この基礎控除額は毎年の使いきりであり、今使わないとそのまま切り捨てにな
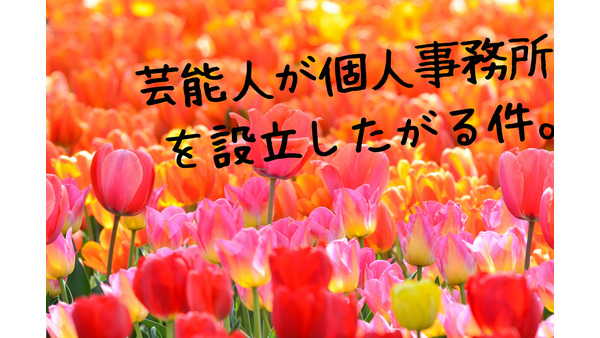
お笑い芸人のチュートリアル徳井さんの脱税報道により、徳井さんが個人事務所を介して芸能事務所から報酬を得ていることがわかりました。 所属事務所があるのにも関わらず、わざわざ個人事務所を設立する動機は節税です。 実は、法人を

政府は令和初の人事院勧告を完全実施することを決定したため、公務員の給料がまた増加します。 「消費税は増税するのに、どうして公務員の給料は増えるの?」 と思うかもしれませんので、公務員の給料が決まる仕組みと、令和元年の人事

会社員の方は、副業が会社にバレないか心配ですよね。 確定申告の手続きを間違えてしまうと、副業が会社にバレる危険がありますので、注意が必要です。 しかし、確定申告書で気をつけるべきポイントはたった1か所です。 そのポイント

人気お笑いコンビのチュートリアル徳井義実さんが東京国税局から脱税の指摘を受けました。 新聞等の報道によりますと、申告漏れとなった金額は1億2,000万円、追徴課税は3,400万円です。 私は元税務署職員ですが、今回の徳井

税務署の情報収集手段 税務署は脱税を防ぐために、主に3種類の手段を使って情報収集をしています。 1. 確定申告書の内容 2. 税務調査 3. 法定調書 なお、税務署にとって情報収集はあくまでも調査をするための手掛かりにす

法人税や所得税などを脱税し、マルサから刑事告発される人は毎年100人以上います。 平成30年度に国税局査察部(通称マルサ)が告発した件数は121件ですので、3日に1件のペースで告発している計算です。 そんなマルサが行う脱
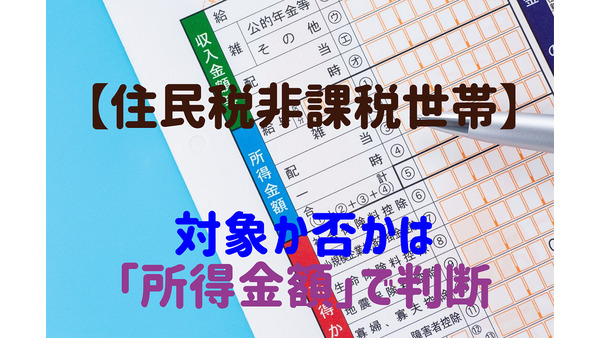
所得金額が一定以下になった場合に、住民税非課税世帯の対象となります。 しかし、基準となる所得計算を間違える人は少なくありません。 なぜなら、所得の種類や申告状況によって、所得金額が変化するからです。 上限を1円でも超える
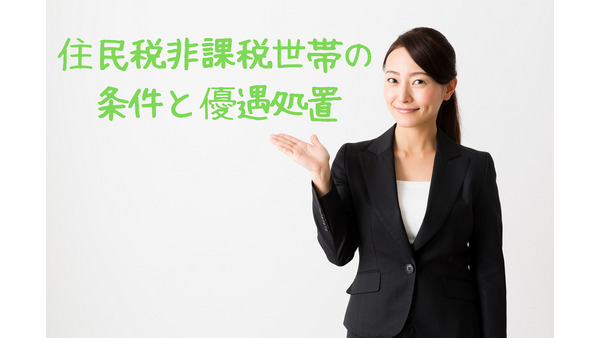
住民税非課税世帯は、収入が少ない世帯が対象です。 長期的でなく、短期的に収入が減少(または亡くなった)場合にも、住民税非課税世帯に該当する可能性もあります。 非課税世帯に該当した場合、住民税以外にも健康保険料や介護保険の
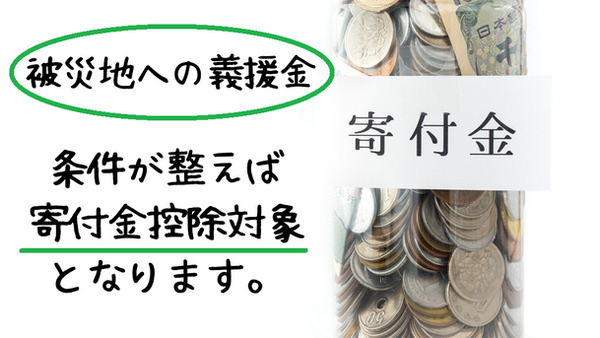
日本は毎年のように台風や地震で被災する地域があり、その際に義援金をお出しすることもあると思います。 被災地への義援金は、条件が整えば寄付金控除対象となりますので、所得税を節税することが可能です。 義援金も、寄附金控除を適
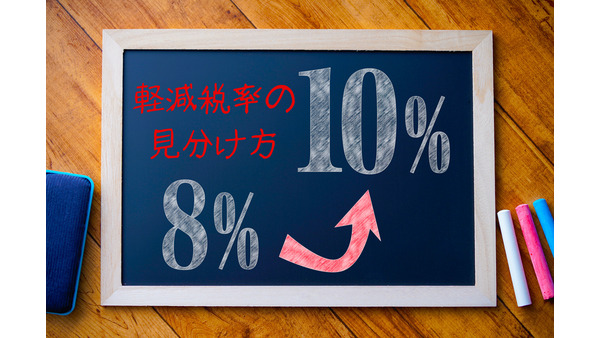
2019年10月から、消費税が8%から10%に増税します。 今回の増税で、一番注目されているのが軽減税率の導入です。 すべての飲食料品が軽減税率の対象であればいいのですが、残念ながら軽減税率の対象品目は限定されています。
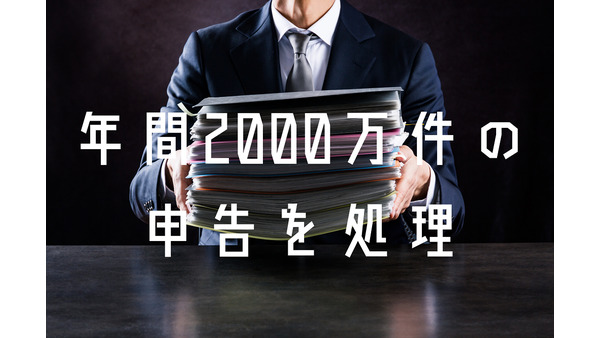
実は確定申告を提出している人は、意外と多いです。 平成30年分の所得税の申告書の提出件数は2,222万件で、日本人の5人に1人は確定申告をしている計算になります。 出典:平成 30 年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定
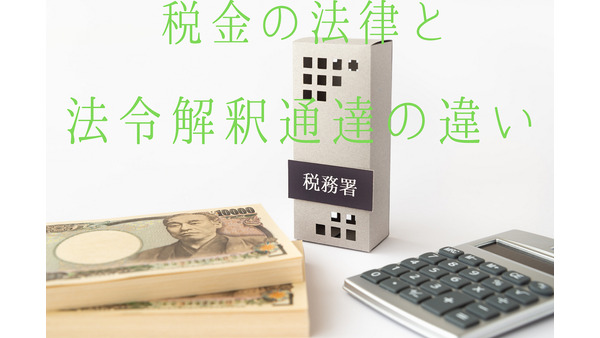
税務署は行政機関ですので、法律に従って申告指導や税務調査をしています。 ただ、法律は原則的な内容しか記載していないので、税務署職員でも解釈に迷うケースは少なくありません。 そんな法律のFAQとなっているのが「国税庁長官通
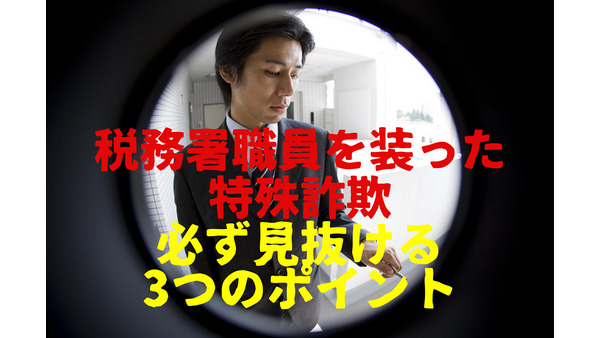
オレオレ詐欺が大流行してから10数年が経過しますが、特殊詐欺がなくなる気配がありません。 平成30年中の特殊詐欺の認知件数は1万7,844件、被害総額は約382.9億円にのぼります。 ≪画像元:警察庁≫ 特殊詐欺に使われ
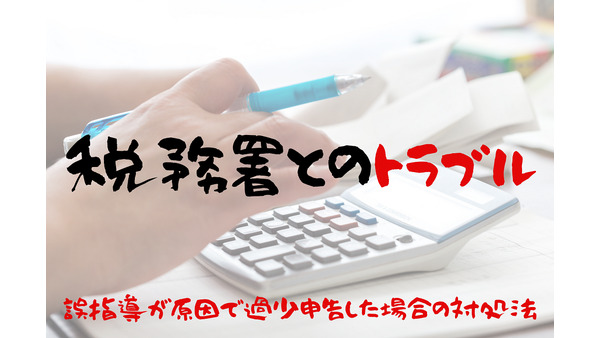
税務署でのトラブルの一つが、税金相談や申告相談の際に職員が誤指導をしてしまうことです。 自分で作成した申告書が間違っていた場合には、指摘されても納得はできます。 しかし、税務署に相談して申告書を作成したのに、後日その税務
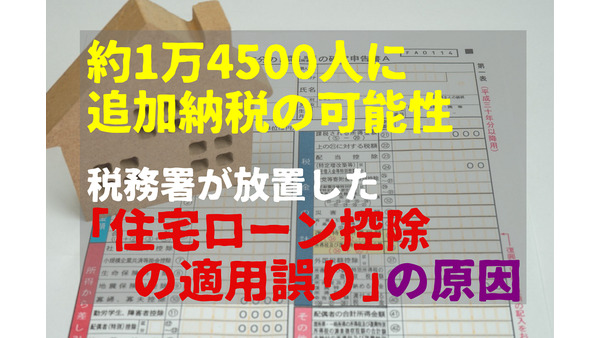
税務署は毎年のように会計検査院から指摘を受けます。 平成30年12月に国税庁が、住宅ローン控除の適用誤りを最大1万4,500人分放置していたと公表しました。 ≪画像元:国税庁≫ 会計検査院に指摘を受けた内容については、「
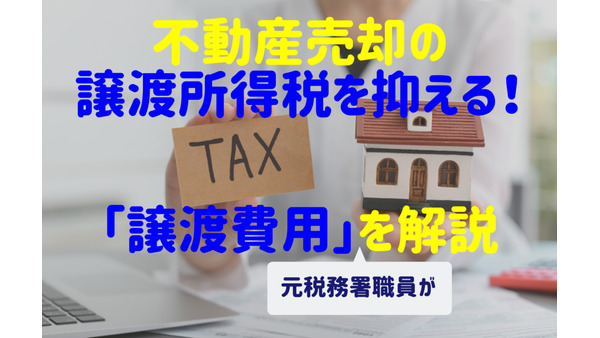
不動産を売却した場合、売却益は「譲渡所得税」の対象 売却益が発生していなければ、税金を支払う必要はありません。 税金の計算で重要になるのが必要経費です。 譲渡所得の計算式は次の通りです。 ≪譲渡所得の計算式≫ 売却金額
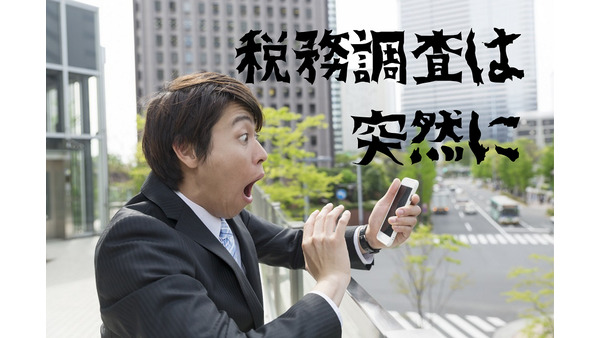
個人の確定申告は3月ですが、税務調査は7月から12月に行うことが多いです。 国税組織の本音は1年通して税務調査したいと思っていますが、確定申告の事務処理に数か月必要なので、税務調査の期間は半年間です。 ただ、突然調査があ
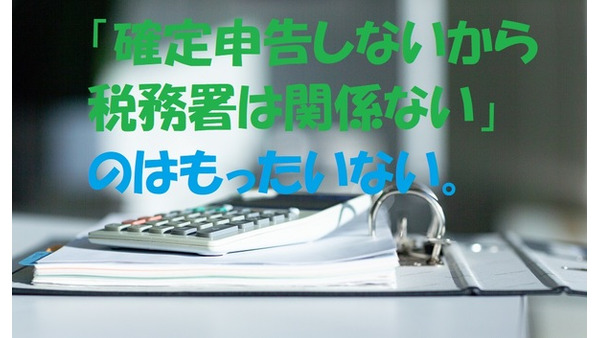
確定申告をしない人にとって、税務署に行く機会はありません。 しかし、「確定申告しないから税務署は関係ない」では、もったいないです。 税務署は確定申告以外でも、所得税・相続税・贈与税などのさまざまな税金を取り扱っています。
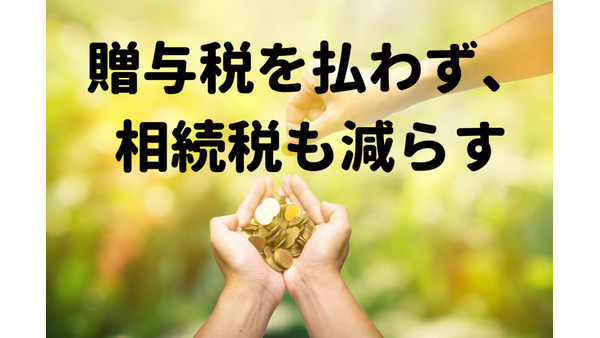
贈与税は、誰でも支払う可能性のある税金です。 何気なくもらう物(財産)も、贈与税の対象です。 ・お年玉 ・タダで車を譲ってもらう ・クリスマスプレゼント 贈与税を申告しない人の大半は、贈与税を支払う認識がなかったとのこと

誰に聞いたらいいのかわからない相続税の疑問 相続はいつ発生するかは、誰もわかりません。 はじめての相続だと、相続税の相談をどこにすべきかもわかりません。 相続税の相談で、最初に覚えておきたいポイントは4つです。 1. 一

所得税を納める人が支払った生命保険料は、所得控除の対象です。 しかし、条件を満たせば、妻の保険料も所得控除の対象にできます。 特別な手続きは必要ありません。 所得を正しく申告するだけで、所得税が還付されます。 夫以外の保
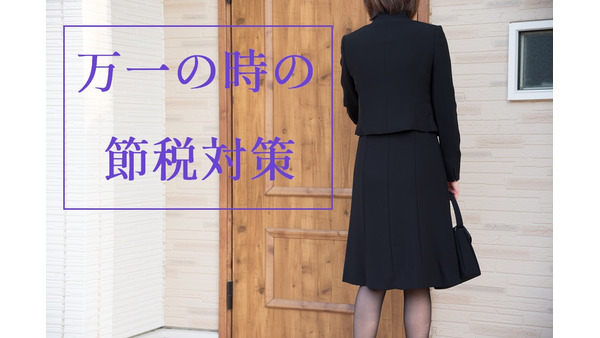
寡婦控除は万一の時、あなたを経済的にサポート 所得税には、配偶者と離婚・死別した時に利用できる控除があります。 「寡婦(かふ)控除」といい、最大35万円の所得控除を受けることが可能です。 万が一の時に所得税を節税できる方
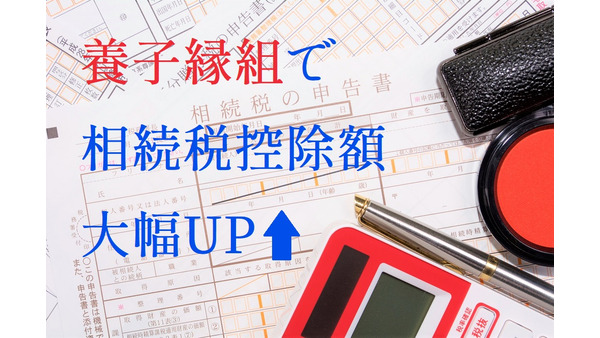
相続税は、お金持ちだけが支払う税金ではありません。 平成27年に相続税の基礎控除額が4割も引き下がりました。 私は元税務署職員ですが、サラリーマン家庭の相続税の申告をいくつも見てきました。 相続税の節税方法はたくさんあり

自宅を売却した代金は、所得税の対象になります。 誰も、余計な税金は支払いたくありません。 ですが、所得税の申告・納税をしないと罰金(加算税・延滞税)を支払わなければなりません。 不動産を売却したお金を少しでも残すために、
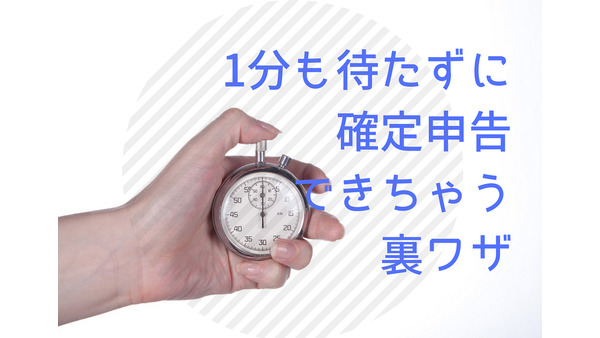
確定申告期間中の税務署は、混雑します。 特に3月中の税務署は、待ち時間だけでも2時間を超えることは珍しくありません。 しかし、そんな確定申告も、1分も待たずに手続きできる方法があります。 気をつけるのは、申告をする時期と