※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています
注目記事※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています
注目記事
2015年(平成27年)1月に相続税が改正されることにより、相続税の増税が予定されています。現状では、相続を迎えた家庭の約4%が相続税を納税しているにすぎませんが、来年からの増税をうけて、全国平均では約6%の家庭で相続
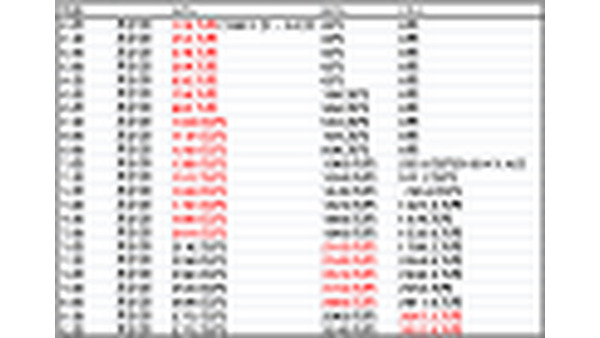
年金の繰り上げ、繰り下げという制度をご存知でしょうか? その名の通り、将来年金をもらう時期を早めたり、遅らしたりする制度のことをいいます。ざっくりこの制度のことを説明しますと、繰上げ支給の年金は受給する時期を早めるかわ

最近皆さまの所に、「固定資産税納税通知書」というものが最近届いていると思います。この通知!皆さんはきちんと開いて確認しているでしょうか? お役所の方が行っている事なので間違いないとたいして気にせずに放って置いている方が

中小企業や個人事業主にとって、相続や事業承継は悩みの種 相続税の基礎控除の引き下げ、相続税の最高税率の引き上げが、税制改正大綱で決定され、2015年1月より相続税が大きく引き上げられます。中小企業オーナーにとっては、頭

『終活』について、これまで何回か書かせていただきましたが、その集大成はやはり『遺言書』です。介護やお墓や葬儀の問題と違い、モロに「お金」が絡んでくる問題です。あなたの財産で仲の良かった家族同士が争うようになったら、それ

先日、某生命保険会社の法人のための生命保険についての講習会に参加してきました。2日間におよんで、法人に適した生命保険の商品や考え方についてのお話を聞いてきました。 法人の生命保険というと、少し前までは保険料の全てを損

「一般の常識ではあたり前のことが通用しない。」相続の世界ではよくあることです。今回は「相続での失敗事例」の2回目で、本人死亡による預金凍結の話。 銀行窓口での”その一言”で口座は凍結 夫が亡くなり、その口座から当面の

Q:当社は法人税等の納付の際に、納付期限から遅れて支払ってしまうことがあります。ところが、延滞税が課されるときと、課されないときがありますが、どのような場合は課されないのでしょうか?また、適用される税率は何%でしょうか?

相続税制改正により、平成27年(2015年)1月1日から、基礎控除額が引き下げられ、相続税の税率構造が変わり、最高税率が引き上げられます。そのため、相続税の納税者数も 納税額も 増える見込みです。これまで 「資産家の問

年金はそもそも損得で考えるものかという議論があると思いますが、誰でもどうしたら最も得なのかについてとても敏感です。最近年金事務所で私が扱ったケースで、その方にとってもっと得な受給のしかたがあったのにご存じなかったのかと

法定相続人の判定は相続開始時です。そのため相続発生時に離婚していますと相続権はありません。離婚しても相手に財産分与を請求することができるので同じことと思われるかもしれませんが、一般に財産分与の額、どうも多くないようです

~はじめに~ 「公認会計士による監査」、企業にお勤めの方なら1度は御社に公認会計士が数名のチームで入ってくるのを見た事があるのではないかと思います。いったい彼らは、突然やってきて、会社の何を見ているのか? 知りたくあり

株式を持っている人は、6月に入ると配当金のお知らせが届き始めます。臨時のお小遣いとしてちょっと嬉しくなりますよね。NISAで高配当銘柄を買った人は特に楽しみですよね! でも、ちょっと待って! NISAで買った株の配

消費増税から、早、3週間が経とうとしています。ここにきて消費増税後の景気の落ち込みが心配になってきます。株価に影響がでなければいいのですが…。コラムを書こう…何を書こう…と思い悩んでいる時に、昔、相談を受けた土地活用が
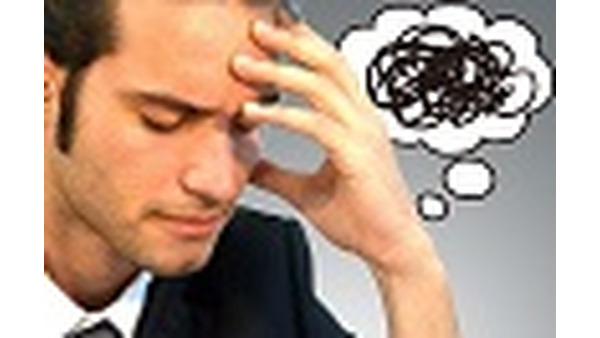
ご存知ですか? 国民年金(厚生年金)の保険料は、平成29年にかけて毎年引き上げられていきます。例えば、平成26年度の国民保険料は、15,250円ですが、平成29年度の国民年金保険料は「16,900円×保険料改定率」とな

厚労省(平成23年パートタイム労働者総合実態調査)によると、パート主婦全体の55.2%は年収130 万円未満で働いている。年収130万円とは、健康保険・厚生年金等について夫の扶養からはずれるかどうかの境界線にあたる金額
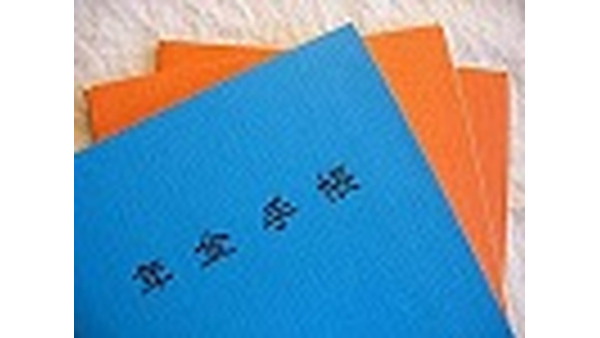
少々遅くなりましたが、新社会人の皆さんおめでとうございます。新たなスタート地点に立つ皆さんがまぶしく見える今日この頃です。 就職活動中の学生さんからは「福利厚生制度の整っている企業に就職したい」という声を聞きますが、

皆さん、こんにちは。今日は「公的年金の基礎」というテーマで述べたいと思います。 公的年金制度の歴史は古く、明治時代の陸海軍人・役人の為の「恩給」に始まる、とされています。つまり当時は「お国の為…」一色の時代だった為、

最近になって、各業種の方が来年からの相続増税に向けて、お客様に有効なアドバイスができるようにならなければと、ひしひしと感じているのが窺えます。 ある相続のセミナーで講師の先生がおしゃっていました。相続の対策というのは

Q:消費税が4 月から8%になり、来年には10%となることが予定されています。一方、消費税の増税に伴い自動車関連の税金負担が減らされています。結局、消費税がアップする前に購入したほうがいいのか、それともアップした後購入し

4月から消費税が増税され、さらに消費財によっては新しい税が導入されたりするなど、家計には痛手となっています。慣れれば値上がりした値段でもどうってことなくなってしまうのでしょうが、そうなる前に、家計に少しでも役に立つ習慣

もともと会社員などの「給与所得者」には、「みなし経費」が認められています。その名は「給与所得控除」。年収をある計算式にあてはめることによって経費の額は決まっており、たとえば、年収800万円の人の場合、200万円が経費と

固定資産額がどのくらいか知っていますか? マイホーム購入に関する情報は巷にあふれています。その中でも『取得後にかかる税金にご注意!』系の情報も多いです。 取得後にかかる税金は「税金系」と「メンテナンス系」に大別されま

遺言がない場合は法定相続人全員で遺産分割協議をしなければ相続人への名義変更ができません。しかし、法定相続人の中に協議が困難な方がおられる場合があります。 海外を放浪している、どこかでホームレスをしているらしいといった

サラリーマンの場合、領収証を発行して、自分で収入印紙を貼ることはまずありませんが、何かを買ったときに、収入印紙の貼った領収証を手にしたことはあるでしょう。 私どもは商売をしていますので、領収証はいつも手元にあり、収入

昨年4月に創設されて話題になった、教育資金一括贈与の非課税制度。制度がスタートして1年が経ちますが、大変な流行になっていて、金融機関への問い合わせも多いようです。 贈与を受ける側の方からの問い合わせだけではなく、贈与

買い物をするとき、今までは物の値段が税込価格で売られていたため、消費税のことは全く意識せずにお金を支払っていました。しかし4月に入ると、物の価格が税抜き表示の店が増え、消費税について関心を持たざるを得なくなったような気

桜の花が満開になり春爛漫、清々しい季節になってきました。そして、いよいよ、消費税が8%にUPしました。3月31日には、消費増税前の電化製品の駆込み購入の現場を見れるものと思い、その日は、新宿で用事を済ました後に、秋葉原

Q:中小企業が少人数私募債を利用して節税をするスキームが、平成26 年税制改正で、ほとんど使えなくなってしまうとのことですが、これはどのような手法なのでしょうか? また、税制改正でどのように変わるのでしょうか? 解説

60歳で退職しても、まだまだ元気で何らかの形で社会参加をしていきたいと考え、退職後もパート等でしばらく働く予定にされている方も大勢いるのではないでしょうか。ただ、その時に気になるのが年金です。その場合には、一体年金はど

皆さん、こんにちは。今日は「法人税の基礎」というテーマで述べたいと思います。今回述べる法人税は、個人に対する税金である「所得税」と並んで代表的な税金です! その為、是非概略ぐらいは理解してほしいと思います。 法人税って

2014年の4月から消費税が3%アップして8%に増税されました。物価も徐々にアップしていますので、ベア等での給料が上がらなければWで家計は痛手を被ります。他にも、公的年金の国民年金保険料は210円のアップ、介護保険料も

いよいよ消費税増税となり、活況だった新築マンションや戸建住宅についてはその後の反動が懸念されます。そしてこの消費税はそもそも論で、課税されるものと課税されないものに対する判断が結構ややこしいのでこれらをしっかり把握する

相続税の納付は4%から8%に? 消費税率が8%に引き上げられ、次は来年の相続税。「“大”増税時代来る~あなたも相続税の納税者に!」などというキャッチ・フレーズを目にしたことはありませんか。改正の一つに基礎控除額の引下げ

3月末まで、買い物をする人がお店にあふれかえっていたように感じた人は多いのではないでしょうか? 消費税は買い物をするたびに払うもののため、現実的に「今のうちに買っておこう」と思いやすかったのだと思います。多くの人が忘れ

遺言書とは 遺言(いごん、又はゆいごん)は、民法において満15歳以上の者は遺言をすることができると定められており、本人の最終意思を確認するものである。 遺言の最も重要な機能は、遺産の処分について、被相続人の意思を反映