※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています
注目記事※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています
注目記事
先般、ご案内の通り、昨今は相続に関する様々なセミナーや相談会・説明会等が開催をはじめ、メディア・雑誌等でも相続特集が組まれています。そのような中で、相続の奥深さを感じること、いわば、一般の方が、勘違いしてしまいやすいの

領収書 or レシート 今回は、コラム 公認会計士による監査の視点はお休みです。かわりに、領収書とレシートの違い、についてお話ししましょう。 「領収書じゃなくて、レシートでは、支払った証拠として税務署に認められないの

その年1月1日から12月31日までに支払った医療費の額が一定額を超えた方は、翌年の3月15日までに確定申告をすると医療費控除の適用を受けることができます。 医療費控除とはどんな制度? 医療費控除とは治療のために要した
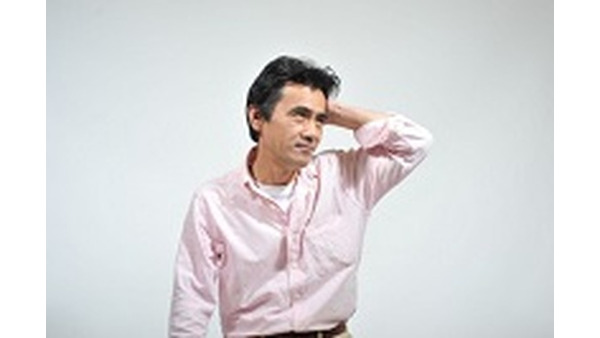
日本公証人連合会によると、公正証書遺言の作成件数は、2013年には9万6020件あり、25年前の2倍以上になっています。また、経済産業省の2012年の調査では、遺言を作成したいと考えている人は3割を超えており、年齢が高

相続税の増税(改正)まで約半年となりました。巷では、“相続”が非常に盛り上がっており、ビジネス雑誌、週刊誌をはじめワイドショー等でも多く取り上げられています。 “相続”における最近のキーワードは“相続税増税”と“

1. 来年度から相続税の基礎控除額が引き下げられます 2013年の税制改正により、2015年1月1日以降、相続税の基礎控除額が現状の6割になり、相続税を払うことになる方が、急増するだろうと言われています。 例:相続人3

Q:当社は、前年度は好業績を挙げ、多額の法人税を納めましたが、この反動で当年度は受注が激減し、前年度とは逆に大きな欠損となりました。こういった場合、前年度に納付した法人税の還付を受けられるのでしょうか? 解説 前年度に

皆さん、こんにちは。今日は「確定拠出年金の基礎」というテーマで述べたいと思います。 確定拠出年金(DC)とは、厚生年金基金や適格退職年金等の確定給付型年金(DB)と異なり、将来の年金支給額が決まってなくて企業が拠出し

OL進化論(某雑誌の4コマまんがです)で「パン屋ライフ」という話があります。 「パン屋がつぶれた後、また新しいパン屋が…。この店は続くかな?」とつぶやく主人公。 店長「いらっしゃいませ~~」 主人公「夫婦でやって
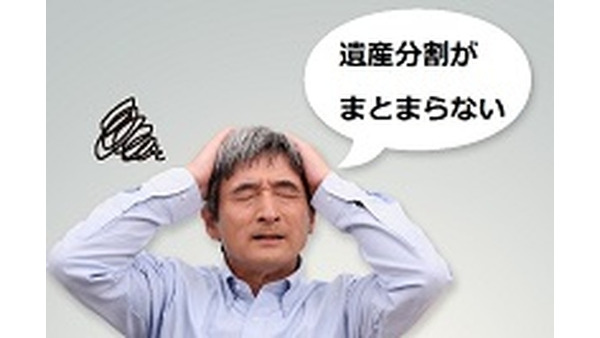
来年からの相続税法改正(基礎控除額が現行の60%に改正他)にむけて、銀行、信託銀行、生保会社、建築会社、デベロッパー等々、個人の財産に絡んでくるあらゆる業種や業態の会社が、こぞって相続対策を売り文句とした営業戦略をたて

両親の財産は一戸建ての自宅と1000万円の預貯金や株だけ。子供たちはそれぞれ家庭をもちマンションを買ってお金には困っていません。「私たち両親がなくなっても、遺す財産もないから、子供たちが相続で争うことはないわ。」本当に

贈与税について勘違いしていたために、あとで多額の相続税がかかってしまうことがあります。正しい知識で、あげる人ももらう人もHappyな生前贈与をしましょう。 「あげたつもり」は贈与にならない 房江さん(60歳)は、相続

来年からの相続増税時代に向けて、あらゆるところで相続対策、争続対策、相続税対策といった言葉を見かけるようになる機会がふえてきました。新聞では、相続増税時代に向けての土地活用のセミナーの広告もまことしやかに目立ってきてい

4月の年金額改定が反映されるのは6月の支払日 年金は2ヵ月に1回、偶数月の15日(土・日・祝日に当たる場合はその直前の平日)に前2ヵ月分が支払われます。したがって、今年の6月13日(金)に振り込まれる年金は、平成26年

Q:来年から相続税が増税となりますが、その節税対策としてタワーマンション(以下「タワマン」といいます)を活用することで大きな力を発揮すると聞きましたが、これはどのような手法なのでしょうか? 解説 一般的に財産を現預金で

5月11日に田村厚労相がNHKの番組で、年金の支給開始を75歳程度まで引き上げられるか検討する考えを示しました。75歳というのはあくまで選択制で、一律というわけではありません。 現状は、繰り下げ受給が70歳まで可能な

「相続の失敗事例」の3回目は、せっかく書いた遺言が無効になるお話です。 遺言が無効になる典型的なケース 「書いた遺言に日付がない」、「遺言の一部を代筆してもらった」…。自筆の遺言で無効になる典型的なケースです。ほかに

サラリーマンの場合、年末調整で所得税の納税は完了しますので、原則的には確定申告の必要はありません。年の途中で退社したサラリーマンの場合は、年末調整をしませんので、確定申告をしなければなりません。ただし、中途退職した同じ

相続・事業承継の対策を考えることの難しさとは何でしょうか? 相続・事業承継を考えた場合、まず、第一に、誰に何を引き継がせるかを決めなければなりません。会社の経営権を誰に引き継がせるか。これが、兄弟がその会社に役員とし

皆さん、こんにちは。今日は「厚生年金の基礎」というテーマで述べたいと思います。厚生年金は前回も言ったように、民間の適用事業所に使用される人(サラリーマン)が、70歳に達するまで全員加入する制度です。 給付には、前回の

国民年金保険料の未納期間が長いと、病気やケガで一定の障害が残っても障害年金を受給することはできません。しかし、その保険料納付要件には「原則」と「特例」があり、特例では長年に亘り未納にしていても直近1年以内に未納がなけれ

最近になって、新聞に2世帯住宅の一面広告を見かけるようになりました。来年からの相続税の基礎控除額の減額(現行の60%、相続人が3人の場合、実に3200万円もの基礎控除額が減ってしまうこととなります。)を見据えての一面広

1. 2013年の税制改正により、2015年1月1日以降、生前贈与を取り巻く環境は大きく変わる。 贈与税の最高税率が相続税と同じになる一方で、子や孫などに贈与する場合に、新たな税率が導入された。 2015年1月からは

家族などが亡くなったときには、市区町村に「死亡届」を提出します。市区町村は、死亡届に記載されている内容を、税務署に通知しなければならないことになっています。なお、市区町村からは、固定資産税評価額なども同時に通知されると

相続税の課税価格を計算する場合の小規模宅地等の特例における特定居住用宅地等とは、原則として被相続人又は被相続人と生計を一にしていた親族の居住の用に供されていた宅地等で建物の敷地の用に供されている一定のものとされています

現在公立大学の他、私立大学の講師を務めているI氏は私宛メールで下記の如く述べています。皆様、下記のI氏の年金制度への見解に賛同しますか? 「今年3月末3度目のフィリピンから帰国し、首都マニラはものすごい活気です。建築ラ

ふるさと納税が注目される3つの理由 (1) 自分のルーツに関係なく、応援したい都道府県・市町村を選んで寄附できる。地方の活性化に貢献できる。 (2) 寄附をした後に確定申告をすると税金が戻ってくる。具体的には、国からは所

消費税の増税や社会保障費の負担が増える中、家計の負担増も気になるところです。来年から相続税の基礎控除が6割になることもあり、家計と相続両面から注目されているのが二世帯住宅です。 生活面でも子育てや介護にも優しい二世帯

Q:離婚にともない、不動産を相手側に渡した場合は税金が課税されるのでしょうか?課税されるとしたら、なんの税金が、課税されるのでしょうか?また、受け取る側、渡す側どちらに課税されるのでしょうか? 解説 財産分与として不動

皆さん、こんにちは。今日は「国民年金の基礎」というテーマで述べたいと思います。国民年金は、国民が全員加入しなければいけない年金です! 給付について、老齢給付は「老齢基礎年金」、障害給付は「障害基礎年金」、遺族給付は「遺

平成23年2月に最高裁の判決が出た武富士事件。簡単にこの武富士事件の概略をお話しします。 武富士の創始者が長男を香港に在住(名前だけの香港支店をつくった)させ、香港在住時に武富士の株式の多数を所有している海外法人の株

平成24年8月に成立・公布された「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」(年金機能強化法)は、平成26年4月以降、順次施行されます。今回はその中から、「国民年金の任意加

父親が亡くなり母親と自分を含めた子供たちへの相続(1次相続)を受ける際にどのように遺産分割をすべきでしょうか。一族のトータルの相続税額を少なくしたいということでしたら、将来の母親からの相続(2次相続)まで考えて1次相続

この春から、遺族基礎年金の受取りについての変更がありました。今までは、夫が死亡した場合には、妻と子どもに受取る権利があったのですが、妻が死亡し、夫と子どもが残された場合に遺族基礎年金の受給はされませんでした。それが平成

前々回に国民年金保険料を支払うのが困難になった場合の対策について、ご紹介しました。未納で放置するのではなく、免除、猶予制度を活用する事をお勧めしたのですが、今回は保険料免除を受けた場合の年金額についてご案内します。

消費税も8%にアップし、サラリーマンとしては懐痛しといった感じですね…。単純に考えて、日々の支出額のうち、+3%相当分が上乗せされて財布から出て行ってしまうのですから…(そもそも消費税が最初からかかっていない支出も、当