※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています
注目記事※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています
注目記事
厚生年金をもらいながら働いていたのに、 「平成28年10月から社会保険の対象者となりそうで、そうしたら厚生年金まで減らされそうだ…」 そういう方もいらっしゃるようです。 社会保険料が給与から天引きされた挙句、年金まで減ら

マイナス金利時代の賢い資金運用法 筆者は、過去に寄稿したコラム記事で、マイナス金利時代の賢い資金運用法として10年物個人向け国債や百貨店「友の会」などの活用を提案した。 (1) マイナス金利時代の「もっともお得な金融商品

【Q】 確定拠出年金の老齢給付金を60歳~69歳で受給しながら、老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)を70歳まで繰下げ請求はできますか。 【A】 確定拠出年金はと老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)は、全く別の年金制
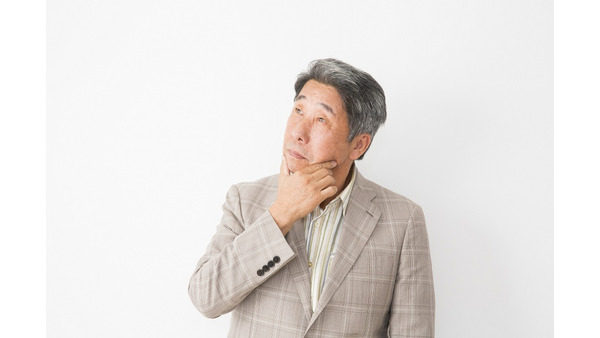
生活保護の扶助は、継続的に支給される 「生活扶助」、「住宅扶助」、「教育扶助」、「医療扶助」、「介護扶助」と、一時的に支給される「出産扶助」、「生業扶助」、「葬祭扶助」の8種類があります。 この中の生活扶助は、生活保護の

2017年1月より拡充されて、公務員や専業主婦でも加入できるようになった個人型確定拠出型年金制度。その桁違いな節税効果が喧伝され、早くも各証券会社の顧客争奪合戦が始まっています。 「こりゃあもう、やらなきゃ損!」と思って

連日、数多くのニュースが新聞やテレビ、インターネットを通じて私たちに届いています。個々のニュースを組み合わせて考えてみることで、今後、起きうることが見えてくるかもしれません。 今回は、いずれも7月下旬または最近の3つのニ
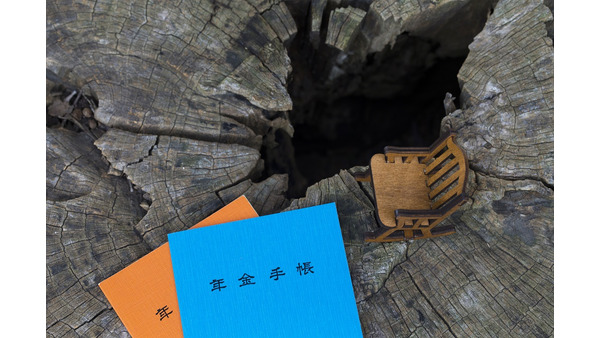
健康保険の料率は労使併せて10%前後、厚生年金の料率に至っては15%弱と、企業・労働者どちらにとっても社会保険料は大変な負担になっています。 昨今、社会保険料の削減がコスト削減の有効策になっていますが、落とし穴もあるので

2016年7月29日に、年金積立金を運用している「年金積立金管理運用独立行政法人(以下では「GPIF」で記述)」は、 2015年度の運用損が、5兆3098億円に上った と発表しました。 そもそも日本の公的年金は原則的に、

5月24日に「確定拠出年金法等の一部を改正する法案」が衆議院で可決成立したものの、詳細がなかなか見えてきませんが、今改正最大の目玉は、個人型DC(確定拠出年金)に、“第3号被保険者と公務員等共済加入者も「確定拠出年金」制

「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」 厚生年金保険の保険料には、国民年金の保険料も含まれているため、厚生年金保険の保険料を納付すると、国民年金の保険料も納付したことになります。 そのため厚生年金保険に加入する会社員などは、

自分年金としての確定拠出年金 老後の支えと言えば、やはり公的年金が柱ですが、現役で働いている世代の方「私の時には年金なんて出るのかな?」と感じたことはありませんか? 退職金代わりや老後の上乗せ年金として企業型確定拠出年金

病気やケガで働けなくなると、一番不安になるのはお金のことではないでしょうか。 いつまでも貯金を切り崩していくわけにもいかない、かといってすぐに働けない…そんなときは、思い切って障害年金を申請してみるのも一つの手段です。

「特別支給の老齢厚生年金」の受給開始年齢の引き上げ 60歳台前半の「特別支給の老齢厚生年金」の受給開始年齢の引き上げの表(表1)は多くの方がご覧になっていると思いますが、この表の上半分の生年月日の方は既に65歳を過ぎて本

原則65歳から老齢基礎年金を受給するには、次のような3つの期間を併せた期間が「原則25年以上」は必要です。 この原則25年は、老齢基礎年金の受給資格を得るために必要な期間なので、「受給資格期間」と呼ばれております。 なお

個人型の確定拠出年金の対象者を拡大する法案が、平成28年4月15日に参議員本会議で、また平成28年5月24日に、衆議員本会議で可決されました。 これにより国民年金の第3号被保険者となり、自分で保険料を納付する必要のない専

老後資金準備の制度として、先日、「確定拠出年金法等の一部を改正する法律」が成立し、2017年から対象者が大きく拡大する個人型確定拠出年金に注目が集まっています。 当サイトの今ホットな話題にも上がっていますし、さまざまなメ

必要納付期間は25年から10年に短縮へ 以前、消費税を10%に引き上げる事に伴い、社会保障の拡充のひとつとして、年金受給の条件であった最低25年間の納付期間というものがありました。 会社勤めの方など、社会保険に加入されて

「会社を退職して初めて知った」とよく言われるのが年金と基本手当の調整です。 つまり雇用保険の基本手当と65歳未満の間に受給する特別支給の老齢厚生年金は併給されませんから、どちらか有利な方を選択する調整の事です。 基本手当

2016年5月24日に成立した「確定拠出年金法等の一部を改正する法律」ですが、すでに何人かの方がメリットを記載されていますが、さらに知っておいていただきたい改正点をお伝えいしたいと思います。 改正にあたって加入者の範囲の

平成13年10月から「確定拠出年金法」の施行によって、日本でも導入された確定拠出年金(DC)制度。 今年でちょうど15年になりますが、平成29年1月からは、専業主婦や公務員そして一部のサラリーマンも個人型確定拠出年金に加

原則65歳から老齢基礎年金と、その上乗せとなる老齢厚生年金を受給するには、国民年金や厚生年金保険の保険料を納付した期間、保険料の納付の免除を受けた期間などを併せて、原則25年以上必要になります。 この原則25年は「受給資

2017年1月から、専業主婦や公務員でも(個人型の)確定拠出年金に加入できるようになります。 また、すでに企業型の確定拠出年金に加入している会社員でも、会社が規約を定めるなどの条件を満たせば新たに個人型に加入できるように
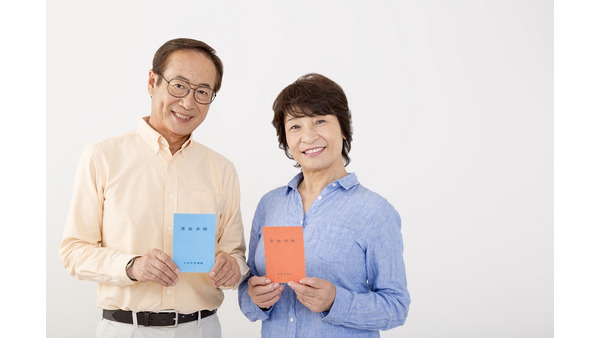
年金の繰り上げ受給について 本来は65歳から支給される老齢基礎年金を、60歳から65歳になるまでの希望する時期に、繰上げて受給することができます。 また昭和28年4月2日以降生まれの男性(昭和33年4月2日以降生まれの女

転職したい、独立したい、しばらくゆっくり休みたい……。 会社を退職することは、決して珍しいことではありません。それでも、会社を辞めるのは勇気がいることですよね。 ただ、退職してすぐに次の会社に入らない場合は、国民健康保険

2016年5月24日に確定拠出年金(DC)の改正法が成立しました。 少額投資非課税制度(NISA)に後れを取っている感のある確定拠出年金(DC)ですが、企業年金の普及・拡大、多様化する生き方・働き方に対応するため、現行の

先回のコラム「レシピ オブ 遺族年金」にて自営業世帯の遺族年金を確認しました。 今回はサラリーマン世帯の遺族年金の仕組み(レシピ)を見てみましょう。 ただサラリーマン世帯は、国民年金と厚生年金の2階建ての支給となりますの

生涯現役社会へ向けて 定年後も同じ会社に、嘱託社員として再雇用された3人の男性が、定年前と同じ仕事をしているのに、賃金が下げられてしまうのは、労働契約法に違反していると争った裁判の判決が、平成28年5月13日に東京地裁か

個人型確定拠出年金について 給料から引かれる所得税・住民税がお得にできる制度についてお伝えしたいと思います。 今回、ご紹介するのは「個人確定拠出年金」についてです。 皆さんは「年金」というのは何となく理解している方は多い

国家公務員や地方公務員、または国民年金の第3号被保険者となり、自分で保険料を納付する必要のない専業主婦は、個人型の確定拠出年金の加入資格がありません。 その他に勤務している会社が、次のような企業年金を実施している厚生年金

年金記録問題のその後 「宙に浮いた年金」とか「消えた年金」と言われた年金記録問題ですが、この頃あまりその話題を聞かなくなりました。 身に覚えのある方からの申し出はもうほとんどなくなり、年金機構での取扱いも縮小されています

先回のコラム「誤解の多い遺族年金」にて老齢年金と遺族年金は全く別で、支給条件も支給額も異なる事を紹介しました。 では、遺族年金は一体、誰に、いくら、どんな仕組み(レシピ)になっているのかを見ていきましょう。 自営業世帯の

企業年金 会社によっては従業員の老後の生活を豊かにするため、福利厚生の一環として、企業年金を実施しております。 その企業年金には様々なものがありますが、多くの会社は次の3つのどれかを単独で、または組み合わせで、実施してい

「老後の生活は何も心配しなくていい」なんていう人は今の日本には少ないのではないでしょうか。 定年まで家のローンを支払いながら必死に働けば、定年後は年金によって生活を保障してもらえるはずなんだけど…と不安が残るのが日本の年

先日、あるシニア世代の方の集まりにて遺族年金について説明する機会がありました。 既に皆さんは老齢年金を受給されているので、ある程度は遺族年金についても内容を掴んでいらっしゃると思ったのですが、予想に反して殆どの方がご存知
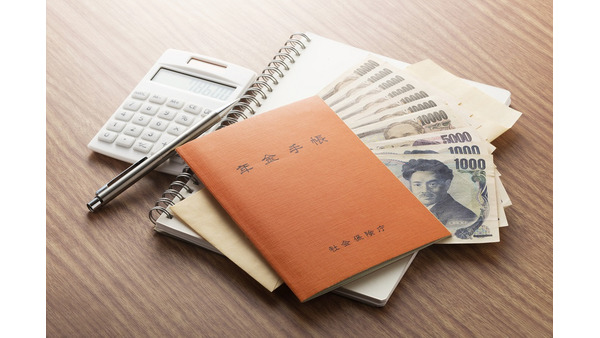
「遺族年金」はいろいろな種類のものがあり、いったい自分がどのもの該当しているのか判別しにくいかもしれません。 そして、「遺族年金」は、原則として亡くなった方の亡くなった時に掛けていた年金により変わりますので注意が必要です

確定拠出年金を企業年金として採用する企業が増加しています。 制度導入時には、会社で説明会や勉強会などのセミナーで詳しく教えてもらえますが、いつあなたの会社が導入してもあわてないように、あらかじめ理解しておきましょう。 1