
毎日のお弁当づくり、「ちょっとしんどいな」と感じるときはありませんか。 筆者はあります。 どこがしんどいのか考えてみると、どうやら「きっちり詰めること」にストレスを感じているようです。 普段のごはんづくりはお皿によそうだ

投資で儲けるための裏技はない 投資や資産運用で多くのお金を稼いでいる人を見ると、次のように感じることも多いのではないでしょうか。 「儲けるための裏技や、誰も知らない情報を持っていたんだろうな」 「この人にはすごい才能があ
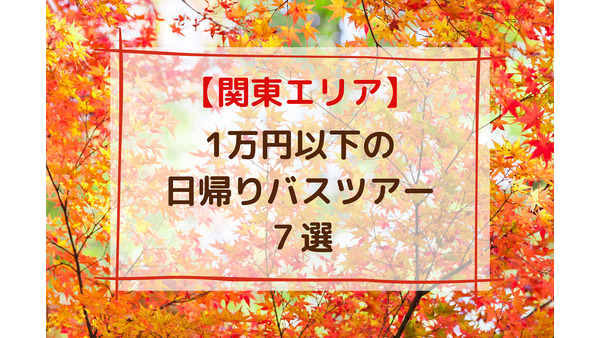
秋の足音が聞こえてくるこの時期。 街中の木々も少しずつ色づき始め、いよいよ紅葉のシーズンを迎えつつあります。 鮮やかな彩りで心身を癒してくれる紅葉スポットは、毎年大勢の人で賑わいます。 しかし今年は10月1日の消費税増税

10月7日より、新しく「PayPayフリマ」のサービスが始まりました。 どんな特徴があるのか、今だけのお得なキャンペーンはあるのか、などについてご紹介します。 「PayPayフリマ」アプリとは? ≪画像元:PayPayフ
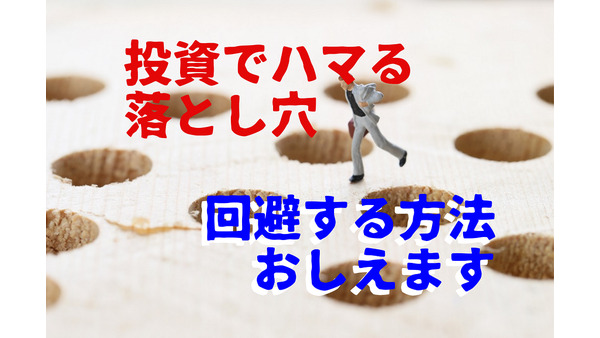
最近では、NISAやiDeCoといった初心者でも始めやすい商品が注目を集め、投資人口の裾野拡大が加速しています。 初心者でも始めやすいとは言っても、実際に口座を開設し投資を始めると、投資というものはやはり奥が深いと感じる

ズボラ主婦だった筆者は以前よりこまめに家の中を整理整頓するようになりました。 すると、浪費の多かった我が家の貯金が少しずつ増えてきました。 家の片付けとお金、一見なんの関係もないように思えますが、実は両者には密接な結びつ

育児休業とは、子が1歳(一定の条件の場合は2歳)まで従業員の申し出により取得できる休業のことです。 また、父母の2人共に育児休業を取得する場合は、子が1歳2か月に達するまで取得できます(パパ・ママ育休プラス)。 育児のた

服やおもちゃ、本やベビー用品、さほど高いものではないうえに「子供のためだから」とタガが外れ、買い込んでいませんか。 我が家のタンスには、私が子供のためと浮かれて買ったアイテムの数々が、眠り続けています。 ここでは、私自身
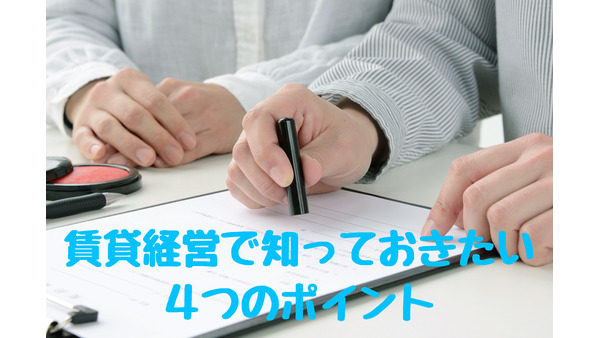
不動産投資は「投資」と呼ばれていますが、実際には入居者に家賃を払ってもらうことで利益を得る賃貸事業と言えます。 そのため、自分自身で空室対策やリフォーム費用を抑えることができるので、他の投資よりもリスクコントロールがしや
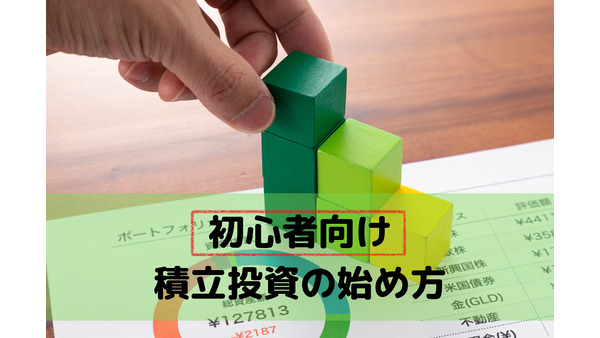
積立投資が、長期安定的な資産形成に資することが、さまざまなところで言われるようになってきたように感じています。 その反面、投資初心者で、これから積立投資を始めたい方にとっては、どのように始めたらいいのか、悩んでしまう方も

10月に入り、いよいよ2019年のクリスマスケーキ予約が始まりました。 スーパーやコンビニ、百貨店など、さまざまなお店でクリスマスケーキの「早割」を実施しています。 今のうちに早割価格で購入しておくと、通常よりもかなりお

民間の保険会社から数多くの保険が販売されています。 「保険」と聞くとみなさんは何を思い浮かべますか? 亡くなってしまった時の保険、自動車で事故を起こしてしまった時の保険、入院に備える保険など、いろいろな種類がありますよね

お金が貯まらない理由を年収のせいにしない お金が貯まらないのは、年収が低いからだけでは決してありません。 年収が高くても貯まらない人はたくさんいるのです。 その理由の1つがお金が貯まる入れ物を用意していないことです。 た

キャンペーン目当てでクレジットカードに新規入会する人は、少なくありません。 一般的に、年会費が高額なクレジットカードほどキャンペーンも豪華な傾向がありますが、「JCB CARD W」、「JCB CARD W plus L
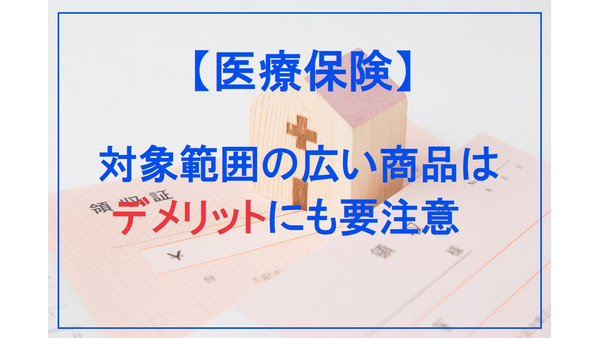
加入している「ガン保険」は、「ガン保険」と「生活習慣病保険金や七大生活習慣病保障つきガン保険」のどちらですか? 該当する病気にかかったら「まとまった金額が支払われる保険」をお持ちの方は、よく確認しておいてください。 三大

「目指せ100万円!」 と意気込んでも、生活がきつくて結局おろしてしまう。 「同じくらいの収入、生活レベルのあの人はちゃんと貯金してるのに、なんで貯められないんだろう…」 そんな自己嫌悪で落ち込むこと、ありますよね。 あ

メルカリで自己紹介文を記載するとき、どのような内容を書けばよいか迷ってしまうことはないでしょうか。 実は、ヘビーユーザーが記載しているものをマネすることがポイントです。 この記事では、メルカリで自己紹介文を記載する際のポ

石油系クレジットカードって何? 石油系クレジットカード(*以下ガソリンカード)は、ガソリンスタンドを展開している石油元売り会社がカード会社と提携して発行するクレジットカードです。 主な石油元売り会社 主要なガソリンスタン

貯金は、たとえ強い決意をもってしても効果が得られないことがあります。 また成果はあっても、どこかに無理があればしんどくなって、続かなくなることもあります。 確実に貯蓄を達成していくには、どうすればよいのでしょうか。 1.

子育て世代の皆さん、将来の教育資金はどのように貯めていますか? 教育資金の貯め方としてメジャーなイメージがあるのは学資保険ではないでしょうか。 かくいう筆者も現在2歳の子どもがいますが、教育費の一部は学資保険で積み立て

2019年10月1日から自動車の取得時にかかる税金が、「自動車取得税」から「環境性能割」に変わりました。 【関連記事】:【自動車税制も変更】中古車購入は増税前・後どちらがお得? 狙うべきクルマのポイントも解説 環境性能割

着なくなった服をそのまま捨てる、なんてことはしていませんか? 着なくなった洋服はゴミではなく、お金を実らせるタネです。 できるだけ上等な実にするため、着なくなった服を高く買い取ってもらえる方法を、実体験を交えてまとめまし

日銀の金融緩和の影響も大きく、ここ数年は不動産投資ブームが続いておりました。 しかし、2019年に入り、かぼちゃの馬車のシェアハウスに始まったスルガ銀行の問題やレオパレスのサブリース問題など、不動産業界では不祥事が相次ぎ

最近、年金に関する不安を感じさせるニュース等も少なくありません。 こういう時代になると、お金をいかにして増やすかという点を、みなさん考えるようになります。 私自身、まさに資産を増やすお手伝いをするお仕事をさせていただいて

生命保険に対して「複雑そうだ」、「分かりにくい」というイメージを持っている方は多いのではないでしょうか? 保険が有効な期間や保険金を受け取れるタイミングなどは、保険によってさまざまです。 そこで今回は、「保険の対象となる

日本は、世界でもトップクラスに食品ロスを出す国です。 食べ物を捨てる、それも未開封でまだまだ食べられる実情を見て、「捨てるくらいならちょうだい!」と叫びたい思いを実現化させたアプリが、Reduce GoとTABETEです
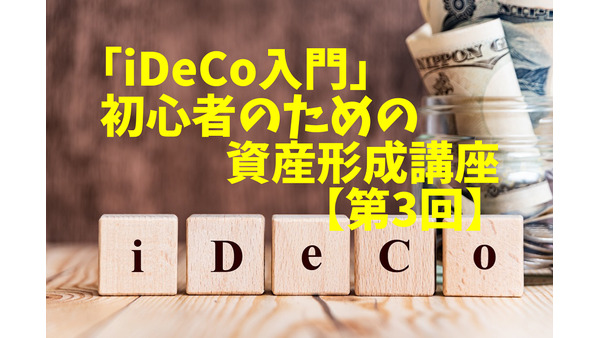
「iDeCo入門」の第3回目となる今回は、「iDeCo」最大のメリットでもある税制優遇について分かりやすく説明していきます。 第2回のおさらいにもなりますが、 「iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)」とは、いわゆる私

コンビニ経営者への対応や「7pay(セブンペイ)」の不正アクセスなど残念なイメージが拭えないセブンイレブンですが、お得なキャンペーンやサービスは多く、ファンも少なくありません。 「7pay(セブンペイ)」の払い戻しが今月

物件価格の高騰で中古マンションが注目されています。 しかし、中古マンションは市場流通量が不安定で、新築時代に欲しかったマンションを中古で手に入れるのは至難の業です。 ただし、新築マンションが多く売りに出される時期があり、

Amazonユーザーは多いですが、Amazonに不要なものを買い取ってくれる買取サービスがあることは、あまり知られていないようです。 今回は、不要な商品を送るだけで査定額に応じたAmazonポイントを付与してもらえる、A
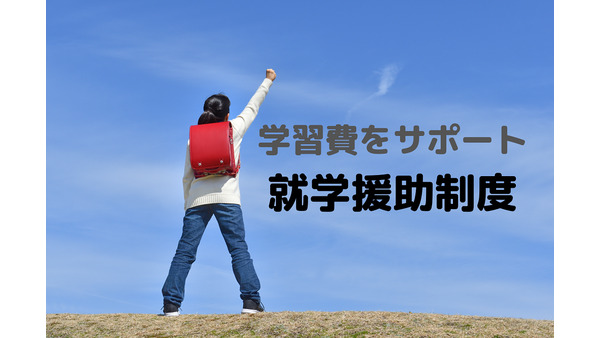
最近はフリーランスの年齢層も幅広くなっていますが、子育て中の世代なら収入が安定しないと子どもの学費が気になります。 小中学生の子どもを持つ方向けに、就学援助という制度があります。 収益が十分に上がらないときは、就学援助制

SBIアセットマネジメントより、新しい投資信託として「SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド」が登場しました。 投資ブロガーの間でも話題になっている商品ですので、概要や特徴を紹介します。 2019年10月

法人税や所得税などを脱税し、マルサから刑事告発される人は毎年100人以上います。 平成30年度に国税局査察部(通称マルサ)が告発した件数は121件ですので、3日に1件のペースで告発している計算です。 そんなマルサが行う脱

2019年10月の増税後に購入する新車(自家用乗用車)の自動車税が安くなりました。 軽自動車税の税率は「1万800円」のまま据え置きです。 自動車税は排気量に応じて課される税 自動車税とは排気量に応じて課される税金のこと
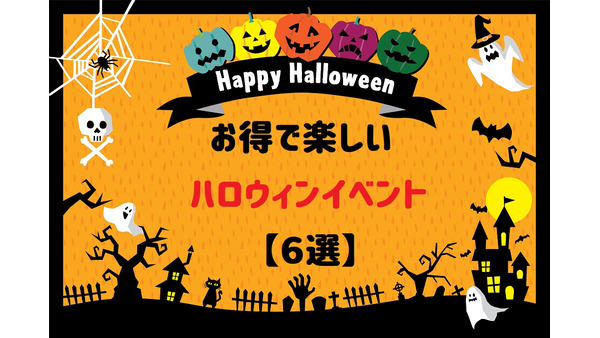
秋の足音が聞こえてくると、街中を楽しく彩るのがハロウィンのキャラクター達。 子どもから大人までみんなが楽しめるイベント、さらに仮装による割引やプレゼントなど様々なサービスが用意されています。 今回は都心を中心としたハロウ
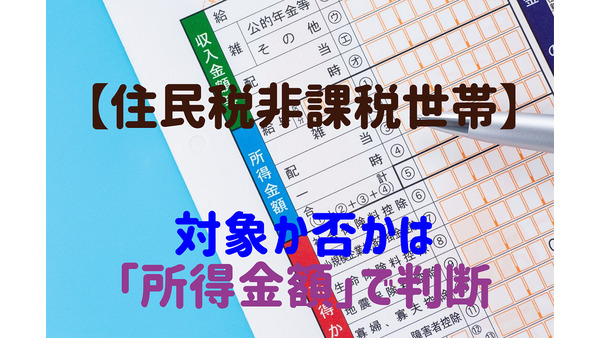
所得金額が一定以下になった場合に、住民税非課税世帯の対象となります。 しかし、基準となる所得計算を間違える人は少なくありません。 なぜなら、所得の種類や申告状況によって、所得金額が変化するからです。 上限を1円でも超える