
厚生労働大臣の諮問機関である社会保障審議会の年金部会は、社会保険(健康保険、厚生年金保険)の加入要件である「月収8万8,000円(年収なら106万円)以上」を、「月収6万8,000円以上」まで引き下げる議論を開始するよう
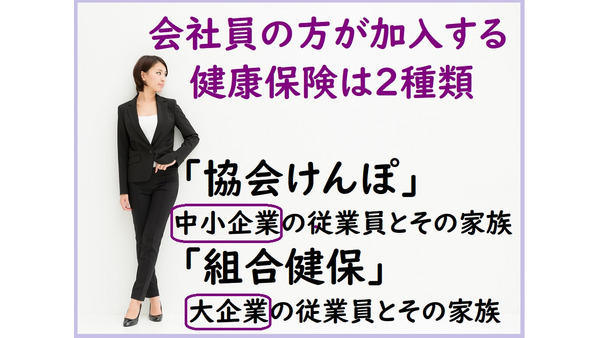
会社員の方が加入する健康保険は、各都道府県にある全国健康保険協会が運営する「協会けんぽ」と、企業などが設立した健康保険組合が運営する「組合健保」の、2種類があります。 前者には中小企業の従業員とその家族が、後者には大企業

全国各地にある労働基準監督署は割増賃金、いわゆる残業代を支払っていない企業に対して、未払いの残業代を支払って下さいと指導する、是正指導を実施しているのです。 2017年度(2017年4月~2018年3月)内に実施された是
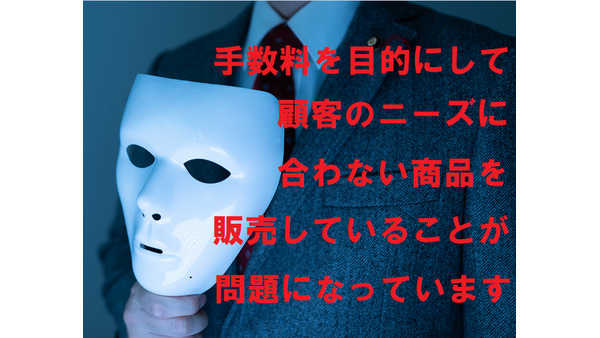
2016年1月に日本銀行が、マイナス金利政策の導入を発表した辺りから、金融機関の営業職員などが、手数料の確保を目的にして、顧客のニーズに合わない生命保険や、投資信託を販売していることが、問題になっております。 またこのよ

厚生年金保険に加入する会社員や公務員などは、原則として65歳になった時に、国民年金から支給される「老齢基礎年金」に上乗せして、厚生年金保険から支給される「老齢厚生年金」も受給できます。 しかし国民年金に加入する自営業者、
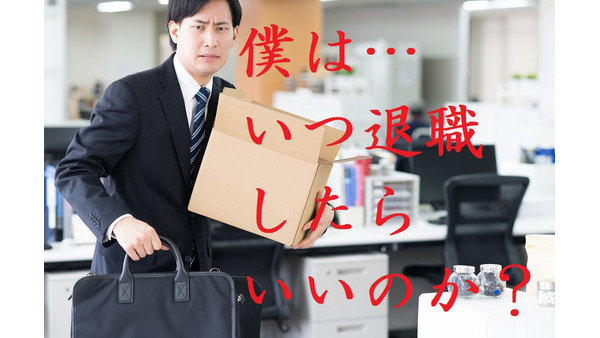
厚生労働省が2018年8月31日に発表した、7月の有効求人倍率(季節調整値)は、前月比で0.01ポイント上昇して、1.63倍だったそうです。 有効求人倍率は「有効求人数÷有効求職者」で算出するため、これが1倍を超えるとい

新卒は10人に9人が内定、正規雇用も増えている 厚生労働省と文部科学省が2018年3月16日に発表した、2018年の春に卒業する大学生の、2月1日時点での就職内定率は、前年比で0.6ポイント上昇して91.2%となり、過去

47歳の女性の読者から、財産分与や年金分割などに関する、質問をいただきました。 その中で加給年金に関する質問を抜き出し、要約して紹介すると次のようになります。 「妻が夫より15歳年下。62歳の夫の年金が一部始まった。 前

2017年1月から個人型の確定拠出年金、いわゆる「iDeCo」の加入資格が拡大されたので、国民年金の第3号被保険者となり、自分で保険料を納付する必要のない「専業主婦」、または「公務員」についても、新たに加入できるようにな
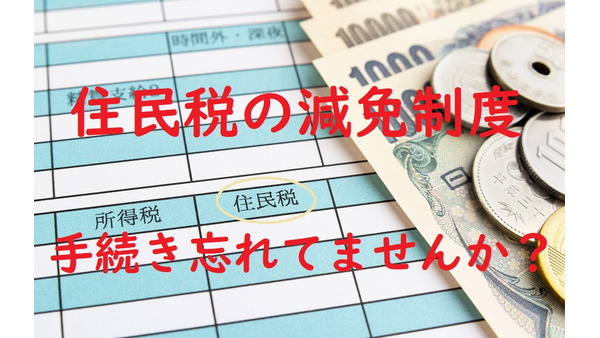
会社員として働いていると、税金や社会保険の手続きの多くを、勤務先の会社がやってくれるため、税務署や年金事務所などに問い合わせをする機会は、少ないのではないかと思います。 しかし、 ・新しく住宅を購入したため、「住宅ローン

退職代行サービス 先日ニュースサイトを見ていたら、退職に関する勤務先の会社とのやり取りを、すべて任せられる「退職代行サービス」が、注目を集めているという記事が掲載されておりました。 このサービスを提供するのは「センシエス

文部科学省は学校給食(完全給食)を実施している、全国の公立小・中学校(約2万9,000校)のうちの583校を抽出して、2012年度の学校給食費の徴収状況を調査しました。 その調査結果の詳細については、「学校給食費の徴収状

新聞やテレビなどを見ていると、医療保険への加入を促す生命保険会社の広告を、毎日のように見かけます。 ただFP(ファイナンシャル・プランナー)などが書いた、生命保険に関する本の中には、医療保険には必要最低限だけ加入すれば良
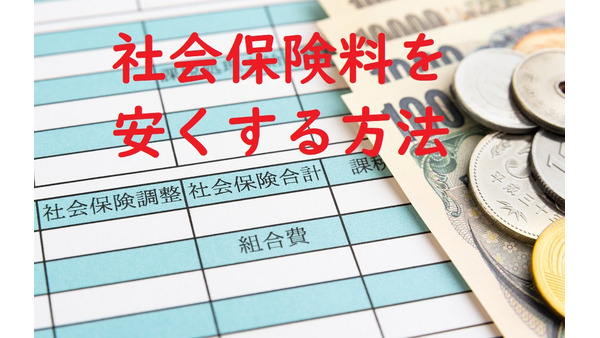
都市部の大学や専門学校に進学する際に、生まれ育った地域を離れ、卒業後もそこに戻らずに、都市部の会社に就職するという若者は、かなり多いそうです。 これにより若者が流出した地域は人口が減少するため、一部の自治体は生まれ育った

政府は2018年6月15日に「経済財政運営と改革の基本方針2018(pdf)」、いわゆる「骨太方針2018」を閣議決定しました。 この「骨太方針2018」の中には、「2019年10月1日に予定されている消費税率の8%から
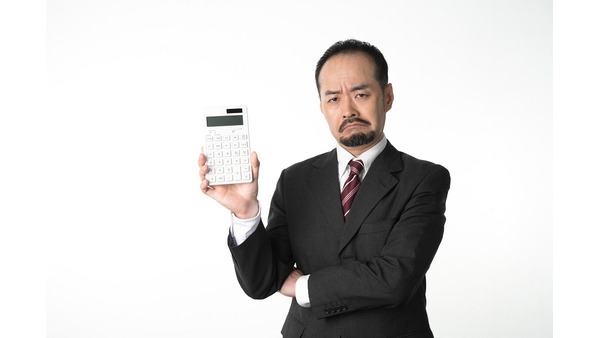
「国民皆保険」 日本は1961年4月に、すべての国民が何らかの公的な医療保険に加入するという、「国民皆保険」を実現しました。 そのため ・ 会社員やその被扶養者の方は「健康保険」 ・ 公務員やその被扶養者の方は、各種の「
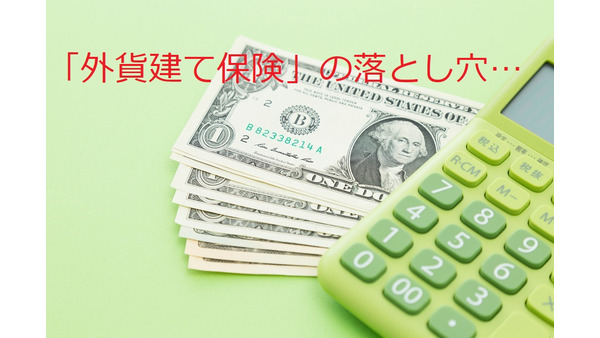
2018年5月の初め頃にアルゼンチンから、世界経済を不安定にするかもしれない、驚きのニュースが発表されました。 それはアルゼンチンの中央銀行が、政策金利を6.75%引き上げ、40%にしたというものです。 しかもわずか8日
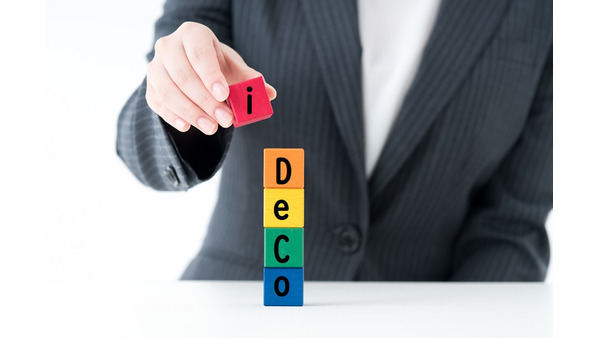
税制面で優遇されている「iDeCo」 2017年1月から公的年金の加入者であれば、国民年金の保険料の免除者などの一部の方を除いて、個人型の確定拠出年金(以下では愛称の「iDeCo」で記述)に、誰でも加入できるようになりま

先日新聞を読んでいたら、2018年5月25日の衆議員法務委員会において、「成人年齢を18歳に引き下げする民法改正案が可決された」という記事が掲載されておりました。 この後は、同月内にも衆議員本会議で可決され、参議院に送付
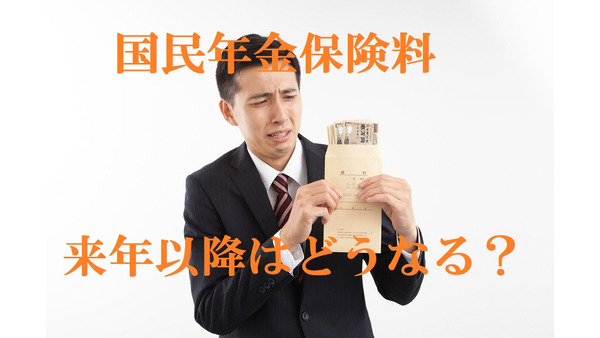
国民年金などの公的年金は原則として、現役世代が納付した保険料を、その時点の年金受給者に年金として分配する、「賦課方式」という仕組みで運営されております。 例えるなら、現役世代の子供が、高齢になった親に対して、生活費などの

仮想通貨は怖いというイメージ 2018年1月26日の深夜に、仮想通貨取引所のコインチェックが取り扱っていた仮想通貨ネムの、約580億円分が不正流出しました。 その数日後にコインチェックは、 「ネムを保有していた方に対して
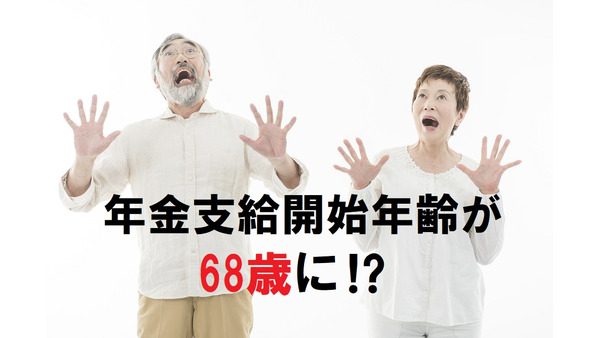
財務省は2018年4月11日に、厚生年金保険から支給される老齢厚生年金の支給開始年齢を、原則65歳から68歳に引上げする案を、財務大臣の諮問機関である財政制度等審議会の財政制度分科会に提示しました。 今のところはこの財政

2018年度が始まってから、食品などの値上げが相次いでおりますが、値下げされているものもあり、それは例えば生命保険の保険料です。 なお生命保険とは一般的に、「人の生命・健康などのリスクに備えるさまざまな保険の総称」になり
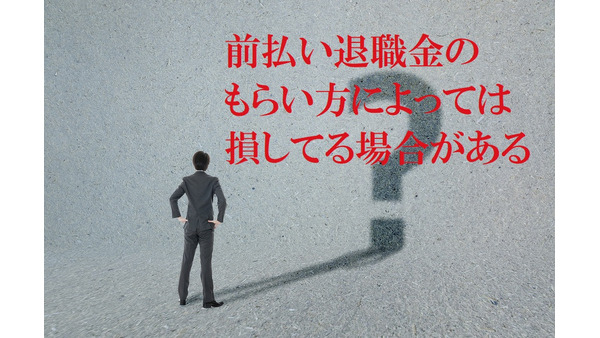
新年度が始まる4月頃になると、退職金を給与に上乗せして前払いで受け取る場合と、退職する時に一時金で受け取る場合の手取り額を比較しながら、いずれがお得なのかを解説する記事をよく見かけます。 また最近は前払いの退職金を、企業

新しい会社で働きはじめるあなたへ 新年度が始まる4月から、期待に胸を膨らませて、新しい会社で働き始める方がいると思います。 しかし実際に働いてみたら、面接の時に聞いた労働条件とはまったく違い、例えば、過労死が心配になるほ
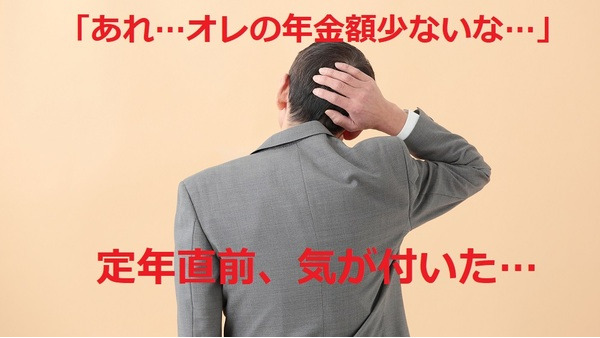
金融広報中央委員会は2016年2月から3月にかけて、18歳以上の金融リテラシー(お金の知識・判断力)の現状を把握するため、「金融リテラシー調査」を実施しました。 この調査結果を初めて見た時、特に印象に残ったのは、次のよう

個人事業主の場合は年間の事業収入から、事業のために必要な支出、いわゆる「必要経費」を差し引いて、事業所得を算出します。 それに対して会社員の場合には、個人事業主のように経費が計上できないため、年間の給与収入から必要経費に

日本年金機構の失態 2017年9月に日本年金機構は、 600億円程度に達する、約10万人分の振替加算の支給漏れ を発表しました。 その翌月には会計検査院の調査により、18億円程度に達する、約1,000人分の遺族年金の過払

「賦課方式」の公的年金 日本の公的年金は原則的に、現役世代から徴収した保険料を、その時点の年金受給者に対して、保険料の納付実績などに応じて配分する、「賦課方式」になっております。 ただ保険料以外に税金も活用されており、例
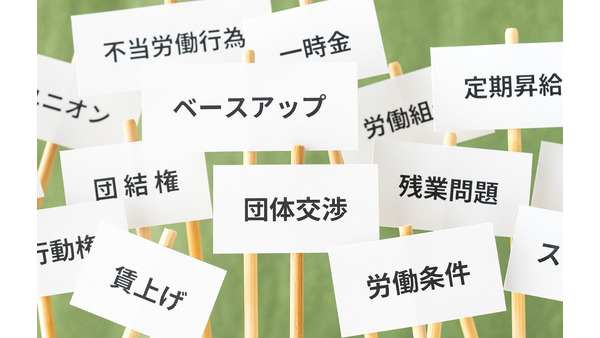
賃上げ率 新年度が近づいてくると、国内の多くの労働組合が賃上げや、労働条件の改善などを経営者に要求する、「春闘」が活発化してきます。 第2次安倍内閣が誕生してから、賃上げ率は伸びているのですが、その勢いは2015年の2.

特例が、2018年内に次々と終了します 国民年金の保険料は原則として、翌月の末日までに納付しなければならないため、例えば2018年1月の保険料は、2018年2月28日が納付期限になります。 その一方で保険料の徴収権の時効

最近はお金に関する情報が掲載された雑誌やウェブサイトを見ると、ビットコインをはじめとする仮想通貨の話題が、よく特集されているという印象があります。 この理由としては2017年の終わり頃に、ビットコインのドル建て価格が過去

給与から控除されている厚生年金保険の保険料は、給与の金額に比例して、増えていく仕組みになっているのです。 【例えば】 月給の金額が15万円の場合には、 1か月あたりの保険料は1万3,725円になり、 月給の金額が30万円
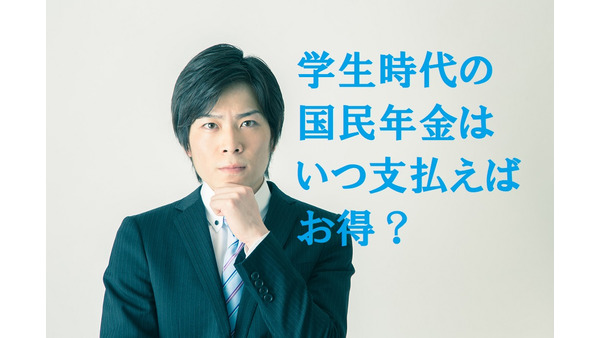
【読者の質問】 「国民年金学生特例を受けていたものです。昨年4月より晴れて社会人となり厚生年金加入者になりました。 2年間の学生特例期間の国民年金を支払わないといけないと思っているのですが、支払いのタイミングはいつがいい
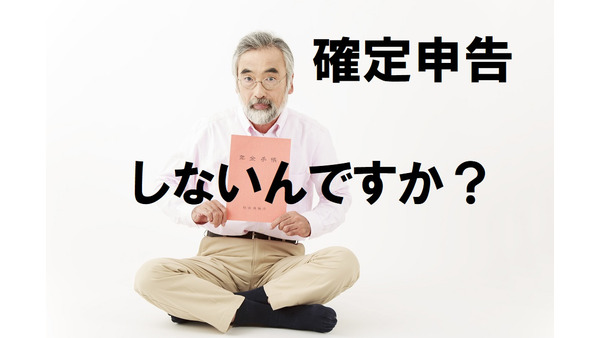
公的年金等(例えば老齢基礎年金や老齢厚生年金など)は、雑所得に該当するため、所得税が課税されますが、その計算方法を大まかに表現すると次のようになります。 (1) 1月~12月の間に支給された公的年金等収入の合計額 - 公

お金に関する雑誌などを読んでいると、「億万長者は○○の習慣がある」や「億万長者は○○を保有している」など、億万長者の特徴について紹介した記事をたまに見かけます。 おそらくその記事の筆者の体験談をもとに書かれているので、間