※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています
注目記事※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています
注目記事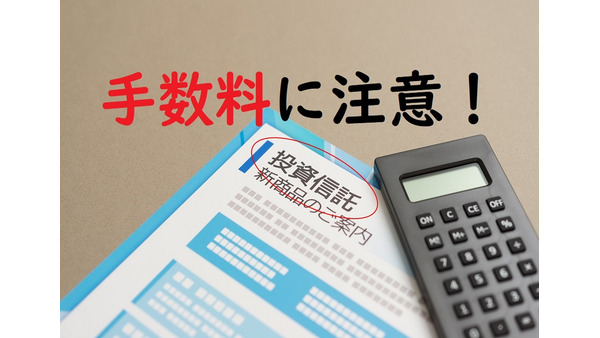
投資信託の購入時に支払う手数料について考えます。 この購入時手数料って、投資信託を販売する会社ごとに違うことが多いことをご存知ですか? 投資信託の「購入時手数料」とは? 「購入時手数料」とは、投資信託を購入する際に、販売

利用者が1,000万口座を超えているNISAですが、注意点もいくつかあります。 投資をする際、リスクを抑えながら高いリターンを得たいと思いますが、NISAではリスクを軽減することが十分にできない場合もあります。 リスクを

多くの人が、住宅購入に向けて、もしくは教育資金として、または老後の資産形成などのために、資産運用を行うことを検討されていると思います。 ただ、「億り人」を輩出してメディアでも話題の仮想通貨取引や、短期間で多額の損益が出る

教育資金ってどうやってためるの? 「子供の教育資金をどうやってためれば良いのか、何から始めれば良いのか分からない」 という家庭も多いのではないでしょうか。 子供1人あたりの学費は1,000万円以上かかると言われますが、特
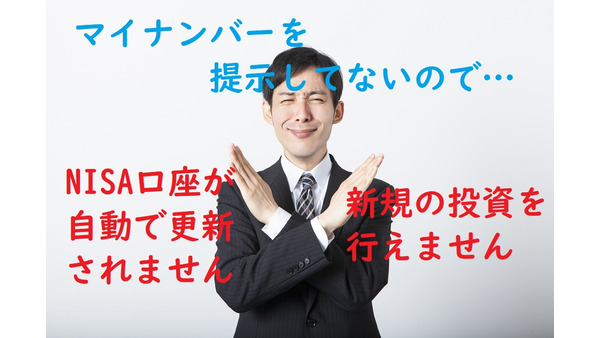
NISA口座開設にマイナンバー提示が義務付け 2014年1月からスタートした少額から投資ができる非課税制度のNISA。 2016年からは、事務手続きの簡素化などを図るため、NISA口座を開設するときには、銀行や証券会社な

老後資金は自分で用意 金融緩和政策により超低金利時代となった現代では、銀行に預けたお金が勝手に増える事はありません。 一方で投資や資産運用を後押しする制度が次々と施行され、初心者でも投資を始めやすい環境が整備されてきまし

毎月分配型投資信託の残高のピークは2015年5月で約43兆円だったが、今年7月末の時点で約25兆9千億円に迄減少した。 これは、金融庁が森信親前長官時代に、毎月分配型投信を問題視して、金融機関による販売を抑制するべく働き

3つのNISA 政府が掲げる「貯蓄から投資へ」のスローガンのもと、お得な税制優遇のある「NISA」が2014年にスタートしました。 その後、 ・ 2016年から「ジュニアNISA」 ・ 2018年からは、「つみたてNIS

前回の「リスクを抑えて、少額から資産運用を始めよう(第1篇) 筆者が「元本保証」の金融商品をご紹介します。」に続き、今回は、元本保証ではないものの、もう少しだけリスクをとりつつ、少額から資産運用できる金融商品をご紹介しま

「億り人」が生まれる仮想通貨投資は、皆さんの周りでも大きな話題となっていると思います。 また不動産投資ローンをもとにしたアパート経営も注目されていることでしょう。 そして、自分も何らかの投資を始めて資産を増やしていきたい

株式会社tsumiki証券 ≪画像元:tsumiki証券≫ 丸井グループが「株式会社tsumiki証券」を設立して、投資信託の販売を開始します。 今、この新しい証券会社のサービスが注目されています。 この「tsumiki

2018年7月2日には、金融庁はつみたてNISAの口座数が約51万に達したと発表しました。 口座開設数自体は一般NISAの初年度より低調ですが、現役世代サラリーマンのような若年層の開設数が多いということです。 同じ非課税

不労所得に近い性質の収入が得られる投資として人気の、ソーシャルレンディング。 しかし投資である以上、ソーシャルレンディングにもいくつかのリスクが存在しています。 では具体的にソーシャルレンディング投資をする時には、どのよ
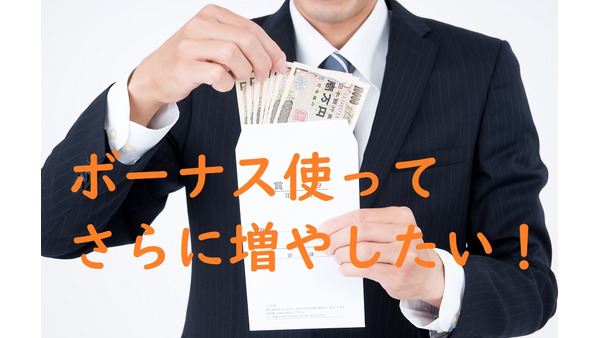
夏のボーナスが支給されたという方も多いでしょう。 ボーナスの支給金額は上昇傾向にあるなど、なかなか景気の良い話が聞こえてきます。 そこでボーナスを使ってさらに効率的に増やしたいという方のために、金額別の投資先を検討してみ

皆さんは資産運用の中に、ETF(上場投資信託)を採り入れておられるだろうか? 投資信託の中でも、銀行でも購入できる一般的な投資信託(非上場)との違いや種類を理解するだけで、低コストで多彩なポートフォリオを組むことが個人投

投資を楽しみたい 投資の目的は「お金を増やす」ことですが、一般的な投資にはリスクが必ずあります。 短期間でお金を増やせる投資ほどハイリスクハイリターンのものが多く、投資経験の浅い人や絶対に元手を減らしたくない人には手が出

今年7月の日銀政策決定会合でも再度注目された、ETF(上場投資信託)をご存じだろうか? 世界的にAIが進歩する中、アクティブ運用が優位になる時代が終わり、情報格差に頼らないパッシブ運用、特にETFを採り入れた運用残高が増

最近注目されてきている投資手法の一つに、ソーシャルレンディングがあります。 しかし具体的にソーシャルレンディングがどんな投資手法なのか、その特徴まで知っている人はそれほど多くないかもしれません。 そこでソーシャルレンディ
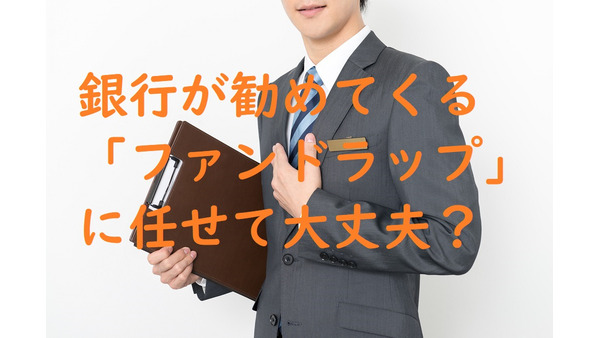
金融業界に変化が起きている 株や債券、投資信託を販売して手数料を稼ぐ証券会社や銀行の営業で最近異変が起きています。 従来の支店や営業マンの評価は、顧客に金融商品を販売して購入時の手数料が評価の対象でした。 しかし、ここ2

投資信託は投資初心者向けというイメージもありますが、個人投資家の上級者でも買っているのです。 ここでは上級者に習い、その使いこなし方を学びましょう。 投資信託の主なメリット・デメリットを整理してみましょう 投資信託の主な

投資信託は、少額から投資でき、簡単に分散投資も実現することができるので、個人投資家にとって魅力的な金融商品です。 しかし、投資信託を保有している間は、ずっと手数料を負担する必要があります。 この手数料の中には、個人投資家

不動産投信 J-REIT アベノミクスで日経平均や株式の方に注目が集まりがちですが、実は日銀は国債だけでなく、不動産投信の方も買い入れています。 J-REITと呼ばれる不動産投信には、日経先物や株式にない魅力があります。

一瞬、目を疑いました。 そして記事をよく読んで納得しました。 個人の半数が、投資信託で損をしているのは事実のようです。 そしてその理由がどうも気に入りません。 ≪画像元:金融庁(pdf)≫ 投資信託は理想的な資産形成商品

海外旅行に行った時に、 「この国は活気があるから投資してみたいけど、方法が分からない…。」 と思った人はいないでしょうか。 他にも留学したことがあったり、お気に入りの国だから応援してみたいと感じた人で、具体的な方法が分か

つみたてNISAをご存知ですか? ≪画像元:金融庁≫ つみたてNISAは、これから資産を作ってゆく若い世代にピッタリの商品です。 つみたてNISAは2018年1月からスタートした商品で、毎年40万円を限度に投資信託などで

個別株の投資家にとって6月は多くの配当が入る時期であり、どれだけ得られるか気になるところです。 上場株の配当も20%強の所得税・住民税が徴収されるようになり、課税されなければ手取が増えます。 また2018年からつみたてN

よく売れているテーマ型投信 最近、「テーマ型」と呼ばれる投資信託がよく売れています。 資金流入が大きいファンドをリストアップすると、上位に複数顔を出すことが多い。 テーマ型とは、例えば 「AI(人工知能)」 「ロボット」

職業柄、筆者はお金の運用に関する質問を受けることが多いが、よくあるのは、 「初心者に向いた運用商品を教えて下さい」 とか 「退職金の運用方法を教えて下さい」 といったものだ。 質問者は「運用する人のタイプや運用する資金に
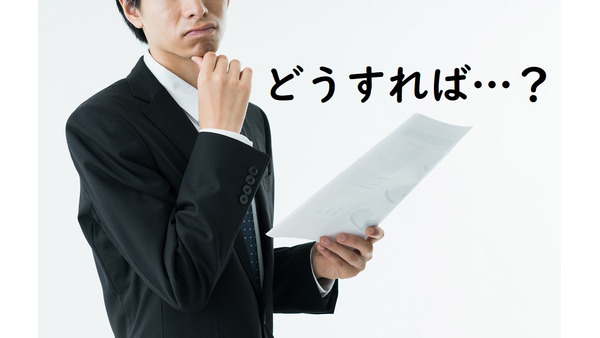
リスク軽減に有効な「資産分散、長期投資、時間分散」 資産運用の世界では、「資産分散、長期投資、時間分散を行うと良い」とされていますが、なぜでしょうか? それは「リスクを減らすことができる」からです。 資産運用の世界では「

6月に入り、いよいよ「ロシアワールドカップ」開催が目前に迫ってきました。 サッカーファンは、世界の一流プレーヤー達の試合を楽しみにしていることでしょう。 そこで今回は、今大注目のサッカーで、資産運用を考えてみたいと思いま
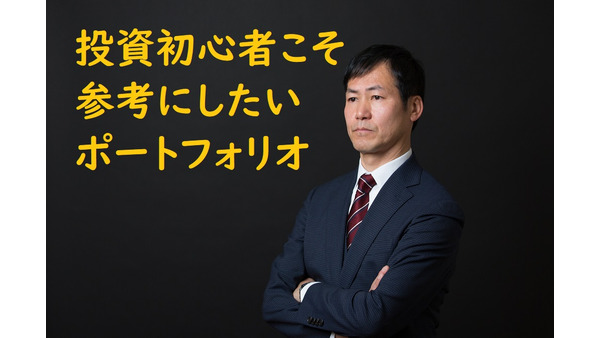
つみたてNISAやiDeCoの登場で、投資に興味を持った人も多いでしょう。 そんな投資初心者が、最初にぶつかる壁があります。 それが 「アセットアロケーションとポートフォリオ、どうしよう」 の壁。 この壁にぶつかったとき
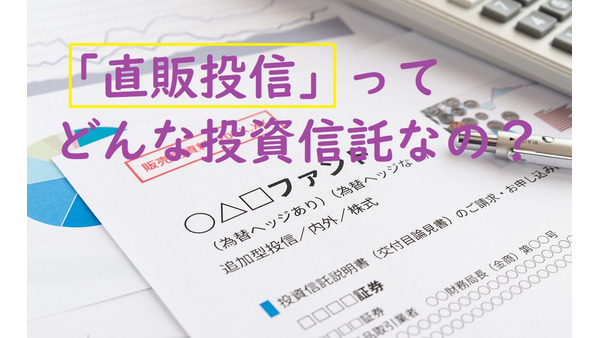
「直販投信」をご存知ですか。 「直販投信」している「投資信託」のことですが、普通の投資信託(ファンド)とは何が違うのでしょうか。 どんな特徴があり、どこで購入できるのでしょうか。 直販投信って? 個人の投資家が投資信託を
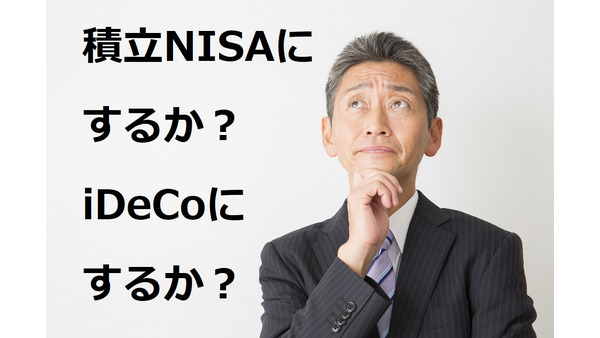
将来を見据えた資金計画を自己責任でする時代が、完全に訪れています。 公的保障がアテにならない、というわけではありません。 わが国の社会保障は手厚いです。 しかし社会保障は、困ったときのもの。 それで贅沢をするというのは、
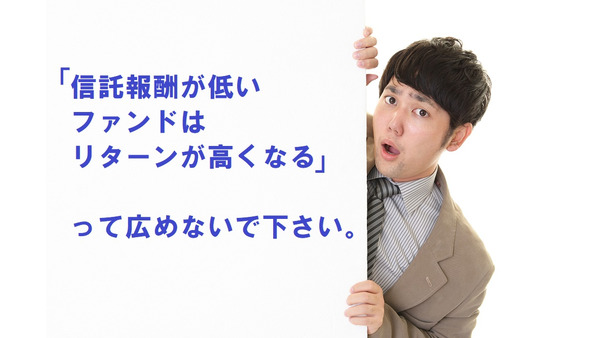
投資信託の分類 投資信託は、投資家に代わって運用会社が、さまざまな投資対象に投資をする投資手段です。 このため、さまざまな観点で分類をし、個々の商品特性がわかりやすいようにしています。 この分類の一環として、ベンチマーク
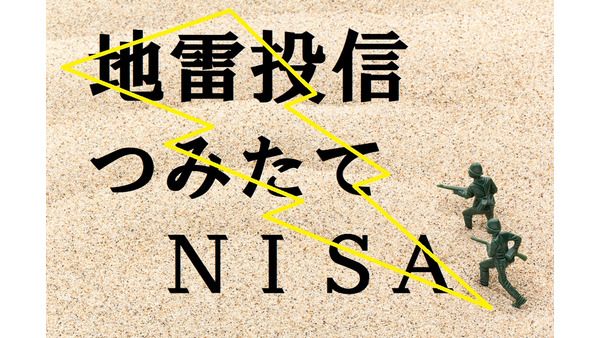
国のお墨付き、でも地雷はあった! 匿名プロが大暴露 つみたてNISAで選べる投資信託は、金融庁の厳しい条件をクリアした長期資産運用に適したもの。 しかし、その「厳しい条件」をクリアしているからといって、すべてをおススメで
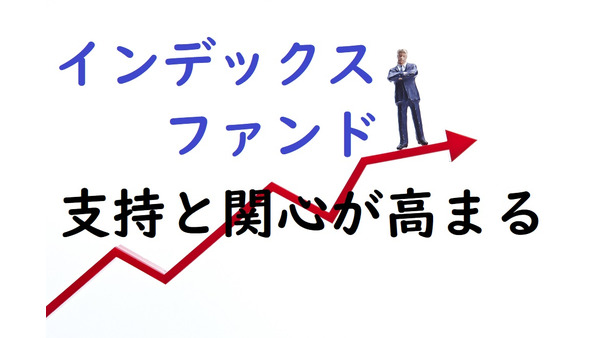
支持と関心が高まる「インデックス・ファンド」 ・ iDeCo(個人型確定拠出年金) ・ NISA ・ つみたてNISA などの税制が優遇された資産形成制度が普及するのと平行して、インデックス・ファンドへの支持と関心が高ま