※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています
注目記事※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています
注目記事
iDeCo(イデコ)とは、個人型確定拠出年金の愛称です。今後は公的な年金だけでは長寿化・少子高齢化に対応できないかもしれません。 そのためiDeCo(イデコ)には「もう一つの年金」として多くの人が加入できます。 そのiD

確定拠出年金iDeCo。2018年8月現在加入者が100万人を超えました。 金融機関の強力なコマーシャルの影響もあって、会社を通じて、あるいは自営業者として、加入者は年々増えています。 確定拠出年金(iDeCo)は、政府
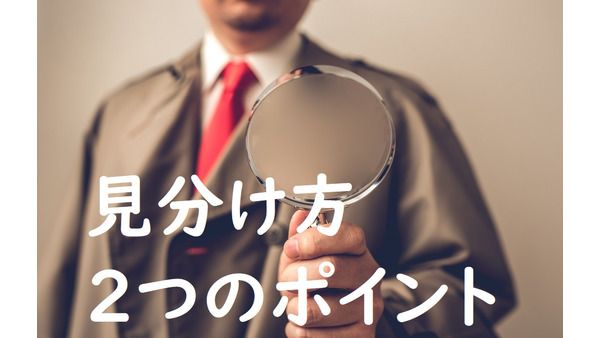
iDeCo(イデコ)のおすすめ商品が分からない人へ iDeCo(イデコ)とは、個人型確定拠出年金の愛称です。ザックリ言うと「もう一つの年金」です。 原則として20歳~60歳までのほとんどの方が加入できますので、すでに入っ

NISA口座の約4割は「休眠状態」 株式や投資信託などへの投資によって発生した、分配金や譲渡益に対しては、原則的に20.315%(所得税:15%、復興特別所得税:0.315%、住民税:5%)の税金がかかります。 しかしN

「損切り」は大事だと言われるが 初心者から、かなりのベテランに至るまで、投資について話をしていると、「損切り」と「利食い」について、誤った知識を持っているケースが頻繁にある 。 誤解の説明を聞くと、喩えて言うなら、不適切

2018年につみたてNISAがスタートし、NISAとつみたてNISAを選べるようになりました。 つみたてNISAとNISAは併用ができず、1つの金融機関を選んで口座開設する必要があります。 そこで、今回はつみたてNISA

iDeCo(イデコ)という言葉を最近よく聞きますし、すでに始めている人も多いかと思います。 それと同時に「iDeCo(イデコ)のことは、なんとなくしか知らない」という人も、まだまだ多いのではないでしょうか。 本記事では、

この記事の最新更新日:2022年4月25日 今や、一般的な銀行の定期預金金利は0.002%まで落ち込んでいます。 そんな低金利が続く中、最近銀行では利回りがよいかわりにリスクもある「投資商品」のセールスに力を入れています

「企業型確定拠出年金制度(企業型DC)」は、老後の生活資金を準備するための制度として多くの企業で導入されています。 2001年10月に施行された確定拠出年金法により導入され、2002年度は400件にも満たなかった導入企業

一口に「財産」といっても、 ・ 銀行預金 ・ 有価証券 ・ 不動産 ・ 土地 ・ 現金 などその形はさまざまです。 いくつかの種類に分散して管理する人もいる一方で、貯蓄額が増えても銀行預金に入れたままというケースも多く見

iDeCoのことは何となく知っているけど、それほど大きなメリットがあると思えず始めていない人は多いです。 そんなiDeCoを軽んじている方のために、今回は老後に大きな差がつくiDeCoを利用した複利運用のメリットを紹介し

予想によると、2019年は波乱要因も多く世界経済も低成長の見通しです。 2017年に「iDeCo」を、2018年に「つみたてNISA」を始めたものの、やっぱり私には向いていない投資は控え、地道に貯金しようかと思った方いら

金融マンに会うと高くつく! ある大手金融グループの役員さんから面白い話を聞いた。 先般金融庁から投資信託販売に関する数値指標(いわゆる「KPI」)を出すように指示を受けたことを切っ掛けにこのグループでは投信販売に関する社
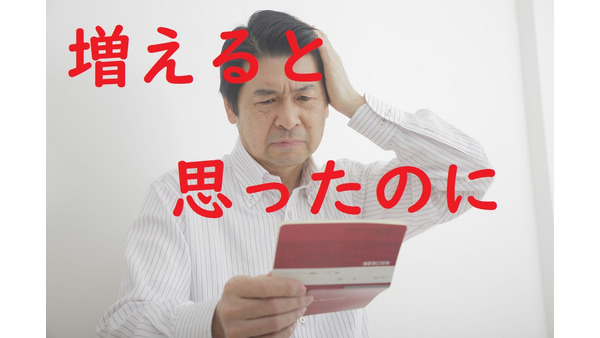
外貨建て保険商品を発売する生命保険会社が増えています きっかけは2017年4月の保険会社の標準利率引き下げです。 標準利率とは、保険会社が将来の保険金支払いのために積み立てている「責任準備金」を計算するための利率です。

ソーシャルレンディング投資 最近何かと問題の多いソーシャルレンディング投資。 それでもその利回りの高さと、手軽に収入が得られるメリットは大きいです。 そこでソーシャルレンディング投資をするときに、手堅い投資先として、公共

オーストラリア絡みの金融商品 銀行で資産運用の相談をすると、必ず取っていいほど出てくるのが、オーストラリア絡みの商品です。 オーストラリアは、日本人から見ると国のイメージが良く、先進国でもあり、何よりも金利の高い国です。

これでもう、悩みません「iDeCo(イデコ)」と「つみたてNISA(ニーサ)」 資産形成・運用を始めたい時に迷うのがiDeCo(イデコ)とつみたてNISA(ニーサ)という2種類の税制優遇制度です。 多くの人は、 「何が違
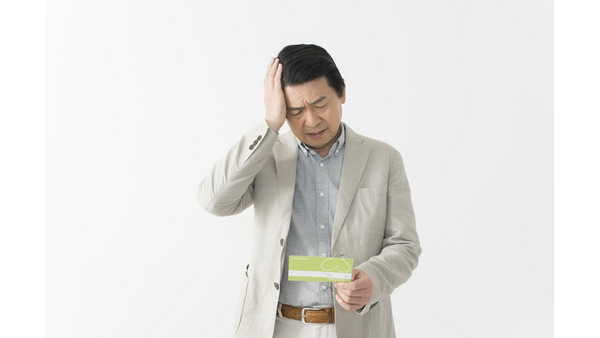
銀行では、様々な金融商品を取り扱っています。投資信託・外貨預金・債券・保険商品…。銀行は、ここ20年であらゆる投資商品を扱うようになりました。 投資商品で切っても切り離すことが出来ないのが税金です。 今回は、投資商品にお
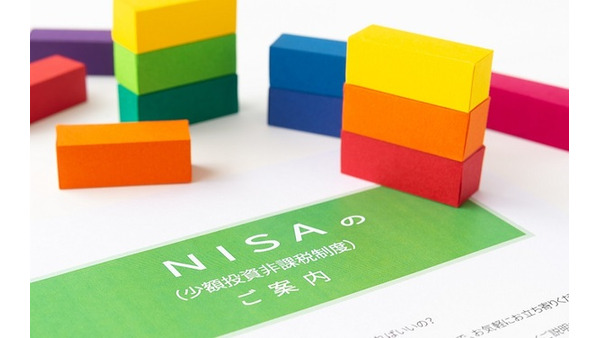
つみたてNISAのデメリット つみたてNISAは年間40万円を投資することが可能で、最長20年の間、発生した利益が非課税になる制度です。 つみたてNISAを始めてみたいけど、デメリットが気になリます。 投資の初心者でも始
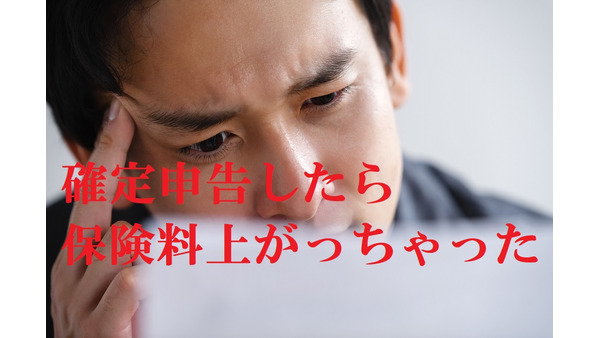
投資信託を銀行で購入 銀行で初めて投資信託を購入したという人は、非常に多いと思います。 購入した投資信託がめでたく利益が出た時、うれしい気持ちが大きいでが、気になるのが税金の支払です。 今回は、投資信託の税金の仕組みと、

ポイントカードを、何枚持っていますか? 私はクレジットカードからコンビニのカードまで入れると5枚のカードでそれぞれのポイントをためています。 ポイントがたまると、お買い物で使えたり、支払額からポイント分を割り引けたり何か

知識がないと投資はムリ? クラウドファンディングというサービスは聞いたことがあると思います。 ソーシャルレンディングは「融資型」のクラウドファンディングになり、企業と投資家をつないでくれるサービスです。 ・ 最低投資額が
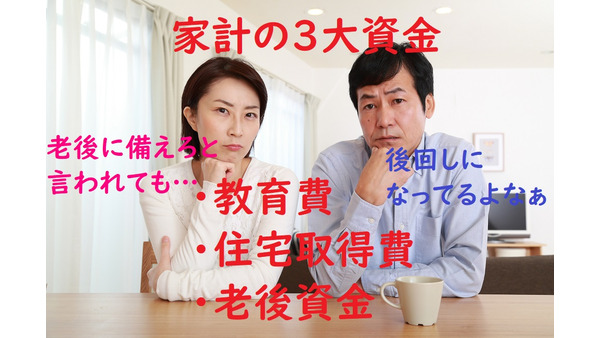
家計の3大資金 ・ 教育費 ・ 住宅取得費 ・ 老後資金 そのうち老後資金への備えはライフステージの後半にやってくるためその準備が後回しになっているのが実状でしょうか。 自分の投資に対するリスク認識を知り、それに合った運
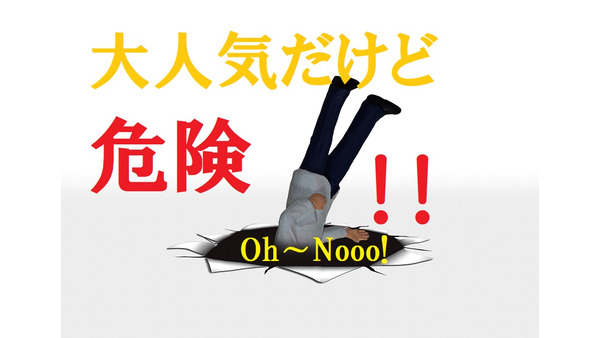
日経レバレッジETF(1570) 株式市場の売買代金上位銘柄ランキングの常連で、トヨタやソフトバンクと肩を並べる、個人投資家に大人気の銘柄です。 ETFは、短期売買を繰り返さない長期投資には不向きです。 個人投資家に人気

超低金利時代が続く中、銀行預金で受けとれる利息の少なさに嫌気がさします。 定期預金で少しでも高い利息を目指すのもいいですが、「個人向け国債」も選択肢の1つです。 投資に興味があるけど、元本割れだけはどうしても避けたい方に

住宅ローン控除 住宅ローンを利用している人にはなじみ深い控除です。 住宅ローン控除とは、住宅ローンの年末の残高から1%の税額控除を受けられるものです。 一般の住宅の場合は40万円、条件を満たした長期耐久住宅に関しては、5
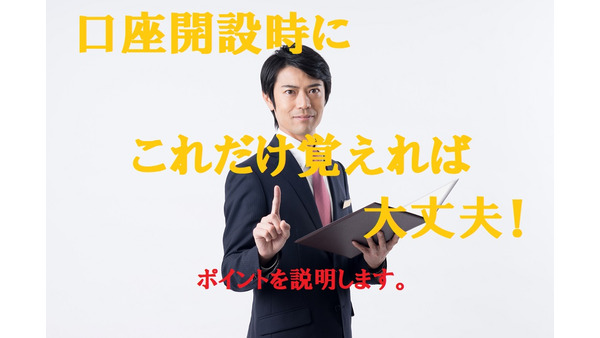
インターネット経由で証券口座は簡単に作成することができます。 また作成時に入金をしなくても登録だけ(=無料)で開設することができます。 ここまでは大半の方が問題なくできるのですが、口座種類に馴染みのない言葉があり、迷って

2020年開催予定の東京オリンピックが近づいてきましたね。 今回の東京オリンピックでの金メダルを「携帯電話などに使われている金から採取して作ろう!」という動きもあるみたいですね。 そんな身近な家電製品にも使われている「金
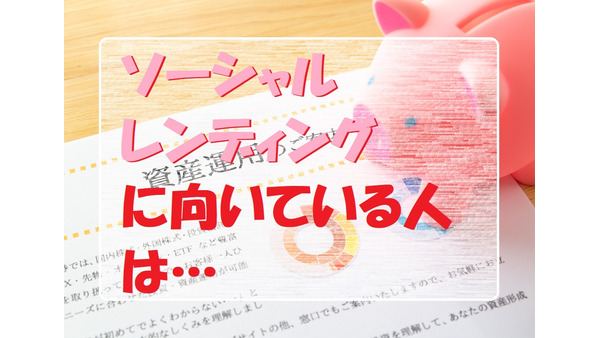
ソーシャルレンディングは新しい投資商品として最近、注目されています。 ですが、 「ソーシャルレンディングを始めてみたいけど、どういうタイプの人に向いているのか気になる…」 という人も多いでしょう。 この記事では、ソーシャ
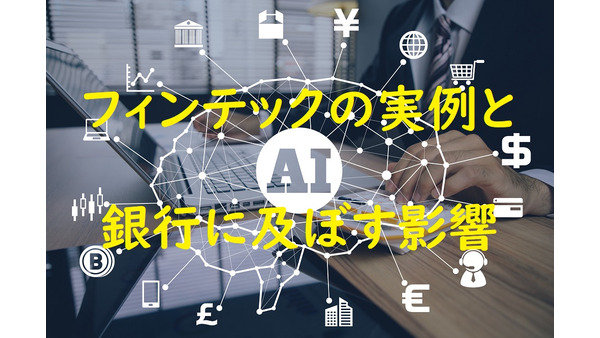
フィンテックによって金融機関が根本から変わってしまうという話題を見かけたことはありませんか。 身近な金融機関といえば銀行が挙げられます。 この記事ではフィンテックの実例と銀行に及ぼす影響をみていきましょう。 フィンテック
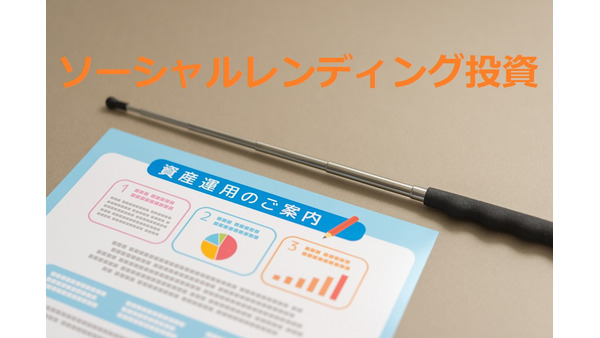
ソーシャルレンディングに投資をする時は、案件の運用期間もよくチェックしておかなければいけません。 半年未満の短期運用案件、そして1年以上の長期運用案件には、それぞれにメリットとデメリットがあります。 ではその具体的な特徴

日経平均などの指数と同じリターンを得ようとするインデックス投資は、個人投資家だけでなく、世界中の機関投資家にも人気の投資手法です。 インデックス投資には、長期的に考えるといくつかの優位性があります。 今回はその優位性を3
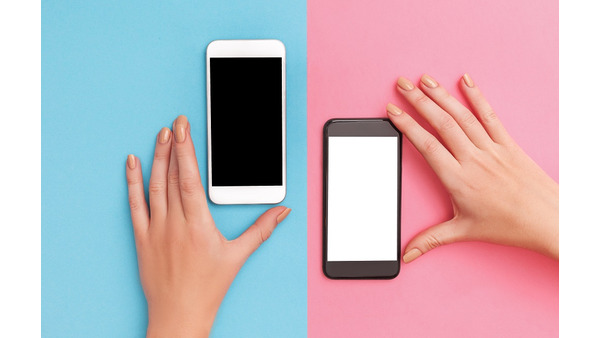
先日、投資ゲームを友人と一緒に楽しんできました。 投資に必要な基礎知識をゲームで楽しく学ぶことができます。 投資には「すごく難しい知識が必要」と思われている方も多いのですが実は身の回りの社会の動きや経済が投資に影響してき
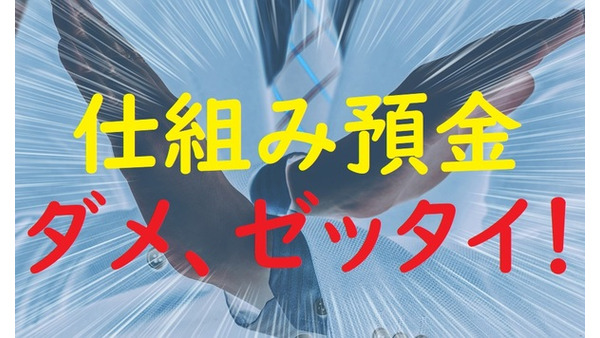
銀行商品の中で比較的人気が高いのが仕組み預金です。 仕組み預金とは期間1か月~1年程度で設定し満期時に通常の定期預金よりも高い金利を受け取ることができる商品のことをいいます。 金利が2-3%付くものもあり銀行商品の中では

数年前証券会社の投資信託の回転売買が問題になりました。 回転売買とは顧客が保有している投信を売却させ新しい投信を購入させる手法です。 この回転売買は顧客が別の投信を購入する度に手数料が入ってくるので金融機関にとっては非常

2014年に「NISA口座」を開設し、残高のある方は大事な作業があります。 2014年に開設した口座は2018年末で非課税期間が終了するため、2019年の「NISA口座」をどうするかの意思決定と手続きが必要です。 選択肢