※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています
注目記事※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています
注目記事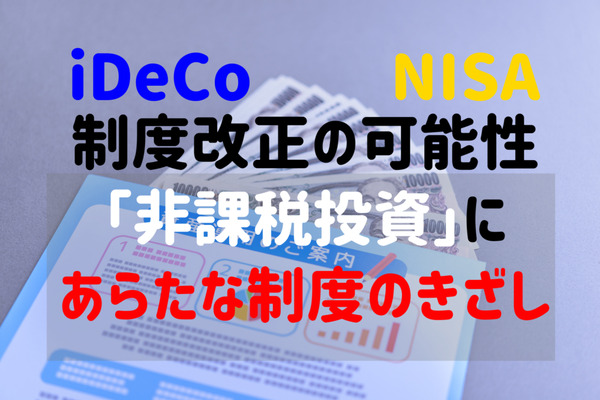
老後資金として2,000万円必要だという試算を出した金融庁の報告書が、年金制度への不信感を増幅させたとして、参院選を控えた政界が揺れています。 反感を買っている理由の1つにこの2,000万円を自助努力・自己責任で形成しよ
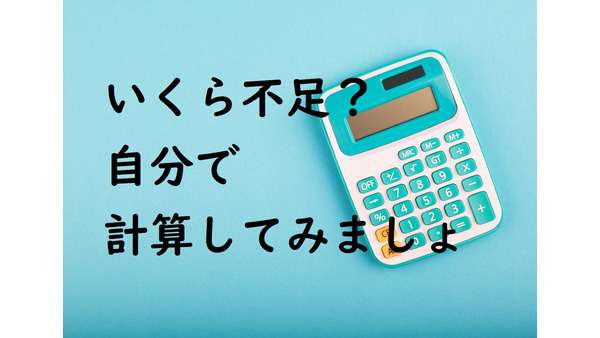
老後資金2,000万円不足問題 先日カナダ在住の友人FPが帰国し、「老後資金2,000万円不足」で揺れる国会論争を見ていて一言、 「カナダは最初から老後資金は自分で貯めなさいと言ってるのよ。」 カナダには最低10年在住し

消費税率10%への引き上げは2度延期されていますが、令和元年10月からの増税は、教育無償化も使途することで信を問う選挙を行っており、既定路線として固まっていました。 しかし平成の終わりから令和の初めにかけて、政府与党関係

別居しても生活費の支払い義務があります 第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。(同居、協力及び扶助の義務) 同居できない事情ができても、扶養義務を負います。 第七百六十条 夫婦は、その資産、収
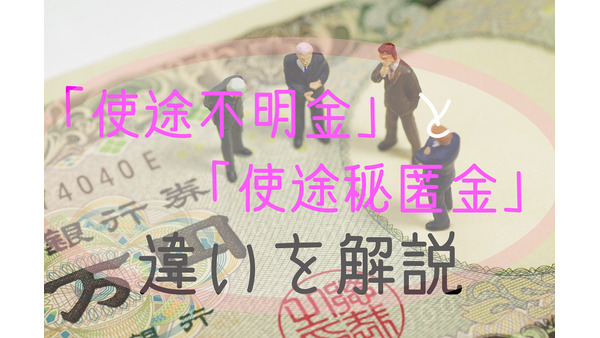
Q:「弊社では出金している事実はあるものの、支出の内容が不明瞭なものや支出や支出先を明らかにしたくない支出先などがありますが、税法ではどのように取り扱うのでしょうか?」 解説 内容が明らかでない支出がある場合、税法はこれ

この記事の最新更新日:2020年11月25日 「年収の境界線、加入しているる健康保険でも違ってくるの?」 「子どもの年齢やいつまで入れるのか、人数も関係してくるのでしょうか?」 「例えば我が家の場合なら夫と私のどちらに扶
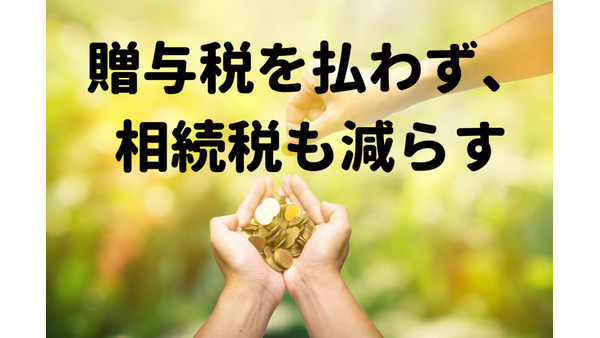
贈与税は、誰でも支払う可能性のある税金です。 何気なくもらう物(財産)も、贈与税の対象です。 ・お年玉 ・タダで車を譲ってもらう ・クリスマスプレゼント 贈与税を申告しない人の大半は、贈与税を支払う認識がなかったとのこと
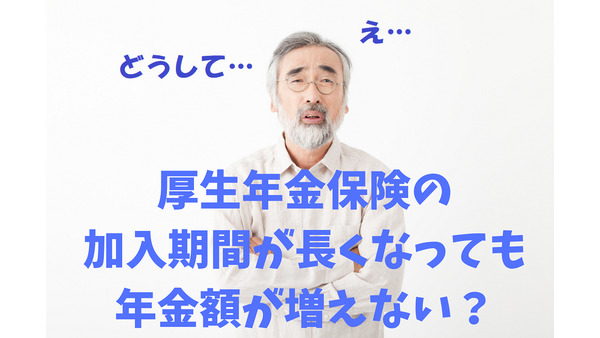
厚生年金の上限引き上げ案 数か月前に新聞を読んでいたら厚生労働省が、厚生年金保険に加入する年齢の上限(現在は70歳)を、引き上げする案の検討に入るという記事が掲載されておりました。 何歳までかは記載されていなかったのです

誰に聞いたらいいのかわからない相続税の疑問 相続はいつ発生するかは、誰もわかりません。 はじめての相続だと、相続税の相談をどこにすべきかもわかりません。 相続税の相談で、最初に覚えておきたいポイントは4つです。 1. 一

先日金融庁の発表した「夫婦2人で年金以外に老後資金2,000万円の準備が必要」などとする試算が話題になりました。 このタイミングで「自助努力」つまり個人個人の資産形成について検討した人も多いのではないでしょうか。 老後資
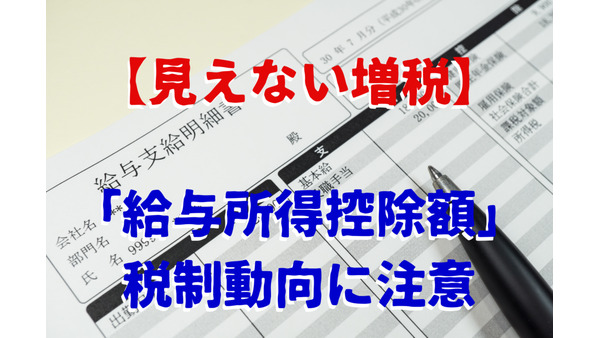
給与所得控除額とは 給与所得控除は、「給与所得」の収入がある方に関係してくる所得税・住民税に関する制度です。 給与所得とは、勤務先から受ける給料、賞与などの所得のことをいいます。 そして、給与所得の計算式は次の通りです。

iDeCo(個人型確定拠出年金)は現役世代から見れば、掛金を出し運用している段階の節税メリットを強く意識しがちですが、受取段階の節税メリットを考えることも重要です。 特に近年では「211万円の壁」なる年金収入の壁も広まっ

所得税を納める人が支払った生命保険料は、所得控除の対象です。 しかし、条件を満たせば、妻の保険料も所得控除の対象にできます。 特別な手続きは必要ありません。 所得を正しく申告するだけで、所得税が還付されます。 夫以外の保
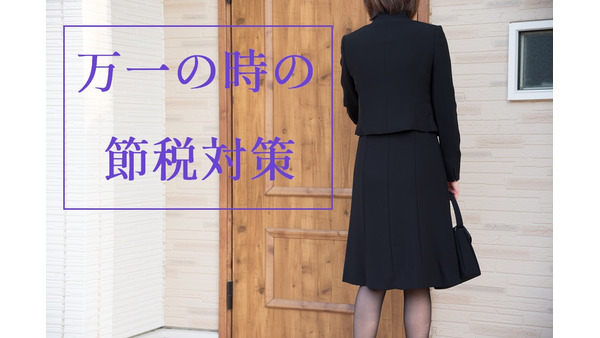
寡婦控除は万一の時、あなたを経済的にサポート 所得税には、配偶者と離婚・死別した時に利用できる控除があります。 「寡婦(かふ)控除」といい、最大35万円の所得控除を受けることが可能です。 万が一の時に所得税を節税できる方

中学校修了前(15歳の誕生日を迎えた後の最初の3月31日まで)の、児童を育てる保護者に対して、児童1人につき月額で5,000円~1万5,000円の児童手当が支給されます。 児童手当は年3回に分けて支給されるため、 2月分

今回の消費税増税の内容 今年の10月に、消費税は現在の8%から10%に引き上げられる予定です。 「増税前に必要なものは買っておいたほうが良いのでは」と考える方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、増税前に買っておく
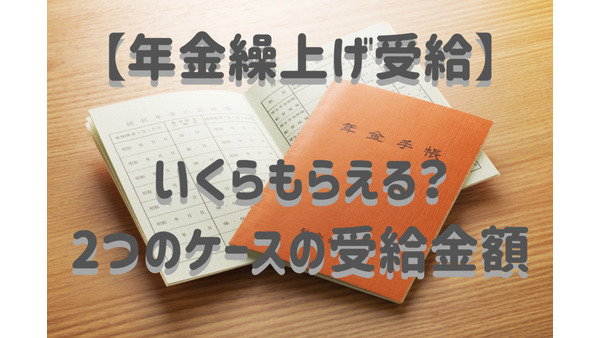
老齢年金の受給には生年月日によって決められた受給開始年齢があり、多くの方はそのとおりに受給されています。 しかし、昨今は、65歳以降の本来の年金の受給開始を遅らせることによって受給額を増やす繰下げがクローズアップされ、希
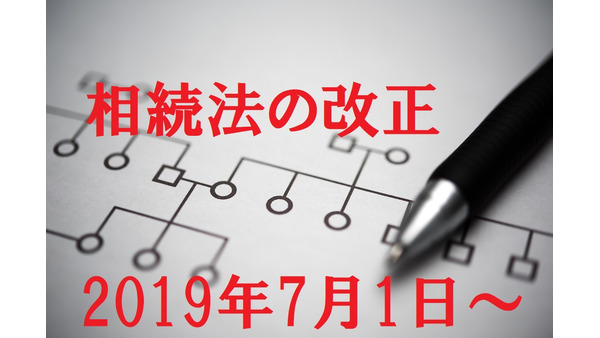
相続人の確認 先日、ある金融機関の方とお話をしていて、「7月1日から金融機関での相続預金の取り扱い」についての話題が出ました。 私が、「相続人を確定するのは、意外に大変ですよ」とお話ししたところ、 「法務局に行けば、法定

人生100年時代 ライフプランは 「いきがい」 「健康」 「経済(資金)」 の3つの観点で中長期スパンで考えましょう。 「いきがい」… 社会、友人、家族との繋がり、仕事や個人活動、ボランティア、趣味など。 「健康」… 毎

今般、国が作成した資料について大きく報じられ、テレビをはじめさまざまなメディアで話題となっています。 ≪画像元:朝日新聞社≫ 報道内容と世間の反応 報じられたのは、金融審議会市場ワーキング・グループ(座長:神田秀樹 学習

2019年10月から消費税率が現在の8%から10%に引上げられる見込みです。 そもそも消費税の引き上げは、高齢化社会における社会保障の財源としての確保を目的とされています。 そこで、消費税率引き上げ分を活用し、「年金生活

Q:「弊社では駐車場として土地の貸し付けを行っていますが、この貸付収入は土地の貸し付けとして消費税法上、非課税売上でよろしいのでしょうか?」 解説 土地の譲渡及び貸付は、消費税法上、基本的に非課税となりますが、貸し付けの
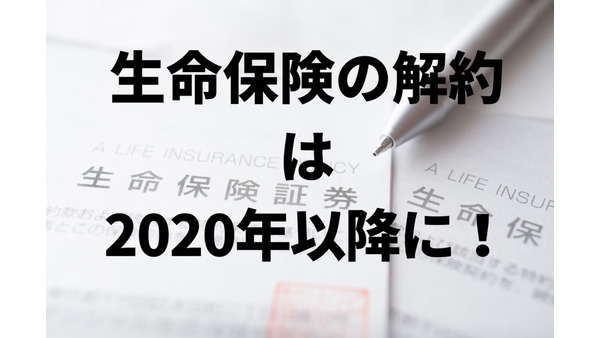
先日に新聞を読んでいたら、外貨建て保険の販売数が伸びるとともに、これに関する銀行と顧客とのトラブル、特に高齢者とのトラブルが急増しているという記事が掲載されていました。 この原因について調べてみると、 「元本割れリスクに
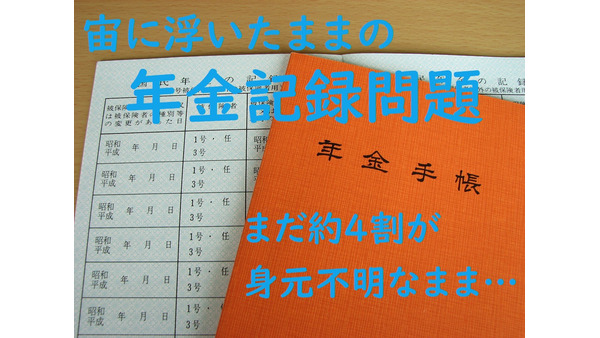
忘れてはいけない「年金問題」 元号が平成から令和に変わるタイミングで、平成にあった出来事を振り返るテレビ番組が、よく放送されておりました。 平成に発生した年金に関する出来事で、もっとも印象に残っているのは、「宙に浮いた年
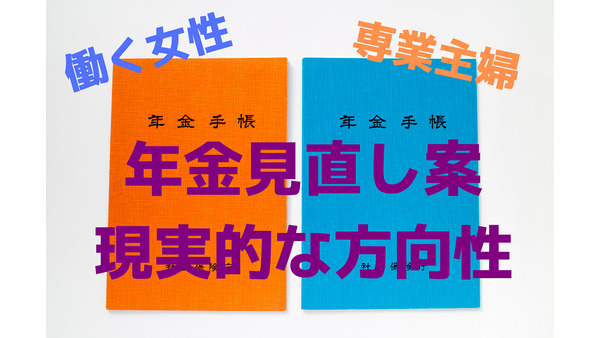
厚生年金保険に加入している方に扶養されている、20歳以上60歳未満の専業主婦(夫)である配偶者は、年収130万円未満などの一定の要件を満たすと、国民年金の第3号被保険者に該当するため、この保険料を納付する必要はありません

公的年金は、破綻するのか 金融庁が、「人生100年時代。年金では満足な生活水準に届かない可能性があり、老後は2,000万円不足するので、そのぶんを投資で確保するべきだ」という報告書を出し、大騒ぎとなりました。 いままで厚

確定申告の手続きに抵抗感があり、それが理由で税金が還付されそうだけど申告したくない…と敬遠している方もいらっしゃると思います。 国や自治体にとっては、還付はともかくそれで納税してもらえないのは困ってしまいます。 近年では

総務省vs自治体のバトルが続く中、ついに、ふるさと納税の規制化が決定しました。 6月から開始される新制度では、高還元の返礼品を多く取り扱っていた「大阪府泉佐野市」、「佐賀県みやき町」、「静岡県小山町」、「和歌山県高野町」

新元号施行まもなく、突如広まった「年金破たん説」 令和元年5月下旬、突然、YouTubeに「公的年金が破たんした」といった趣旨の動画が続々とアッブされるようになりました。 発信元をたどっていくと、朝日新聞デジタルの5月2
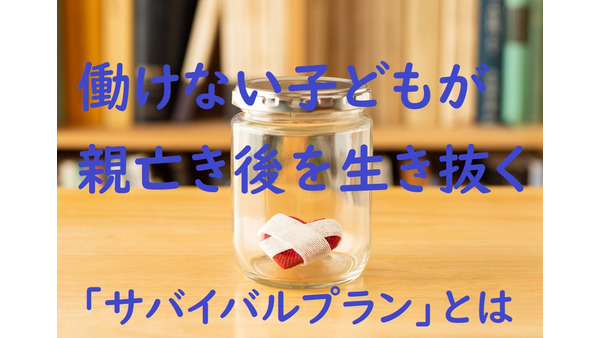
今年の春、40歳から64歳までの中高年のひきこもりが61.3万人いるという調査結果が発表されました。 過去には、39歳までのひきこもりが54万人という調査が出ていますので、2つの調査を合わせますと、ひきこもりの人が115
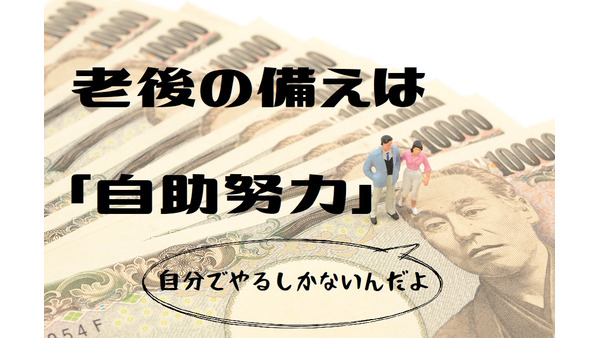
老後の備えは「自助努力」 先日政府は希望する人が70歳まで働けるようにするための制度案を示しました。 ここでは、年金の支給開始年齢を引き上げるようなことは出てきませんでしたが「いずれは年金の支給開始年齢を引き上げるのでは
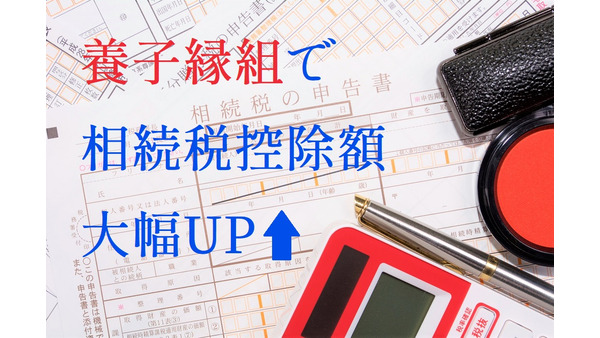
相続税は、お金持ちだけが支払う税金ではありません。 平成27年に相続税の基礎控除額が4割も引き下がりました。 私は元税務署職員ですが、サラリーマン家庭の相続税の申告をいくつも見てきました。 相続税の節税方法はたくさんあり

自宅を売却した代金は、所得税の対象になります。 誰も、余計な税金は支払いたくありません。 ですが、所得税の申告・納税をしないと罰金(加算税・延滞税)を支払わなければなりません。 不動産を売却したお金を少しでも残すために、
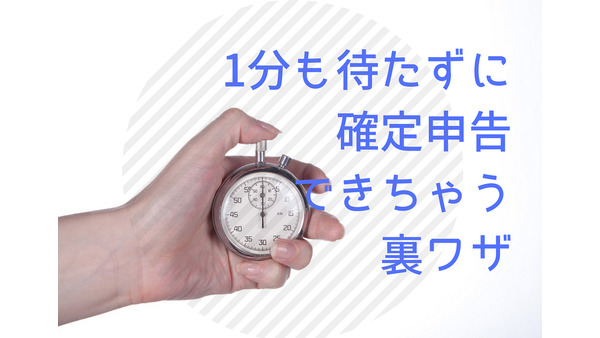
確定申告期間中の税務署は、混雑します。 特に3月中の税務署は、待ち時間だけでも2時間を超えることは珍しくありません。 しかし、そんな確定申告も、1分も待たずに手続きできる方法があります。 気をつけるのは、申告をする時期と
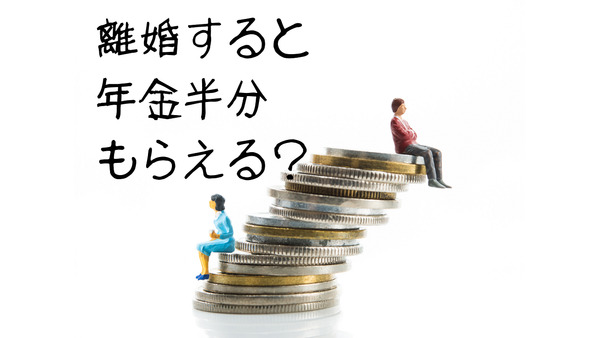
年金分割 離婚をする際や、事実婚(内縁)を解消する際の年金分割は、次のような2種類に分かれております。 (1) 合意分割 2007年4月以降に離婚が成立した場合に、婚姻期間に関する厚生年金保険の保険料納付記録を、これが多
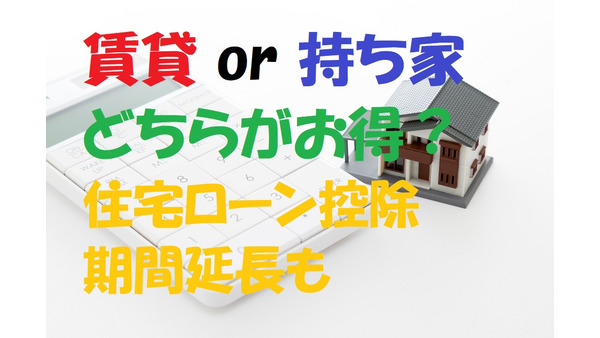
住宅において、「賃貸か購入か」これは常に議論に上る永遠のテーマですが、自分にはどっちが適しているのか? あらためて、それぞれのメリットとデメリットを見てみましょう。 賃貸物件のメリットとデメリット 賃貸物件のメリット 賃