※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています
注目記事※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています
注目記事
親族が亡くなると同時に相続が開始します。 相続財産といってもプラスの遺産(債権)ばかりではありません。 故人の借金などの負債(債務)も当然対象となります。 差し引きがマイナスになるようであれば相続放棄も視野に入れておくべ

姉からの相談で思いついた、円満相続と相続税対策 発端は、姉から 「教育ローンの保証人になって欲しい」 とのお願いからでした。 姉は、自分の子供(母からみると孫)が、大学に入るための、授業料および下宿代が不足しているので、

年金財政については、別の記事でもふれました。 今回は、より深く考えてみたいと思います。 念のため確認しておくと、公的年金の財政状態は地方・国家公務員共済が赤字状態を継続しており、その赤字部分を制度統一まえの「本来の厚生年
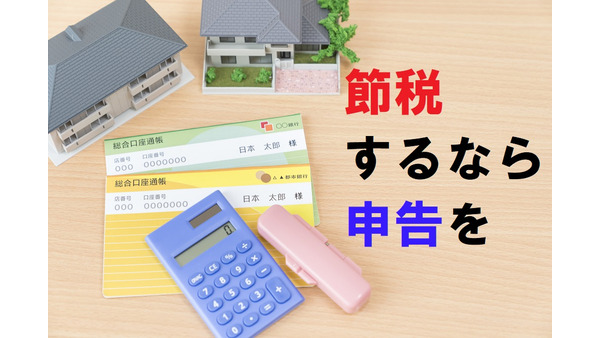
相続税増税時代となり、自分なりに勉強して相続税額を試算したりする人も多いかと思います。 勉強する中で節税対策を知り、試算した結果「相続税額0円」となることがあるかもしれません。 この場合、喜ぶだけでなく注意が必要です。

ご自身が遺族年金を受け取っている方や遺族年金の受取り対象者の方のなかで、今後の生活に不安を抱いている人も多いのではないでしょうか? けれど、 「働くと税金がかかってしまう=もらえる遺族年金が減ってしまうのでは?」 と考え

10人を超える芸人が謹慎・活動禁止になったことで大きく話題になった「闇営業」問題について、脱税にまつわる話題を取り上げております。 【関連記事】:芸人「闇営業」脱税を巡る問題 (1) 「源泉徴収義務」は果たされたのか?
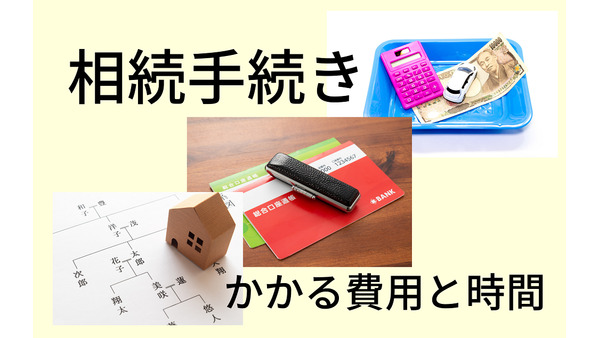
相続手続きに取りかかる場合、細かいながらも必ず発生する費用があります。 何にどんな費用がかかるのかを事前にしっかり把握しておきましょう。 預貯金の名義変更 1. 印鑑証明書の取得費用 まずそれぞれの預貯金口座につき誰が相
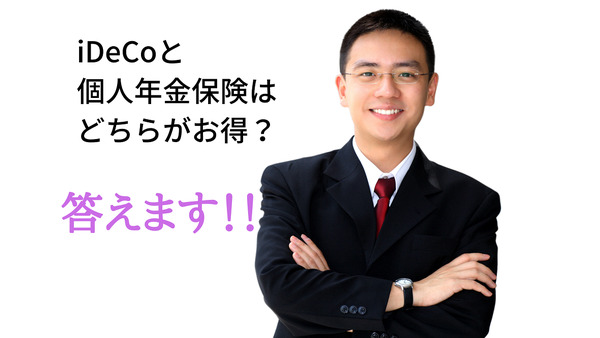
2,000万円問題で注目のiDeCo 老後資金が2,000万円不足すると記載された金融庁の報告書が、大きな話題になりました。 そのためこの報告書で紹介されているiDeCo、一般NISA、つみたてNISAを活用して、老後資

遺言は、自分の財産を誰に、どのような割合で遺すかを自由に決定できる、法律で認められた唯一の制度です。 子供一人だけに全財産を相続させることも、家族ではなく慈善団体に全額寄付することも可能です。 ただし、その際「遺留分請求
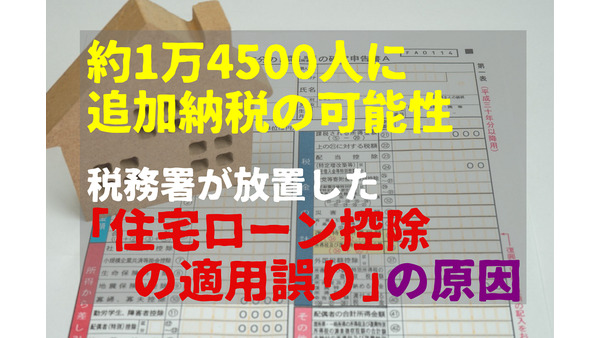
税務署は毎年のように会計検査院から指摘を受けます。 平成30年12月に国税庁が、住宅ローン控除の適用誤りを最大1万4,500人分放置していたと公表しました。 ≪画像元:国税庁≫ 会計検査院に指摘を受けた内容については、「

Q:「消費税率引き上げ前には、住宅などの高額商品の駆け込み需要が発生しますが、そのあとはその反動で景気が悪化するのが一般的です。 景気対策の一環として、住宅ローン控除の改正があったそうですが、その内容はどのようなものでし
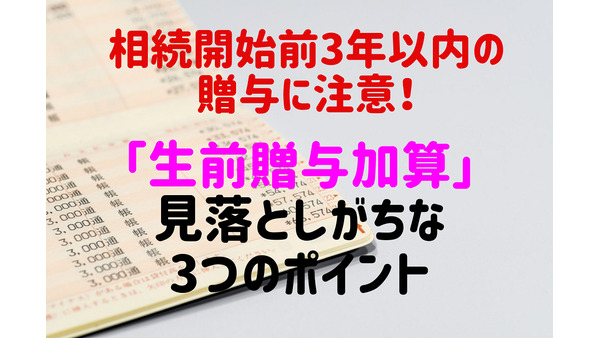
2015年の相続税法改正以来、少子高齢化もあいまって相続税に関心を向ける人が増えました。 よく知られている相続税の制度のひとつが「相続開始前3年以内の贈与財産の取り扱い」です。 ただ、この制度はきちんと理解していないと痛
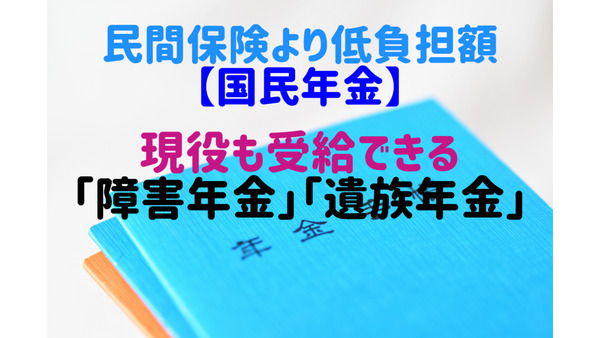
2019年6月初旬に金融庁が公表した「高齢社会における資産形成・管理」のレポートが国会だけでなく一般の国民からも大きな反響を呼びました。 2,000万円の不足というレポートの中身についてはここでは詳しく触れませんが、一部
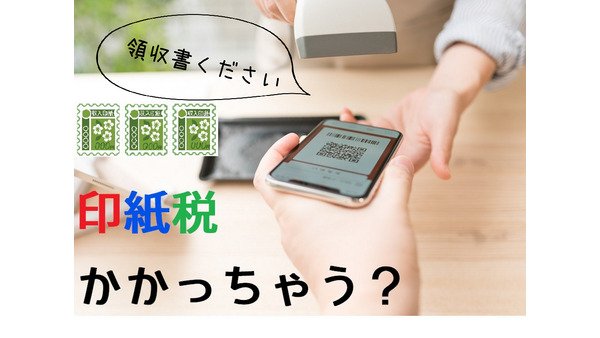
消費増税の影響を緩和するため、キャッシュレス決済のポイント還元制度が導入予定です。 さらに購買データ取得を目的に各社の営業戦略が展開されるなど、何かと話題となっているキャッシュレス決済。 先日も「7pay」(セブンペイ)

あなたに金遣いのアラい親戚がいたとします。 家計の収支は万年赤字体質。 自分ひとりでの家計維持はムリにということになって、いつのまにか連帯保証人となっていたあなたが、これからは一緒に、その親戚の赤字の穴埋めを手助けするこ
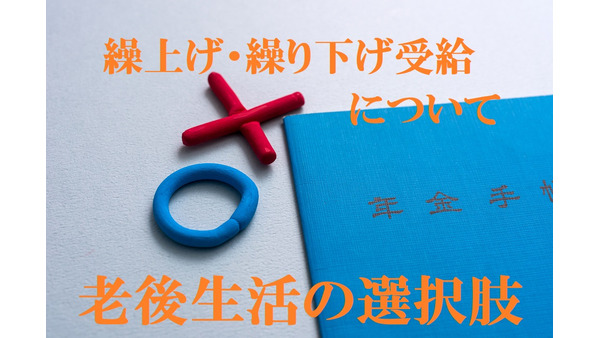
先ごろ金融庁から発表された報告書より、夫婦2名が年金収入のみを頼りに65歳から95歳まで平均的な生活を送ると毎月5万円の不足が生じ、合計で2,000万円の自己資金が必要になると発表され物議をかもしました。 しかし年金収入
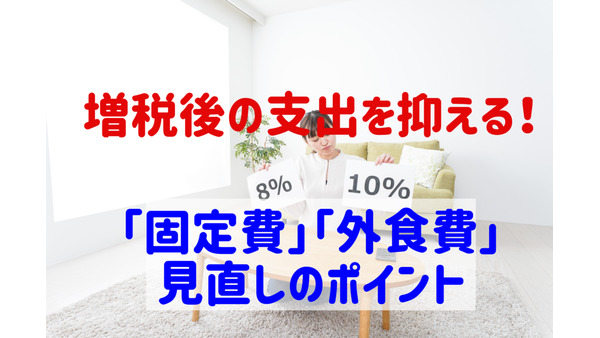
2019年10月から消費税が10%に増税されると、家計への大きな影響が予想されます。 そこで今回は、今のうちに見直しておきたい支出削減ポイントと増税後も影響を受けない項目についてまとめていきます。 増税後どれくらい支出が
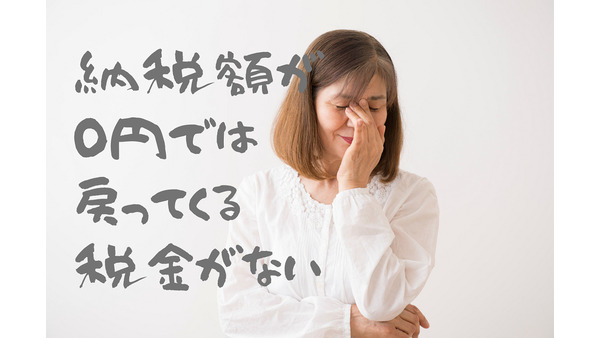
医療費控除 ここ十数年程で医療費控除という言葉が世間一般に浸透してきて、1年間にかかった医療費の領収書を税務署へ持参し、確定申告をするという方が増えています。 これは私が税務署に勤めていた時の話になりますが、確定申告時期
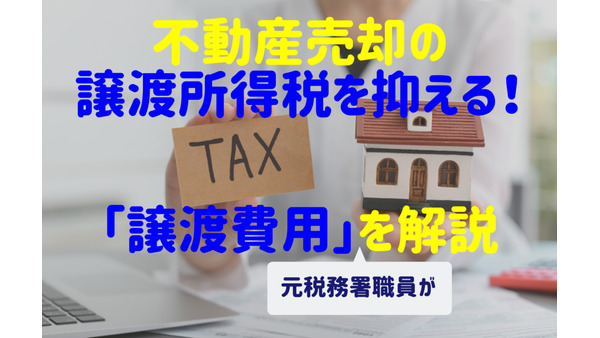
不動産を売却した場合、売却益は「譲渡所得税」の対象 売却益が発生していなければ、税金を支払う必要はありません。 税金の計算で重要になるのが必要経費です。 譲渡所得の計算式は次の通りです。 ≪譲渡所得の計算式≫ 売却金額

ご両親や親族に毎月仕送りしている方は、ぜひ知っていてほしい所得控除が扶養控除です。 扶養控除というと同居していることが前提と思っている方が多いようですが、実は別に暮らしていても一定の条件を満たしていれば控除を受けられます
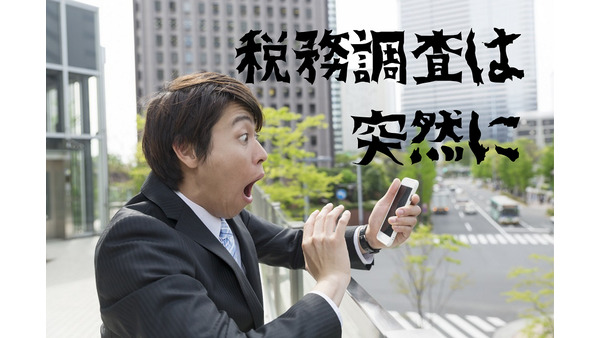
個人の確定申告は3月ですが、税務調査は7月から12月に行うことが多いです。 国税組織の本音は1年通して税務調査したいと思っていますが、確定申告の事務処理に数か月必要なので、税務調査の期間は半年間です。 ただ、突然調査があ

令和元年10月、ついに消費税が10%に引き上げられます。 コストが増えて生活費が圧迫されてしまうのでは? と不安に思っている方も多いかもしれません。 しかし実は生活に密接に関わる特定の品目については、現行の8%のままに据
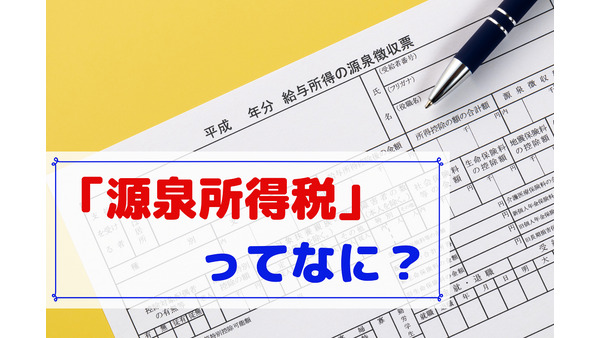
先月6月、弊社の税理士さんより「7月10日は源泉所得税の納付があります」とのお知らせを頂きました。 「源泉所得税?」 「所得税とは違うのかな?」 と、納めている税金について詳しく知らないことに気づき、改めて源泉所得税とは

吉本興業所属の芸人を巡る「闇営業」問題は、反社会的勢力と関与したことが原因で10人を超える芸人が謹慎・活動禁止処分となり、一般紙でも報道されるようになりました。 当初は1人契約解消、他数人の芸人が疑惑の釈明に追われただけ

「老後に2,000万円足りない」問題で、年金は破綻するのではないかと思う人もいるようです。 前回の記事では、年金はさまざまな方策をとっているので破綻することはないという話を書きました。 その方策とは、 1.「保険料を上げ
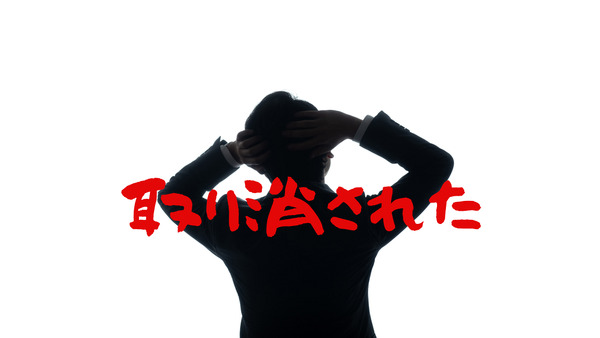
【質問】 「弊社では昨年期限後申告をしているのですが、今年も期限後申告となりそうです。 この場合、青色申告が取り消しになるとのことですが、これはどういうことでしょうか?」 解説 2期連続で期限後申告をすると青色申告の取り

平成30年分よりスマートフォンでも電子申告で利用できるようになった確定申告書等作成コーナーですが、申告パターンが限定されている点が批判の的にもなりました。 さすがに次の年もこのままでという方針ではなく、対象者拡大を予定し
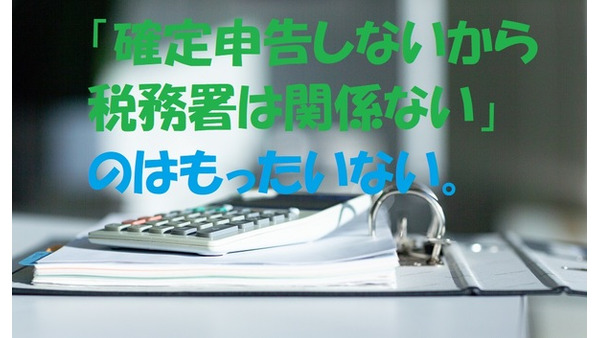
確定申告をしない人にとって、税務署に行く機会はありません。 しかし、「確定申告しないから税務署は関係ない」では、もったいないです。 税務署は確定申告以外でも、所得税・相続税・贈与税などのさまざまな税金を取り扱っています。
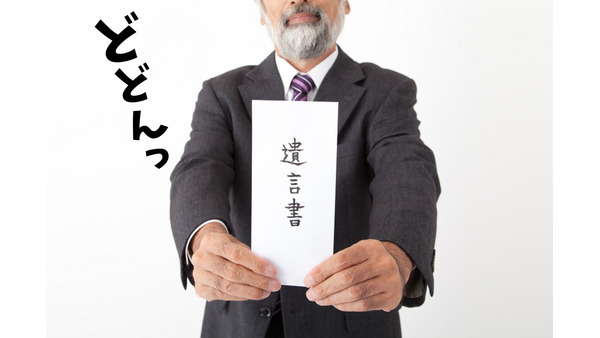
親が死亡したとき「遺言書」が残されているケースがあります。 その中に「長男にすべての遺産を相続させる」などと書かれていたら、他の子どもたちはまったく遺産を受け取れないのでしょうか? 実はそうとも限らず「遺留分」を請求でき

iDeCo(以下イデコ)と呼ばれる税制優遇制度があります。 これは老後のための資産形成を「自分で行う」ための制度です。 そして、このイデコと呼ばれるいわば「もう1つの年金」では運用商品も自分で選ぶ必要があります。 運用商
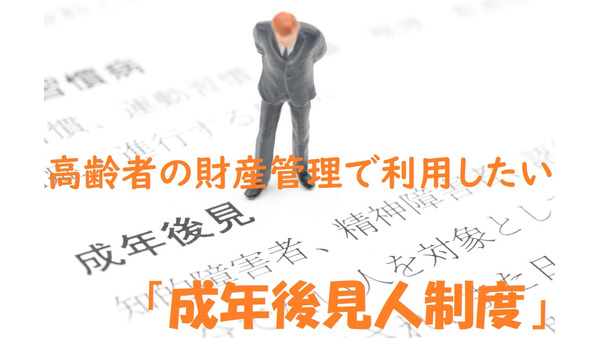
少子高齢化や核家族化が進む現代、高齢者の独居や夫婦2人暮らしという世帯が多くなっています。 介護や支援が必要になっても、近くで支援できる身内が居ない場合や頼れる身寄りがいないというケースもあります。 そこで困ってくるのは

ニュースなどでよく取り上げられる割には、なんとなくややこしい…と思われがちな年金制度ですが、1階建て、2階建て、3階建ての建物をイメージすると分かりやすくなります。 年金制度1階:対象は自営業や学生、無職の方 1階部分に

多くの方にとって、マイホームは人生で最も高価な買い物です。 しかし、その高価さから消費税が数%上昇すると購入価格が大きく高騰してしまいます。 多くの人は、 「消費税が増税される前に、マイホームを買った方が得なのではないか

企業年金連合会の前身は、厚生年金基金連合会 皆さま、「企業年金連合会」をご存知でしょうか? 「企業年金連合会」とは、その名のとおり企業年金の連合体です。 昭和42年に厚生年金保険法に基づき厚生年金基金の連合体の「厚生年金

年金制度を表現する場合に「100年安心」という言葉が使われるのを聞いたことがあるかもしれません。 平成16年、現在につながる大規模な年金制度の改革が行われました。 「100年安心」というのは、その時に使われたスローガンで
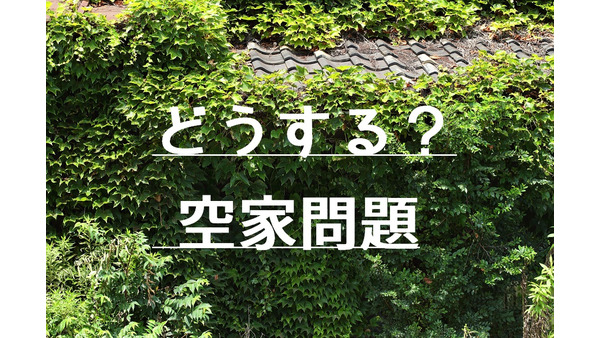
現代の日本に広がる深刻な空き家問題 日本は少子化に伴い、実家を相続したものの住む者もおらず、固定資産税が上昇してしまうため、取り壊すこともできないといった空き家が多く発生しています。 しかし空き家は適切に管理しないと倒壊