※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています
注目記事※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています
注目記事
働いて給料をもらえるだけの十分な収入がある高齢者には、厚生年金の支給額を抑制する制度が在職老齢年金制度です。 ただ生涯でもらえる年金額が純減となるため、就労調整が起きるという問題点も指摘されています。 雇用契約でなく請負

結婚されている奥様であれば一度は、 扶養枠内で働いた方がよいのか、社会保険に加入してフルタイム勤務で働いた方がよいのか。 悩んだ事があるのではないかと思います。 扶養枠内で働くと言っても、よく分からない方も多いのでは?

イデコ(iDeCo)とは個人型確定拠出年金の愛称です。 いわゆる「もう一つの年金」と呼ばれる制度です。 個人の老後の資産形成のために、個人の意思で加入し、掛け金や運用商品の選定を行います。 原則として20歳から60歳まで

お金に関するお得な制度は使いたいと思いつつも、日々の生活に追われていると面倒な手続きほど後回しにしてしまいます。 しかし、例えばiDeCoの年間の節税額だけを見ても、年収600万円の会社員の場合で8万円前後、同程度の年収

人生100年時代という言葉をよく聞くようになりました。 人生を長く楽しめる一方で、老後が長くなる分、お金の心配をされていらっしゃる方も多いと思います。 そこで、老後に向けた準備の選択肢の1つとして、公的年金制度をベースに
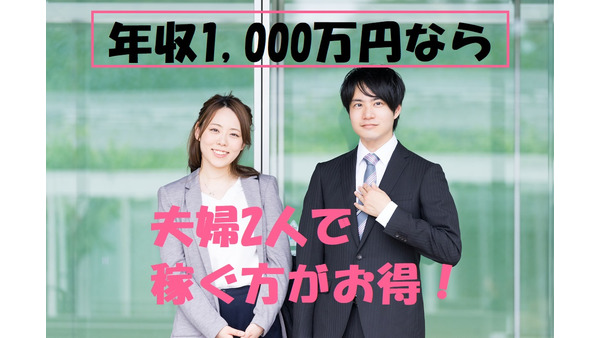
年収1,000万円以上のハイスペック会社員になったり、そんな配偶者を捕まえたりするのは難しくても、夫婦2人で頑張った世帯年収でなら1,000万円に近づけそうだと思いませんか? 平成29年分の国税庁調査によると、給与所得者

人生100年時代の到来 「あなたは何歳まで生きますか?」 「80歳位までは生きたいなぁ…」 「えっ、人の寿命なんて分からないでしょう」 ひとりひとりの寿命は神のみぞ知るところですが、日本人全体の「平均寿命」は、男性が約8
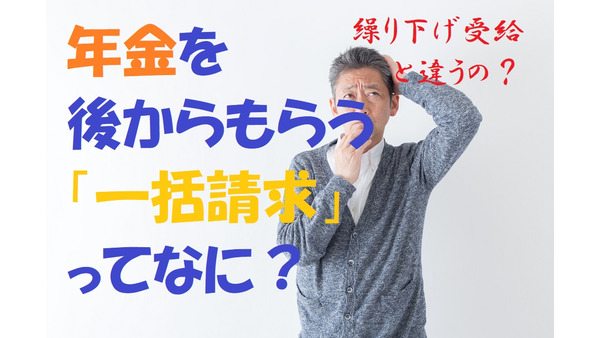
政府としては老齢年金を現行制度では70歳まで、さらに制度改正して75歳まで繰下げ受給してほしいという思惑もあります。 ただ税・保険料負担が増える、遺族厚生年金を受給することになった場合に不利になるなどの悪影響が出る危険性

お金の話はプライベートに深く関わる話です。親子といえどもうかつに触れられません。 しかし、高齢の親はいつ倒れるかわからないのも事実です。 介護や葬儀の費用、相続に関するお金も懸念材料です。 だからこそ、親が元気なうちにど

ネット証券が普及したことにより投資は身近になりました。 そして海外への移住や赴任、一時滞在なども現在は海外旅行や留学に気軽にいける時代になりました。 そこで問題によくなるのが海外に移住したり赴任したりするときに証券会社で

子供が生まれたら学資保険 その考え方もマイナス金利導入以来、お金が余り増えなくなり、すっかり変わってしまったようです。 そんな中、学資保険の代わりとして提案されるものの1つが終身保険です。 ですが終身保険は一生続く死亡保
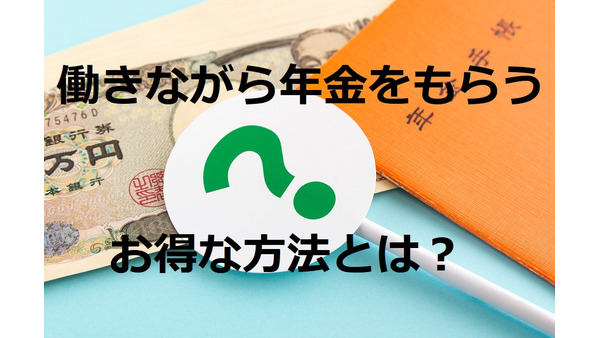
在職老齢年金とは? 年金をもらいながらの働き方について、週刊誌などに特集が組まれています。 「在職老齢年金」とはどんな制度か確認してみましょう。 在職老齢年金とは、60歳以降に厚生年金に加入して働きながら受ける老齢年金の

iDeCoの給付金や企業年金を受け取る際、一時金として受け取ったほうが有利だとよく言われます。 税務上退職所得に該当するからですが、具体的に有利な点を税制の他に、保険料まで見ていきましょう。 退職所得の税制メリット 退職
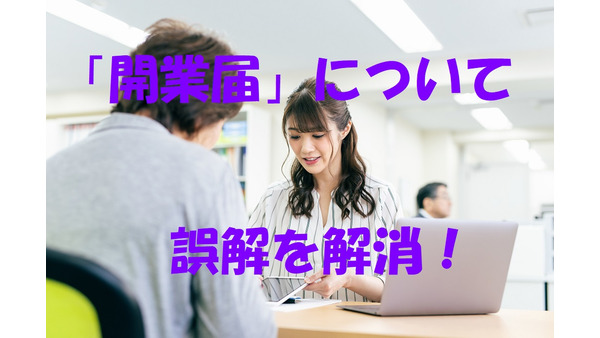
扶養内で働く主婦起業家や副業起業家の中には、開業届を提出するべきかと悩まれる方がいます。 お話を伺うと、悩む原因は「開業届について誤解」があることだと気づきました。 そこで開業届のよくある誤解を解いていきます。 また、実
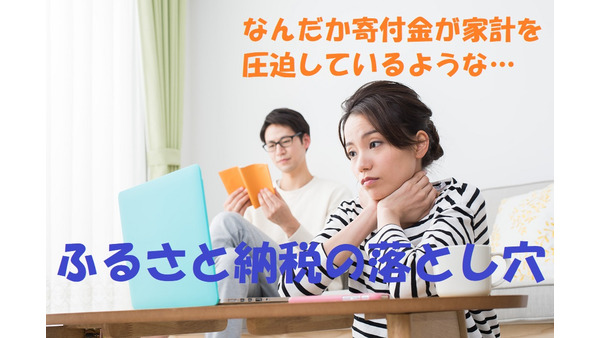
ふるさと納税は、実質2,000円でさまざまな返礼品をゲットできるお得な制度です。 しかし、寄付金の支払いが家計を圧迫していると感じる人も多いでしょう。 そこで今回は、ふるさと納税が家計を負担しているように感じる理由や対策

iDeCoの老齢給付金を年金形式でもらう場合「公的年金等に係る雑所得」、一時金形式でもらう場合は「退職所得」となり、受取時の税制メリットとして公的年金等控除額や退職所得控除額の存在もよく言われます。 ところでiDeCoに
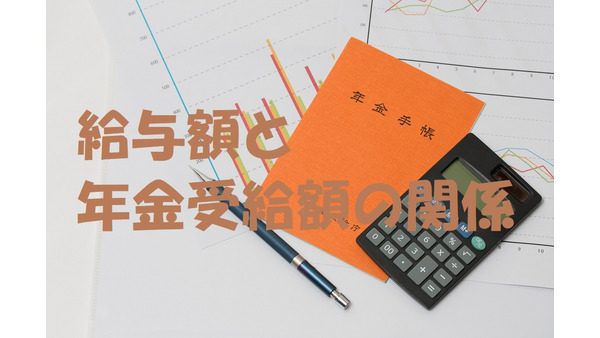
「平成29年分民間給与実態統計調査」によると、平均給与が最も高い業種は電気・ガス・熱供給・水道業で、次が金融業・保険業、さらに情報通信業と続きます。 これらの業種で働く人たちの給与額は、平均値をうわまわっています。 この

いま日本は急速に少子高齢化が進み、多くのメディアで「年金不安」や「老後不安」など将来を悲観するワードが飛び交っています。 誰しもが、旅行や音楽など趣味を満喫する豊かな老後生活を送りたいと思い描いていることでしょう。 老後

二人のすれ違い 最近、よく相談を受けるのが、シニア世代の夫婦仲の問題です。 夫は、今までさんざん家庭を顧みず好き放題やってきたものの、定年を過ぎると、やはり奥さまが一番かなと思うようです。 そこで、 「旅行にでも、一緒に

原則として65歳から受給できる、公的年金の一種である老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金)の支給開始を、1か月繰下げる(遅らせる)と、0.7%ずつ年金額が増えていきます。 この繰下げができる年齢の上限は70歳になるため、

マイナス金利の影響で、預貯金にせよ保険にせよ、円建てのものはお金がほとんど増えません。 その対策として外貨建ての金融商品を活用する人は多いですが、一方で外貨には抵抗がある人も少なくありません。 そこで私が考えるのは、円建

所有不動産の調査方法が分からない 自宅にあった、父の固定資産税の課税明細書には、いっぱい土地が載っていました。 その土地が具体的にどこにある土地なのか不明です。 市役所へ行き尋ねると、地籍図(公図)というものがあり、1枚

令和元年(2019年)10月から予定されている消費税増税で、外食店での支払いも持ち帰りであれば軽減税率8%が適用されます。 しかし2019年4月に、2月期本決算発表を行った際の外食業界の対応を見ると、持ち帰りなら必ず安く

国際的な交流が活発化し、海外で生活されている方も年々増加しています。 海外在留邦人数調査統計(外務省・平成30年)によると、長期滞在者、永住者の合計額は、平成元年には約58万人だったのが、30年には約135万人にも上って
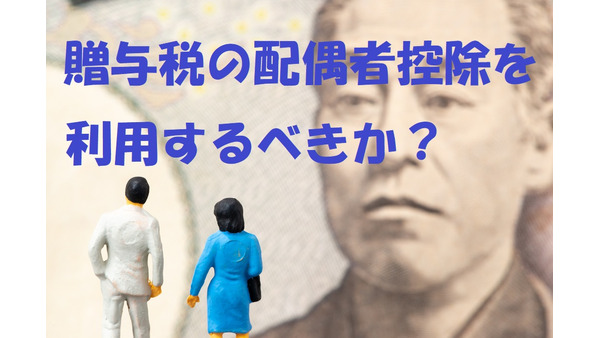
相続税の節税を考える際の鉄則は、 時間をかけて少しずつ多くの相続人に財産を承継すること です。 事前にできる対策として、贈与税の基礎控除の範囲内で毎年、贈与を行うことで相続財産を減らしていくことが考えられますが、基礎控除

厚生年金保険では平成26年4月1日から法改正があり、出産前後の一定期間(産前・産後期間)の「厚生年金保険料」は免除されています。 少子化対策の一環で次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産を行った場合に、出

5月は年末年始やボーナス月と並んで、住宅ローンの延滞が多い月です。 GWでお金を使い過ぎたからと考えやすいですが、実はその後に待っている税金の支払いが影響しています。 今年はGWが最大10連休ということもあり、例年以上に

私達不動産鑑定士が土地と建物の評価をするときに賃借権が設定されている場合があります。 不動産鑑定評価上は賃借権は土地と建物全体に対して設定されていると考えるため、評価をする類型を「貸家及びその敷地」とし、あくまでの一体の

日本の公的年金制度 公的年金制度は2階建てと呼ばれて、国民年金と厚生年金で構成されています。 国民年金 原則20歳以上60歳未満の人は強制的に被保険者となります。 厳密には、被保険者の区分(第1号被保険者、第2号被保険者
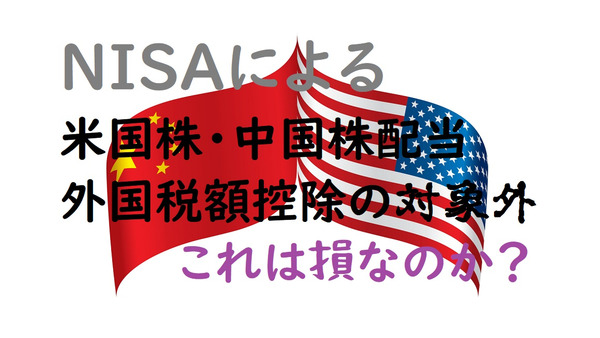
日本の投資家でも増えてきた米国株・中国株などの外国株取引ですが、10連休中に売却取引できる証券会社もあります。 税制を考えた場合には国をまたいだ取引となるため、国内で完結して所得を得るのと異なる扱いになります。 株式投資

配偶者控除等の改正により、103万円の壁(税制上の扶養の壁)はなくなりましたが、パート収入が130万円を超えると健康保険の扶養から外れてしまうという「130万円の壁」は残っています。 この時期、パートで働き始める方などか

老齢年金に関しては、政府は繰下げ受給を推奨しており、さらに70歳まで可能な現行制度を75歳までに引き上げる方向です。 一方で、年金「211万円の壁」を生かすために繰上げ受給という策もあります。 【関連記事】:社会保障にも

70歳以上の人も厚生年金の被保険者となる可能性が出てきました。 4月15日から各紙が伝えています。 厚生労働省は、現在のところ70歳未満と定められている厚生年金への加入義務を70歳以降にも延長する方向で検討に入ったとのこ
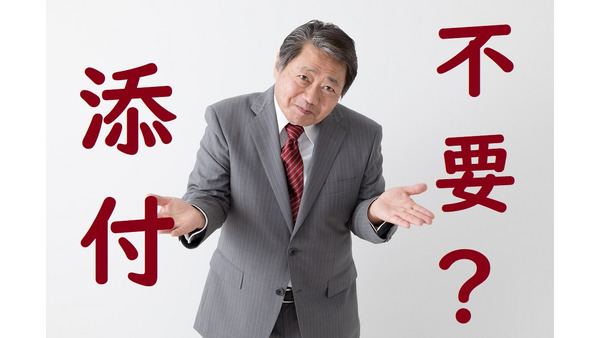
マイナンバー制度については番号管理の危険性が以前より指摘されていましたが、一方で行政手続きが簡略化されるという、国民にとってのメリットも言われています。 簡略化は徐々にですが進んでおり、確定申告書の提出においても、ついに

香典辞退の申し出が… 先日、親類から「香典辞退しようと思う」との相談を受けました。 辞退するかどうかは、故人の遺志かご遺族の思いで決める事なので当方がとやかく言えるものでないです。 当方は、両親が亡くなった際、香典をいた

Q:「国税庁は長期平準定期保険など節税色が濃い保険の取扱いを見直すため、パブリックコメントで意見を聴取するとのことですが、これはどういうことでしょうか? また、今、公表されている改正案はどのようなものでしょうか」 解説