※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています
注目記事※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています
注目記事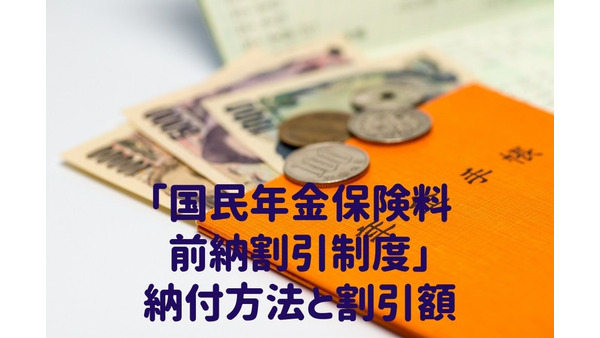
自営業者や学生などの国民年金「第1号被保険者」は、毎月国民年金の保険料を自分で支払わなければなりません。 また、国民年金保険料は、納付対象月の翌月末日と定められている納付期限までに納める必要があります。 このように、保険

年金に関する用語や手続きなどで疑問が生じた際は、まずは日本年金機構のウェブサイトを見た方が良いのです。 また国民年金に関する疑問については、住所地の市区町村のウェブサイトでも良いと思います。 これらの上乗せを支給するため
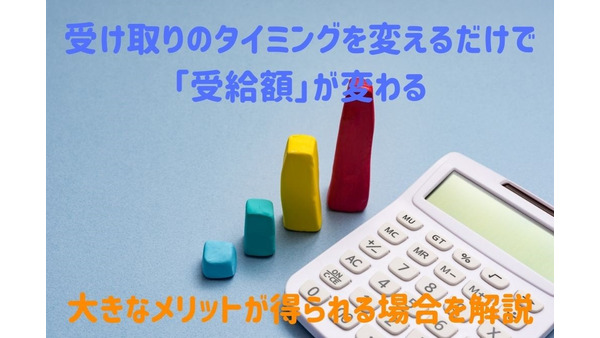
何歳からが「老後」なのか、人それぞれ考えがあるでしょう。 高年齢者雇用安定法によって雇用が確保されている年齢が65歳、公的年金の受け取りが始まる年齢も65歳です。 このように「収入源が切り替わる65歳」を、ひとつのボーダ
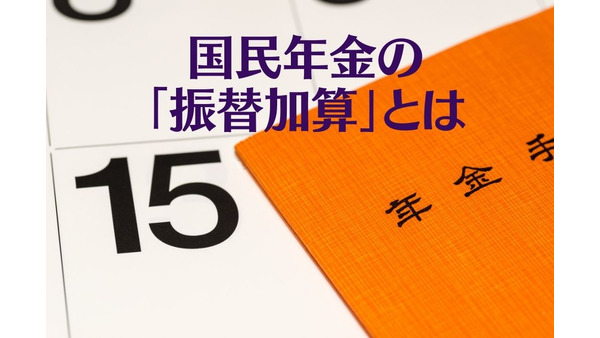
国民年金から支給される年金の1つに「振替加算」という制度があるのをご存じでしょうか。 この制度は将来的には対象者がいなくなってしまうのですが、当分の間は続く制度です。今いち度確認していきましょう。 「振替加算」とは 国民

障害基礎年金で2級相当に該当しないと判断された場合や、障害厚生年金で3級相当に該当しないと判断された場合などは、不支給決定書が届きます。 このようなケースで本当は障害基礎年金の2級や障害厚生年金の3級に該当していると思っ

ねんきん定期便などで度々目にする合算対象期間とは老後の年金生活においてどのような影響を及ぼすものなのでしょうか。 今回は合算対象期間(書籍などではカラ期間と表示されることもあり)について解説してまいります。 合算対象期間

厚生労働省の発表によると、2021年度(2021年4月~2022年3月)に支給される年金は、前年度より0.1%減額するそうです。 20歳から60歳までの40年間、国民年金の保険料(厚生年金保険の保険料の一部は、国民年金の

「人生100年」「老後の生活資金は夫婦で4,000万円」などと言われるものの、「預金してもお金は増えないし年金受給額も減る一方で老後が不安」それが今の時代です。 ここでは老後資金を貯えるための目安として、「入ってくるお金

学生であっても日本国内に在住する場合、国民年金は20歳から強制加入です。 しかし、大学生活中にアルバイトをしている場合であっても毎月の国民年金保険料を納めるのは容易ではありません。 また時代のトレンドであるリカレント教育
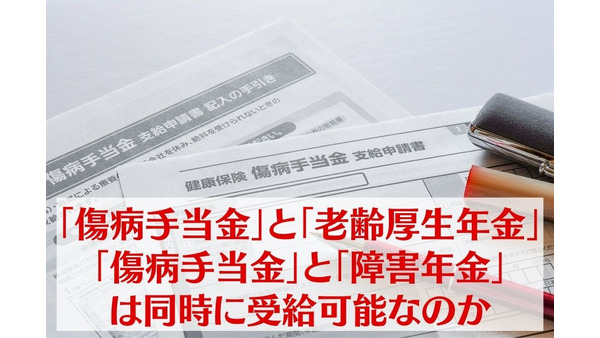
健康保険法では、業務外の疾病または負傷により労務不能となり一定以上収入が減少した場合に「傷病手当金」が支給されることになっています。 一般的には年齢を重ねるごとに病気等のリスクはあがり、若年層よりも「傷病手当金」の受給可
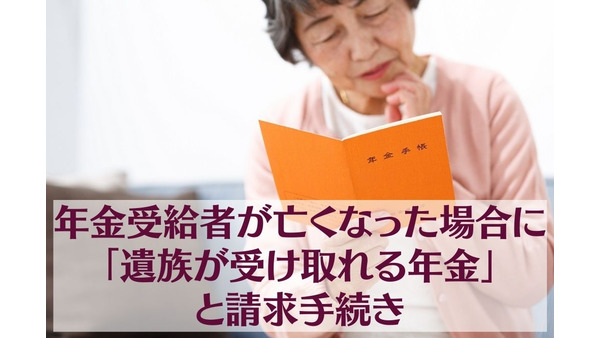
公的年金を受給中の方が亡くなった場合には、年金を受給する権利は当然ですがなくなってしまいます。 しかし、まだ受け取っていない分の年金などは遺族の方が受けとることはできるのか、該当の遺族の方はどのような年金を受給することが

日本国内に居住している20歳以上60歳未満で厚生年金保険に加入していない方は、国民年金に加入する義務があります。 国民年金に加入するということは、国民年金保険料を納付しなければなりません。 しかし、20歳以上であっても大
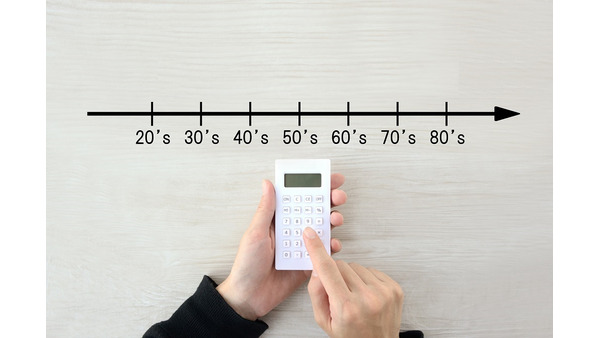
70歳までの就業確保努力義務を始め高齢期の就労拡大がクローズアップされています。 また、年金の分野では2022年4月1日からは繰り下げの上限が75歳まで拡大されます。 繰り上げ請求の上限年齢である60歳を起点とすると受け

働いている女性が会社を辞めるタイミングには、結婚や出産が考えられます。 昔と違って今は、ほとんどの会社で結婚後や出産後にも仕事を続けられる環境が整っていることでしょう。 しかし、今も結婚や出産を機に辞める風潮になっている
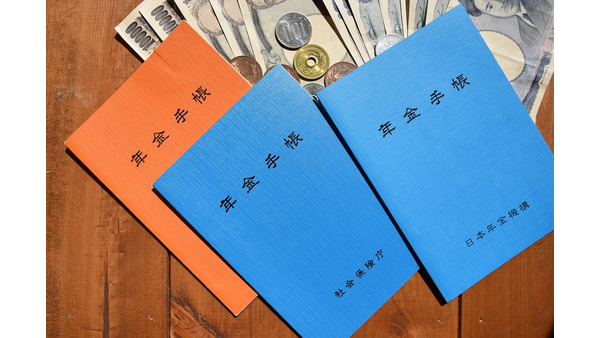
国民年金は、基礎年金として20歳以上60歳未満で日本国内に住所のある人はすべて加入することが求められ、老齢基礎年金として65歳から受給が始まります。 老後に受け取る公的年金には、老齢基礎年金のほかサラリーマや公務員などの

公的年金には、 ・ 老齢になって受給できる「老齢基礎年金」や「老齢厚生年金」=「老齢年金」 ・ 障害を負った場合に受給できる「障害基礎年金」「障害厚生年金」=「障害年金」 ・ 被保険者が死亡した場合に遺族が受給できる「遺
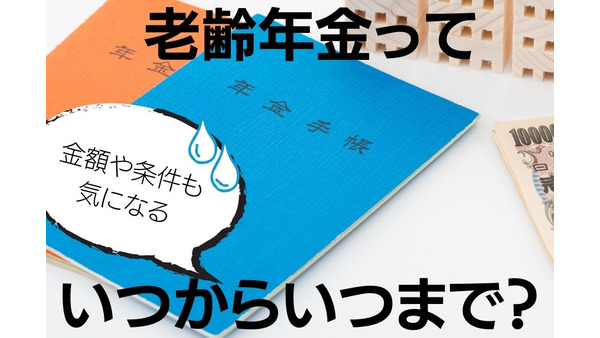
老後の生活を考えると、公的の老齢年金がいつからいつまで受給できるのかは非常に気になると思います。 老齢年金の基本的な部分なので、しっかり押さえておきたいところです。 本記事では、主に以下のことについて解説します。 ・ 老

晩婚化の時代であると同時に熟年離婚というキーワードも珍しくなくなってきました。 一定期間以上の婚姻期間を経て離婚する場合にはその家計の働き方によっては格差が生まれてしまうことがあります。 例えば夫のみが厚生年金の適用事業

社会保険料の中で健康保険料と厚生年金保険料は、一年間同じ給与の額で計算されています。 毎月給与の額は変わるのにおかしいと思ったことはありませんか? 社会保険料の計算は会社が標準報酬月額を使って毎月給与から天引きしています
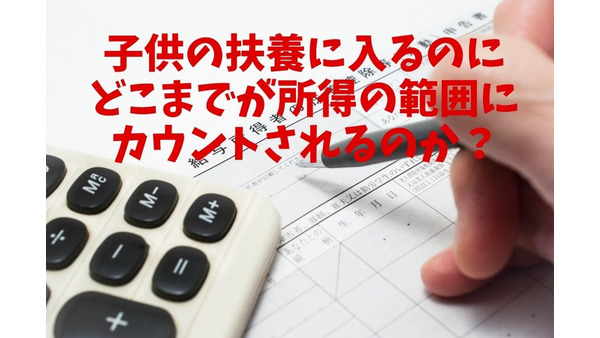
今回は、以前に読者の方からいただいた質問に答える形で、扶養の範囲について解説していきます。 「娘の扶養に入りたい」どこまでが所得で扶養範囲はどのくらいなのか 【質問内容】 私は50代女性です(A子さん)。昨年(令和元年)

夫婦であることが前提の遺族年金と夫婦ではなくなったことが前提の離婚時年金分割では前提となる条件、支給開始時期、支給額は全く異なります。 今回は相反する2つの制度を並列的に確認していきましょう。 また、子供にも支給可能性が

公的年金の中には、病気やケガなどが原因により生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代も含めて受け取ることができる障害年金という制度があります。 障害年金には障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があり、それぞれ
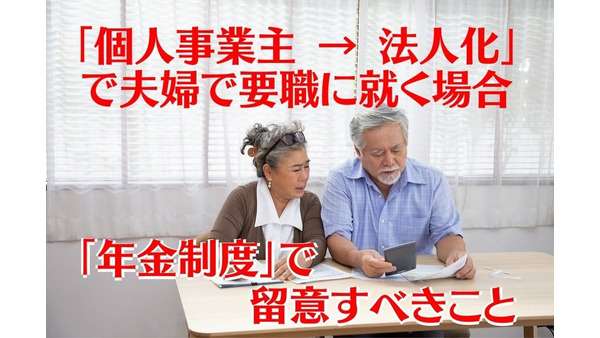
昨今、働き方が多様化して必ずしも企業に雇用されて働くことのみではなくなってきました。 フリーランスを始めとして、派遣、マルチジョブホルダー、起業など多くの働き方が存在します。 たとえば、個人事業主から数年後に法人化して事
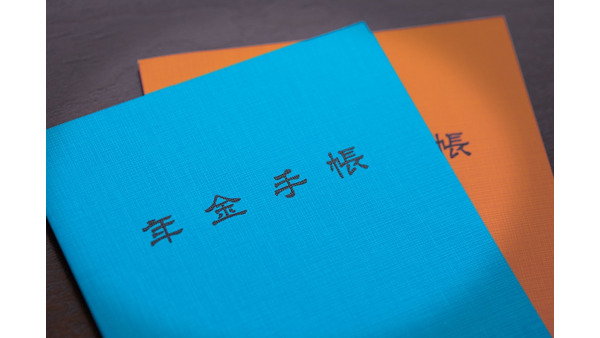
扶養外の共働きの夫婦がそれぞれ加入する年金は、厚生年金保険です。 また、自営業の人が加入する年金は、国民年金です。 では、専業主婦や主夫は、どの年金に加入するのでしょうか? 日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満のすべ

公的年金に加入して保険料を納付した期間や、国民年金の保険料の納付を免除された期間などを合わせて、原則10年に達していると、受給資格期間を満たすため、年金の受給権が発生します。 そのため原則65歳になると、2020年度額で

離婚をしたら年金はどうなってしまうのか、心配に思われている方もいるかもしれません。 そういう方のために年金には、分割制度があります。 ただ、単純に配偶者の年金額を半分もらえるという制度ではなく、少し複雑な仕組みになってい
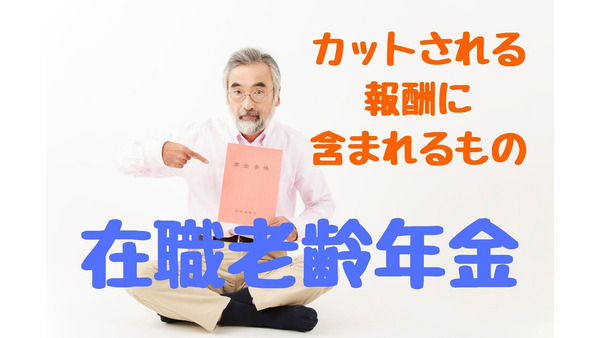
70歳までの継続雇用努力義務化など長く働くことが前提の社会が到来しています。 また、エッセンシャルワーカーを除き、対面一択での働き方よりも対面とリモートをハイブリッドに使いこなした働き方が一般化しつつあります。 数年前は
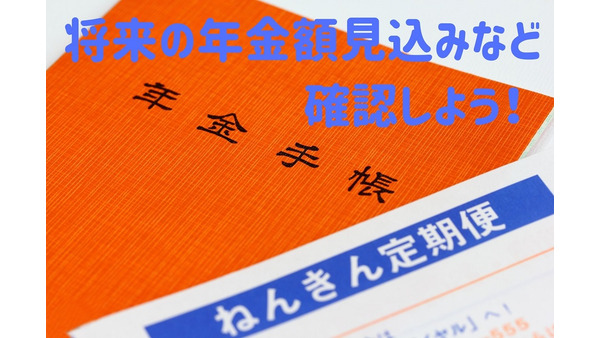
ねんきん定期便という名前は、ほとんどの人が聞いたことがあり、毎年1回送られてくるために、1度は目にした人も多いと思われます。 なんだかよくわからないので、中身をきちんと確認しないで捨ててしまう人も一定の人数いるのも事実で

現在は夫婦共働き世帯が多くを占めるようになってきましたが、当然のことながらいずれか一方のみが働く世帯もあります。 たとえば、妻が早期退職して専業主婦となるものの、夫は定年後も再雇用職員として65歳以降も働くという場合です
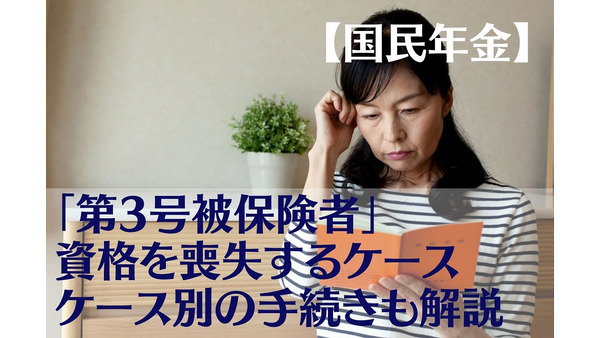
国民年金の「第3号被保険者」とは、第2号被保険者に扶養されている年収が130万円未満の20歳以上60歳未満の配偶者のことを言います。 「第3号被保険者」の国民年金保険料は、配偶者が加入している年金制度が一括して負担してい

あまり聞きなれませんが、国民年金から支給される年金に「寡婦年金」という年金があります。 年金制度の中で唯一「婚姻期間」が支給要件に含まれている珍しい年金です。 また、遺された妻が60歳から65歳に達するまでの間の「期間限

厚生年金から支給される「遺族厚生年金」には「短期要件」と「長期要件」という2つの支給要件があります。 今回は「遺族厚生年金」を請求するにあたり、「どちらの要件で申請すべきか」と「それに付随する一時金の受給の可能性」につい
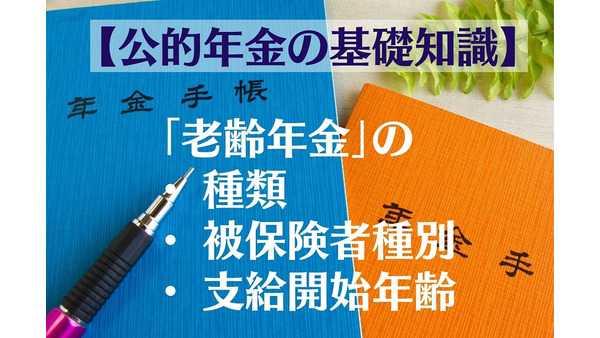
年金をいつからもらえるのかは、皆さんの関心の高いところでしょう。 「公的年金」は、生年月日や性別によって受給できる年齢が変わってくるので、しっかりと押さえておく必要があります。 本記事では、年金の受給開始年齢や2階建て年
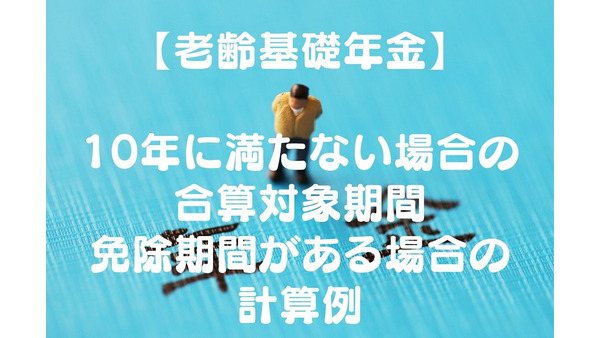
自営業者・会社員・公務員などの区分に関わらず、条件を満たせば受給できる公的年金が「老齢基礎年金」です。 「老齢基礎年金」の満額は約78万円で、定年後のゆとりあるセカンドライフを送るのに欠かせない資金だと言えます。 本記事
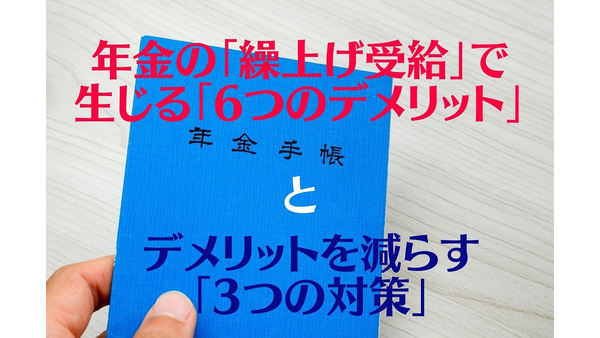
公的年金(国民年金、厚生年金保険)の支給 公的年金(国民年金、厚生年金保険)の保険料の納付済期間や国民年金の保険料の免除期間などを合算した期間が、原則として10年に達している場合には「国民年金」から「老齢基礎年金」が支給
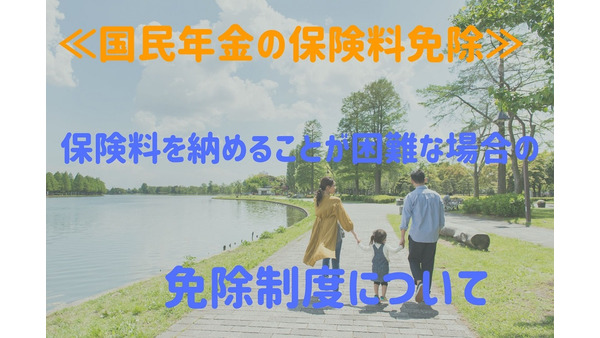
国民年金には、失業や病気などで収入が減少して保険料を納めることが困難な場合に、保険料の納付が免除される制度があります。 ただし、申請しないと制度を利用できない場合もあるので、免除制度や種類について詳しく解説します。 やむ