※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています
注目記事※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています
注目記事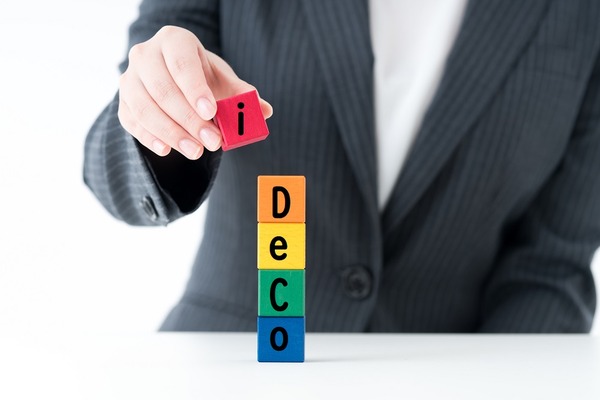
税制面で優遇されている「iDeCo」 2017年1月から公的年金の加入者であれば、国民年金の保険料の免除者などの一部の方を除いて、個人型の確定拠出年金(以下では愛称の「iDeCo」で記述)に、誰でも加入できるようになりま

勤務先に副業がバレるルートとして、職場に送られてくる住民税の決定通知書の存在が有名です。 給与の所得のみならず、給与以外の所得情報が記載されるからです。 住民税決定通知書における給与所得(赤枠)と給与以外の所得(青枠)の
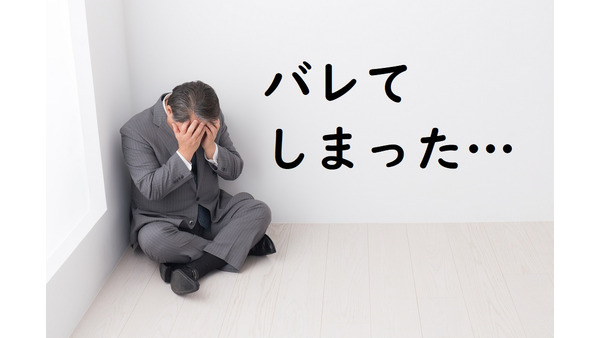
1,000万円貰えるかも? 父が亡くなり、四十九日法要も終え帰ろうとした時のことです。 兄の真一さんが弟の博さんを呼び止め、遺産分割のことを話しておきたいという。 父の相続人は、兄と弟の二人。 兄・真一さんの分割案は…

ご夫婦で同じ銀行に預けてませんか? ご主人が給与の受け取り等で銀行に口座を保有しているケースで、奥さまも同じ銀行に口座を持たれているケースがあります。 奥さまとしては、へそくりだったり、生活資金だったり、または子供の学費
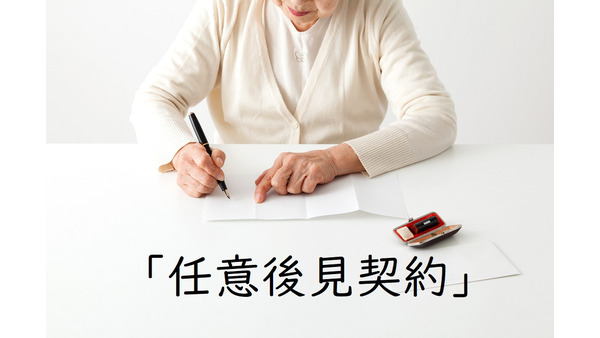
子供たちが独立した後、1人暮らしとなる人は増えてきています。 身内が遠方に住んでいて近くに頼る人がいない場合、将来に不安を感じる人もいるのではないでしょうか。 いつ自分が介護の必要な状態になるとも限らない状況で、最も心配

もうすぐ、うだるような暑さの夏がやって来ます。 「夏バテにならないように、がっつり肉料理を食べてスタミナをつけたい」という方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。 そういったニーズにピッタリなのが、昨年から話題のステー

やりましたか?「仮想通貨」の確定申告 今年3月の確定申告でもっとも注目を集めたのが「仮想通貨の確定申告」。 先日25日、国税庁が仮想通貨関連の確定申告の結果を発表しました。 それによると、仮想通貨による収入が1億円を超え

6月は住民税の切り替わりの時期 勤務先や個人のお手元に住民税の納付書が届いているはずです。 ざっと金額を見て 「あれ…なんで増えているの?」 と感じた人もいるかもしれません。 住民税が増える原因は所得税と同じ その増税感

先日新聞を読んでいたら、2018年5月25日の衆議員法務委員会において、「成人年齢を18歳に引き下げする民法改正案が可決された」という記事が掲載されておりました。 この後は、同月内にも衆議員本会議で可決され、参議院に送付

ふるさと納税は、返礼品の魅力で普及してきました。 しかし加熱する返礼品競争に規制がかかってきており、ふるさと納税ポータルサイトも新たな方向性を発掘しました。 「ふるさとチョイス」のようなポータルサイトも発掘する新たなふる

相続税が増税になった今でも、「死んだ後の話をするのは縁起が悪い」としてなかなか向き合おうとしません。 しかし、それでも事前に対策を取っておいたほうがよいものもあります。 特に、死後必要となるお墓や仏壇などは、被相続人候補
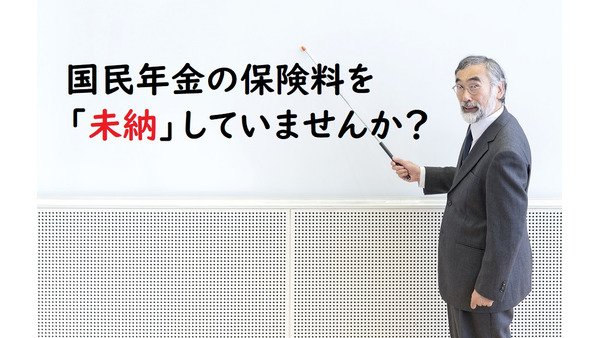
収入が少なく、国民年金の保険料を納めていては生活が困難な方もいらっしゃると思います。 国民年金の保険料を「未納」にしていませんか。 「未納」ではなく、国民年金の保険料の「免除」というものがありますので、ぜひ活用しましょう

実質2,000円の負担で、様々な返礼品を受け取ることができるふるさと納税。 家計の節約になるだけでなく、地域の美味しい食材が食べられるメリットがあります。 我が家でもふるさと納税を積極的に利用しているのですが、とくにおす
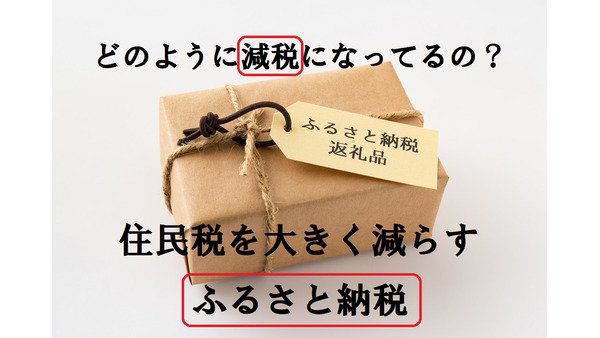
所得税・住民税減税としてポピュラーになったふるさと納税ですが、確定申告やワンストップ特例申請の手続き段階では、いまいち実感がわかないのも実情です。 住民税の減税額が大きく、住民税は自治体が計算するところに原因があります。
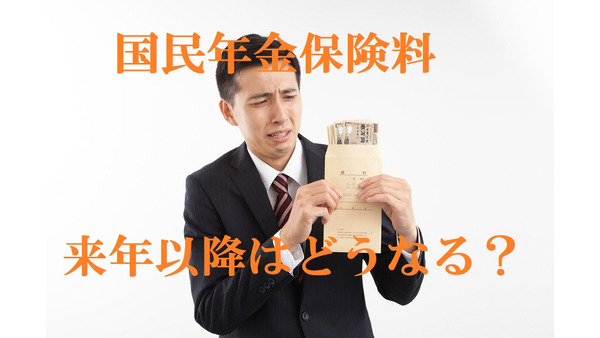
国民年金などの公的年金は原則として、現役世代が納付した保険料を、その時点の年金受給者に年金として分配する、「賦課方式」という仕組みで運営されております。 例えるなら、現役世代の子供が、高齢になった親に対して、生活費などの
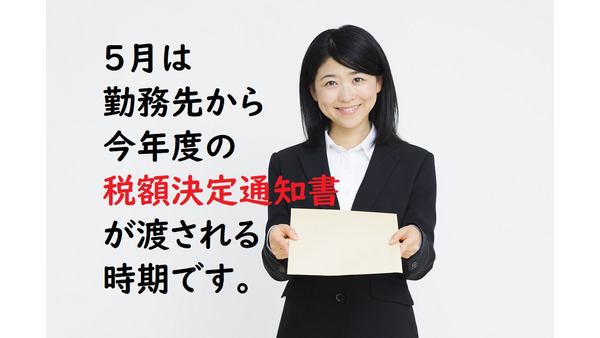
サラリーマンにとっては、給与から徴収される住民税は還付されるわけでもなく、払っている感覚が薄いかもしれませんが、5月は勤務先から今年度の税額決定通知書が渡される時期です。 わかりにくいところですが、扶養やふるさと納税など
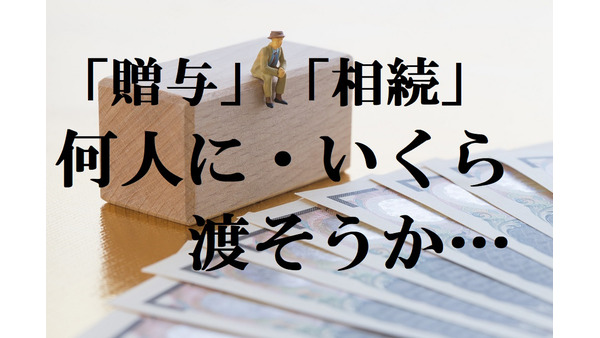
贈与・相続の仕方によって、税額は変化します いくつかのパターンを見てみましょう。 被相続人であるAさんには3億円の財産があり、法定相続人は、 ・ 妻 ・ 長男 ・ 次男 で、それぞれの子に2人ずつ子(Aさんの孫)がいると

今年1月から、合計所得1,000万円以上の納税者は配偶者控除を受けられなくなりました。 この税制改正を悲観的に受け止める人が多いのですが、会社経営をしている社長にとっては節税のチャンスです。 妻を役員にして報酬を抑えれば

「結婚したら専業主婦になりたい」 「子供との毎日を大事にして家事や趣味を楽しみたい」 このように考える女性は少なくありません。 特に、就職氷河期などで苦労してきた人ほど「結婚してラクになりたい」願望が強いものです。 ただ

「教育資金の一括贈与の非課税制度」とは 教育費に充てる目的で、多額の資金を孫らに贈与する際に非課税となる制度があります。 この制度を教育資金の一括贈与の非課税制度といいますが、これを使って、非課税で贈与できるのは、201

「扶養」に関しての質問 「夫の扶養を外れて、子どもの扶養に入ることはできますか?」 この春、お子さんが就職されたAさんからこんなご質問を受けました。 お子さんと生計を一にしていれば、子の扶養に入ることは可能です 「配偶者

子育て世帯の家計相談において、「教育資金の一括贈与制度」についてお伝えすることがあります。 この制度は、平成25年度税制改正において導入された「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」に基づいて創設されました。 教育資
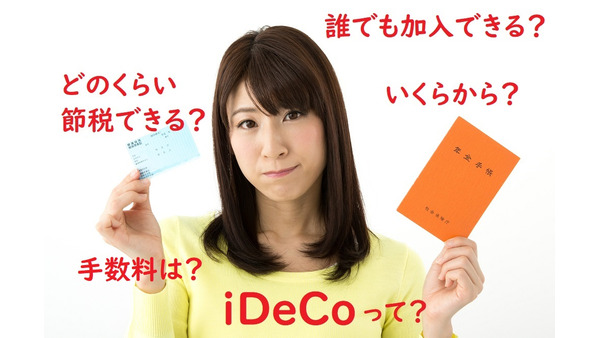
個人型確定拠出年金(iDeCo)とは、簡単に言うと「年金を自分で作る」ための制度です。 この制度への加入は任意で、自分で申し込み、自分で掛金を支払い、自分で運用方法を選んで、掛金とその運用益の合計金額を元に年金の給付を受

インターネットが生活のインフラとなった今、ネット上の銀行口座や証券、仮想通貨などといった「デジタル資産」は当たり前のものとなりました。 紙や通帳のような実体がなく、すべてデジタルで完結するため、 「言わなければ、自分以外
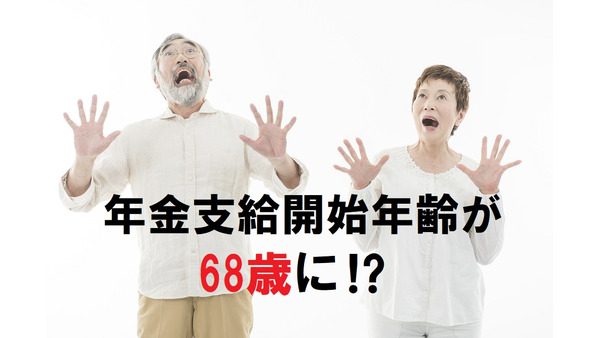
財務省は2018年4月11日に、厚生年金保険から支給される老齢厚生年金の支給開始年齢を、原則65歳から68歳に引上げする案を、財務大臣の諮問機関である財政制度等審議会の財政制度分科会に提示しました。 今のところはこの財政

4月になり、進学や転勤などに伴い、マイホームの購入を検討する人もいるかもしれません。 しかし昇給や手取りの増加はなかなか増えない昨今、住宅ローンをすべて自弁するのは難しいもの。 ここで検討材料に上がりやすいのが 「住宅取

子供が家を持っていなければ、相続税がゼロになる? 「家なき子」だと、相続税が安くなる。 こんな話を聞いたことありませんか? これは相続税の課税価格を計算する際、故人の居住用の土地(上限330平方メートル)があり、適用要件

毎月もらう給与明細の内容はご存じですか? 「給料なかなか増えないな」、「今月は残業が多い」など入るほうはよく見るかもしれません。 しかし、控除される項目については「何かよくわからないけど引かれている」という方も多いのでは

春は出会いと別れの季節、卒業と入社の季節ですね。 長い長い学生生活に別れを告げた新社会人のみなさまも、やっと初任給を受け取る時期でしょうか。 これまで悲喜こもごもありながらも子育てを続けてこられたお父様お母様、初めてまと

高齢者も働く生涯現役社会となり、働く一つの手段としてシルバー人材センターの会員となり業務を引き受ける方法があります。 会員は発注者の事業所に派遣されますが、収入はシルバー人材センターからの配分金という形になります。 配分

平成30年に入り、税制改正で見直された配偶者控除や配偶者特別控除が適用になります。 この改正では「103万の壁」がなくなり、所得上限が150万円に増額され、働く人を増やすことが狙いです。 実際に私たちの生活にどのような影

退職、脱サラ、その前に… 脱サラ等で退職を考えている人の中には、多少具合の悪いところがあっても「退職してからゆっくりお医者さんに行けばいいや」と思っている人もいるかもしれません。 しかし、病気は「早期発見・早期治療」が基

日本年金機構の委託業者が、年金データ入力を(契約に反して)国外業者に再委託していた問題が原因で、自治体とのマイナンバー連携が再延期となりました。 1度目は、平成28年に起きた個人情報漏洩により、管理体制が問われたことから

実は、「寄付金控除」を利用したもの 豪華な返礼品が話題になり、すっかり認知度が上がった「ふるさと納税」。 とはいっても、実際に利用したことがある人は10%程度というデータもあり、取り入れるにはハードルの高さが伺えます。

5月の大きな出費 4月の新生活も慣れた頃、 GWは何をしようかな? と計画を立てる時期ですが、5月は「自動車税」の納税が… 冬のボーナスから数か月、夏のボーナスはまだ先。 GWや自動車税のような大きな出費はこの時期に厳し
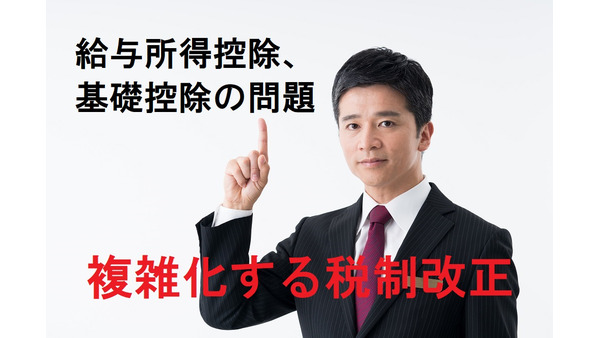
平成30年度税制改正大綱は2017年(平成29年)12月には作成され大々的に報道されましたが、正式に税制改正法が成立したのは、2018年(平成30年)3月下旬です(毎年、正式に決定するのはこの時期です)。 なお一時期「出