※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています
注目記事※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています
注目記事
文房具などの備品から交際費、出張旅費にいたるまで、会社の経費を自分の財布から立替払いをした経験は誰にでもあることと思います。 中には、クレジットカードやポイントカードを賢く使ってポイントがたまるように工夫している人もいる
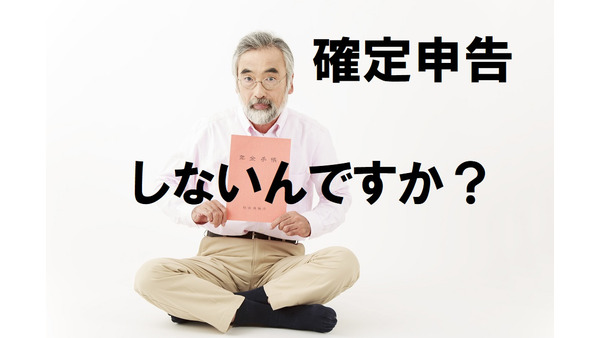
公的年金等(例えば老齢基礎年金や老齢厚生年金など)は、雑所得に該当するため、所得税が課税されますが、その計算方法を大まかに表現すると次のようになります。 (1) 1月~12月の間に支給された公的年金等収入の合計額 - 公

平成29年より始まるセルフメディケーション税制を活用すべく、対象市販薬を購入し領収書を集めてきた方もいらっしゃるでしょうが、いよいよ確定申告の時期です。 平成29年分確定申告に関しては、平成30年1月4日より国税庁の確定

最近立て続けに質問を受けたので、この話を共有したいと思います。 「いくらまで働いていいんですか? 〇〇の壁っていろいろあるみたいですがわかりません。 わかりやすい言葉で教えてください。」 聞きなれない言葉が多いです。 被

平成21年の改正で、上場株の配当所得も上場株式の売買による損失と相殺できるようになりました。通常相殺できる損失があれば、相殺するのが得だという判断になりがちです。 しかし上場株配当の申告にあたっては、損失と相殺する形の申

「寄附金控除と言えば『ふるさと納税』」というイメージを多くの方はお持ちのことと思います。 しかし、中には日本赤十字社などの公益財団法人などに寄附する人もいます。この場合の控除額の計算はどうなっているのでしょうか。 所得税

配偶者に居住権 民法改正案として「配偶者に居住権」ということが、先日新聞に大きく図解とともに載っていました。 この改正案が実際の相続にどう影響するのか検証してみました。 改正の趣旨 「高齢の配偶者の住む場所と生活資金の安

「セルフメディケーション税制」 平成29年より医療費控除の特例として「セルフメディケーション税制」が導入されました。 これにより、薬局などで購入した対象医薬品が1万2,000円を超える場合も、通常の医療費控除との選択によ
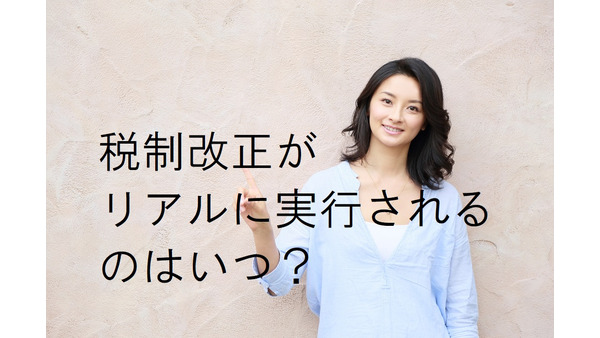
2017年度に引き続き2018年度においても、一般人にとても身近な所得税の税制改正が行われました。 たくさん稼ぐ人にとっては厳しい内容となりましたが、毎日の生活費に悩む低所得者にとっては助かる内容となっています。 ここで
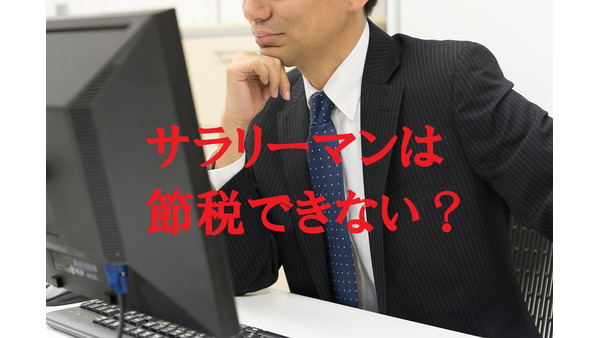
「サラリーマンは節税できない」なんて思っていませんか? これ以上何を節税しろって言うの? これ以上生活を切り詰めるのは無理… こんな時代だからお金を使わないなんてありえない といったお話を聞く機会が多いです。あなたはいか

新年を迎え、ほっとしたのもつかの間…。 年末年始の出費が家計にのしかかり、「節約しなきゃ!」と身が引き締まる時期でもありますよね。 我が家でも、年末年始のお酒代がかさみ、毎日パパの晩酌代がいつもより増してつらく感じていま
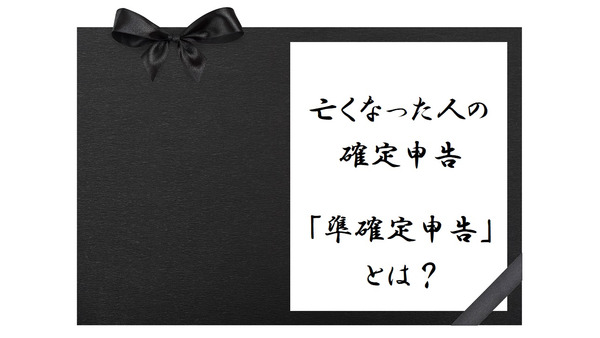
確定申告で忙しくなる年明けですが、確定申告が必要なのは生きている人間だけではありません。 実は、亡くなった人にも確定申告が必要なのです。 どのような場合に必要なのでしょうか。 また、どのように確定申告を行えばよいのでしょ

Q:「12 月22 日に平成30 年税制改正大綱が発表されました。この中で、個人所得税に関する改正のポイントはなんでしょうか?」 解説 給与所得控除や公的年金等控除、基礎控除について見直しが行われています。いずれも平成3

最近は実費補償型の医療保険がCMでよく流れていますが、5年毎の期間を区切って契約更新する更新型の定期医療保険になります。 一方で一生涯保障するタイプの終身医療保険がありますが、平成23年以前から契約しているものですと、更

年末調整で「扶養控除等申告書」にパート主婦(夫)の方やお子さんなどの扶養家族を記入しますが、年が明け扶養家族の方が所得計算した場合に扶養の範囲を超えているケースは問題です。 この場合は会社側が対応することができますし、万
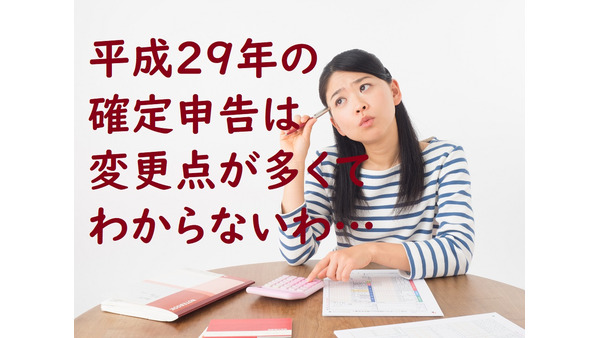
毎年恒例ですが…確定申告とは? 確定申告の手続きの流れ。 1. 前年1月から12月までの総収入から社会保険料などを引いて所得を計算 2. 所得に税率をかけて所得税を計算 3. 納める予定の税金などがある場合には税金の支払

住宅ローン控除を受けて所得税が全額還付になっている皆様、ひょっとすると勘違いされていらっしゃるかもしれません。 今回は確定申告を目前に控えて、あらためて住宅ローン控除とその他の所得控除の関係について、給与所得者の方を前提

「経費」の概念 年末に、経団連が副業・兼業の容認へ方向転換という話題が出ました。 サラリーマンはもちろん、フリーランスや、専業主婦の方にとって、副業を行うことは税制面での優遇があります。 その一番大きなものと言えるのが「

来月はいよいよバレンタインデー! 彼や気になるアノ人への本命チョコや、職場、友人への義理チョコなど、チョコレートを用意する時期が近づきました。 ふるさと納税でもらえるチョコレートの返礼品があるのをご存じでしょうか。 今年

大切な人との別れとなるお葬式は、できるだけ盛大に行いたいもの。 しかし、盛大に行うとそれだけ費用がかかり、残された人にとっては大きな負担です。 先立つかもしれない人も、「残される人に金銭的負担をかけたくない」という気持ち

サラリーマンであれば12月もしくは1月に年末調整が終わると給与所得の源泉徴収票をもらいます。 これをもって確定申告……と考えている方も多いと思いますが、想定したような還付額が得られず手間だけがかかってしまうようなこともあ

「公的年金」とは 高齢や障害などで働けなくなった人たちや、大黒柱を失って生活に困っている人たちを、現役世代が払う保険料と税金で支える制度です。 「年金はあてにしていない」と言う現役世代の中にも、実は、すでにあてにして生き
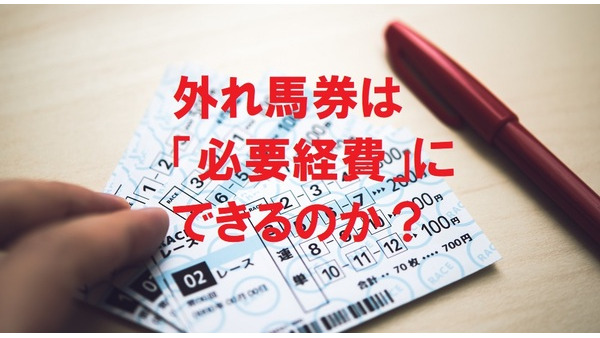
平成29年の年末、外れ馬券の必要経費算入を巡って2つの異なる最高裁判決が出ています。 一方は認められ、もう一方は認めないというもの。 「どういうこと?」と首をかしげた方もいらっしゃると思います。 この判決を理解し、そして
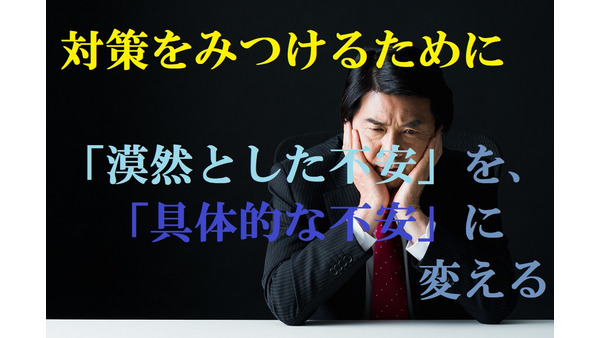
年金の支給開始年齢の引き上げを考える 2017年も終わりに近づいたので、今年話題になったニュースを振り返ってみると、個人的には「年金の支給開始年齢の引き上げ」に関連したニュースが、もっとも印象に残っております。 その発端

基本的には家族の間でも贈与税がかかる 基本的に、個人から個人へのお金のやり取りは、年間110万円を超える金額になると贈与税が課されます。 しかし、扶養義務のある人が提供する生活費と教育費において 「通常必要とみなされるも

Q:「12 月22 日に平成30 年税制改正大綱が発表されました。この中で、法人税に関する改正のポイントはなんでしょうか?」 解説 賃上げ・生産性向上のための税制改正が行われました。また、平成30 年で期限が切れる租税特

セルフメディケーション税制 2017年(平成29年)1月1日からスタートした「セルフメディケーション税制」は、セルフメディケーションの推進を目的としています。 WHO において 「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の

年末になり、芸能人の離婚のニュースがたびたび流れるようになりました。 ここで地味に気になるのが財産分与。芸能人の方だとそれなりの資産が対象になりそうな気がします。 一般人の我々も含め、離婚の際の財産分与について、税金はど
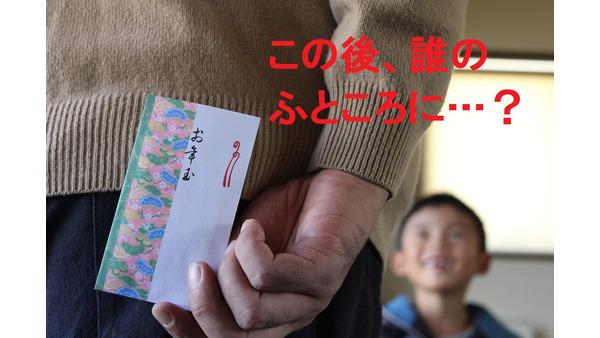
もらってうれしい「お年玉」は誰のふところに? クリスマスにお正月、年末年始はプレゼントやお年玉をもらえるとあって子どもたちはウキウキする季節ですね。 大人はというと、年末年始は忘年会や新年会、お歳暮や年賀状などただでさえ
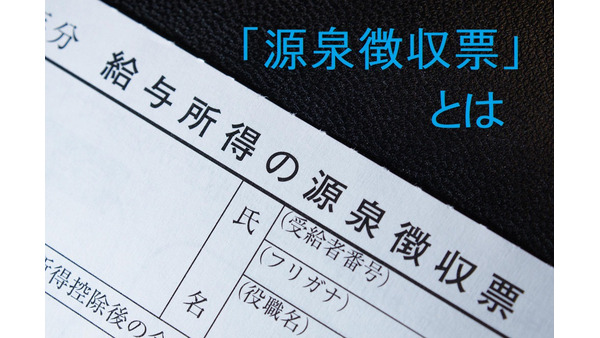
全ての会社ではないですが年末調整が終わる頃になり、源泉徴収票がもらえる時期になってきました。 確定申告の添付資料として、そして年収証明としても利用しますが、意味を理解しておくと節税にも役立ちます。(この部分に関しては確定

「遺族年金失権届」 夫の死亡によって受給権が発生した、遺族年金(遺族基礎年金、遺族厚生年金など)を受給している妻が、再婚(事実婚を含む)した時は、その遺族年金の受給権は消滅します。 また親の死亡によって受給権が発生した、

将来の退職金(老後資金)に対する不安をお持ちの方も多くおられると思います。 今年より加入対象が広がったiDeCo(イデコ)も退職金を積み立てるには素晴らしい制度です。 それ以外にも、あまり有名ではありませんが、小規模企業

よくある相談 父が亡くなると、銀行の口座が凍結されてしまい、電気、水道などの料金が引き落とされなくなると聞きました。どうしたらいいのだろう? 公共料金の引き落しが、父の通帳より行っている方からの相談です。 銀行口座が凍結
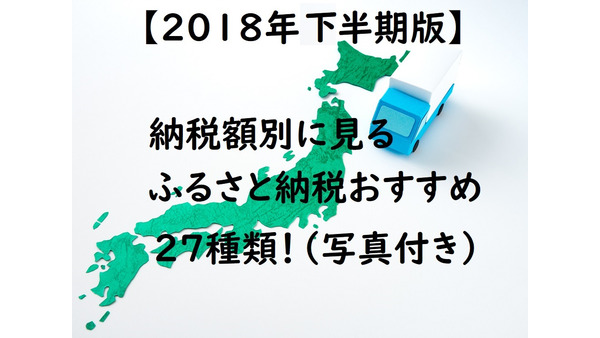
いよいよ12月に入り、2018年も残すところあとわずかとなりました。 年越しや新年の順位、仕事納めも迫る中、忙しい日々を過ごしている方も多いかと思いますが、ふるさと納税の駆け込みも終盤を迎えます。 来年からふるさと納税の

関心が高まる「相続税対策」 2015年に相続税が増税されて早2年が経過しようとしています。 少子高齢化と今後の増税が見込まれる今日、高齢世代だけでなく、現役世代も相続税対策を意識しています。 そんな中で関心を集めるのが「

ふるさと納税もいよいよ最終追い込みの時期になりましたね。 「さて、何の返礼品を受け取ろうか」 と考えたとき、寄付限度額がたっぷり残っている人は、なかなか選びきれないですよね。 また、駆け込み時期に急いで決めず、後からゆっ