※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています
注目記事※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています
注目記事
原則65歳から老齢基礎年金と、その上乗せとなる老齢厚生年金を受給するには、国民年金や厚生年金保険の保険料を納付した期間、保険料の納付の免除を受けた期間などを併せて、原則25年以上必要になります。 この原則25年は「受給資

近年、相次いで子や孫にまとまった資金を非課税で贈与できる制度が制定されてきました。 子や孫への生前贈与は、上手く利用すれば非常に有効な相続対策となります。今回は、その中でも2015年に制定された「結婚・子育て資金の非課税

Q:母が一人暮らしをしていた家を昨年相続しましたが、私は別の場所に自宅をもっていますので、この相続した家はずっと空き家になっています。今のうちに売却するとかなりの節税になると聞きましたが、これはどういうことでしょうか?

2017年1月から、専業主婦や公務員でも(個人型の)確定拠出年金に加入できるようになります。 また、すでに企業型の確定拠出年金に加入している会社員でも、会社が規約を定めるなどの条件を満たせば新たに個人型に加入できるように
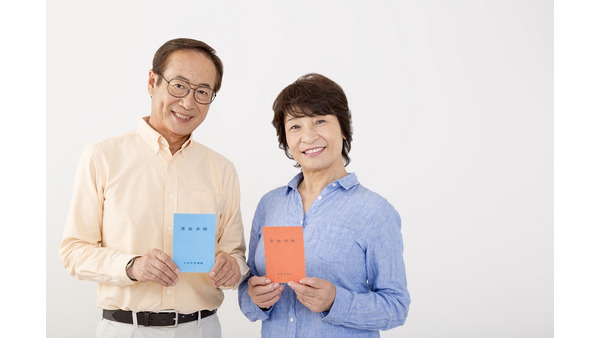
年金の繰り上げ受給について 本来は65歳から支給される老齢基礎年金を、60歳から65歳になるまでの希望する時期に、繰上げて受給することができます。 また昭和28年4月2日以降生まれの男性(昭和33年4月2日以降生まれの女

土地や家屋を所有している人は、その所在地の市町村(東京23区内の場合は東京都)に毎年固定資産税(都市計画税を含む)を納付しなければなりません。 送られてきた納付書に記載されている税額を何の疑いもなく納めている方が大半では

転職したい、独立したい、しばらくゆっくり休みたい……。 会社を退職することは、決して珍しいことではありません。それでも、会社を辞めるのは勇気がいることですよね。 ただ、退職してすぐに次の会社に入らない場合は、国民健康保険

2016年5月24日に確定拠出年金(DC)の改正法が成立しました。 少額投資非課税制度(NISA)に後れを取っている感のある確定拠出年金(DC)ですが、企業年金の普及・拡大、多様化する生き方・働き方に対応するため、現行の

先回のコラム「レシピ オブ 遺族年金」にて自営業世帯の遺族年金を確認しました。 今回はサラリーマン世帯の遺族年金の仕組み(レシピ)を見てみましょう。 ただサラリーマン世帯は、国民年金と厚生年金の2階建ての支給となりますの

生涯現役社会へ向けて 定年後も同じ会社に、嘱託社員として再雇用された3人の男性が、定年前と同じ仕事をしているのに、賃金が下げられてしまうのは、労働契約法に違反していると争った裁判の判決が、平成28年5月13日に東京地裁か

相続税対策が「相続から贈与へ」という流れに変わっている中、さまざまな生前贈与制度に注目が集まっております。 そのさまざまな生前贈与制度のなかの「暦年贈与」を活用したサービス(商品)である『暦年贈与信託』について今回はお話

高齢者のパソコン・インターネット利用率が年々上昇しており、本人が亡くなったときに、PCのハードディスクや各種記録メディア、金融取引で必要なログインパスワードの管理、さらにはクラウド上に残された「デジタル遺品」をめぐってト

住宅の取得に際し、両親や祖父母から資金の贈与を受けるということは珍しくありません。 人生の中で最も大きな買い物であり、資金計画を考える上で非常にありがたいものです。 この住宅取得のための資金の贈与については、贈与税の非課

個人型確定拠出年金について 給料から引かれる所得税・住民税がお得にできる制度についてお伝えしたいと思います。 今回、ご紹介するのは「個人確定拠出年金」についてです。 皆さんは「年金」というのは何となく理解している方は多い

不動産所得や事業所得がある人の多くは毎年確定申告をする必要があります。65万円の青色申告特別控除を受ける場合、複式簿記による帳簿書類の作成が必須となります。 そこで欠かせないのが会計ソフトですが、ここ数年でクラウド型の会

Q:被相続人の土地の上にある家屋に被相続人や親族などが住んでいた場合、小規模宅地等の特例の適用を受ける事が出来ると思いますが、毎月の家賃の受け取りがあった場合も適用されるのでしょうか? 解説 被相続人の宅地の上に住んでい

「自宅から遠い所に墓があって、思うように供養ができない」 「後継者がいない」 「子どもに迷惑をかけたくない」 等と言った理由で、実家の墓じまいをし、近くのお墓等に移す「改葬」を希望している方も増えているようです。 遺骨を

平成28年度税制改正により、「スイッチOTC薬控除制度」が創設されました。 これは、国が医療費を抑制するために、病院の処方箋はなく薬局などで医療薬を直接購入するのを後押しするために創設されました。 制度の概要 一定の取組

この時期は自動車税の支払い時期ですね。 自動車をお持ちの方はこれ以外に自動車保険、毎月のガソリン代、メンテンナンス代なども費用が掛かりますから、所有するだけでも結構な金額になりますね。 この金額がもったいないという事で、

パナマ文書によって、グローバル企業の租税回避に対する風当たりがいよいよ強くなってきていますね。 これについては、日本で企業活動を行っているグローバル企業がちゃんと日本に税金を落としていってくれているのかという点が、僕たち

安倍晋三首相が来年4月予定の消費税率10%への引き上げを2019年10月まで延期する方針を示しました。 現時点では延期が決定したわけではありませんが、このニュースを聞いたとき、正直ビックリしたというのが素直な印象です。

この時期、会社には2016年度の特別徴収税額の決定通知書が送付されてきます。 特に入社から2年経過した従業員の中には、給与明細を見て、住民税という項目から万単位のお金が控除されるため、手取り額が減り驚かれる方もいらっしゃ

国家公務員や地方公務員、または国民年金の第3号被保険者となり、自分で保険料を納付する必要のない専業主婦は、個人型の確定拠出年金の加入資格がありません。 その他に勤務している会社が、次のような企業年金を実施している厚生年金

年金記録問題のその後 「宙に浮いた年金」とか「消えた年金」と言われた年金記録問題ですが、この頃あまりその話題を聞かなくなりました。 身に覚えのある方からの申し出はもうほとんどなくなり、年金機構での取扱いも縮小されています

先回のコラム「誤解の多い遺族年金」にて老齢年金と遺族年金は全く別で、支給条件も支給額も異なる事を紹介しました。 では、遺族年金は一体、誰に、いくら、どんな仕組み(レシピ)になっているのかを見ていきましょう。 自営業世帯の

企業年金 会社によっては従業員の老後の生活を豊かにするため、福利厚生の一環として、企業年金を実施しております。 その企業年金には様々なものがありますが、多くの会社は次の3つのどれかを単独で、または組み合わせで、実施してい

「相続大増税」 「相続税は、お金持ちの問題だけではなくなった…」というのが、平成27年以降のお話ですが 「相続税をどの程度、納税しなけれらばならないのか分からず、冷や冷やしている…」 という相談が増えています。 中には、

(1) 相続税の還付についての関心が高まっている 平成27年より相続税法が改正され、基礎控除額の引下げにより相続税申告対象者が大幅に増加していると言われています。 これに関連して、「相続税の還付」の関心が高まっています。

「老後の生活は何も心配しなくていい」なんていう人は今の日本には少ないのではないでしょうか。 定年まで家のローンを支払いながら必死に働けば、定年後は年金によって生活を保障してもらえるはずなんだけど…と不安が残るのが日本の年

最近、独身のまま高齢になって亡くなる方が増えている。 結婚しない男女、しても離婚してしまう男女が増えていたり、少子高齢化が加速していることから、いずれこんな時代が来ることは分かっていたことではある。 しかし、納得して独身

マイカーユーザーにとって、5月は憂鬱な時期かもしれません。そう、自動車税の納付時期なのです。 納税は国民の義務ですので致し方ありませんが、どうせならば少しでもお得に納付したいですよね。 そこで注目なのが、「Yahoo!公

この4月(平成28年4月)から、一人住まいの親が亡くなって相続人が空き家になった実家を売却したとき、一定の要件を満たした場合に適用できる優遇税制 「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」(以下、空き家特例) が施行されて

熊本や大分で発生した地震の影響により、平成29年4月から予定されていた消費税率の10%への引上げが再延期、あるいは凍結される可能性が出てきました。 果たしてどのような結論が出るのでしょうか。 今回は予定通り消費税の増税が

相続実務をやってきて分かってきたことがあります。まず相続は大きく4つのパターンがあります。 相続のパターン 1. きょうだい間の相続 きょうだい同士は比較をするものです。 分割内容に公平感をもたせることが大切です。 2.

前回の記事では、タックスヘイブンを利用した租税回避の単純化した仕組みを説明しました。 その中で少しだけ触れましたが、租税回避を防止するための移転価格税制においては、「無形資産」というものがテーマとして出てきやすいんです。

先日、あるシニア世代の方の集まりにて遺族年金について説明する機会がありました。 既に皆さんは老齢年金を受給されているので、ある程度は遺族年金についても内容を掴んでいらっしゃると思ったのですが、予想に反して殆どの方がご存知